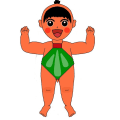これは、山地に囲まれた地方都市の駅のホームでの出来事である。
通勤や通学で利用する乗客で賑わった時間が終わると、ホームにいる客もまばらになってきた。この駅は、ローカル線の中でも駅長が配置される主要駅なので、利用する乗客もそこそこ多いはずである。
1番ホームにいる客の中に、紺色のリュックサックを背負った1人の男がいる。その男の外見は、カジュアルなシャツにスラックスをはいたごく普通の青年である。
ホームにあるベンチへ座ると、その男はリュックサックを隣へ置いてファスナーを開けた。そこから取り出したのは、デジタル一眼レフカメラと駅スタンプ帳である。
駅スタンプ帳の名前記入欄には、『福吉章洋』とボールペンで書かれている。
「よし! きょうもスタンプを押したことだし、今日はこのホームから出る山奥へ向かう区間に乗るとしよう」
この駅には、山奥へ向かう1番ホームと県庁所在地へ向かう2番ホームがある。電化はされておらず、この駅に停車する列車は全てディーゼルカーである。列車本数も、2番ホームからは1時間当たり1~2本運行されるが、1番ホームから発車される列車は1日10往復程度である。時間帯によっては、次の列車がくるまで2時間半も待たなければならないことがある。
「次の列車まで、まだ1時間以上あるのか……」
そうつぶやく章洋であるが、閑散区間のローカル線を乗り継ぐ彼にとってはそんなにつらいわけではない。章洋はトイレへ行って用を済ませると、右のほうに何か列車らしきものを見つけた。
その列車が止まっているのは、0番ホームのほうである。章洋は、一眼レフカメラを取り出してその列車の写真を撮った。
しかし、章洋はその列車を見ながらなぜか首を傾げていた。なぜなら、この0番ホームはもう使うことがないからである。
かつては、この0番ホームからもこの駅を始発又は終着として列車を走らせでいた。その列車は、山の中にある小さな集落に沿って走りながら日本海側にある町を結ぶローカル線であった。そのローカル線の総距離は100km近くあったが、1日に4~6往復という閑散区間で収益が見込めないことから1年前にその路線は廃止するに至った。
そういったこともあり、0番ホームに列車が止まっていることは普通に考えてもあり得ない話である。けれども、章洋がこの目で見ているのは0番ホームに止まっている1両の列車である。
この事実に、鉄道マニアの血が騒がないはずがない。章洋は、0番ホームからその列車の中へ入ることにした。
章洋が入った列車は、キハ5200系と呼ばれるローカル線向けの新型気動車である。出入口付近はロングシート、それ以外のところはクロスシートとなっている。もちろん、こうしたローカル線のワンマンカーで欠かせない運賃表示器と運賃箱が運転席の後方に置かれているのは言うまでもない。
それよりも気になったのは、何人かの乗客がすでに座っているということである。普通だったら、そんなに気にしなくていいはずである。
けれども、この列車が止まっているのは廃線となった0番ホームである。しかも、乗客の顔を見ると無愛想でその場から動こうとはしない。
「なぜだろう、乗客がいるのにこの静けさは……」
章洋は、静まり返った車内の様子に不気味な違和感を感じ取った。すぐにこの列車から出ようとしたとき、列車のドアが急に閉まった。
「えっ? ど、どうなっているんだ?」
章洋が戸惑っていると、ディーゼルエンジンを響かせながら0番ホームから列車が動き出した。車内のほうでは、ワンマン列車ではおなじみの自動音声が聞こえてきた。
その自動音声は、章洋にとって耳を疑うような内容であった。
「ご乗車ありがとうございます。この列車は三途川行きのワンマンカーです……」
「三途川っていう駅なんか、このローカル線にはなかったはず……」
章洋は、リュックサックからポケットタイプの時刻表を取り出した。その時刻表は、ローカル線が廃止になる前に発売されたものである。
「三途川、三途川……。この時刻表には三途川という駅は見当たらないぞ」
三途川という駅名がないことに、章洋は次第に不安を感じ始めた。座席に座っている乗客も、無表情のままその場から移動する気配すら見せない。
「普通だったら、何がしらの仕草があってもおかしくないのに……。もしかして、この列車は……」
章洋が乗っているその空間は、まるで日常から切り離されたかのような妖気に包まれている。しかし、それはあくまでこれから始まる恐怖の序章であるに過ぎない。
※第2話以降は、こちらの小説投稿サイトにて読むことができます(無料です)。
小説家になろう:https://ncode.syosetu.com/n5727fa/
小説家になろう:https://ncode.syosetu.com/n5727fa/