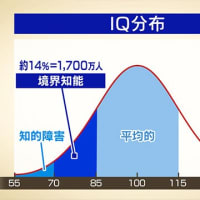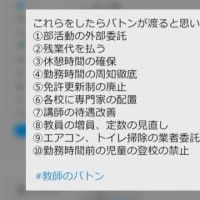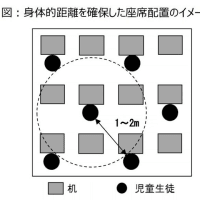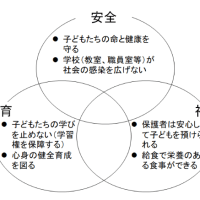中3「教科書理解できない」25%…読解力不足
新聞や教科書などを読み取る基礎的な読解力を身に付けられないまま中学を卒業する生徒が25%にのぼることが、国立情報学研究所(東京都)・新井紀子教授らの研究チームの初調査で明らかになった。
社会生活を送るのに最低限必要な読解力の不足が懸念される状況だ。
調査は2016年4月~17年7月、全国の小6~社会人を対象に、独自の読解力テストを実施。公立・私立中高生2万1000人の結果を中心に分析した。
主語や目的語など文章の構造が理解できているかを問うタイプの設問群で、中学1年の正答率は62%、中学2年が65%、中学3年が75%となった。中学3年の4人に1人(25%)が、教科書レベルの基礎的な読解力を身に付けないまま義務教育を終えていることになる。
(http://www.yomiuri.co.jp/national/20170923-OYT1T50000.htmlより引用)
前にも書いたと思うのですが、最近の子達は、本当に文章読解力が無いと思います。
ちなみに、学校ではどのくらい、国語の授業が行なわれているかご存じですか?
なんと、小学校低学年では、週5日しか学校は無いのに、週に9時間も国語の授業を行なっています。
中学年になると、7時間/週。
高学年になると、5時間/週。
中1および中2で4時間/週。
中3になると、驚くべき事に、3時間/週にまで削減されます。
これは、義務教育課程を開始したばかりの子どもたちには、まずは日本語を習得させない限り、あらゆる指導が成立しないからだと思われます。
極端な例ですが
「○○時に××に集合して下さい」
と教師が発言したとして、子どもたちが「集合」という語の意味を知らなければ、これは指示として成立せず、集団生活は行えないのです。
だから、低学年では国語の授業に多くの時間が割かれます。
しかし、基礎が身についてしまえば、他の授業や行事などを通してでも、自然と日本語力は身につくであろうと推測できます。
そのため、どんどん国語の時間は減っていき、他の授業に当てられるようになるのです。
これは、裏を返すと
「小学校低学年で日本語の基礎基本を習得し、卒業段階ではある程度の日本語力をみんな備えている」
という前提で、小学校中学年以降および中学校のカリキュラムが組まれていることを意味します。
ところが、ご存じの通り、小学校卒業テストがあるわけではありませんから、日本語力不十分でも、本人の意思にかかわらず、時間の経過とともに中学校に入学しなければならないのです。
自分は理科教師ですが、教科書の文章と、子どもたちの文章読解力に乖離があると感じています。
現場にいる者として、この
「主語や目的語など文章の構造が理解できているかを問うタイプの設問群で、中学1年の正答率は62%、中学2年が65%、中学3年が75%となった。」
というデータは、とてもリアリティのあるものに感じられます。
「勉強ができない子」がなぜ勉強ができないのかは、難しい問題です。
しかし、全員では無いでしょうけれども、国語力の問題で勉強ができない子は一定数いると思います。
要するに、教科にかかわらず、教科書や教師の説明が理解できないのです。
例えば、数学で方程式の解き方の説明を受けても、その説明を正しく理解・読解できない子がいたとして
その子はきっと数学ができないでしょうが、それは数学力の問題では無いのです。
では、なぜ最近の子どもたちは、国語力が落ちているのでしょうか。
これには2つ原因があると筆者は考えています。
1つ目は、娯楽の変容。
説明書などを読まなくても、遊べるようになりました。
昔は、プラモを作るにも、テレビゲームをやるにしても、まずは説明書を読むところから始まりましたが
今では直感的に遊べる娯楽が好まれ、実際売られているのはそんなものばかりです。
もちろん、プラモやテレビゲームは一例に過ぎませんが、何にせよ「文章を読まざるを得ない状況」が減少していると思います。
2つ目は、小学校の教育力の低下。
そうはいっても、私は「小学校の先生は努力不足だ!」なんて言うつもりはないですよ。
そうではなくて、構造的な問題です。

学校教員統計調査(http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/kekka/k_detail/1395309.htm)から引用しているグラフなのですが
35歳から45歳程度の、中堅と呼ばれる年齢の職員が異様に少ないことにお気づきでしょうか。
現在の教師は、社会人として成熟し、バイタリティもあるこの年齢の人たちが少なく
若さはあるが練度不足の人たちと、経験はあるがバイタリティが低下傾向にある人たちによって支えられているのです。
この組織的な問題が、指導力低下をもたらし
今までの小6なら当然身につけていたような、文章読解力や計算能力、基本的なしつけが怪しい状態で中学校に入学してきてしまう子どもが増加傾向にあるのです。
ちなみに、この組織的欠陥は中学校でも同じです。
なので、小学校での指導不足が中学校で挽回される可能性は残念ながら低いです。
この組織的な欠陥は今さらどうしようもないとして
今回話題に挙げた国語力の低下は無視してはいけないものだと思います。
ですから、今こそ、国語の授業を強化……もっとストレートに言えば増やすべきでは無いでしょうか。
そのためには他の授業を削る必要がありますが
自分は英語やプログラミングなんかより、国語に注力するべきだと思います。
日本語という、何かを学ぶために最も基礎となることが怪しい子どもたちに、何を勉強させても時間の無駄だと思います。
新聞や教科書などを読み取る基礎的な読解力を身に付けられないまま中学を卒業する生徒が25%にのぼることが、国立情報学研究所(東京都)・新井紀子教授らの研究チームの初調査で明らかになった。
社会生活を送るのに最低限必要な読解力の不足が懸念される状況だ。
調査は2016年4月~17年7月、全国の小6~社会人を対象に、独自の読解力テストを実施。公立・私立中高生2万1000人の結果を中心に分析した。
主語や目的語など文章の構造が理解できているかを問うタイプの設問群で、中学1年の正答率は62%、中学2年が65%、中学3年が75%となった。中学3年の4人に1人(25%)が、教科書レベルの基礎的な読解力を身に付けないまま義務教育を終えていることになる。
(http://www.yomiuri.co.jp/national/20170923-OYT1T50000.htmlより引用)
前にも書いたと思うのですが、最近の子達は、本当に文章読解力が無いと思います。
ちなみに、学校ではどのくらい、国語の授業が行なわれているかご存じですか?
なんと、小学校低学年では、週5日しか学校は無いのに、週に9時間も国語の授業を行なっています。
中学年になると、7時間/週。
高学年になると、5時間/週。
中1および中2で4時間/週。
中3になると、驚くべき事に、3時間/週にまで削減されます。
これは、義務教育課程を開始したばかりの子どもたちには、まずは日本語を習得させない限り、あらゆる指導が成立しないからだと思われます。
極端な例ですが
「○○時に××に集合して下さい」
と教師が発言したとして、子どもたちが「集合」という語の意味を知らなければ、これは指示として成立せず、集団生活は行えないのです。
だから、低学年では国語の授業に多くの時間が割かれます。
しかし、基礎が身についてしまえば、他の授業や行事などを通してでも、自然と日本語力は身につくであろうと推測できます。
そのため、どんどん国語の時間は減っていき、他の授業に当てられるようになるのです。
これは、裏を返すと
「小学校低学年で日本語の基礎基本を習得し、卒業段階ではある程度の日本語力をみんな備えている」
という前提で、小学校中学年以降および中学校のカリキュラムが組まれていることを意味します。
ところが、ご存じの通り、小学校卒業テストがあるわけではありませんから、日本語力不十分でも、本人の意思にかかわらず、時間の経過とともに中学校に入学しなければならないのです。
自分は理科教師ですが、教科書の文章と、子どもたちの文章読解力に乖離があると感じています。
現場にいる者として、この
「主語や目的語など文章の構造が理解できているかを問うタイプの設問群で、中学1年の正答率は62%、中学2年が65%、中学3年が75%となった。」
というデータは、とてもリアリティのあるものに感じられます。
「勉強ができない子」がなぜ勉強ができないのかは、難しい問題です。
しかし、全員では無いでしょうけれども、国語力の問題で勉強ができない子は一定数いると思います。
要するに、教科にかかわらず、教科書や教師の説明が理解できないのです。
例えば、数学で方程式の解き方の説明を受けても、その説明を正しく理解・読解できない子がいたとして
その子はきっと数学ができないでしょうが、それは数学力の問題では無いのです。
では、なぜ最近の子どもたちは、国語力が落ちているのでしょうか。
これには2つ原因があると筆者は考えています。
1つ目は、娯楽の変容。
説明書などを読まなくても、遊べるようになりました。
昔は、プラモを作るにも、テレビゲームをやるにしても、まずは説明書を読むところから始まりましたが
今では直感的に遊べる娯楽が好まれ、実際売られているのはそんなものばかりです。
もちろん、プラモやテレビゲームは一例に過ぎませんが、何にせよ「文章を読まざるを得ない状況」が減少していると思います。
2つ目は、小学校の教育力の低下。
そうはいっても、私は「小学校の先生は努力不足だ!」なんて言うつもりはないですよ。
そうではなくて、構造的な問題です。

学校教員統計調査(http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/kekka/k_detail/1395309.htm)から引用しているグラフなのですが
35歳から45歳程度の、中堅と呼ばれる年齢の職員が異様に少ないことにお気づきでしょうか。
現在の教師は、社会人として成熟し、バイタリティもあるこの年齢の人たちが少なく
若さはあるが練度不足の人たちと、経験はあるがバイタリティが低下傾向にある人たちによって支えられているのです。
この組織的な問題が、指導力低下をもたらし
今までの小6なら当然身につけていたような、文章読解力や計算能力、基本的なしつけが怪しい状態で中学校に入学してきてしまう子どもが増加傾向にあるのです。
ちなみに、この組織的欠陥は中学校でも同じです。
なので、小学校での指導不足が中学校で挽回される可能性は残念ながら低いです。
この組織的な欠陥は今さらどうしようもないとして
今回話題に挙げた国語力の低下は無視してはいけないものだと思います。
ですから、今こそ、国語の授業を強化……もっとストレートに言えば増やすべきでは無いでしょうか。
そのためには他の授業を削る必要がありますが
自分は英語やプログラミングなんかより、国語に注力するべきだと思います。
日本語という、何かを学ぶために最も基礎となることが怪しい子どもたちに、何を勉強させても時間の無駄だと思います。