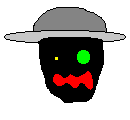|
第13章 ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほうほほほほほほ
|
|
第12.3章 列車が止まり、あたりが一斉にばたつき始めましたので、キーホーがガリ版刷りから顔を上げますと、さっきの親戚を名乗る小説家は、すでに姿を消し、青いビロード張りの座席には小さな声が影のように這っているではありませんか。 声は波が月光にゆらめく様にするすると窓ガラスの底からプラットフォームに降りてゆきました。 こうです。 ど こ か で 偶 然 に 会 え る と い い ね 、 き っ と 会 え る さ 、 じ ゃ ぁ ね ・ ・ ・ ・
三十秒ほど過ぎると列車の中には、まるで砂浜に打ち上げられた巻き貝の内側にいる様な、吸い込まれる様な、透んだ静けさが立ちこめていました。 キーホーが再び、ガリ版刷りの小説に目を落とすと、列車は、前進しているのか?後退しているのか?それとも、動いているのか?動いていないのか?も、わからないくらいに、ソロソロゆっくりと揺れ始めました。
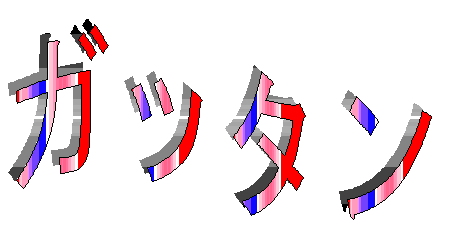
超宇宙的な、その美青年に引きつられて洞穴に入って行った僕は、この鍾乳洞の構造が極端に、上昇志向と下降志向のアンヴィヴァレンツな心理作用を与える事に気づいた。 登ったかと思うと、側面には、ぽっかりと深い口を開けた小さな穴が無数に下降している。 その中から針の先の様な光がチラチラと、と、とっ、とっとっとっと。 さぁて、これから奇型的美男子は、主人公の僕に、実は、この世、この宇宙は、卵の殻の表面の様なもので裏面の死界とピッタリ重なっているという事を説明し、裏側に迷い込んでしまったプロクシマ星系からやってきた宇宙一の美女、シャングリ星のリュィッテを助け出して行くのであるが、詳しくは、私の小説「クルベムゲイル・サガ」断片五十一の長編小説「遙か彼方のラブピース・ターボ」に描かれている。 続きと、断片五十一を読みたければ、この小説にノーベル塵芥川賞を与えたまえ。 与えるまで、この物語はここまでしか公開しない。 地下室の巨大な押入れの奥深くに眠らせる。 さよなら。
|
|
第12.2章 キーホーは読み続けます。
第一章
あちこちで河川が氾濫し乗客たちが足止めをくらい、土砂は元の居場所を離れ、災害を生み、百姓たちが青ざめた。 暴風雨は三日間続き、三十分程の小雨を経て地上に在るもの、あらゆるものに希望を与える光に変わった。 空には雲も太陽も無く輝きだけが広がり、それは、とてつもない力が完全に活動を停止した時に、じわじわと広がり、しみ出してゆく、無という沈黙の侵略の様に感ぜられる。 蝉たちが一斉に鳴き始めた。 僕は静かな町を歩いていた。 町内会の人達が路面に散乱したガラクタを一カ所に集めていた。 その音が、やけに静かな朝を盛りたてていた。 近くの川の鉄橋がぐらつき、上りの列車は全面不通になっていたので、僕は、しばらくこの町で時を過ごさねばならなくなった。 木造の家並みが続く風景を眺めながら、登校中の子供たちと擦れ違い、泥だらけの白犬を見、細い砂利の坂道を抜けると、丸くひろまった空き地に出た。 全体が中心に向けて窪み、小さな池の様に雨水を溜めていた。 僕は濡れないように注意深くぬかるんだ池の端を進んだ。 空き地の回りには高い杉の木々が壁の様に囲っていて、今来た坂道のちょうど真向かいに、森の中へ、その先を隠している石段が、雨水で黄色く光っていた。 もと来た方を振り仰ぐと、山々にすっぽりと包まれ、孤立した町の全容が見下ろせた。 数える程しか建物がない。 小さな町だ。 あちこちで山々が風雨に喰い荒らされた、その痛々しい傷跡を、一斉に空に向けて訴えているようだ。 小屋の様な駅舎に、行き場のない乗客たちが群がっているところを見ると、まだまだ汽車は動き出しそうにない。 汽車は石の様に黒い胴体を、ずっしりと大地に接着していた。 橋桁が外れたのなら、まあ、当分動かない。 事によると何日も止まったままかもしれない。 それなら、又、この坂を下りて戻れば良い。 まぁ、僕は、行く場所も特に無いわけだが、どうも今来た方向に引き返すのは気の進まぬ事だ。 水の滴る石段を巨木たちに挟まれて、ゆっくり登っていくと、遙か上方に大きな赤い鳥居が見えてきた。 高くなるにつれ、蝉どもの不協和音が、やけに強くなり右耳の奥で渦巻のように、ドリル音が暴れ出した。 僕の耳は昔から蝉の鳴き声に弱く、特にあぶら蝉のコーラスに会うと、「ギュィーン」という気が薄れて遠くなる様な轟音を耳内部で製造してくれる。 これが始まると、頭の右側がジーンと痺れ、思考もとたんにピントが外れだしてしまう。 僕はポケットをまさぐり、水泳用の耳栓を取り出して右耳に深く押し込む。 それでも、蝉の声はジワジワと耳の奥に、右脳の奥に、染み込んでくる。 登りながら、重力が左側だけ強まったように重心が傾いていく。 赤い鳥居の全体が現れた頃、僕は、ぴったりと石段の左端に体を寄せ、殆ど木々に体を摺り合わせるように立っていた。 汗が顔を這い、顎の先端からしたたり落ちた。 汗は、その中で小さな太陽を弾ませていた。 近くで見ると鳥居の赤ペンキは、かなり粗雑で、血飛沫がへばり着いた様な塗り方だった。 鳥居を抜ける時、背筋に雨水が連続して降りかかってきた。 ひやっ、とした感覚が、意識を一瞬、鋭角的にした。 その時、僕は確かに手水舎の脇に黒い人影を見た。 白い石の道が、僕の前から手水舎と本殿の方に流れるように続いていて、その向こうは高い杉木立が被さる様に立ち並んでいた。 僕は、いつもの癖で、すぐに人影から目を逸らしてしまい、再び横目で確認しようとした時には、不思議な事に、そこには誰かがいた痕跡さえもないのだった。 意識が左側から白くなった。 錯覚か? 次に僕は不安が音も無くやってくるなと、予想し、その通り、不安は好奇心を伴って、すぐにやって来た。 来るな、来るな、と思えば思う程、恐ろしくなってくる。 僕は、この不安の呪縛から解放されたく、静寂の中に言葉を発した。 「あっ!」 僕は夜中、金縛りにかかった、又、かかったなと思うと、恐ろしくて、それを否定してみたく思い、手足を曲げてみたり声を上げてみる事がある。 今、それと同じ事をやった。 短い間だが、僕は、うぶ毛一本動かさずに、あの場所を見ていた。 ゆっくりと通り過ぎる風を感じ、頭上に広がる巨大な空間を感じた。 大気圏から、山に囲まれた小さな町の神社の中の小さな自分を俯瞰しているようだ。 気が納まり、安心してくると僕は自分を愛したくなる。 手は自然に口や局部の粘膜へと動いてゆく。 唇に人差し指を走らせながら僕は本殿に近づき、手水舎の背後を確認できる位置を求めた。
この症状は幼い頃からの父や兄たちの僕に対する過度の干渉に根ざしている。 父や兄たちの強い制圧の下で僕は少年期を過ぎても、じっと屈従していなければならなかった。 しだいに恐怖と憎悪の的であった父や兄たちを避けようとする欲求が、人間全般に向けられ、無意識が、他者から顔を背ける行為として僕を駆りたてている。 そんな時、僕は無機質を凝視せずには、いられない。 僕は再び視線を彼の上に移した。
彼の目は澄みきった灰色に見えた。 彼の額は、一本の皺もなく、完全にアクセントを排した冷たい永久性があった。 彼の鼻は、両目の真ん中から、全く不統合を感じさせぬ強烈な美しさを持って配置されていた。 口もとまで、少しの変化も無く、真っ直ぐ、のびていた。 彼の頬は、ナイフで抉られたように鋭く、見ようによっては痛々しく削げていた。 彼の口は、強烈な怒りによってできた、亀裂の様であった。 弾けたように大胆で、それでいて、あまりにも人儀的な、あまりにも人工的な裂け方でもあった。 耳は大きめで正面に向かって翼のように開いていた。 髪は短く、荒々しく、前髪が、ところどころ額にへばりつき、他は全体的に逆毛立ち、殆ど真っ直ぐ突っ立っているようだった。 僕は軽いショックを憶えた。 この様に美しい顔を僕は、かつて見た事が無かったし、全く想像も出来ない、斬新で何か地球上では味わう事の出来ない、全く新しい文化に接したかの様な奇怪な陶酔があった。 それは、古今東西、人類が、あらゆる物に見出してきた、美の概念とは完全に次元の違うものだった。 異次元の美だった。
彼は皺だらけの白いシャツの汚れを払い、何かを呼び寄せるかの様に空を見上げた。 彼は、泥の付着したジーンズに小型の黒いカメラを下げていた。 彼が僕に向かって力強く歩き始めた時、背後の杉林から鳥たちが跳ねるように飛び出した。 僕には限りない喜びと不安があった。 というのは、彼に対して希有な愛着を抱いている事と、それを彼に見透かされ、彼の全てを洞察するような目で僕の、彼とは比較にもならない愚鈍で、ちっぽけな人間を見抜かれ、軽蔑されたくないのとで、対処の方法を破裂しそうな動悸の中で考え巡らせていたのだ。 (平然としているのだ。 平常時の声が出るように。 動揺を表してはならない。)
透明な、ハイトーンの声で彼は口を切った。 尖った白い犬歯が見えた。 どういう事だ? 彼は何かで僕を利用しようとしているようだ。 通常の礼儀を知らんのか? それとも、全く僕に対する興味、関心が無いという事を意味しているのか? 僕は彼への好奇心ではち切れそうなのに。 人格を無視された。 僕は恥辱を感じ、それでも、もう彼の美しさに完敗し心を奪われてしまっている自分が情けなく、何とか、自分の尊厳を保とうと必死になった。 「どういう事ですか?」 唇が、少し震え、声が上ずんだ。 くそっ! 「失礼。 いきなり無礼でしたか? 旅行者ですね。 ああ。 台風で電車が止まってしまったんで立ち往生なんですね。 ああ、太陽が、まぶしいですねぇ。」 彼は襟に吊り下げてた薄茶色のサングラスをかけた。 その時、光線の具合か?彼の瞳が青色に輝いた。 当然、僕は新鮮な感動を受け、彼に全てを委せたいと思った。 しかし、すぐに自尊心が、それを抑圧し軽い怒りに変えた。 「こんなとこで、君は何してるんだ?」 又、声はうわずった。 おそらく僕は彼を睨みつけていただろう。 「僕は、ここ十日間、人と会ってなかったんでね。 ちょっと精神的に外れてしまってて・・・・・・・・・。 誰かに、ずっと、ある事を頼みたくてね、要するに待ち焦がれていたんだ。 変に思うだろうけど、どうしても君に僕と一緒に、あるところに来てもらいたいんだ。 時機を逃したら、もう決して誰も見る事が出来なくなるんだよ、それは。」 「どうして、この町の人に頼まなかったのかい? 誰でもいいんだろ。」 彼は、しばらく沈黙し、仮面の様な顔を、じっと保った。 そしてポツリ。 「だめなんだ。町の人は。 こんな事、頼めやしないよ。 こんな事に力を貸してくれるわけが無い。 わかっているんだ。 そうさ、君みたいな僕と同じ年ぐらいで、一人でこんな場所へ散策しにやって来る、ちょっとばかし感性の鋭い感激家。 そんな人間でなければ、これから行くところへついて来てくれるわけが無い。」 緊張が少し解れてきたようだ。 彼の感情の起伏の全く無い淡々とした話を聞いていると、不思議と身体全体が軽くなってゆく。 まるでサイダーの気泡が身体全体を通り抜けてゆくようだ。 怒りや屈辱感は、殆ど感ぜられず、これから彼を助けてやれる喜びと、性欲に似たとろける様な興奮があった。 「話を聞かせてくれ、面白そうだ。 いったい君は何を手伝って欲しいんだ?」 「この神社の本殿の裏に小さな穴がある。 その穴は百m程、真っ直ぐに続いていて大きな鍾乳洞につながる。 百m先から急に石灰岩地形に変わっているんだ。 鍾乳洞は、しばらく天井も高く、横幅も広く、実に快適に続くが、しだいに狭くなり、上下左右から押さえつけられる様な状態になる。 そして、それを抜けると、ポッカリと周囲百mぐらいの空洞に出る。 天井は、ドームの様に、そこ一帯を覆っている。 その広まった場所からも又、小さな穴が無数に枝分かれしていて、地の底へ、死の国の入り口へと続いている。」 僕は、その洞穴の構造を必死に理解しようと神経を集中し、他の事は一切考えず、阿呆の様に唯、突っ立って、彼の完全と異常の混在した容姿に見入っていた。 彼は話しながら右手の人差し指を、ポキッと鳴らした。 「そこで、君に頼みたいのは----随分、自分勝手な事なんだけど----一緒に洞内に入ってもらって探索して欲しいんだ。 事情は、一口では話せないが、一人の女性が、その死の国の迷路に迷い込んでしまった。 その女性を探し出して、助け出さねばならない。 わかったかい? 頼む、協力してくれ。」 (RPGかいな・・・ぼそっ) 倒れる様に彼は頭を下げ、僕に懇願した。 襟元のプラスティックのような肌がジワッと光った。 すぐに承諾の意志が僕の口から飛び出しそうになったが、自我の抵抗が、それを抑えた。 確かに彼の容姿容貌は、遙かに人間の美感を越えてしまっていて、僕を虜にせずにはいられない。 それだけで、もう僕の心は体は、全て、彼の意のままになる事を切望している。 今だって、彼の言葉の、そのままの意味だけを、いつもの僕の キキーィ シュゥ シュウゥゥゥゥゥ ゴットン  
|
|
第12.1章 列車は走り続けます。 「ふふふふふふふふふ、うふっ。」駅が小さく小さく置いてけぼりを喰らってしょんぼりしてるのがサイドミラーに映し出されています。 キーホーは口を大きく開けて、バンザイの様な格好で、のびをしました。 すると、いつの間にか、向かいの席でウインクを繰り返している小説家が「レティシアのテーマ」を口笛で吹きながら、キーホーに釣られてバンザイをしているではありませんか。
小説家は言いました。
私と君は親類同士だ。」
君は知らない風だけど、僕ら一族はね、クルベムゲイルの血筋なのだよ。 神の血筋だ。」
そうだと思ったんだ。 じゃあ、これを読みたまえ。 私の書いた本だ。 世界の秘密とクルベムゲイル一族の関わりについて書いてある。 遠慮せずともよい。 さぁ。」
小説家は、うれしそうにニッコリと笑みを浮かべてキーホーの一挙手一投足を曼珠沙華のように揺れながら凝視しているのでした。
|
|
第10章  ☆オハヨウ☆ さて、一体全体どうしたことでしょう。 キーホーはゴトゴト揺れる列車の座席で目を覚ましたのです。 キーホーは、寝ぼけ眼を、こすりながら、何故、バスじゃなくて列車で目覚めたのかをクルクル考えておりますと、車内モニターにカラス女が映っているのに気づきました。
キーホーは税理士の肩先を、ちょんとつついてみました。 すると税理士は、くるりと身体を逆回転させて汗まみれの汚い顔をキーホーの胸元に、くっつけて、埃の様な声を出したのです。 「おい。苦しいぞ。イ・イキが出来ない。」
ただ、うようよだけがあり、がんとして在った。 うようよを紙の様に破いて向こう側へ行く人は少ない。 もっと、うようよしていく人達が多かったのだ。 まして果実や、マサカリを買い求める事など、とてもできなかった。
しかし、人々は憧れ、せめて外装だけでもと、格好つけるのだが、そこから矛盾が生じ、内部戦争を心に宿し、発狂した人もいた。 しかし肥満型の現実人間達は利欲打算を構造化し、団体・組織を作り、うまくやり、それを再び、すっかり正しいのだと受け入れ、入団し、団体・組織内でヌクヌクしようと本気に思い込む奴もいた。 しかし、皆、心の片隅では果実を欲して止まなかったのさ!」
無能者は、もっと悲しかった。 何のせい? うようよだよ。 チョッ。」
』
|
|
第9章 キーホーは夢を見ました。 キーホーは、ふわふわと夢の世界を漂います。 ・・・・・・・・・・・・ゆめ・・・・・・・・・・・・  ( 地面から立ちのぼる不思議の煙に包まれて、その午後の世界の中の僕は、とっても宇宙的でした。 内宇宙での空は死人の目の様に澱んでいましたし、ホルマリンの中を歩いてる様で、街の景色も、なんだか巨大な死骸を連想させる奇妙なフラスコ空間な午後でした。 僕は地面から3㎝くらい浮遊して、まあ空中を歩いていました。 通り過ぎる人々は決まって昆虫採集用の捕獲網を被って、柄の部分をカラカラと引き摺っていました。 それは流行なんです。 でも僕は流行は嫌いなんです。 だから、ほら、今の大学生達が皆、熱狂している柱時計ファッションなんて身震いしちゃうのです。 馬鹿みたいに身体中に柱時計を、くっつけて、そんなぁ事じゃぁ、ろくな理念は持てないのですよ。 ああいうものは独自性が売りものなんです。 流行するこたぁないです。 価値を擦り減らすだけなんです。 僕は灰色の乳首の突起が浮き出るポロシャツに、水色の先の細いコットンパンツに真っ黒い運動靴を履き、自慢の赤毛をなびかせながら、しゃっくりをしました。 でも、しゃっくりは止まりません。 僕は高い赤煉瓦の壁に囲われた、この細くて白い坂道を登りきるまで、しゃっくりを終える事が出来ませんでした。 しゃっくりは何故、坂の上で止まったのでしょうか。 それは坂の頂きに非常に衝撃的な建物を発見したからなのでした。 その建物は性器の形をしていました。 そして、その建物は、僕、いや、僕らの全然知らない色で塗られていたのです。 地球上に今まで存在しなかった、誰も知らない色で。 僕は性器の建物に知らず知らず引きつけられ、ついには、ノブに手を掛けていたのでした。 ドアーの色は僕の知ってる色でした。 まっ赤。 そして、赤いドアーの上半分に「珍品屋」と大きく緑で描かれたシールが、ナメクジのように、突然に貼り付いているのに気づきました。 静かに、僕はドアーを開きました。 店の中では、いかにも使い古された自分を誇示するかのように、壁や床や天井達が、ふんぞり返って重みのある油の臭いを放っておりました。 はにかみながらも僕は蜂の巣の様な陳列棚を、ひとつ、ひとつ丁寧に覗いていきました。 マスクをした金の鳥籠。 知識の一杯詰まったフラスコ。 向こう側が透けて見える鏡。 目に見えぬ絵画の数々。 詩で、できたコーヒー。 コーヒーで、できた詩。 元気の良い蝉の抜け殻。 本物の糞。 ∞∞∞etc。 静かな雲の流れのようにボレロが聞こえてきました。 タッタカタ、タッタカタ、タッタカタ、タッタカタ、タッタカタ、タタタタタタ。 青い棚の中に、美しい入れ目がありました。 僕と目が合うと入れ目は、剃刀で角膜を削りました。 自分を傷つけて人を喜ばせようとする、あまりの涙ぐましさに僕は耐えられません。 僕は入れ目の瞳孔に優しく接吻すると、そそくさと陳列棚を離れました。 一瞬、若干、瞳孔が小さくなった様でした。 店の片隅で黒いショールを羽織ったカラス達が、何やらパントマイムを演じているのがチラッと見えました。 白い絨毯を響き渡るボレロの流れに従って進んでゆくと、大きなピンク色の指が、ありました。 小指でした。 タッタカタ、タッタカタ。 でも、近くで、よく見ると、違いました。 タッタカタ、タッタカタ。 それは、ピンク色のゴミ箱だったのです。 タッタカタ、タッタカタ。  ・・・・ムニャ。むにゃ。 ~ )
|
|
第8章
     
脊髄をガンマ・アミノ核酸が、ゆっくりと流れていきます。
キーホーが後悔したのは、脳波が低振幅θから丘波+紡錘波のレム期に突入する直前だった。 |
|
第7章 深海夜を黒いバスは音無しで走り続けていました。 窓から月明かりの中を降るプランクトンの死骸がチラチラと時折、内部で火を燃やしているのが窺えます。 30分程でキーホーは瞼を閉じ、瞼の裏に輝く夏休みの空が、彼方の永遠が、花畑が、砕け散る水滴が、はためく白い麻のシャツが、映像となって映し出された時には、もう眠りの中に半身を沈み込ませておりました。

眠ります。眠ります。 瞼の裏の微生物。光り苔。 緑の灯。近づいたり、遠のいたり。 (瞼の裏を見つめます。皆、そうやって眠るんだ。僕も見つめるんだ。 でも、僕一人が、誰もいない遠い遠いエーテル・ゾーンに放逐されてゆくような、この寂しさ。 ああ、早く眠ろう・・・・・・) (おっ!この感覚は遊泳だ、と思った時、眠りは始まる・・・・・・・・・・)
全身を寒気が這い、キーホーは目と口を一緒に開きました。 カッと、大きく。
頭の血管が脹れてゆくのが感じられました。 性欲が強まるのが、よくわかります。 彼女は黒い口紅を塗っていて、その高く突き出した鼻と、バサバサ重なった羽の様な服からカラスを連想させました。 キーホーは、あがっていました。 心臓は高鳴り、靄が頭脳全体を支配し、筋肉は突っ張って、もうメチャクチャで、倒れて丸まってオギャー、オギャー泣き喚きたいのでありました。
そして、女の髪は風に逆立ったのです。
カラスは僕の友達を喰ったんだから。あの時。 そうだ、あれは、もう十年以上も昔の事、僕が九才の誕生日を迎える一週間程前。 恐ろしい。そうさ。僕は永久に呪われたのだ。 だから、いつも、ひとりぼっちで、こんなに寂しいんだ。 友人を見殺しにしたのは結局、僕なんだ。僕だ。 わかったぞ。 カラス女に化けて、やって来たんだな。 カラス女! ) 
キーホーの思考回路を、パッと走り抜けた考えです。 キーホーは歯車で制御された自動マネキン歩行機の様に、カキ、カキ、カキと段階的に、床に前のめりに倒れていきました。 |
|
第6章 暗く油の臭いの染み込んだ洞窟のような黒いバス。 キーホーは、最後部の長椅子のド真ん中に座って“しん”とした車内を見回しました。 乗客は、どうやらキーホーと、燃えつきたトーテムポォルみたいに突っ立って吊り輪にしがみつている嵩張った黒服の女だけのようでした。
「あっ。」 思い出しました。 「夜子。」 キーホーは叫びました。

黒服の女が、ぐるりと首を反転させて振り向きました。 そして、その冷たく、鋭角的(シャープ)な眼差しに照射されますと、キーホーは遠い昔、黄色い空間(イエローゾーン)の教室で彼女に、ちっちゃな赤鉛筆を借りたいといふ水色のゼリーのよふな記憶が突然、海馬の内側の中心点からドライアイスの、ひんやりした煙みたいに、ふんわかと、プカプカと、やって来るのを感じてしまいました。
ですから、その記憶がキーホーの懐古趣味(ノスラルジアァ)を刺激しても、すぐに彼女を撃ち殺してやりたいという欲求が、爪先から途方もない勢いで回転しながら漸増的に脹れあがり、ついには頭の天辺に達して、ドッカァァーンです。 恒星の破裂の様に巨大な光粒子がキーホーの内宇宙に拡散し、すぐさま収縮し始めます。 精神の中核にポッカリと黒い吸入孔(ブラックホール)が開き、秩序の保たれていた意識が吸い込まれてしまうのです。
十何年振りかの邂逅に感動し、瞳は輝くは、良心的な体つきに善人そうな唇の曲げ具合、と来ました。 その熱心な偽感情表示は、果たして何をもたらすのでしょうか? キーホーは、密かに期待していたのです。 〇夜子 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」 彼女は完全にキーホーを無視しました。 (夜子は、 完全に 僕を無視した。 完全に。 なんて僕は、僕と世界の関わりは、空しいのだろう。 なんて寂しいんだろう。チョッ。 ) (表情を1Å(いちおんぐ)だって変えやしない。 果たして生きているのだろうか? )
“おだやかな波のような平和” なのでした。
ヘラクレイトスは、火は全ての源であり全ては、やがて火に戻るという。 信じたまえ。半分はデタラメだ。
|