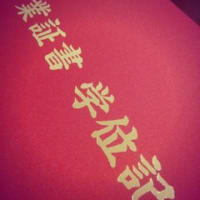さて本日は 休日ヘンジョー!!! で ガッコで補講
モウねぇ てんやわんやでねぇ 脳内エンジョー!!!ですよ そーそーそーそー でもやるんだよ
本日の補講内容は 1年時から教えて下さってる 元幼稚園のセンセの授業で 『子ども理解』について
すこし天然系だけど みんなから慕われていて ボクも教育者として尊敬しているセンセ是
子ども理解 保育や育児において 最も大切な部分であるワケだが 理解ってなんやねん???って話よ
教科書的にいえば 『子どもの氣持ちに寄り添う』 とか 『大人の固定的な価値観を捨てる』 とか
で 実践的には どうなのよ??? って噺ですよ
実際に子育て奮闘中のボクですら 子ども理解が出来ているかと言えば ウン イエース ウィ とは言えない
それはひとえに 我が子ゆえのものかも知れず コチラの設定したタイムスケジュールや 都合 Egoっといった
所謂『オトナの理由』によって 子どもたちは 常に 左右されている っということになろう
家族でない他者の子どもを保育するに当たっては 子ども理解と言うのは 想像以上に重要である事がわかる
たとえば 保育室で 御片付けの時間になったとしよう ピアノで『御片付け♪』なんか弾いちゃたりしてね
それでも 中には 気持ちの切り替えが出来ずに ずっと 友達と遊んでる子どもがいる ぜったい一人は
保育士なら どんな言葉がけをする??? 『センセと一緒に片付けよう』とか 『○○君御片付け上手だよ』とか
片付けは なんのため??? ボク的回答は "次の活動に移行する為の場面転換" ヒプホプ的に言うとINTERLUDE是
確かに 遊具のお片付けは大事 でも ちょと待って それって"片付けをさせるための声カケ"になってない???
事例:『AちゃんとBちゃんは 片付けが始まっても ずっとお人形ハウスで遊んでいる
保育者が促しても "イイの!!!" っと声を荒げ 片づける様子はない』
まず 二人の最近の様子に目を向けてみる Aちゃんは活發でハキハキズバズバ言うタイプ 友達が少ない
Bちゃんは そんなAちゃんと遊べる数少ない子 先日Aちゃんが風邪で少しの間 園をおやすみした
その間にBちゃんは 別のグループで遊び Aちゃんが復帰しても なお 別グループで遊んでいた
事例当時 いつものようにAちゃんが遊びに誘うと 久しぶりにBちゃんがそれに応じた
で 前出の『イイの!!!』ですよ イイの!!!だけ見たら ワガママンに受け取れるんだけど その奥には
自分が病気で休んでるうちに 仲間関係が変わってしまい ながらくBちゃんと遊べなかったAちゃんの氣持ち
そして 久しぶりに自分のリクエストに応えてくれたBちゃんとの関係性を崩したくなかったAちゃんの氣持ち
そういうものが 見え隠れするのではないだろうか これが 子ども理解 っというものなのだそうだ
字面だけで書くと なんて言うことのない考察かもしれないが これこそが"寄り添う" なのだ
episodeの奥にある 子どもたちだけの心の動きや 葛藤に 寄り添う事 目の前の事だけを見てはイケナイ
ボクは この講義をウケて あらためて 自信が無くなった 難しいなと思った 子育てをしているのニダ
いや 子育てをしてるからかもしれないけど 保育者として仕事をすれば 出来るのかもしれないけど
保育士は 子どもの発達や特性を段階的に熟知し 的確な援助が出来る 国家試験資格を有する 専門職であるが
あらためて 職務における責任性と 押しつぶされそうな重圧 やりがい 達成感を 感じずには居られなかった
帰宅 雨がきついので 妻と娘を駅までお迎えに
ガッコで参加できなかった 保育の就職フェスティバルに "保護者"として 偵察に行ってくれていた
色々な情報を持ってかえってきてくれた 娘は ボクに 重い冊子の束を 手渡してくれた
ガムバらなきゃイケナイな 明日は 弾き歌いの本番 テストだ
本日の練習:通学RIDE 16km
本日の映像:『THE EYES OF A CHILD』
講義でセンセが見せてくれたMovieです ついたてをして 映像と同じヘン顔をしていくオヤコ
身障者の方が出てきた時 多くの保護者は マネするのをためらってしまう でも 子どもは楽しそうにマネする
子どもには 健常や身障の垣根はなく オトナはマネしてはイケナイのではないかという葛藤が垣間見れる
固定的な概念が時に邪魔をすることもあるというケース みんな違ってイイのだ っていう氣付きのある映像だ是