
美しいお写真です

秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)
秋分の日に皇霊殿で行われるご先祖祭
秋季神殿祭(しゅうきしんでんさい)
秋分の日に神殿で行われる神恩感謝の祭典

■ 秋季皇霊祭遥拝式 (伊勢神宮)
----------------------------------------------------------------------------
日本に昔からあった先祖まつり、春分と秋分の日を、中日とした七日間を彼岸といいます。
この期間に法要や墓参りをしたり、お寺では彼岸会(ひがんえ)が催されるなど、仏教の影響が色濃く感じられます。しかし、仏教思想とは解釈できない要素が含まれていて、もともと我が国固有の信仰行事が、基調をなしていることがわかります。
「日本書紀」には、「皇祖神武天皇陛下」が、「皇祖天神を祭りたまふ」とあり、天武天皇十年(682)五月十一日条に「皇祖の御魂を祭りたまふ」と記述がみえます。
従って、このような祖先祭祀の伝統が前提にあったからこそ、やがて仏教的なお彼岸会も行われるように至ったのです。
中世・近世の宮廷では、御所の一角(清涼殿のお黒土)に歴代天皇の霊牌(れいはい)や念持仏を安置して、ご命日の法要など営まれてきました。
明治維新の際、神仏分離令により、従来の歴代霊牌は、京都・東山の泉湧寺(せんにゅうじ)などへ遷されました。明治二年(1869)改めて神祇官で歴代天皇の御霊代(みたましろ)を招き祭り、明治天皇陛下の御拝礼がありました。
明治十一年六月、「春秋二季祭」を置き、「神武天皇を御正席とし、先帝まで御歴代天皇、ならびに后妃以下皇親(皇族)」も「合祭」すると定められました。
この時、春秋二季(春分・秋分)の皇霊祭が、明治六年以来の国家的な「祭日」(元始祭・神武天皇祭・孝明天皇祭・神嘗祭(かんなめさい)・新嘗祭(にいなめさい)。他に「祝日」は、新年宴会・紀元節・天長節)に付け加えられました。
それによって全国の神社などでも一斉に祭典が行われるようになりました。
さらに、明治四十一年公布の「皇室祭祀令」で皇霊祭は「大祭」と定められ、祭典の中で東遊(あずまあそぶ)(楽師の歌舞)も奉奏されることになりました。
この春分と秋分には、皇霊祭に続いて神殿祭が行われます。
その神殿には、日本国中の天神地祇(てんじんちぎ)が祀られています。
天神地祇の由緒を遡れば、記紀神話にみえる高天原(九州)から降臨された、大和朝廷と関係氏族が奉齊する天神(あまつかみ)と元来地上にいた土着氏族が奉齊する地祇(くにつかみ)から成るとみられています。
両方が長らく共存交流し、不離一体となっていますので、むしろ「八百万神」(やおろずのかみ)というほうが相応しいかもしれません。
歴代天皇陛下が古くから直接的な祖先神だけでなく、全国の神々を崇敬してこられたことは多言を必要としません。
例えば、大宝・養老の「神祇令」に「天皇即位(踐祚)したまはば、惣(すべ)て天神地祇を祀れ」と定められています。
また「延喜式」では、「宮中神」以下全国の「天神地祇」総計三千百三十二座をあげ、そのすべてが毎年二月の祈年祭には神祇官か国司の国幣に与る(あずかる)とされています。
それらは、中世・近世に衰退し、廃絶したものもありますが、明治維新の際、積極的に復興されました。
明治二年、神祇官に神殿を設けて、中央の座に宮中八神(神産日神(かんむすびかみ)~事代主神(ことしろぬしかみ)、西の座に歴代皇霊、東の座に天地地祇を奉齊している。ついで明治四年、その三座
で春秋二季に「祈念祭」が行われることになり、翌明治五年、宮中八神と天神地祇を合祀して一座とされました。
明治二十四年、春分と秋分に行う「神殿祭」と定められ、その十年後から、新築(現存)の宮中三殿の「神殿」において「天神地祇」が祀られるようになりました。
さらに、明治四十一年公布の「皇室祭祀令」により、春分と秋分の神殿祭は、皇霊祭と同じく大祭と定められました。
このように皇室、全国の神社では、先祖の供養(くよう)をする日とされています。ところが、こうした行事の意味を知らずに、休日であるからといって結婚式を挙げたり、行楽に出かけたりする方を最近多く見受けますが、このようなことは慎まなければなりません。春・秋の中日は、氏神さまや、お墓参(はかまい)りをしてご先祖さまをお慰めし、感謝をする大切な日であることを忘れてはなりません。
古来、日本人は家族や地域の共同体の「和」を大切にし、名誉を重んじてきました。何気無い不用意な自分の行為が、家族や地域の人の和を損(そこ)なわないように、自分を律(りつ)する自制心を高めるために、常に身を修(おさ)め、家を斉(ととの)えてきたのです。
近年は個人主義の考え方が非常に強くなり、遠いご先祖から続いてきた家の意識や家族や親族の絆(きずな)の意識が希薄になってきています。その結果、自分さえよければ、他人の苦しみや痛みをまったく無視するような風潮さえ生じてきました。
経済優先・物質万能主義による現代人の生活形態は、限りある天然資源を枯渇(こかつ)させ、環境を破壊させて止どまる所がありません。
日本人は、「人もまた、自然の一部である。」という世界観(せかいかん)のもとに、自然に優しく抱かれながら、山川草木はもとより、すべての生きとし生けるものと共に、生活をしてきた民族です。
日本古来の習俗を体現され、今日に継承されておられる、皇室。
「敬神崇祖(けいしんすうそ)」のこの日に日本人としてのありかたを考えなければなりません。
日本の国は現世の人々の為にあるわけではなく、神代の昔からの祖先と、未生の子孫の為にあるのですから・・・
参考文献 所功 著
天皇の「まつりごと」
★「美し国(うましくに)さんから転載させて頂きました。
-----------------------------------------------------------------------------
 --------------
--------------秋のお彼岸
おはぎ~~
でも良いと思います!
先祖を敬う心が大切
美しき日本の未来のために


























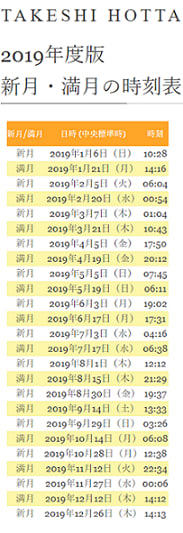






本当にお美しいですね
絵になるじゃありませんか。
このまま額縁に入れて飾っておきたい。
あらまっ ちょっと失礼な表現になりましたか?