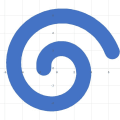2025年02月04日(火)、放送分。
興味ある人は、
NHKの聞き逃し配信から聞いてください。
間違いあれば、
私の聞き間違いか、理解不足です。
また、" " 内は感想だったり私が追記したものです。
興味ある人は、
NHKの聞き逃し配信から聞いてください。
間違いあれば、
私の聞き間違いか、理解不足です。
また、" " 内は感想だったり私が追記したものです。
歴史苦手だし、
人の言葉聞き取るの苦手だし、
大変苦労しました。
古代史の謎〜ヤマト王権の形成 (6)王権の始祖
"初めにキーワード言っときます"
"欠史八代の天皇は実在でないと、
考えられている。"
"崇神天皇も、実在しない天皇と考えられているとのこと。”
"私が思うに、実在の人物に、
伝説を盛ったということなのかもしれないと、
ふと思ったのだが。
ここの研究は学者さんに任せます。"
"ヤマト王権と倭王権の、
言葉の使い分けの基準は、
何処にあるのか?。"
"さて、メモの開始です。"
・ヤマト王権の最初の王が、
どのようなものだったかは、
非常に難しい問題だ。
・3C後半に奈良盆地のヤマトを中心とする、
各地の豪族が前方後円墳を共有する体制を作り上げた。
・その中心がヤマト王権であった。
その盟主は大王だった。
・その大王がどのような人物であったのか、
誰が始祖だったのかを、明らかにすることは、非常に困難。
・そこで、後の時代から見て、
王権の始まりをどのように理解していたのか、
という観点で考えて行く。
・考古学的には論証が非常に難しい。
・文献資料(古事記、日本書紀)は、
奈良時代に編集されたものなので、
作為が入っていることに気を付けなければならない。
・皇統譜は、
ヤマトタケルのところで多少乱れはあるが、
神武天皇から応神天皇までは、
父から子へとほぼ一直線で書かれているが、
仁徳天皇以降は兄弟で継承されている。
・古くは、兄から弟への継承が一般的であり、
同世代がいなくなったら、
下の世代へ継承するという考えがあったので、
応神天皇以前は、
極めて不自然な継承であると言えいる。
・では、応神天皇以降は信用できるかと言うと、
5Cくらいの中国の資料と比較すると、
同族くらいではあるが、兄弟のような近い血縁とは、
必ずしも言えないのではと考えられる。
どのようなものだったかは、
非常に難しい問題だ。
・3C後半に奈良盆地のヤマトを中心とする、
各地の豪族が前方後円墳を共有する体制を作り上げた。
・その中心がヤマト王権であった。
その盟主は大王だった。
・その大王がどのような人物であったのか、
誰が始祖だったのかを、明らかにすることは、非常に困難。
・そこで、後の時代から見て、
王権の始まりをどのように理解していたのか、
という観点で考えて行く。
・考古学的には論証が非常に難しい。
・文献資料(古事記、日本書紀)は、
奈良時代に編集されたものなので、
作為が入っていることに気を付けなければならない。
・皇統譜は、
ヤマトタケルのところで多少乱れはあるが、
神武天皇から応神天皇までは、
父から子へとほぼ一直線で書かれているが、
仁徳天皇以降は兄弟で継承されている。
・古くは、兄から弟への継承が一般的であり、
同世代がいなくなったら、
下の世代へ継承するという考えがあったので、
応神天皇以前は、
極めて不自然な継承であると言えいる。
・では、応神天皇以降は信用できるかと言うと、
5Cくらいの中国の資料と比較すると、
同族くらいではあるが、兄弟のような近い血縁とは、
必ずしも言えないのではと考えられる。
"その資料はなんでしょうか?。"
・古事記と日本書紀とでは皇統譜は一致する。
しかし、継承は政治的な関係で変化しやすいものだ。
古事記と日本書紀の一致は、
同時期に作られたからだという理解の方が説明しやすい。
・古事記、日本書紀の継承関係は、
大変気を付けて扱わなければならない。
・初代天皇は、
日本書紀では、はつくにしらすすめらみこと。
しかし、日本書紀では同盟の人物が2人いる。
・一人めは、神武天皇。
・二人めは、崇神天皇。
・↑なぜ、初めて国を治めた天皇が、
2人いるのか整合的な説明が求められる。
・神武天皇について。
アマテラスの命令で、
地に下ったニニギノミコトのひ孫であり、
筑紫に生まれ、日向加から大和に軍を動かし、
正月に即位したとある。
・↑即位までは書かれているが、
その後はほとんど書かれていない。
・神武天皇の父は神である。
この神ついては、系譜だけで何をしたとか話が全くない。
・母も海の神の娘とあるが、ほかに記述がない。
・しかし、この系譜は興味深い手がかりを提供する。
・神武天皇はアマテラスの5世子孫である。
これはわりあい新しい概念だ。
"律令の時代は古墳時代よりも新しいという意味だろう。"
古事記、日本書紀の成立と同時代の律令には、
天皇よりも6代後になると、
皇族ではないといく決まりがある。
・↑つまり、神武天皇は先祖から、何かを引きつぐギリギリの世代だった。
5代後の子孫だから、ギリギリ天皇になれたという位置づけとなる。
・↑継体天皇も応神天皇からの5代目子孫でギリギリだった。
当時の感覚では5代目までが、継承権があるという感覚だったのだろう。
・↑神武天皇はアマテラスから数えて、5代後以内の子孫であったから、
天皇になれたという意味合いだろう。
・アマテラスと神武天皇の間の、神々に込められた意味あい。
・1代目子孫、アメノオシホミミ。
最初に、葦原中国への天孫降臨を命じられた神。
しかし、さぼったらしい。
・↑それを引き受けたのが、
2代目子孫、ニニギノミコト。
祖母と孫という関係は、古事記、日本書紀編集の初期の段階の8C初頭では、
持統天皇と文武天皇関係と同じ。
・文武天皇は16歳と異例に若く、
周辺の兄弟たちを抑えることが出来るのは、持統天皇しかいなかった。
そこで、持統天皇は譲位して太上天皇になり後見し、
文武天皇を即位させた。
・↑神話に祖母の命令を孫が引き継ぐ物語を書くことで、
現実を正当化させようとした。
・天孫降臨付近の話は、かなり政治的な意図が含まれていたのであろう。
・天孫降臨自体は、世界のあちこちにある話である。
・太上天皇(上皇)は、
現代では政治的に引退して、
政治には関わらないが、
奈良時代ではもう一人の天皇であって、
同じ力を持ち続けた。
なので、天皇と対立し、
なので、天皇と対立し、
王権が分裂する危機が何度かあった。
・ニニギノミコトが結婚したのが、
美しいコノハナサクヤヒメだが、
姉のあまり美しくない、イワナガヒメとの結婚を拒否したので、
人間の寿命が岩のように長くはならず、
花のように短くなったとある。
・3代目子孫、ホオリノミコト、山幸彦である。
つまり、山幸彦が天皇家の先祖であり、
兄の海幸彦は九州南部の異民族である、
・ニニギノミコトが結婚したのが、
美しいコノハナサクヤヒメだが、
姉のあまり美しくない、イワナガヒメとの結婚を拒否したので、
人間の寿命が岩のように長くはならず、
花のように短くなったとある。
・3代目子孫、ホオリノミコト、山幸彦である。
つまり、山幸彦が天皇家の先祖であり、
兄の海幸彦は九州南部の異民族である、
隼人の先祖となると書かれている。
日本列島に住む隼人は、
天皇家に奉仕しなければならないと言う考えが、
7C後半から出てくるが、それを神話的に書いている。
・ホオリノミコト(3代子孫)と、ウガヤフキアエズノミコト(4代子孫)は、
海の上の娘と結婚している。
ニニギノミコト(2代子孫)は、山の神の娘と結婚している。
山と海との結婚を繰り返している。
・↑古代では山や海は人間のいる世界とは、別世界であると考えられていた。
それらとの、結婚を繰り返すことで、
別世界をも支配する存在になると強調している。
・神武天皇即位の辛酉年(かのととりのとし)は、
中国では、
天命が改まり、
新しい王朝が建国されるのにふさわしい、
革命の年であるとされている。
・日本の古来の思想や、中国の思想など、
様々な思想を君合わせている。
・神武天皇から後の8代後までの天皇は、
欠史八代と呼ばれる。
・天皇の神武などの漢字2文字の名前は、
漢風諡号(かんふうしごう)と言い、奈良時代半ばに定められた、
中国風の呼び名である。
つまり、それ以前にはそのような呼び名はなかった。
それ以前は和風諡号が使われていた。
・欠史八代の和風諡号は、
オオヤマトや、タラシヒコという名前が繰り返し使われている。
・↑律令国家成立時の、文武天皇や元明天皇の時代にも、
これらの名は出てくる。
・↑これらの称号は、
7C終わりから8Cはじめによく使われているものであり、
欠史八代にそれらが使われているのは、
欠史八代の和風諡号は、そのころに作られたからという考え方ができる。
・神武天皇以降の欠史八代は、
日本書紀編纂の7C後半~8C初頭に、付け加えられたものであると、
はっきりするわけである。
・崇神天皇について、この時代に日本書紀に記載があるのは、
大神神社(おおみわじんじゃ)の縁起(纏向にある最古の神社)
四道将軍の派遣
箸墓古墳の造営(纏向の近辺)
出雲の神の宝を献上させた
農業のためのため池のを作ること
など。
・↑崇神天皇は纏向と関係が深いと書かれている。
纏向は2C終わりから、3C終わりか4C初めまで続いた遺跡。
・崇神天皇は実在したと言って良いのか?。
四道将軍について。
実在ではなくても、
5C後半に王権と地方豪族を結び付ける役割の人がいて、
日本書紀まで名前を残していたということになる。
・四道将軍は、日本書紀から読むと、
ヤマト政権が軍事力で拡大した読めるが、
3C後半から4Cにかけて、
軍事的に拡大していったとは成り立たない。
(前回までに話したこと)
・四道将軍の話は、
ヤマト政権が各地を支配し、天皇が君臨することを正当化するための、
フィクションであると理解べき。
・崇神天皇は2つの面がある。
始祖の記憶と結びつく、纏向との関係があること。
8C的な天皇支配の正当性を持っている。
崇神天皇は、
この二つを統合して作り出された、
実在しない天皇とみなすべきだろう。
日本列島に住む隼人は、
天皇家に奉仕しなければならないと言う考えが、
7C後半から出てくるが、それを神話的に書いている。
・ホオリノミコト(3代子孫)と、ウガヤフキアエズノミコト(4代子孫)は、
海の上の娘と結婚している。
ニニギノミコト(2代子孫)は、山の神の娘と結婚している。
山と海との結婚を繰り返している。
・↑古代では山や海は人間のいる世界とは、別世界であると考えられていた。
それらとの、結婚を繰り返すことで、
別世界をも支配する存在になると強調している。
・神武天皇即位の辛酉年(かのととりのとし)は、
中国では、
天命が改まり、
新しい王朝が建国されるのにふさわしい、
革命の年であるとされている。
・日本の古来の思想や、中国の思想など、
様々な思想を君合わせている。
・神武天皇から後の8代後までの天皇は、
欠史八代と呼ばれる。
・天皇の神武などの漢字2文字の名前は、
漢風諡号(かんふうしごう)と言い、奈良時代半ばに定められた、
中国風の呼び名である。
つまり、それ以前にはそのような呼び名はなかった。
それ以前は和風諡号が使われていた。
・欠史八代の和風諡号は、
オオヤマトや、タラシヒコという名前が繰り返し使われている。
・↑律令国家成立時の、文武天皇や元明天皇の時代にも、
これらの名は出てくる。
・↑これらの称号は、
7C終わりから8Cはじめによく使われているものであり、
欠史八代にそれらが使われているのは、
欠史八代の和風諡号は、そのころに作られたからという考え方ができる。
・神武天皇以降の欠史八代は、
日本書紀編纂の7C後半~8C初頭に、付け加えられたものであると、
はっきりするわけである。
・崇神天皇について、この時代に日本書紀に記載があるのは、
大神神社(おおみわじんじゃ)の縁起(纏向にある最古の神社)
四道将軍の派遣
箸墓古墳の造営(纏向の近辺)
出雲の神の宝を献上させた
農業のためのため池のを作ること
など。
・↑崇神天皇は纏向と関係が深いと書かれている。
纏向は2C終わりから、3C終わりか4C初めまで続いた遺跡。
・崇神天皇は実在したと言って良いのか?。
四道将軍について。
実在ではなくても、
5C後半に王権と地方豪族を結び付ける役割の人がいて、
日本書紀まで名前を残していたということになる。
・四道将軍は、日本書紀から読むと、
ヤマト政権が軍事力で拡大した読めるが、
3C後半から4Cにかけて、
軍事的に拡大していったとは成り立たない。
(前回までに話したこと)
・四道将軍の話は、
ヤマト政権が各地を支配し、天皇が君臨することを正当化するための、
フィクションであると理解べき。
・崇神天皇は2つの面がある。
始祖の記憶と結びつく、纏向との関係があること。
8C的な天皇支配の正当性を持っている。
崇神天皇は、
この二つを統合して作り出された、
実在しない天皇とみなすべきだろう。
"実在しないとは、言い過ぎでは?と思う。
ありもしない伝説が付けられたり、
ありもしない疑惑が付いたりすることは、
あると思うよ。
崇神天皇以後も、
山ほどあっただろうし、
(例えば戦国武将の逸話とか、
ナポレオンの逸話とか。)
現代でも、山ほどあると思うのだが?。
実例は示せないが。
説得力ないけど。。。"
・ただし、纏向と崇神天皇のつながりによって、
この周辺が倭王権の始まりの地とされているのは、
古くからの記憶によるものと認めても良いのではないのか?。
"倭王権、ヤマト王権?、
違いはなんなのか?。"
"調べる気力が出なかったので、
後の課題です。。。"