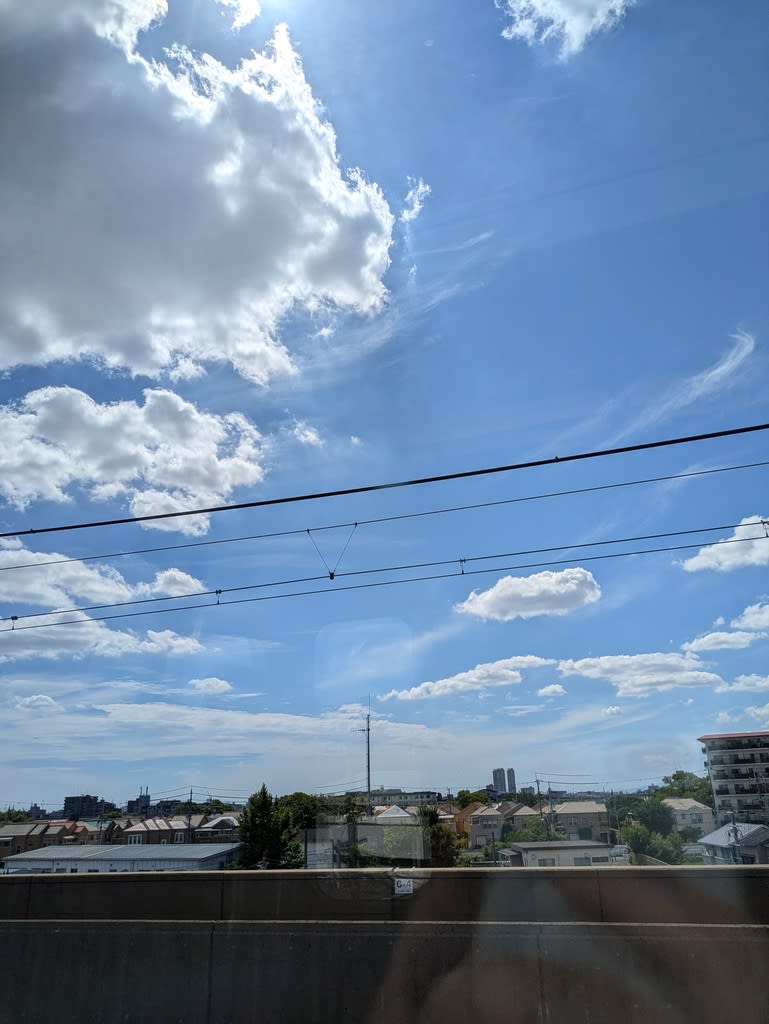ノートに書く日記の話とSNSで人が見えるところに各文章の違いは、日記だと自分しか読まない前提なので、思いついたままに書くことが出来ることだ。SNSだとそうはいかない。例え人にそんなに読んでもらわなくてもいい、とか、独り言レベルで書きたい、と思ってても、やっぱりどこか読んでる人を意識してるものになる。誤解を避けるための文言を付け加えたり、状況を説明したり、違いを区別するための書き方を無意識にでもしようとする。私はそう思いながら書いても、いつもどこかわかってもらえないだろうと思っているので、説明することはどこか諦めている。
諦めていても、表面的なやり取りとしての人付き合いは疎かにしてはいけないと私は思ってる。それは基本的に分かり合えない人でもどこかでは助け合って生きてると思っているからだ。誰かの作った服を着て、誰かの作った食べ物を賜べて生きているとわかっているからだ。誰かの教えてくれた教えを本で読み、テレビやネット記事などの媒体から情報を得て、話を聴いてくれる人に助けられて生きているから。
こういう話をすると、仕事してない人は助け合いしてないから駄目なのか、とか言う人がいる。私は論文を書いているわけではないので、すべての状況を想定して、余すことなく書かないといけないとは思ってないだけで、もちろん仕事してないからといってその人を価値がないとか無視して良い存在とは思っていない。飛躍してしまうけど、哲学の世界で「存在」ということについて掘り下げられているのは言うまでもない。私は哲学の世界に詳しいわけではないけど、自分にだってわかる問題だ。
アドラー心理学でもそういうのは出てくる。他人を認めるために条件を満たしたから人を褒めるのではなく、それが出来るように励ますということ、それは、出来ていなくても存在が認められているということだ。条件付きの承認ではなく、条件がなくても相手の存在を認め、与えていくことが奨励されている。私はアドラーと誕生日が同じなせいか、この考え方にはとても共感できる。そうはいっても、アドラーの考えのすべてに同調するわけではないが。
それ以前に、アドラー心理学は解釈が難しいのか、引用して書く人によって中身が違って見える気がする。一応私はアドラーが書いた神経症に関する本を読んたことがあるのだけど、神経症という言葉にも自分は何故か親和的なところがあった。それはそれ以前に加藤諦三さんの本を読んだりもしていたからだ。加藤諦三さんの本はコンビニで売っていたのをなんとなく買ってみたのが初めての出会いだったのだけど、はじめははっきり言ってそこまて意味を深く考えていなかったし、正直よくわからない部分もあった。やたら何度も「神経症の人は」という言葉が出てきて、神経症という言葉の意味はわからなかったけど、神経質なまでに繰り返されるその言葉のせいで「この人が神経症なのではないの?」と、勝手に思ったりしていた。
でも、自分が人生ですごく挫折したと感じた時、その繰り返されていた言葉が急に自分に響くものになった。その加藤諦三さんが繰り返していた神経症という言葉について書いているアドラーに、私が勝手に縁のようなものを感じたのは不思議なことではないと思う。
そうはいっても、私はいい加減なので、自分が共感できる部分をもってなんとなくわかった気になっているに過ぎない。だからアドラーであっても加藤諦三さんであっても、言ってることには同調できないようなものもある。でも自明なのは、私が読んでいた神経症の本では、人生でいろんな状況に遭遇して悩んだり不適応を起こす人々について書かれたものが、自分にも覚えがあるようなことが多く、それがとても納得できるような解説がされていたので、私はこの人の視点は理解できるように思っている。
SNSでは様々な人が自分の遭遇したつらい状況や、そこでおったトラウマの辛ささや回復の大変さについて書いている。自分の経験したことについて、言葉にして言えたり説明できたりすることは、回復の程度の一つの指標と言えると思う。それでも、それを言葉にするのは難しい。わかっていてもそれを言葉にすることには大変な苦痛が伴う。それは、他人に理解できないことへのおそれや恥の気持ちがあるからだ。そういうのには無頓着な人は理解をしめさず酷い言葉を投げつけたりすることも時にはある。自尊心が崩れてしまった状態ではそういった言葉はものすごく酷いダメージになってしまうし、そうでなくても、自分で言いたくないような類のものもある。誤解をされると自分自身のイメージが酷く脅かされることになったり社会的ダメージを受けるかもしれないことについて、それが難しいのは言うまでもない。逆に言うと、他人の評価に無頓着だったり自分の気持ちを言うことに抵抗がない人にとってはそこまでの苦しみはわからないかもしれないと思う。わからないだろうと思ってしまうからこそ苦しむのだと思う。
また、誰かに助けを求めていても何度もわかってもらえない経験をしたり、無視されたり軽視されたりを繰り返すと、余計に話せないものになっていってしまう。だから私は人の話は基本的に聴くことにしているし、わからなくてもその人の苦しみ自体をとりあえずは疑わないようにしている。その人の辛さを認めることは、その人の存在を認めることだと思う。それで回復出来たり問題が解消することはかなり多いと思う。それなのに、そういったことはとても得ることが難しかったりする。
中途半端だけど、ここで一旦終わっておく。