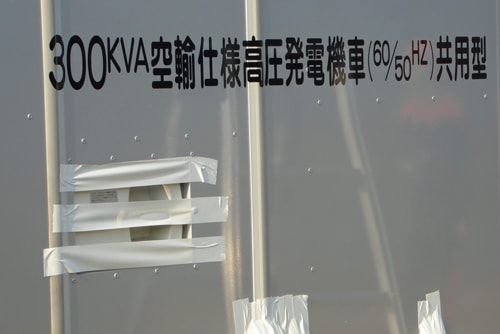最近の更新について、某団体のイインチョ様からお電話にて「内容がマニアックすぎて理解し難い」というご指摘を態々いただきました。今回はサルでも解る、緊急車両ネタで進めていきますので、どうぞお付き合いください(笑)
緊急車両と申しましても、今回ご紹介する車両は長野県総合防災訓練会場で撮影したNTT東日本長野支社が保有する「非常用電源車(公共応急作業車)」です。
非常用電源車とはガスタービンで交流発電機を駆動させ、対象施設に電力を供給する車両です。発電出力は車両の大きさによって異なり、今回紹介する車両は出力が1000kVA、電圧が最大で6600Vの定格性能です。燃料は入手・取り扱いが容易だと思われる軽油を使用しています(A重油や灯油も使用可)。
ガスタービンと発電機、その間に介された減速機は共通架台に設置され、車両に架装されています。他にはガスタービン用の吸気装置、吸気用消音装置、排気装置、排気用消音装置、軸受潤滑油用冷却機、始動用発電機、整流器、制御盤、配電盤、内部換気装置、給電部、給電ケーブル用リール、駐車用ジャッキ等の機器が設置、架装されています。
ちなみに新車で導入されたガスタービン等の主要機器は必ずしも新製されるとは限らず、載せ換えられて長年にわたり、使用されることもあるようです(2006年製のPJ-車台に1973年製のガスタービンが架装されている例もあり)。
なお、車両の内部(発電装置)は撮影しておりませんので、取り上げる内容は車両外観のみとなりますが、後述のリンク先のサイトで内部が確認できます。ただし中古車取扱業者のサイトですのでリンク切れになっている場合があります。
2011年に長野県総合防災訓練で撮影した「NTT東日本 非常用電源車」
いすゞGIGA(KC-CXH81P1)をベースに日本フルハーフ製のアルミボディ構造を利用し、発電装置はHIHジェットサービスの「ガスタービン発電」システムを搭載。最終的な架装をヤシカ車体が行っています。

ベースとなるGIGAは型式が示すとおり初期型でフロント22.5インチ、リア17.5インチのホイールを装着する異径4軸車(8×4)。非常用電源車は低床構造が用いられることが多く、当時のシャシ構成からするとこれが最適だったのでしょうか。GVWを20t以内に抑えた構造(W/B)で、前後軸と後前軸間に発電用の機器類を架装するという独特のスタイルに興味がそそられます。
車両のバッテリーやエアタンクといった補機類が見当たりませんが、キャブと主荷台との間に設けられた小さめの箱部分に補機類を移設、またスペアタイヤや車載工具等が積載されているものと推測します。

車両右側(運転席)に設置された機器類の状況です。一見すると冷凍車の冷凍機のようにも見えますが、これはガスタービンと発電機の間に介された減速機の軸受を潤滑させるための油を冷却する油冷却機(オイルクーラー)です。写真でも判るとおり設置はシャシを介した方法ではなく、荷台床面から吊り下げられており、通常の箱車構造とは違い床面は強化されているものと推測します。
フェンダーとオイルクーラー間には僅かながらサイドバンパーを設置。その奥側には駐車時にタイヤの変形を防ぐことを目的としたジャッキが設置されています(発電時の車両安定用ではないのか)。ジャッキは左右・前後に4ヶ所設置されています。

車両左側(助手席)に設置された機器類の状況です。車両前方から駐車用ジャッキと荷室内進入用ステップを兼用したサイドバンパーを設置。スペースのほとんどを燃料タンクが占めています。車両用(走行用)燃料タンクは約100Lほどでしょうか。装置用(発電機用)燃料タンクは370Lの容量があり、燃料配管には筒状のストレーナーが設置されています。ちなみに車両用にもストレーナーが設置されていますが写真では判明できません。また車両用燃料タンクの保持方法に特徴がありますね。初めてみました。
2013年に長野県総合防災訓練で撮影した「NTT東日本 非常用電源車」
こちらはいすゞGIGA(QKG-CXY77AJ-QX-M(W/B区分のQは推測))をベースに発電装置はMEIDEN(明電舎)の「GV型ガスタービン発電」システムを搭載。最終的な架装をコーワテックが行っています。発電運転時にはガスタービン用の空気を取り込めるよう、天井の前方が開放されるようになっています。
余談ですが、コーワテックは自社でバン型ボディをイチから製造しているのでしょうか…一部の製品(車両)に限った話でありますが、箱の裾や角といった部分を気にしていると「既製品のボディパーツを流用しているのではないのかな…」と思ってしまいますがいかがでしょう。裾の構造も車両によって異なり、ビス止めもあればボルト止めもあります。個人的にかなり気になる点ですので今後も観察を続けましょうか。

ベースとなるGIGAは型式のQKG-が示すとおりポスト新長期規制適合車でタイヤサイズはフロント275/70R22.5、リア245/70R19.5を装着する低床3軸車(6×4)。これらのタイヤサイズや前面に“20t超”の表示がないことからGVW20t車であると思われます。こちらも低床構造となっており、非常用電源車の基本姿勢であると思われます(GVW25t車を除く)。

NTT災害用伝言ダイヤル…等の文言が表記された後方上部はガスタービンから排出されたガスを排気する排気口が設置されています。二段構造となっており、発電運転時にはこの部分が開放すると思われます。そのためリアカメラ本体の設置位置も車体中間部となっています。

先の車両とは違い、車両右側(助手席)には排出ガス処理装置とバッテリーがW/B間を占めています。潤滑油用の油冷却機が見当たりませんが、荷室内に設置されている若しくは、明電社製は不要となるシステムなのでしょうか。気になります。

バッテリーは車両機関始動用(24V)と発電機関始動用(48V)とが供用と思われます。メーカーサイトによれば「ガスタービン専用(DC48V…)」と記されていましたが、車両外観からは車両機関始動用バッテリーが見当たらず、この配置(12V×4)から供用されているのではないかと推測。またリレーボックスが手前のバッテリー前に設置されていることも大きな推測理由です。
またサイドバンパーはバッテリーの交換時に引き出せるよう、手前に折りたためるように加工されており、整備のことも考えられた仕様となっています。バッテリーの奥には駐車用ジャッキも見えます。

同じく車両右側、ROH部分の構造です。こちらも駐車用ジャッキと輪留め収納部分が設置されています。後輪用スペアタイヤ(19.5インチ)とその上部両側にはジャッキの油圧発生装置と思われる機器が設置されています。前輪用スペアタイヤ(22.5インチ)は車両左側ROH部分に設置されています。またスペアタイヤキャリア上にはリレーボックスらしき箱が見えます。ちなみにチラっと見えていますがエアサス仕様です。

車両左側(助手席)には前方から尿素水タンク、走行用(車両用)燃料タンク、発動発電機用(装置用)燃料タンクが架装されています。燃料タンクはそれぞれ300Lの容量かと思われます。
メーカーサイトからの引用となりますが、発電時の燃料消費量は一時間あたり480Lとのことで、連続運転時には途中給油が必要となってきます。この消費数値はA重油で100%負荷運転時の数値であり、燃料の発熱量によって異なるようです。ちなみに連続運転は72時間以内だそうです。
インターネット上で拾ってきた情報を主に「非常用電源車」の紹介をしてきましたが、詳細は下記のリンク先(コピペしてね♪)を参考にしてください。
▼昭和47年から基本的なスタイルが変わっていない。

日本ガスタービン学会「1000kVAガスタービン移動発電装置」
http://www.gtsj.org/gasturbin/gallery/g_0106.html
▼中古車販売業のサイト。内部詳細写真有。
関東トラック販売「H18/6 いすゞギガPJ-CYZ51Q6J 移動電源車」
http://www.kanto-truck.com/Photo/2013070049.html
▼今回、一台目に取り上げた車両と同じ仕様だと思われる。
ヤシカ車体「電話用非常電源車」
http://www.yashika.jp/article/13977788.html
▼電源車と制御車の二台セットでの運用。電源車は低床4軸。制御車は中型3軸。
ヤシカ車体「非常用移動電源システム」
http://www.yashika.jp/article/14880877.html
▼ショートキャブ低床4軸車と中型3軸車(FVZ)
IHIジェットサービス「4500kVA級 ガスタービン電源車 IM-400 MGG」
http://www.ihi.co.jp/ijs/catalog/IM400.pdf
▼今回、二台目に取り上げた車両はこのサイトを参考にした。
明電舎「GV型 明電移動電源車」
http://www.meidensha.co.jp/catalog/jp/cb/cb38-2735e.pdf
▼内部構造のイラストやガスタービンの利点が書かれている。
川崎重工業「移動電源車(カワサキMPUシリーズ)」
http://www.khi.co.jp/gasturbine/product/industry/move.html
▼主要諸元や搭載品、またジャッキは安定用というより、駐車用であるとの記述も。
川崎重工業「第161号 ガスタービン・ジェットエンジン特集号(移動電源車NTTドコモ向け)」
https://www.khi.co.jp/rd/tech/161/nj161ts02.html