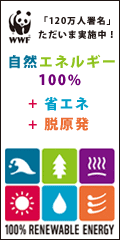日本の政治経済的課題(その4- - -1970年代の総括(2))
前回に引き続いて、1970年代の総括を続けます。日本は脅威の成長がまた復活できると信じて、政界、官庁、産業界とも知恵を絞りますが、当然のことながら、世界第2の経済大国の問題点は、アメリカもOECDも看過してはくれず各種の圧力がかけられたのです。お金は使い方によっては暴力になります。日本人として世界への影響を常に考える態度が必要です。見方によっては、アメリカについで2番目に、世界で暴力を振るう危険性を日本は持っているのです。著者は続けます。
”1970年~1971年の期間の日本の反応はヒステリーであった。いざなぎ景気で日本の脅威の成長の機械が停止したことを日本人は誰も理解していなかった。1969年に円を切り上げずに緊縮政策を取り、経済を成長路線に戻す為に、その障害になる全ての政策をやめた。日本だけでなく、ドイツと他のヨーロッパ諸国におけるドルを防衛する為の、外国為替市場での介入の結果、国際市場での通貨が急速に増大した。アメリカはニクソン大統領の下で国際社会に対して全く無責任に振る舞い続けた。貿易収支を改善する為には、輸出と代替輸入を増やすべく資源を自由にする為に、国内需要を抑制することが必要なことは良く知られている。しかし財政抑制と金融引き締めの政策を採用するどころか、ニクソン政権の政治は1972年の再選挙にのみ焦点を当てて、より一層放漫になった。税金は下げられ消費は増加し、利率は下げられた。貿易収支の赤字は減るどころか更に増えた。アメリカは世界にドルを注ぎ続けた。1970年の終わりから1973年初めまでの間に、国際通貨の流動性は2倍になった。円の切り上げにも拘らず、日本の経常収支は増加し続けた。表面的にはその理由は、世界規模の国際市場での通貨の増大により作り出された1972年~1973年の世界需要の増加であった。Bretton Woodsの固定外国為替システムの崩壊に続いて、最初の世界規模の大きな同期したブームが起こった。そこでは全ての大国の経済が同時に拡大したので、その需要の増加は記録的なものだった。”
”円の切り上げを抑える為になされた金融刺激は、1950年代1960年代の様に、脅威の成長機械を再スタートさせなかった。そこで政府支出である財政支出により、さらに財政刺激が行われた。均衡財政は1965年に放棄された(国債発行を禁止する法令は廃止された)が、1970年までの国債発行は、ごく抑えられたものであった(1970年で国債残高2.8兆円)。(この時点を境にして、日本は国債発行を漸増的に続けていくことになる)1971年佐藤内閣は前例のない1650億円の減税を発表した。1971年12月のSmithsonian Agreementに続いて、佐藤内閣は政府消費を22%増やし、公的投資を32%増やした。1972年7月に、田中首相は、年率で10%GNPを増やすことを目標にした日本列島改造論をもって、佐藤内閣を引き継いだ。同時に国際的にも、日本の構造的な経常収支の黒字の状態が続いていたので、日本のに対しての国際的な圧力が、繊維品の様な個々の貿易カテゴリから、一般貿易やマクロ経済政策に至るまでの問題に広げられたのである。1972年にはOECDさえもが、日本に1973年度は膨張政策を取るように要求した。ニクソンショックと円の切り上げを経験したにも拘らず日本の経常収支の黒字は減る気配がなかった。その故に田中内閣は1972年10月補正予算を組んで公共工事予算を更に増やした。1973年の予算は、(1972年10月補正予算を含んだ)1972年の合計予算に基づいて作られたが、政府消費は25%、投資はほぼ30%増やされた。会計と金銭の過剰の結果は予想されたものではなかった。それは、成長を加速するより、インフレを加速した。それはまた1つの新しい悪現象を生み出した。(ドルを守るために金を余らせ、金利を、再度、安くした1980年代にも出てくることになる)資産インフレである。ローンが豊富で安くなった時に、設備投資の必要がないので、土地と株式市場に投機する為に金を借りる競争が生じたのである。土地の購入のラッシュは田中内閣の列島改造論にも煽られて、開発が予定されている地域での土地の購入競争に発展した。資産投機は、不動産会社だけに留まらず、貿易、建設、投資会社、銀行、からさらに個人にまで広がった。製造メーカーは製品を作るより、財政資産を投機から儲けることに使ったのである。対象は土地だけではなくなった。会社は、他の会社の株式を購入する為にお金を借り始めたのである。さらに株式市場への投機で得た、資本利得は、営業利益とともに会社利益に計上できたから、株式市場の株式価格の上昇そのものが、会社の利益を押し上げ、それがまた株式市場の株式の価格の上昇を加速した。1972年3月と1972年12月の間に日経平均株価は66%上がった。工場のプラントや設備への投資ではそんなに短期間にそれほど多く儲けることはできなかったであろう。日本の宣伝の行き届いた貿易上の譲歩とこの野心的な経済刺激策もSmithsonian Agreementの固定外国為替制度の救済計画の崩壊を防ぐことは出来なかった。1973年2月13日、ドルは SDR (IMFのSpecial Deposit Receipts- - 外国通貨を一括したもの) に対して10%下げられた。そして円を含む全てのメージャな通貨は、ドルに対して浮動させられたのである。円は素早く 280円/ドル に上がった。日本とドイツの刺激策はドルを救うことは出来なかったけれども、経済が大きく過熱することを防ぐことには成功した。1970年~1971年のリセッションはニクソンショックの時に底をつき1972年の中ほどまでの1年間にはGNPは10%に加速した。しかしこれは今までとは異なった種類の成長だった。生産と製造能力が同じ率で上昇するというのではなく、製造能力一杯まで現存の余分の製造能力を使い切って生産を増やした結果であった。需要の圧力がかなり増えインフレを加速したのである。脅威の成長機械は、もはや10%の年率でGNPを増やすことは出来なかったのである。神武景気の末(1957年)の時の様に、1973年の夏ごろまでには、設備の不足とボトルネックが経済を息切れさせていた(throttlingさせていた)のである。発電所は需要の電力を賄えなかった。旱魃の結果、水でさえも不足した。石油化学の工場はその限度を超えて操業された結果、数多の爆発や事故を生んだ。これが全てではなかった。1972年~1973年の世界の同期的な経済のブームは原材料の世界規模の不足を生んだ。最初は建設材料、セメント、木材、鋼、しっくい、に集中したがすぐに紙やプラスティックにまで広がった。異常な気象条件が同時に世界の食料生産に打撃を与え、小麦、大豆、コーヒー、砂糖や綿花の供給を減少させた。ニクソン大統領はアメリカの食料品の価格を下げる為に穀物輸出を減らしたのが更に事態を悪化させた。物資の不足は供給品の争奪を生み投機の買いや隠しを生み、事態を更に悪化させ、価格を更に吊り上げる結果になった。土地と株式への投機に過剰で低利率の金を投資してきた日本の会社は、今度は投機的な原料買いや隠しに方針変更した。1972年~1973年に、日用品の価格は、世界的に、劇的に上がった。その結果各国は自国のインフレに、輸入したインフレを加えることになった。日本国内のインフレは大抵のOECDの加盟国より悪かったが、世界インフレを輸入した結果は災害的であった(1972年は12%、1973年は24%のインフレであった)。1973年の3月頃には、日本政府は警戒を強めていたが、この問題に対して強力な対策を講じることが出来なかった。過度の流動性を正す唯一の試みも、不動産取引への融資に対するの抑制であったが、お座なりなものであった。経済企画庁は ’市場を囲い込み物資を隠す試み’ を防止する法律 を 作ったが、その法律は、既にその行為を行っていた大企業を抑える というよりも 中小企業の自殺の可能性を 増やすことになってしまった。大企業は、常に政治家や官僚と手を携えてやって来た。政府は法律を通すことによって、ひとかどのことをするという表示はするが- - -しかし効果的に実現されたものは1つも無かった。これが日本政治のやりかたであった、あるいは、日本人はその様に信じるようになって来た。”
前回に引き続いて、1970年代の総括を続けます。日本は脅威の成長がまた復活できると信じて、政界、官庁、産業界とも知恵を絞りますが、当然のことながら、世界第2の経済大国の問題点は、アメリカもOECDも看過してはくれず各種の圧力がかけられたのです。お金は使い方によっては暴力になります。日本人として世界への影響を常に考える態度が必要です。見方によっては、アメリカについで2番目に、世界で暴力を振るう危険性を日本は持っているのです。著者は続けます。
”1970年~1971年の期間の日本の反応はヒステリーであった。いざなぎ景気で日本の脅威の成長の機械が停止したことを日本人は誰も理解していなかった。1969年に円を切り上げずに緊縮政策を取り、経済を成長路線に戻す為に、その障害になる全ての政策をやめた。日本だけでなく、ドイツと他のヨーロッパ諸国におけるドルを防衛する為の、外国為替市場での介入の結果、国際市場での通貨が急速に増大した。アメリカはニクソン大統領の下で国際社会に対して全く無責任に振る舞い続けた。貿易収支を改善する為には、輸出と代替輸入を増やすべく資源を自由にする為に、国内需要を抑制することが必要なことは良く知られている。しかし財政抑制と金融引き締めの政策を採用するどころか、ニクソン政権の政治は1972年の再選挙にのみ焦点を当てて、より一層放漫になった。税金は下げられ消費は増加し、利率は下げられた。貿易収支の赤字は減るどころか更に増えた。アメリカは世界にドルを注ぎ続けた。1970年の終わりから1973年初めまでの間に、国際通貨の流動性は2倍になった。円の切り上げにも拘らず、日本の経常収支は増加し続けた。表面的にはその理由は、世界規模の国際市場での通貨の増大により作り出された1972年~1973年の世界需要の増加であった。Bretton Woodsの固定外国為替システムの崩壊に続いて、最初の世界規模の大きな同期したブームが起こった。そこでは全ての大国の経済が同時に拡大したので、その需要の増加は記録的なものだった。”
”円の切り上げを抑える為になされた金融刺激は、1950年代1960年代の様に、脅威の成長機械を再スタートさせなかった。そこで政府支出である財政支出により、さらに財政刺激が行われた。均衡財政は1965年に放棄された(国債発行を禁止する法令は廃止された)が、1970年までの国債発行は、ごく抑えられたものであった(1970年で国債残高2.8兆円)。(この時点を境にして、日本は国債発行を漸増的に続けていくことになる)1971年佐藤内閣は前例のない1650億円の減税を発表した。1971年12月のSmithsonian Agreementに続いて、佐藤内閣は政府消費を22%増やし、公的投資を32%増やした。1972年7月に、田中首相は、年率で10%GNPを増やすことを目標にした日本列島改造論をもって、佐藤内閣を引き継いだ。同時に国際的にも、日本の構造的な経常収支の黒字の状態が続いていたので、日本のに対しての国際的な圧力が、繊維品の様な個々の貿易カテゴリから、一般貿易やマクロ経済政策に至るまでの問題に広げられたのである。1972年にはOECDさえもが、日本に1973年度は膨張政策を取るように要求した。ニクソンショックと円の切り上げを経験したにも拘らず日本の経常収支の黒字は減る気配がなかった。その故に田中内閣は1972年10月補正予算を組んで公共工事予算を更に増やした。1973年の予算は、(1972年10月補正予算を含んだ)1972年の合計予算に基づいて作られたが、政府消費は25%、投資はほぼ30%増やされた。会計と金銭の過剰の結果は予想されたものではなかった。それは、成長を加速するより、インフレを加速した。それはまた1つの新しい悪現象を生み出した。(ドルを守るために金を余らせ、金利を、再度、安くした1980年代にも出てくることになる)資産インフレである。ローンが豊富で安くなった時に、設備投資の必要がないので、土地と株式市場に投機する為に金を借りる競争が生じたのである。土地の購入のラッシュは田中内閣の列島改造論にも煽られて、開発が予定されている地域での土地の購入競争に発展した。資産投機は、不動産会社だけに留まらず、貿易、建設、投資会社、銀行、からさらに個人にまで広がった。製造メーカーは製品を作るより、財政資産を投機から儲けることに使ったのである。対象は土地だけではなくなった。会社は、他の会社の株式を購入する為にお金を借り始めたのである。さらに株式市場への投機で得た、資本利得は、営業利益とともに会社利益に計上できたから、株式市場の株式価格の上昇そのものが、会社の利益を押し上げ、それがまた株式市場の株式の価格の上昇を加速した。1972年3月と1972年12月の間に日経平均株価は66%上がった。工場のプラントや設備への投資ではそんなに短期間にそれほど多く儲けることはできなかったであろう。日本の宣伝の行き届いた貿易上の譲歩とこの野心的な経済刺激策もSmithsonian Agreementの固定外国為替制度の救済計画の崩壊を防ぐことは出来なかった。1973年2月13日、ドルは SDR (IMFのSpecial Deposit Receipts- - 外国通貨を一括したもの) に対して10%下げられた。そして円を含む全てのメージャな通貨は、ドルに対して浮動させられたのである。円は素早く 280円/ドル に上がった。日本とドイツの刺激策はドルを救うことは出来なかったけれども、経済が大きく過熱することを防ぐことには成功した。1970年~1971年のリセッションはニクソンショックの時に底をつき1972年の中ほどまでの1年間にはGNPは10%に加速した。しかしこれは今までとは異なった種類の成長だった。生産と製造能力が同じ率で上昇するというのではなく、製造能力一杯まで現存の余分の製造能力を使い切って生産を増やした結果であった。需要の圧力がかなり増えインフレを加速したのである。脅威の成長機械は、もはや10%の年率でGNPを増やすことは出来なかったのである。神武景気の末(1957年)の時の様に、1973年の夏ごろまでには、設備の不足とボトルネックが経済を息切れさせていた(throttlingさせていた)のである。発電所は需要の電力を賄えなかった。旱魃の結果、水でさえも不足した。石油化学の工場はその限度を超えて操業された結果、数多の爆発や事故を生んだ。これが全てではなかった。1972年~1973年の世界の同期的な経済のブームは原材料の世界規模の不足を生んだ。最初は建設材料、セメント、木材、鋼、しっくい、に集中したがすぐに紙やプラスティックにまで広がった。異常な気象条件が同時に世界の食料生産に打撃を与え、小麦、大豆、コーヒー、砂糖や綿花の供給を減少させた。ニクソン大統領はアメリカの食料品の価格を下げる為に穀物輸出を減らしたのが更に事態を悪化させた。物資の不足は供給品の争奪を生み投機の買いや隠しを生み、事態を更に悪化させ、価格を更に吊り上げる結果になった。土地と株式への投機に過剰で低利率の金を投資してきた日本の会社は、今度は投機的な原料買いや隠しに方針変更した。1972年~1973年に、日用品の価格は、世界的に、劇的に上がった。その結果各国は自国のインフレに、輸入したインフレを加えることになった。日本国内のインフレは大抵のOECDの加盟国より悪かったが、世界インフレを輸入した結果は災害的であった(1972年は12%、1973年は24%のインフレであった)。1973年の3月頃には、日本政府は警戒を強めていたが、この問題に対して強力な対策を講じることが出来なかった。過度の流動性を正す唯一の試みも、不動産取引への融資に対するの抑制であったが、お座なりなものであった。経済企画庁は ’市場を囲い込み物資を隠す試み’ を防止する法律 を 作ったが、その法律は、既にその行為を行っていた大企業を抑える というよりも 中小企業の自殺の可能性を 増やすことになってしまった。大企業は、常に政治家や官僚と手を携えてやって来た。政府は法律を通すことによって、ひとかどのことをするという表示はするが- - -しかし効果的に実現されたものは1つも無かった。これが日本政治のやりかたであった、あるいは、日本人はその様に信じるようになって来た。”