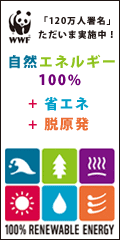日本の政治経済的課題 (その6- - -1980年代(その1) )
ここで、第2次オイルショックを経て1980年代に入ります。著者は続けます。
”1970年代が終わりに近づいた時やっと時代は落ち着いて来た様に見えた。過剰な生産能力は徐々に減らされ投資は回復していた。成長は加速し国際収支の黒字は減少し始めた。インフレは適当なレベルに下げられ来て、もう一度国家予算の赤字を減らすことを考え始めることが可能であった。しかしながらこの時にまた不幸な運命が介入することになった。イラン革命とイラク-イラン戦争が石油の供給を大幅に減らしたのである。1979年から1980年にかけて石油の価格は3倍になった。世界経済は10年間に2度目の石油価格ショックに襲われたのである。1980年代は為替市場と財政市場の混乱の著しい時代であった。この10年間の初期の3年間は(1970年代の後書きとも言うべき)第2次の石油価格の上昇に支配された。この時期、日本経済は第1次の石油価格の上昇の時期より遥かに巧く、また他の大国よりも巧く、機能した。中間期の3年間は、日本は、アメリカのレーガン大統領の供給者側の経済学(supply-side economics=Reaganomics)(供給側重視の経済学)によって箍(たが)をはずされた:即ち日本経済は再び急速なアメリカの需要の成長に引っ張られたのである。しかし1985年にドルはピーク(260円/ドル)に達し、1987年には、ドルの価値は円に対して半分(130円/ドル)になってしまった。
これを境にアメリカは世界を牽引することが出来なくなった。日本は、貿易戦争を恐れてその構造的貿易黒字の是正に循環的なリフレーション(*日本の政治経済的課題 (その5)の注記参照)という緩和策で対応した。日本の国家予算の赤字は心配なほど大きく、リフレーションの重荷は、安価なお金の上に投げられたのである。1980年代の後期には日本経済は、貸し出し限度額が大幅に上げられ、今までかってなかった様に簡単にお金は借りられ金利も安くなったのである。これが”バブル”経済を生み出し、”バブル”経済は1990年に破裂し、多くの著名人のスキャンダルを露呈したのである。”
この時代の分析を著者は以下の様に続けます。
”第2次オイルショック”が襲った時、日本は、第1次オイルショックの時より遥かに良く備えが出来ていた。1978年のボンのサミットで、日本とドイツはその経済を刺激して世界の経済成長を進行させる様に説得された。その年日本は、輸出金額は1%以下の増加で、輸入金額は8%増加したにも拘らず、約6%のGNP成長を成し遂げた。(日本政府の経常収支の黒字の減少はGNPのほぼ1%を切り落としたのに)
1979年の経済サミットでは、日本はもう悠々としていた。1979年の中頃には、日本政府は上昇しているインフレーションを抑える為に会計的にも、金銭的にもブレーキをかけるのが安全だと感じていた。1970年にGNPの4.6%に達していた予算の赤字に取り組むべく、18年間で最も厳しい予算を作成した。この時期を得たデフレーションが日本経済を第2次オイル価格上昇に備えさせたのである。第2次オイル価格上昇は第1次よりは緩いものであった。第1次の場合は、1972年と1974年の間で石油価格は5倍になった。第2次は1978年と1980年の間でそれは2倍と少しであった。しかしその最初の値上がりは(1978年)にはもっと高かったので、日本の輸入価格への影響は同じように高かった。高い石油価格は、価格に転嫁されるのではなく、主に、低い利益と2回目となる実質賃金の減少によって吸収されたのである。1973年のオイル価格上昇に続く2年間で卸売り価格、消費者価格と時間当たり賃金は約40%上がった。第2次オイル価格上昇に続く2年間で卸売り物価は22%、消費者物価は14 %、時間当たり賃金は約13%上がった。円の交換レートは暫く下がったがその後回復した。1972-1974年の日本のインフレーションは英国とほぼ同じくらい悪かったが、ピークの1年は25%になった。1978年-1980年の日本のインフレーションはドイツよりも良く10%以下であった。高いオイル価格のコストを低い賃金と利益で吸収して、日本の輸出はより競争力がついた。貿易条件が悪化して日本の経常収支はなお赤字であったが貿易収支は大きく改善した。結果として、行動は力強く、経済はリセッションに陥ることなく、成長が少し緩くなっただけであった。他の国は日本の良い運営状態を敬服はしなかった。そして特に彼らの市場への日本の侵入を嫌った。例えば日本の自動車の輸出は1980年の4月までの12ヶ月で50%増えた。一方アメリカとイギリスの自動車の生産は1/3減った。ヨーロッパとアメリカは、もし日本が ’自主的に’ 減らさなければ、日本の自動車を締め出すと脅した。自主的な自動車の輸出規制は受け入れられた。そして1981年5月から日本はアメリカに輸出される自動車の数を制限したのである。従って日本の自動車業界は上層の市場を狙った。直ちに彼らは台数は少ないがより高価な車を輸出し始め、継続して輸出の金額を増やしたのである。他の製品にも同様な事を行うことになり、1982年の初めには、日本は、アメリカとヨーロッパへの輸出の1/3は何らかの自主規制を受けていると主張した。輸出はなお増加した。日本はアメリカとヨーロッパを第3世界から締め出した。そこで外国からの攻撃は日本の閉ざされた輸入市場に向けられた。1981年12月には、日本の通産相 河本敏夫は、'日本は貿易戦争の瀬戸際にある' と警告していた。1982年~1984年に亘って実施予定のGATTラウンドの関税削減の年度毎の予定は、1982年の4月1日に前倒しにされた - - がこれだけでは十分でなかった。1982年6月のベルサイユサミットでのトラブルを心配して、日本は更なる貿易自由化対策を提供した。いや諸外国を鎮静させる対策と言ったほうが良いかもしれない。そのパッケージは1983年4月からの119項目に関する関税カットと更に96項目に関しての関税の撤廃を含んでいた。日本は、”輸入手続きは簡素化され輸入は加速されるであろう。輸入の分配に制約を加えることはしないように努める。貿易上の不平を解決する為にはオンブズマンを任命し、外国は 日本が将来の規則を作るときには、発言権を持つようにする。”
巧みな言葉だった。また印刷物も良くそれがもっと効いた。貿易の自由化対策は、輸入の増加を加速するのに殆ど役立たなかった。そこで外国の非難は、日本の輸入現場の最前線の貿易障害から国内経済の不公正なやり方に,焦点を移した。ロナルド・レーガンがアメリカ大統領に当選し、1981年にホワイトハウスに供給側の政策をもたらした。
アメリカの新しい行政府は減税に乗り出したので、レーガノミックス(Reaganomics)は、厳しく押し詰められた日本の救済になった。供給者側経済論者は、この政策は急速な成長とより高い貯蓄を奨励し、その故に税による歳入を増やすと主張した。出費の削減と合わせて、行政府は1983-1984年までに連邦予算を収支均衡にすると予測した。大抵のアメリカ人と同じ様に、供給者側経済論者は、外国のことについては考慮せず、減税がドルとアメリカの国際収支に及ぼす影響を無視した。これは致命的な間違いであった。この減税は、税引き後の借金のコストを下げ、貸し出し限度額の引き上げの需要を増やした。連邦準備銀行は、その強力な議長のフォーカー(Paul Volker)の下で、マネーサプライの増大を抑え、インフレーションと戦う為に利率を高くした。レーガンの安易な減税策とフォーカーのタイトな財政策とが組み合わされた。これが、1980年に為替市場の制御が排除された日本からではないが、外国からの資金の流入を呼び込んだ。ドルの価値は急上昇した。1980年の第3四半期から1981年の第1四半期の間に他の通貨に対して平均60%上がった(しかし円に対しては20%だけだった)。アメリカの製造者は、世界市場から価格の点で追い出され、外国からの輸入が押し寄せた。1981年と1985年の間に
、アメリカの経常収支は、GNPの0.2%(70億ドル)の黒字からGNPの3%(1220億ドル)の赤字になった。経済成長は、楽観的に、年率5%と予測されていた。国内需要は4%を少し下回って、悪化した貿易収支のせいで、GNPの成長は3%に達しなかった。1981年~1985年の間のアメリカ人の異常な消費の1/4は追加的な輸入に費やされた。したがってこの消費によって作られた収入の1/4は外国人によって稼がれたのである。この収入への税金は外国へ逃げてしまった。それは、輸出がドルの強さによって急に増大したドイツと日本の政府に行ったのである。アメリカの歳入は減ってしまったのである。アメリカの連邦予算の赤字は消えうせるどころか、1980-1981年のGNP比2.8% (740億ドル)から1984-1985年のGNP比5.3% (2120億ドル)に膨張した。もしドイツと日本の政府がこの僥倖的な税の増大を消費に回していたら、全てはうまく行ったであろう。ドイツと日本の需要が増大し彼らの増大した輸出に見合う輸入に通じたであろう。アメリカの収支の悪化も少なくなっていたであろうし、生産と収入ももっと早く増え、歳入ももっと上がったであろう。しかし日本とドイツの予算の赤字は、1980年代のはじめの期間は、大きく口を開いていた。アメリカの会計的な放漫さが、両国をして罰されることなく緊縮財政を施行することを可能にした。急増した輸出が、公的予算カットのデフレ的な衝撃を差し引いたのである。レーガンの供給者側の理論に基づいた減税はアメリカ経済を歪めた。過大
評価されたドルは、アメリカの製造者の販売に打撃を与え、税引き後の借金のコストの低下を帳消しにしたのである。産業界は新しい設備増大への投資を控えるようになった。外国との競争に影響されないサービス・セクターは、強いドルに助けられた。オフィスビル、ショッピング・モール、ホテル、レジャー用の巨大な複合施設、の様なものへの投資は急増加した。これらは輸出を生み出したり輸入を減らす為には、殆ど役立たなかった。アメリカが、貿易赤字によって蒙った負債を埋め合わせる 能力 は増やされることはなかったのである。マクロ経済の点では、レーガンの対策は、国内投資に比較して国内貯蓄の深刻な不足を生んだ。サービス産業の投資は増えた。個人の借金は増えた。個人貯蓄は減少した。家庭の可処分所得に対する貯蓄の比率は、1981年の7.7%から1985年の4.5%に落ちた。予算赤字の増大は政府支出を増やした。国家の貯蓄は、全体として、GNPの18.8%から15.8%に減少した。不十分なアメリカの貯蓄は、アメリカの経常収支の悪化を通して、過度のドイツと日本の貯蓄の為の はけ口を提供した。この4年間(1981年~1985年)の間に日本の経常収支の黒字は、GNP比0.4% (50億ドル)から3.7% (500億ドル)に増大した。国内需要は年率3%上がり、実質GNPは輸出先導の成長のお陰で年率4%上がった- - アメリカが経験した需要と成長の鏡像(アメリカはマイナスで日本と正反対であった)であった。即ちアメリカの酔っ払いを、健全でない(酔っ払った状態の)日本が支えたのである。”
ここで、第2次オイルショックを経て1980年代に入ります。著者は続けます。
”1970年代が終わりに近づいた時やっと時代は落ち着いて来た様に見えた。過剰な生産能力は徐々に減らされ投資は回復していた。成長は加速し国際収支の黒字は減少し始めた。インフレは適当なレベルに下げられ来て、もう一度国家予算の赤字を減らすことを考え始めることが可能であった。しかしながらこの時にまた不幸な運命が介入することになった。イラン革命とイラク-イラン戦争が石油の供給を大幅に減らしたのである。1979年から1980年にかけて石油の価格は3倍になった。世界経済は10年間に2度目の石油価格ショックに襲われたのである。1980年代は為替市場と財政市場の混乱の著しい時代であった。この10年間の初期の3年間は(1970年代の後書きとも言うべき)第2次の石油価格の上昇に支配された。この時期、日本経済は第1次の石油価格の上昇の時期より遥かに巧く、また他の大国よりも巧く、機能した。中間期の3年間は、日本は、アメリカのレーガン大統領の供給者側の経済学(supply-side economics=Reaganomics)(供給側重視の経済学)によって箍(たが)をはずされた:即ち日本経済は再び急速なアメリカの需要の成長に引っ張られたのである。しかし1985年にドルはピーク(260円/ドル)に達し、1987年には、ドルの価値は円に対して半分(130円/ドル)になってしまった。
これを境にアメリカは世界を牽引することが出来なくなった。日本は、貿易戦争を恐れてその構造的貿易黒字の是正に循環的なリフレーション(*日本の政治経済的課題 (その5)の注記参照)という緩和策で対応した。日本の国家予算の赤字は心配なほど大きく、リフレーションの重荷は、安価なお金の上に投げられたのである。1980年代の後期には日本経済は、貸し出し限度額が大幅に上げられ、今までかってなかった様に簡単にお金は借りられ金利も安くなったのである。これが”バブル”経済を生み出し、”バブル”経済は1990年に破裂し、多くの著名人のスキャンダルを露呈したのである。”
この時代の分析を著者は以下の様に続けます。
”第2次オイルショック”が襲った時、日本は、第1次オイルショックの時より遥かに良く備えが出来ていた。1978年のボンのサミットで、日本とドイツはその経済を刺激して世界の経済成長を進行させる様に説得された。その年日本は、輸出金額は1%以下の増加で、輸入金額は8%増加したにも拘らず、約6%のGNP成長を成し遂げた。(日本政府の経常収支の黒字の減少はGNPのほぼ1%を切り落としたのに)
1979年の経済サミットでは、日本はもう悠々としていた。1979年の中頃には、日本政府は上昇しているインフレーションを抑える為に会計的にも、金銭的にもブレーキをかけるのが安全だと感じていた。1970年にGNPの4.6%に達していた予算の赤字に取り組むべく、18年間で最も厳しい予算を作成した。この時期を得たデフレーションが日本経済を第2次オイル価格上昇に備えさせたのである。第2次オイル価格上昇は第1次よりは緩いものであった。第1次の場合は、1972年と1974年の間で石油価格は5倍になった。第2次は1978年と1980年の間でそれは2倍と少しであった。しかしその最初の値上がりは(1978年)にはもっと高かったので、日本の輸入価格への影響は同じように高かった。高い石油価格は、価格に転嫁されるのではなく、主に、低い利益と2回目となる実質賃金の減少によって吸収されたのである。1973年のオイル価格上昇に続く2年間で卸売り価格、消費者価格と時間当たり賃金は約40%上がった。第2次オイル価格上昇に続く2年間で卸売り物価は22%、消費者物価は14 %、時間当たり賃金は約13%上がった。円の交換レートは暫く下がったがその後回復した。1972-1974年の日本のインフレーションは英国とほぼ同じくらい悪かったが、ピークの1年は25%になった。1978年-1980年の日本のインフレーションはドイツよりも良く10%以下であった。高いオイル価格のコストを低い賃金と利益で吸収して、日本の輸出はより競争力がついた。貿易条件が悪化して日本の経常収支はなお赤字であったが貿易収支は大きく改善した。結果として、行動は力強く、経済はリセッションに陥ることなく、成長が少し緩くなっただけであった。他の国は日本の良い運営状態を敬服はしなかった。そして特に彼らの市場への日本の侵入を嫌った。例えば日本の自動車の輸出は1980年の4月までの12ヶ月で50%増えた。一方アメリカとイギリスの自動車の生産は1/3減った。ヨーロッパとアメリカは、もし日本が ’自主的に’ 減らさなければ、日本の自動車を締め出すと脅した。自主的な自動車の輸出規制は受け入れられた。そして1981年5月から日本はアメリカに輸出される自動車の数を制限したのである。従って日本の自動車業界は上層の市場を狙った。直ちに彼らは台数は少ないがより高価な車を輸出し始め、継続して輸出の金額を増やしたのである。他の製品にも同様な事を行うことになり、1982年の初めには、日本は、アメリカとヨーロッパへの輸出の1/3は何らかの自主規制を受けていると主張した。輸出はなお増加した。日本はアメリカとヨーロッパを第3世界から締め出した。そこで外国からの攻撃は日本の閉ざされた輸入市場に向けられた。1981年12月には、日本の通産相 河本敏夫は、'日本は貿易戦争の瀬戸際にある' と警告していた。1982年~1984年に亘って実施予定のGATTラウンドの関税削減の年度毎の予定は、1982年の4月1日に前倒しにされた - - がこれだけでは十分でなかった。1982年6月のベルサイユサミットでのトラブルを心配して、日本は更なる貿易自由化対策を提供した。いや諸外国を鎮静させる対策と言ったほうが良いかもしれない。そのパッケージは1983年4月からの119項目に関する関税カットと更に96項目に関しての関税の撤廃を含んでいた。日本は、”輸入手続きは簡素化され輸入は加速されるであろう。輸入の分配に制約を加えることはしないように努める。貿易上の不平を解決する為にはオンブズマンを任命し、外国は 日本が将来の規則を作るときには、発言権を持つようにする。”
巧みな言葉だった。また印刷物も良くそれがもっと効いた。貿易の自由化対策は、輸入の増加を加速するのに殆ど役立たなかった。そこで外国の非難は、日本の輸入現場の最前線の貿易障害から国内経済の不公正なやり方に,焦点を移した。ロナルド・レーガンがアメリカ大統領に当選し、1981年にホワイトハウスに供給側の政策をもたらした。
アメリカの新しい行政府は減税に乗り出したので、レーガノミックス(Reaganomics)は、厳しく押し詰められた日本の救済になった。供給者側経済論者は、この政策は急速な成長とより高い貯蓄を奨励し、その故に税による歳入を増やすと主張した。出費の削減と合わせて、行政府は1983-1984年までに連邦予算を収支均衡にすると予測した。大抵のアメリカ人と同じ様に、供給者側経済論者は、外国のことについては考慮せず、減税がドルとアメリカの国際収支に及ぼす影響を無視した。これは致命的な間違いであった。この減税は、税引き後の借金のコストを下げ、貸し出し限度額の引き上げの需要を増やした。連邦準備銀行は、その強力な議長のフォーカー(Paul Volker)の下で、マネーサプライの増大を抑え、インフレーションと戦う為に利率を高くした。レーガンの安易な減税策とフォーカーのタイトな財政策とが組み合わされた。これが、1980年に為替市場の制御が排除された日本からではないが、外国からの資金の流入を呼び込んだ。ドルの価値は急上昇した。1980年の第3四半期から1981年の第1四半期の間に他の通貨に対して平均60%上がった(しかし円に対しては20%だけだった)。アメリカの製造者は、世界市場から価格の点で追い出され、外国からの輸入が押し寄せた。1981年と1985年の間に
、アメリカの経常収支は、GNPの0.2%(70億ドル)の黒字からGNPの3%(1220億ドル)の赤字になった。経済成長は、楽観的に、年率5%と予測されていた。国内需要は4%を少し下回って、悪化した貿易収支のせいで、GNPの成長は3%に達しなかった。1981年~1985年の間のアメリカ人の異常な消費の1/4は追加的な輸入に費やされた。したがってこの消費によって作られた収入の1/4は外国人によって稼がれたのである。この収入への税金は外国へ逃げてしまった。それは、輸出がドルの強さによって急に増大したドイツと日本の政府に行ったのである。アメリカの歳入は減ってしまったのである。アメリカの連邦予算の赤字は消えうせるどころか、1980-1981年のGNP比2.8% (740億ドル)から1984-1985年のGNP比5.3% (2120億ドル)に膨張した。もしドイツと日本の政府がこの僥倖的な税の増大を消費に回していたら、全てはうまく行ったであろう。ドイツと日本の需要が増大し彼らの増大した輸出に見合う輸入に通じたであろう。アメリカの収支の悪化も少なくなっていたであろうし、生産と収入ももっと早く増え、歳入ももっと上がったであろう。しかし日本とドイツの予算の赤字は、1980年代のはじめの期間は、大きく口を開いていた。アメリカの会計的な放漫さが、両国をして罰されることなく緊縮財政を施行することを可能にした。急増した輸出が、公的予算カットのデフレ的な衝撃を差し引いたのである。レーガンの供給者側の理論に基づいた減税はアメリカ経済を歪めた。過大
評価されたドルは、アメリカの製造者の販売に打撃を与え、税引き後の借金のコストの低下を帳消しにしたのである。産業界は新しい設備増大への投資を控えるようになった。外国との競争に影響されないサービス・セクターは、強いドルに助けられた。オフィスビル、ショッピング・モール、ホテル、レジャー用の巨大な複合施設、の様なものへの投資は急増加した。これらは輸出を生み出したり輸入を減らす為には、殆ど役立たなかった。アメリカが、貿易赤字によって蒙った負債を埋め合わせる 能力 は増やされることはなかったのである。マクロ経済の点では、レーガンの対策は、国内投資に比較して国内貯蓄の深刻な不足を生んだ。サービス産業の投資は増えた。個人の借金は増えた。個人貯蓄は減少した。家庭の可処分所得に対する貯蓄の比率は、1981年の7.7%から1985年の4.5%に落ちた。予算赤字の増大は政府支出を増やした。国家の貯蓄は、全体として、GNPの18.8%から15.8%に減少した。不十分なアメリカの貯蓄は、アメリカの経常収支の悪化を通して、過度のドイツと日本の貯蓄の為の はけ口を提供した。この4年間(1981年~1985年)の間に日本の経常収支の黒字は、GNP比0.4% (50億ドル)から3.7% (500億ドル)に増大した。国内需要は年率3%上がり、実質GNPは輸出先導の成長のお陰で年率4%上がった- - アメリカが経験した需要と成長の鏡像(アメリカはマイナスで日本と正反対であった)であった。即ちアメリカの酔っ払いを、健全でない(酔っ払った状態の)日本が支えたのである。”