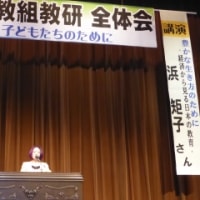6月17日(日)13:00~ 東海大付属仰星高校メデイア館で、第3回医療通訳フォーラムが開催され、参加してきました。
誰もが安心して医療を受けられるための医療通訳制度の実現をめざし活動している、枚方市の医療通訳を実現させる会主催です。
第1回「医療通訳の必要性」、第2回「アメリカの医療通訳の現状」 と続き、今回は、「遠隔通訳の実用性」ということで、国立大学法人群馬大学医学部附属病院医療情報部・厚労科研地域医療基盤開発推進研究(遠隔医療)研究員である瀧澤清美さんの講演でした。
テレビ電話を利用すれば距離や場所に関係なく通訳を利用することができるようになります。
遠方の場所のみならず、例えば感染症の患者さんへの通訳も通訳者に危険の及ばない状態ですることができます。通訳者の移動時間というロスをなくし、気軽に利用することができる通訳システムとなります。
手話通訳もテレビ電話なら遠隔通訳として利用することができます。
ご自身の臨死体験なども含んだプロフィールも話されながら、遠隔医療通訳の実用性、有効性について話されました。
現実、医師と患者さんとのコミュニケーション(相互理解)が不足しているという判断のもと、どうしたら市民にとってより良い医療が受けることができるのか、を考え、大学院に医学部を卒業していないのに、既に論文等を発表されていたこともあり入学し、研究されています。
ITを使うこと、産官学民で市民が介在する医療チームの構築システム等を考えられていて、NPOを立ち上げ、予防医学勉強会や、「病院どうし・患者 情報共有の試み」なども行われたそうです。
群馬大学附属病院では、医療通訳ボランティアのスキルアップを行い、登録をしていただき、遠隔通訳をおこなっています。
この日も、群馬大学とのテレビ電話(skype)を使ってデモンストレーションをおこなってくださいました。 群馬県では、ふるさと雇用再生特別基金事業を使って「医療通訳コールセンター運営管理事業」を3年前に始めたのですが、現在は特別基金事業は廃止されています。
群馬県では、ふるさと雇用再生特別基金事業を使って「医療通訳コールセンター運営管理事業」を3年前に始めたのですが、現在は特別基金事業は廃止されています。
瀧澤先生は、患者さん(外国人も含む)への通訳サービスではなく、医療機関が医療をしやすくするためのとりくみであることを強調されていました。
東日本大震災では、遠隔通訳は、災害時にも大きく被災者に対しての情報格差をなくすことに寄与することが証明されています。医療ツーリズムにももちろん活かされていきますね。
もちろん多言語の中に手話もひとつの言語としてあることを共通認識しなければなりません。
IT機器がすすんでいくことによって、医療格差や情報格差が少しでも解消されることはうれしいことです。
昨年6月議会で私が「医療通訳」をとりあげてから、他の会派の方も取り上げ始めています。「健康医療都市」を枚方市は掲げているわけですから、「遠隔通訳」「同行通訳」を観点を変えて、広域で考えていくことも必要ではないか、と思っています。
17日の午前中は、五常校区自主防災会主催の防災会議にも参加してきました。
今年度1回目は、研修ということで、人と未来防災センター長でもある関西大学社会安全学部の河田教授の5年前に、枚方市主催の防災シンポジウムで、枚方市における地震災害等について話された講演のDVDをみせていただきました。東日本大震災も経験してしまったわたしたちです。この地域における災害可能性は変わることがないわけで、経験したことをいかに教訓として生かしていくことか、が重要となります。
自治会長さんが集まっての防災会議、いろいろなご意見等も出て活発に行われました。
自助・共助が一番大切ですが、もちろんそこに公助がしっかりと加わっていかなければなりません。
地域力・住民力を高めていくためにも私ができることを考え、実行していきたいです。