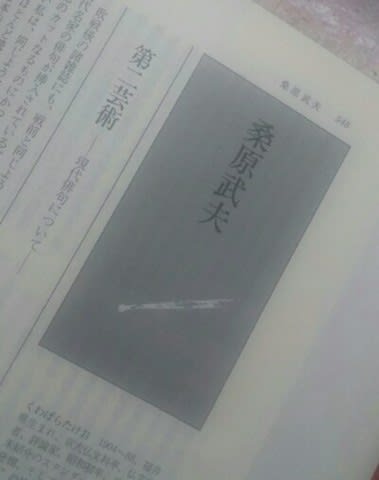
【第二芸術】桑原武夫
立続けに桑原武夫さんの著作を読む。
⬆⬆⬆で書いた木村先生から『第二芸術』論を教わった。今度は高3の受験勉強の時に。
まず、私たち生徒が子規、虚子、利玄、茂吉、左千夫の作品名や作者を当てる問題を解いた。木村先生曰く、「こんなん我慢して覚えるしかないわな。」
ところでと、この論文の骨子の紹介があったのだ。でも、先生は所感は敢えて言われなかったと記憶する。私はと言えば、素直に桑原論文に頷いた。これらの17文字や31文字のどこがいいのか解らないし、素人の作品があっても識別なんて無理だよなぁ、と。
で、初めてこの桑原論文を活字で全文を読んでみた。「結構、上から目線だなぁ」というのが率直な、感想。1946年発表の時、桑原は東北大助教授。俳句は「芸事」と切り捨てる。良くて「第二芸術」だ、と。
ただ、桑原先生には、同じ文学領域でありながら、短詩形への愛情(まぁ、これは譲っても)や敬意が感じられない。というか、そもそも興味がないんだよね、短歌や俳句には。(笑)
でも、この論文にある「ブラインド・フォールド・テスト」は当時は斬新な切り口だったろうなぁ。そして長きにわたり歌壇で話題に登るということは、正鵠を得た点もあると一定程度の国民が考えていた。そしてそのことを歌壇としては、否定できなかったのではなかろうか。
さて、私はと言えば、短歌が芸術かどうか、はたまた、小説に劣る第二の地位であるかどうかは、私の作歌態度には、何の影響も変化も及ぼさない。
ところで、桑原先生。
私は、若山牧水と北原白秋の歌に触れて、歌を詠みはじめたんです。誰に勧められるでもなく。そして、誰に強制されるでもなく詠み続けてきました。歌壇の端くれにも属さないような「日曜歌人」に過ぎませんが、、。
でも、これらの心の動きは、先生が『文学入門』で、すぐれた文学のいわば定義とされた
「インタレストを契機として、作家と読者が、精神共同体を形成する。」
「作者の広義の経験を通した読者における再経験により、人生の発見と自己変革がなされる。」
に「近似」(あえて、同一などとは申しません。)してると考えています。そこんとこ、否定はしてほしくないなぁ。(もっとも、高きに至らず、底に貼りついてますけど、、。)
若山牧水に捧ぐ
「青とあを心になくば翔べぬ身は歩くほかなしこの深い息(新作)」
立続けに桑原武夫さんの著作を読む。
⬆⬆⬆で書いた木村先生から『第二芸術』論を教わった。今度は高3の受験勉強の時に。
まず、私たち生徒が子規、虚子、利玄、茂吉、左千夫の作品名や作者を当てる問題を解いた。木村先生曰く、「こんなん我慢して覚えるしかないわな。」
ところでと、この論文の骨子の紹介があったのだ。でも、先生は所感は敢えて言われなかったと記憶する。私はと言えば、素直に桑原論文に頷いた。これらの17文字や31文字のどこがいいのか解らないし、素人の作品があっても識別なんて無理だよなぁ、と。
で、初めてこの桑原論文を活字で全文を読んでみた。「結構、上から目線だなぁ」というのが率直な、感想。1946年発表の時、桑原は東北大助教授。俳句は「芸事」と切り捨てる。良くて「第二芸術」だ、と。
ただ、桑原先生には、同じ文学領域でありながら、短詩形への愛情(まぁ、これは譲っても)や敬意が感じられない。というか、そもそも興味がないんだよね、短歌や俳句には。(笑)
でも、この論文にある「ブラインド・フォールド・テスト」は当時は斬新な切り口だったろうなぁ。そして長きにわたり歌壇で話題に登るということは、正鵠を得た点もあると一定程度の国民が考えていた。そしてそのことを歌壇としては、否定できなかったのではなかろうか。
さて、私はと言えば、短歌が芸術かどうか、はたまた、小説に劣る第二の地位であるかどうかは、私の作歌態度には、何の影響も変化も及ぼさない。
ところで、桑原先生。
私は、若山牧水と北原白秋の歌に触れて、歌を詠みはじめたんです。誰に勧められるでもなく。そして、誰に強制されるでもなく詠み続けてきました。歌壇の端くれにも属さないような「日曜歌人」に過ぎませんが、、。
でも、これらの心の動きは、先生が『文学入門』で、すぐれた文学のいわば定義とされた
「インタレストを契機として、作家と読者が、精神共同体を形成する。」
「作者の広義の経験を通した読者における再経験により、人生の発見と自己変革がなされる。」
に「近似」(あえて、同一などとは申しません。)してると考えています。そこんとこ、否定はしてほしくないなぁ。(もっとも、高きに至らず、底に貼りついてますけど、、。)
若山牧水に捧ぐ
「青とあを心になくば翔べぬ身は歩くほかなしこの深い息(新作)」



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます