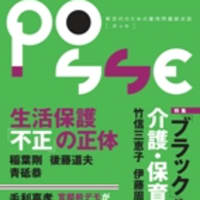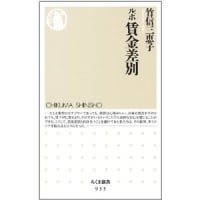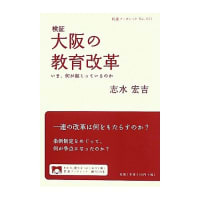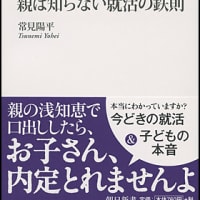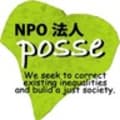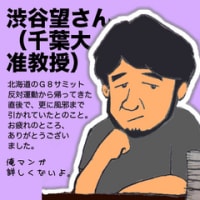http://nomalabor.exblog.jp/
8日の東京での上映後には、『POSSE』編集長の坂倉もゲストとしてトークに出演します。『フツーの仕事がしたい』の感想や雑誌『POSSE vol.3』の特集について先行的にお話しする予定です。なお、この日は日曜日なので、どなたでも1,000円で映画を観れるそうです。まだご覧になっていない方は、ぜひご参加ください。
<東京><劇場公開>
・2009年1月10日(土)より 渋谷・UPLINK(アップリンク)2階 X
1/30(金)~ 2/13(金)19:00
19時の回上映後、舞台挨拶&トークあります。
2月3日(火) 土屋トカチ監督
2月6日(金) 土屋トカチ監督
2月7日(土) 竹馬靖具監督『今、僕は』×土屋トカチ監督
2月8日(日) 雑誌『POSSE』坂倉昇平編集長×土屋トカチ監督
2月9日(月) 平井正也(マーガレットズロース/本映画主題歌提供)ライブ!
2月10日(金) 土屋トカチ監督
2月13日(金) 飯田基晴監督『あしがらさん』『犬と猫と人間と』×常田高志撮影監督
×土屋トカチ監督 3名は映像グループ ローポジションのメンバーになります。
<大阪><劇場公開>
・2009年1月24日(土)より 大阪 第七藝術劇場
1/31(土)~2/6(金)20:10
2/7(土)~2/13(金)18:40
2/14(土)~2/20(金)11:00/17:20
2/17(火)11:00の回のみ休映
2/21(土)~2/27(金)10:00/20:40
2/25(水)、26(木)、27(金)20:40の回のみ休映
本作については、前述のようにPOSSEのイベントや雑誌で何度も取り上げていますが、劇場公開を記念して改めて感想を述べたいと思います。
なお、08年の9月に開催された上映会と、雨宮処凛さん、土屋トカチさんのトークライヴの報告については以下で報告しています。
http://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/44081e4ab5bf21265f4f4b02fc81483d
さて、本作が各メディアで紹介されるに際し、あまりに壮絶な体験や暴力的な登場人物たちにばかり注目が集まっているようにも思えますが、労働組合の描かれ方についても、もっと強調されていいように思います。以下では、この映画における主人公の皆倉さんと労働組合の関係について、労働組合の役割と日本のサブカルチャーにおける意義という観点から、簡単に紹介してみたいと思います。
この点においては、『POSSE vol.2』での土屋トカチ監督の発言が示唆に富んでいるので、引用してみます。
「この映画はある意味、『機動戦士ガンダム』みたいな成長物語なんですよ。すごくいやいや仕事をしていたんだけど、労働組合に入って、やっぱり誇りを持てるようになる。最終的には自分の思い通りに、仕事も労働条件もコントロールできるようになっていったんです。他の運転手さんも、法律に則ってちゃんと残業手当ては出るというまともな感じで働けるようになりましたし。」
ここには、個人が労働組合に参加することの意義が端的に示されていると思います。
皆倉さんは、労働組合に参加することを通じて、職場の労働条件を改善するばかりか、下請企業にしわ寄せを与える大手ゼネコンの責任を追及するという、日本の企業社会の構造に切り込むことにまで成功しました。
これは、労働組合という集団性を通じて、労働者自身が労働のあり方、そして産業のあり方をコントロールできるようになっていったという意味を持っています。
このことが、皆倉さんが仕事そのものにおいて力や自信をつけ、エンパワーメントしていくことにもつながっていったし、自分以外の労働者にも労働運動の成果が広がっていき、更なる集団性を獲得していったわけです。
単に居場所になってしまったり、賃上げを求めるだけと思われがちな労働組合の真の役割が、ここに鮮やかに凝縮されていると言ってもいいと思います。
さらに、土屋さんの発言を踏まえながら、日本のサブカルチャーにおける本作の意義についても強調したいと思います。『フツーの仕事がしたい』は映画という体裁をとっていますが、あまりにわかりやすいストーリーでありすぎて、日本的な「ポストモダン」言説のシニシズムをとる人からは、躊躇してしまうような筋書きかもしれません。実際、現在の日本のサブカル批評においては、社会的な共同体は「コミュニケーションの能力の低い人のアイデンティティ的な居場所」と揶揄して表象されることすらあります。これは、雑誌『POSSE』でも批判し続けているとおりです。
しかし、そんな中で『フツーの仕事がしたい』が描き出した、ユニオンという集団性を獲得した労働者のビルドゥングス・ロマンが、ゼロ年代の現在において有効であったという事実は大きな意味を持つと思います。このように、個人の能力を伸ばし、かつ社会を変えることの出来る新たな集団性について描くことが、今の日本のサブカルチャーに求められているように思います。
いずれの意義も、『フツーの仕事がしたい』の映し出した社会と個人・共同体の関わり方が、労働運動としても、映像作品としても、ラディカルな要素を持っていたことによります。ぜひ、一度本作をご覧になった方も、こうした観点からまた映画館に足を運ばれてはいかがでしょうか。(坂倉)
最新の画像もっと見る
最近の「書評・メディア評」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事