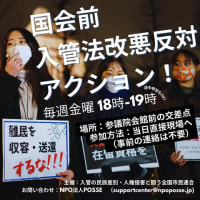POSSEにも関係あると思ったので、感想を書いてみたいと思います。
映画ホームページはこちらから。(画像はこちらのサイトから拝借しました。)
●格差社会に対する「希望」 ―ハードコア・パンク―

80年代、アメリカ。経済が構造的な不況を迎える中、時の大統領ロナルド・レーガンのとった政策は、金持ちを優遇し、貧乏人に自己責任論を押しつける、格差拡大政策であった。
激しい競争社会の中、貧困で希望のない閉塞的な社会に耐えきれず、ドロップアウトする若者は少なくなかった。
そんな彼らが集った、アンダーグラウンドな一大コミュニティがあった。
それが、アメリカン・ハードコア・パンクなのだ!!
本作は、世間的にあまり知られていない(私は知りませんでした)その歴史がマジメに紹介されているドキュメンタリーである。

パンクといえば、70年代後半にイギリスの労働者(&失業者)たちを一世風靡した、セックス・ピストルズ、クラッシュに始まるロンドン・パンクが有名だろう。シンプルなギターコードをかき鳴らし、過激な反エスタブリッシュメントな歌詞を叫び、従来の社会・価値観、既存のロック・ミュージックを全否定した。
2,3年で音楽的にも行き詰まった彼らの一部は、よりアンダークラスなジャマイカ移民の文化に接近することで、レゲエやダブの手法を取り入れ、ニューウェイヴへと深化していった。後期クラッシュしかり、ピストルズのボーカルだったジョン・ライドンしかり。
しかし、さらに一部のハードコアな彼らは違った。パンクの手法を、より音量&スピードという点でバージョンアップさせ、ほとんどメロディのない、ノイズまみれのディストーションギターを高速の轟音でかき鳴らし、政府や社会に対する怒りを絶叫する。それが彼らなりのパンクへの返答だった。そして、これがアメリカ(ただしアンダーグラウンド)へも飛び火していくのだ。

当時アメリカのメジャーな音楽シーンを牛耳っていたのは、ディスコ・ミュージックやハードロック/へヴィメタルだった。キラキラしたライトに照らされて、華やかな格好をしたスターたちが、社会意識のカケラもなく、甘ったるい歌詞をメロディアスに壮大に歌いあげるようなショー。これに違和感を感じた若者たちが、よりリアルで熱気のあるハードコアシーンに集結していったのである。
その怒りのパワーは激しかった。暴走も常態化した。ライブ会場では、客席へのダイヴ、客同士の殴り合いが恒例行事となり、何十台ものパトカーが取り締まりに来ることすらあり、警官との暴動にもしょっちゅう発展した。
しかし、それは決して単なるネガティブな意識の吹きだまりではない。
開放感、そして既存の社会システムとは違ったコミュニティを求めた若者たちが巻き起こしたある種の社会運動だったのだ。
●パンクの哲学 -DIY精神-

ロンドン・パンクから受け継がれたパンクの画期的コンセプト、それがD.I.Y.
(Do It Yourself)。金をかけなくても、必要なものを自分たちで作るという哲学だ。
金のないアンダークラスな若者だから、レコードのジャケットも自分たちで作る。売っているジャケを解体してその作り方をマネするところがスタートだ。ライブ会場なんてどこでも構わない。教会、空き家、ガレージ、人の家…。小さなホールでボーカルが大暴れする様子は、冷静に見るとショボさと紙一重だが、その手作り感もまた良し。それに、演奏が始まって盛り上がれれば関係ない。
そのおかげで、ステージとフロアの境界がかなり低くなったと言える。メジャーにありがちな、「演奏するロックスター」と「金を払って聴くだけのオーディエンス」という図式は存在しない。ステージなんてほとんどないし、あっても関係ない。ステージに客が上がり、ダイヴするなんざ当たり前。本作ではブラック・フラッグのボーカルがステージ下から客にぶん殴られたり(そして殴り返す…)する様子すら捉えられている。
さらにすごいのが、アンダーグラウンドでありながら、インターネットもないこの時代に、ハードコアシーンは数年のうちに全米の地方都市に浸食し、若者たちの支持を獲得していったという事実だ。ロス、ワシントンDC、デトロイト、インディアナポリス、ニューヨーク…ひいてはカナダ。それぞれその地域を代表するバンドが生まれ、独自のシーンが育っていった。
●「白人男の初期衝動」を乗り越えるために ―イアン・マッケイ、HRの闘い―

もちろん、USハードコアは理想的なユートピアだったわけではない。
問題はいくつもある。その過剰な暴力性、ドラッグとの結びつき、そしてマッチョ主義・女性蔑視…。
パンク自体、ハードロックに比べれば、演奏する側への女性参加を促したとはいえ(本作にも何人も女性メンバーは登場する)、やはり「白人男の初期衝動」を極端にしたともいえるから、女性蔑視的な側面は強い。本作でも、その点はしっかりと指摘されている。
しかし、同時にこうしたダークサイドに対する問題提起もあった。
元マイナー・スレットやフガジなどのバンドの伝説的ヴォーカル(…らしいが、映画で見ると小柄で気さくなおっさんでしかない。それがまたすごいのだろう。)、イアン・マッケイが提唱した、「ストレート・エッジ」という精神だ。酒、タバコ、ドラッグ、快楽主義のためのセックスを自らに禁じ、両手の甲に×を書く。イアン・マッケイはこのストイックな精神を提示し、多くの追従者を産んだのである。

また、移民文化との接点も注目したい。えてして白人中心の文化になりがちなパンクだが、文化的な多様性を体現したバンドもあった。特に、本作でも大きくフューチャーされている、ヴォーカルのHR率いるバッド・ブレインズだ。激しく、スピーディーで、シンプルなハードコアによって、数え切れないフォロワーを生み、本作でも数多くのアーティストがリスペクトを惜しまない。そんなこのバンドは、アフリカン・アメリカンのグループなのだ。しかも、彼らの音楽は。時にはレゲエやスカなど、ジャマイカのリズムを取り入れ、独特の文化を作り上げていった。
●90年代ロックへ残したもの ―そして失った哲学―
本作曰く、レーガンの大統領2期目が始まった1986年ごろには、ハードコアはとりあえずはその勢いを失っていくこととなる。とはいえ、後続の音楽シーンに与えた影響は計り知れない。
何と言っても、90年代前半に全米のユースカルチャーを席巻することになる、いわゆるグランジやオルタナと称されるムーブメントだろう。かのニルヴァーナはハードコア・パンクとハードロックの両方を融合したものだと言われるし、前述のバッド・ブレインズは、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンらにつながるブラック・ミュージック×ハードコア、いわゆるミクスチャーの先駆けである。さらに90年代後半のグリーン・デイやオフスプリングやSUM41などのいわゆるメロコア(その始祖で現役のバッド・レリジョンは本作に登場します)は言うまでもないだろう。
本作でもヒップホップのビースティ・ボーイズ(イニシャルのB.Bはバッド・ブレインズを意識したとか!)が紹介され、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーが登場してその影響を語る。ついでにモービーが衝撃的な理由で登場する。確かに気づいてみれば、テクノやポストロックにもハードコア出身のメンバーは多い。それほどに、ハードコア・シーンのエネルギーとスピリットはすさまじかったのだ。

ただし、アンダーグラウンドからメインカルチャーに浮上したことで、大幅に金のかかったマーケティング、特大スタジアムでのライヴなど、かつてのDIY精神やコミュニティ意識に、商業主義が取って代わってしまった側面も事実だ。
本作では、売れるためにハードコアからハードロックに「転向した」バンド、ギャング・グリーンの姿が描かれる。ど派手なステージできらびやかな衣装を身にまとって熱唱するその光景には、言いようのない虚しさが漂っている。
現在の日本も格差が拡大するまっただ中である。メインカルチャーは頼りになるまい。金がない若者たちが集って、アイディアとそれぞれの努力で、新しいコミュニティを作り上げていく、ムーブメントを起こしていくことが必要とされている。
…以上、映画評でした。
(るヒ)