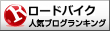三連休、皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか

明日から、また仕事…

今朝、コンタクトレンズを入れようと容器から出して、指でつまんだら割れてしまい 、長年使ってるからしょうがないか…と思い直し、メガネスーパーに電話☏
、長年使ってるからしょうがないか…と思い直し、メガネスーパーに電話☏
 、長年使ってるからしょうがないか…と思い直し、メガネスーパーに電話☏
、長年使ってるからしょうがないか…と思い直し、メガネスーパーに電話☏度数を直したいので、すぐには手に入らず処方箋がいるようで眼科の併設された姫路駅前のみゆき通り店でないと対応出来ないとのことでした。
水曜日に予約でき、とりあえず今週一週間メガネ生活となり、ややテンション低めでおります

さあ、信楽高原鉄道ジョギング散策の翌日の日記が書き上がりました

やって来ました、法隆寺



参加者:私と夫の2人
前日より、プチ旅行に出かけてきております

前日は滋賀県の信楽高原鉄道の散策をしてきました

今日は、二人とも訪れたことがない「法隆寺」へやって来ました

二人とも小学校の修学旅行の旅先は「奈良·伊勢」が定番でしたが、「奈良」は「大仏」「東大寺」でしたので「法隆寺」には来たことがありません

世界遺産となってから随分となりますが、なかなか来ることができませんでした。
しかし、ようやく念願の法隆寺に 観光ですが、今日もジョギング観光で、服装はジャージとリュックです
観光ですが、今日もジョギング観光で、服装はジャージとリュックです
 観光ですが、今日もジョギング観光で、服装はジャージとリュックです
観光ですが、今日もジョギング観光で、服装はジャージとリュックです
法隆寺から約1km離れてますが無料の「三井観光自動車駐車場」に駐車し出発です
 写真の塔は「法輪寺」の三重塔です
写真の塔は「法輪寺」の三重塔です

 写真の塔は「法輪寺」の三重塔です
写真の塔は「法輪寺」の三重塔です

観光案内図を見て👀
「斑鳩町」という名前だけでも聖徳太子の「斑鳩宮」を連想し、歴史に触れてる感満載で気分上々

今日は、本物の「斑鳩寺」を見学できるのでやや興奮気味です 「斑鳩寺」は法隆寺の別称です。我が町太子町にも聖徳太子ゆかりの「斑鳩寺」があります
「斑鳩寺」は法隆寺の別称です。我が町太子町にも聖徳太子ゆかりの「斑鳩寺」があります



今日は、本物の「斑鳩寺」を見学できるのでやや興奮気味です
 「斑鳩寺」は法隆寺の別称です。我が町太子町にも聖徳太子ゆかりの「斑鳩寺」があります
「斑鳩寺」は法隆寺の別称です。我が町太子町にも聖徳太子ゆかりの「斑鳩寺」があります

『606年、聖徳太子が推古天皇から播磨国揖保郡の土地を賜り、大和国斑鳩宮から移住して当地を斑鳩荘(鵤荘)と命名、伽藍を建立』
これが太子町の「斑鳩寺」です。
町の名前も、太子町が誕生する前、斑鳩寺のある村名が「斑鳩村」でしたが、3つの村が合併し、聖徳太子縁の地として「太子町」の町名になったのが始まりです

…と、言うのもあって「斑鳩町」にやって来たかったのです

しかし、めっちゃいいお天気です☀

「斑鳩神社」菅原道真公をお祀りしてあるそうです。

見えました👀あそこに見えるは法隆寺の五重塔

駐車場から1kmしか離れてないのでソラすぐ着くわな とツッコミを入れて。
とツッコミを入れて。

「斑鳩神社」菅原道真公をお祀りしてあるそうです。

見えました👀あそこに見えるは法隆寺の五重塔


駐車場から1kmしか離れてないのでソラすぐ着くわな
 とツッコミを入れて。
とツッコミを入れて。右の塀は「築地塀(ついじべい)」と呼ばれる土塀ですがめちゃめちゃ重厚感があって立派です

12時、東大門に出ました。よく分かってないので、お父さんは、「南大門から入りたかったあぁ」と叫んでましたが、ここから入場させてもらいました

東大門から中へ入りました。ずぅっと築地塀が続いてます。「版築」という工法で土や小石、砂利、藁などを混ぜて突いて突いて固めて作ってあるそう。

修学旅行生がたくさんいます。中高生のようです。みんな、コロナで中止にならず良かったですね

「やはり、南大門から入りたい 」とお父さん。南大門から出て入り直しです
」とお父さん。南大門から出て入り直しです



12時、東大門に出ました。よく分かってないので、お父さんは、「南大門から入りたかったあぁ」と叫んでましたが、ここから入場させてもらいました


東大門から中へ入りました。ずぅっと築地塀が続いてます。「版築」という工法で土や小石、砂利、藁などを混ぜて突いて突いて固めて作ってあるそう。

修学旅行生がたくさんいます。中高生のようです。みんな、コロナで中止にならず良かったですね


「やはり、南大門から入りたい
 」とお父さん。南大門から出て入り直しです
」とお父さん。南大門から出て入り直しです

こちらが正門だけあって立派な軒の深いお屋根でお父さん、正解です
ずっと南大門から松並木の参道が伸びてます

さぁ、入り直しで南大門より中へ


次の門は中門と言って、3mの仁王像が両サイドに立ってます。ちなみに東大寺の仁王像は8m 上には上がいます
上には上がいます

ずっと南大門から松並木の参道が伸びてます


さぁ、入り直しで南大門より中へ



次の門は中門と言って、3mの仁王像が両サイドに立ってます。ちなみに東大寺の仁王像は8m
 上には上がいます
上には上がいます
法隆寺の仁王像は寺門に安置されてる塑像で、日本最古とのこと


上半身裸で筋骨隆々

私、仁王像でもなんでも、こんな感じの歴史的な像はみんな、木の彫刻だと思ってました

「塑像」って。🤨粘土のことです

(あまり何も深く考えてないので、自分の馬鹿さ加減にいつも驚きますが… )
)
 )
)一本の大木を彫ったんじゃないとのこと

2つの像は本来は木の芯の上から粘土で肉付けし、形を整える塑造という手法で造られた塑像ですって🧐
どちらも法隆寺創建時ではなく、奈良時代に入った711年に造立されたものだそうです😯
コレは向かって右の「阿(あ)形像」
塗装は朱色だったそう。

心なしか赤色が見えますがもうほぼ白いです


向かって左に「吽(うん)形像」
黒い塗装です。

今や白と黒ですが、朱色と黒の塗装の違いは何か意味があったんでしょうね🤔

どちらの像も1300年も風雨にさらされ、吽形像(向かって左)は16世紀に顔以外の部分は木造に作り替えられてるそう

塑土で塗り重ねて、かなりの補修が後世でされてるとのことですが、ここで1300年警備してるなんて…
と思うと自然に手を合わせて拝んでしまいました

…こんな調子で見学していくのでちっとも進みません



二人で門の前に立ち尽くして、スマホから情報を得て「ほぉ~」「ほぉ~」と
 (「この人、ほんまは赤かったんやて
(「この人、ほんまは赤かったんやて お父さん
お父さん 」とこんな風に)
」とこんな風に)
でも、この門は通せんぼされてて、通してもらえないので左手の入り口まで移動。

入り口から拝観料を払って伽藍の中に入ると中門と大講堂が繋がる立派な回廊がグルリと。(アッ、入る前にトイレに行ったので入り口を通り越して、その後戻って入り口に向かってます。)

伽藍は整然とした回廊に取り囲まれ、中央に金堂と五重塔が立っていて「ふわぁ~
 」としばらく立ちすくみました。
」としばらく立ちすくみました。世界最古の木造建築群だけあります やはり来てよかったです
やはり来てよかったです
 やはり来てよかったです
やはり来てよかったです
回廊の柱はエンタシス効果を目的にしてあるのか、上下が細くなっています。パルテノン神殿の柱は上に行くほど細いことで知られてますが。

日本の建築でエンタシス効果が取り入れられてるのはこの法隆寺の柱だけだそうです

法隆寺の柱は下から1/3のところが1番ふっくらとして太くなっているとのこと。近くで見たときに直線に見えるように🧐

回廊の連子格子もとても素敵です

もみじが紅葉🍁してたら、自然の一枚の絵ですね。

この「五重塔」は日本最古の塔です。
屋根も柱も何もかも素晴らしく、誰かに説明してもらわないと、せっかく来たのに勿体なかったなぁと思います



軒の出っ張りが深くて重厚感ありあり それに、どの屋根も本瓦葺で見ていて飽きません
それに、どの屋根も本瓦葺で見ていて飽きません 荘厳でひたすら感動しています。
荘厳でひたすら感動しています。
 それに、どの屋根も本瓦葺で見ていて飽きません
それに、どの屋根も本瓦葺で見ていて飽きません 荘厳でひたすら感動しています。
荘厳でひたすら感動しています。
どの角度から見ても気持ち良く揃ってます。柱も屋根も何もかも
 この丸瓦がずぅっと連なってやはり立ちすくみます
この丸瓦がずぅっと連なってやはり立ちすくみます

よぉ~く見ると、こんなかわいい子達が屋根を支えていました

四方でそれぞれ屋根を支えていて違う顔、形、支え方をしていました。

江戸時代の後世補修だそうです。守り神としてなのか、はたまた悪いことをしたので戒めなのか…


四方でそれぞれ屋根を支えていて違う顔、形、支え方をしていました。

江戸時代の後世補修だそうです。守り神としてなのか、はたまた悪いことをしたので戒めなのか…
後の方なら、ちょっと恐いですよね

コレは五重塔の下の土台ですが、これも最初に来たときに見た外壁の築地塀と同じ版築工法で造られた土の上に建っているそう😯

どう見ても「石」に見えますが土を突き固めた出来た土台です。
五重塔の一階には4面とも塑像(粘土造りの像)が安置されています。中には入れず、ガードの外から覗くのですが、これがまた、気色の悪い感じの、でもでも素晴らしい芸術の仏像が。これもみんな国宝とのこと。(写真撮影禁止なので写真がありません)
「金堂」これが世界最古の木造建築物です。法隆寺の本尊を安置している殿堂とのこと。ここも写真撮影禁止なので写真がありませんが窓の外から見る感じでよくわかりませんでした


感動したのはここにも軒を支える柱に昇り龍と降り龍の彫刻がしてありました。

こちらは降り龍です。江戸時代の補修で付加されたそうですが魅入ってしまいます


五重塔と金堂の後ろに堂々と建っているのが「大講堂」こちらにも仏像が安置されていて写真撮影禁止でした。

東側の角に「鐘楼」
平安時代の国宝とのこと。
正岡子規の「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」の鐘ではないようです


既に14時が来ていて、お腹が空くのを通り越し、少々疲れています 西院伽藍を出て、「大宝蔵院」に入りました。(↓コレは見終わったあとの写真)
西院伽藍を出て、「大宝蔵院」に入りました。(↓コレは見終わったあとの写真)
 西院伽藍を出て、「大宝蔵院」に入りました。(↓コレは見終わったあとの写真)
西院伽藍を出て、「大宝蔵院」に入りました。(↓コレは見終わったあとの写真)
写真撮影禁止なので何もありませんが、教科書に載っていた「玉虫厨子」の本物を見ることが出来ました


東院伽藍も拝観。「夢殿」
聖徳太子の斑鳩宮の跡に宮跡の荒廃ぶりを嘆いて、高僧行信が太子供養の伽藍の建立を発願して出来たとのこと。聖徳太子の聖地だそう。

…とりあえず何か食べよう
 とエネルギー切れに襲われる。
とエネルギー切れに襲われる。東大門の脇の南に伸びる築地塀の間を通って街の中に出ることに




古民家を利用したカフェ。
何か食べれるお店を探して、結局、お店が上手く見つからず、

南大門近くのお食事処に飛び込み、

お父さんはカツカレー、私はナポリタンを頂き、休憩。もう15時30分が回ってました

もう一つ、行きたいところがあって、ここより少し西にある、藤ノ木古墳へ
 未盗掘で1988年の大発見です。
未盗掘で1988年の大発見です。


もう一つ、行きたいところがあって、ここより少し西にある、藤ノ木古墳へ

 未盗掘で1988年の大発見です。
未盗掘で1988年の大発見です。奈良のマンホールのフタはカラーでキレイです



この辺り、大きなお屋敷がたくさんあります。

すぐ着きました
 公園になってて、中央に小高い丘があります。
公園になってて、中央に小高い丘があります。
中を覗けるようになってて、人感センサーで、電気がついて覗いたずっと先に石棺が見えました👀

覗き穴にスマホをかざして、写真を撮ると中にある石棺が撮れました


1400年の時を経て、開けられた。中には2体の骨が確認され、冠や太刀などの副葬品が約1万点も見つかったそう。すごいですね

さぁ、たくさん勉強して駐車場に戻ります




16時40分駐車場に戻ってきました。17時00分で閉まってしまうのでギリギリセーフです


この日もたくさん学べました✏️

大阪モノレール。
普段、目にしないので…

好きなんです、乗り物


プチ旅行これで終了

お付き合いありがとうございました。