四、仁徳天皇の聖帝像
第十六代天皇・仁徳天皇は名君として誉れ高く『記紀』に記されている。難波は高津宮(たかつみや)にて天下を治め、高台から昼に炊飯の焚く煙が上がらないので、炊事も出来ないほど苦しい民の暮らしに、税金の猶予を施し、数々の治水事業に尽し聖帝と称された。
仁徳天皇(にんとくてんのう)の御世(みよ)は『古事記』干支崩年から試算して西暦394年から427年となっており、皇位継承をめぐり父の言い残した三人の役割を兄御子(大山守)は謀反を企て、弟皇子に知らせ謀反を制圧した。
勝利した兄弟は、弟皇子と皇位を譲り合ったと美談があるが、『日本書紀』では自殺と記され、順調に皇位に就いたとは思えず、何かは波瀾があっての大雀命(仁徳天皇)擁立が有ったのだろう。
またある説に応神天皇と類似している点があって、同一人物かもしれないと、また存在そのものが疑われる説から、聖帝仁徳の裏面はいろいろと語られている。
説話によれば渡来した秦氏を使って、この時代河内平野に大坂湾岸部は洪水や耕作に適さない湿地地帯、そこで治水に着手したのが、池・河・道・堤などの治水事業に力を注いだと記され、港湾として墨江津を整備、茨田の堤と屯倉、丸迹池、依網池と堀江の海への水路などの社会事業を施したと記されている。
「日本書紀」には外交と内政では新羅が五十三年間朝貢は無かった。使者を遣わし朝貢のない事を問われた。戦いになり必死の抵抗についに新羅軍が潰れ五百人を殺し、四つの邑の民を捕えて帰った。
その後呉国・高麗国が朝貢をした。
蝦夷が叛いた。そこで田道を遣わして討たせた。蝦夷に破られ伊時の水門(石巻)で死んだ。田道の墓を掘った蝦夷は墓から出てきた大蛇に、蝦夷は沢山死んだ。
断片的に蝦夷と新羅国などが記されている。
仁徳天皇の存在について伝承上の人物とする反面『倭の五王』の中国の『宋書』の記述も見逃す事は出来ない。下記の◆「倭の五王」を参照。
それらの地名も現存し確かに関与し施策をした形跡は窺える。一方、仁徳天皇自身の人間像としては、女性関係が多くみられ、それによる皇后との嫉妬が多く語られ『古事記』では歌に詠まれて、皇后の出身有力豪族の葛城氏との関係も窺える。
女性にまつわる説話に「皇后の嫉妬と吉備の黒日売」では皇后石之日売命は、嫉妬されることが多く、天皇が召された妃を宮殿には入れられなかった。
天皇は吉備の海部直の娘の容姿が美しいので天皇が召されたが、黒日売は皇后の嫉妬深さに恐れて国元の吉備に逃げ帰ってしまった。
天皇は淡路に行った折に、黒日売に会いたさに島伝いに吉備に行かれ、暫しの間、黒日売と日々を過ごされたと言う。
その後皇后石之日売命が酒宴に奉じる御綱柏を採りに紀伊国に行かれた折、天皇は八田若郎女を召して大宮の中に入れられ、この際の皇后の嫉妬から不仲になられた皇后と天皇の不仲は以後皇后の郷、葛城(かつらぎ)に帰り二度と宮中には戻らず、筒城宮でなくなり、平城山に葬られ、三年後に八田日売は皇后になられた。「聖帝」と言われた仁徳帝も女性には積極的であったようだ。
★仁徳天皇*第十六代天皇、仁徳天皇はただ一人「聖帝」と評され、父は応神天皇、母は品陀眞若王の女仲姫命、第四子であり大雀命と言う。
大雀命は高津宮で天下を治めた。葛城の曾都毘古の女、石之日売命を皇后として、生まれた皇子は大江の伊邪本和気命、墨江の中津王、蝮の水歯別命、男浅津間若子宿祢の四人、髪長比売妃から生まれた御子は二人、八田若郎女妃からは御子が生まれず、宇遅能若郎女妃からも生まれなかった。
御子は合わせて六人である。
◆仁徳陵(百舌鳥古墳群)*大阪堺市の西部中央に位置する古墳中期に象徴される大型古墳群、墓域は河内・和泉に移った五世紀造営のピークを迎えた。その頃中国の『宋書』の記載される「和の五王」の時代と重なり、日本第一の大山古墳などが点在する。
◆倭の五(ご)王(おう)*『宋書』夷蛮(いばん)出(で)伝倭(でんわ)国(こく)条(じょう)に見える五人の倭国王、「讃さん」・「珍ちん」・「済せい」・「興こう」・「武ぶ」・の五人の王について、仁徳天皇もその一人に該当する考えである。
五王について『古事記』『日本書紀』で五王がどの天皇に該当するかについては、伝えられる天皇名や系譜関係から検討され試みられたが、讃については、それがホムタのホムと意訳からみて応神天皇、オホサザキの讃の音訳から仁徳天皇、珍は反正天皇の実名ミツハワケのミツの意訳、反正天皇とみなし、その兄とされる履中(りちゅう)天皇(てんのう)はあてる諸説がある。済は允(いん)恭(ぎょう)天皇(てんのう)に実名オアサツマワクゴノスクネのツ(津)の意訳。興は安康(あんこう)天皇(てんのう)の実名アナホの音訳とみる。
武についてはワカタケルのタケルの意訳とみて雄略天皇に否定するのが今日一般的見解である。
※応神天皇の神功皇后の九州で出産はとりもなおさず、九州に関係の深い氏族の大和朝廷の征服と穿った見方もできないわけでもない。
なれば仁徳天皇は難波・河内を拠点にした「河内王朝」の創始者と言ってもよいだろう。その理由に治水事業の所在地が未だ大阪近辺に地名として残されていて、その形跡もある。何より河内から泉にかけての古墳群と仁徳・応神の巨大古墳が何よりそれを物語る。
これほどの巨大古墳の造成は豊かな財力と支配地が広まっていて、支える豪族の背景が無ければ到底成しえないことである。
第十六代天皇・仁徳天皇は名君として誉れ高く『記紀』に記されている。難波は高津宮(たかつみや)にて天下を治め、高台から昼に炊飯の焚く煙が上がらないので、炊事も出来ないほど苦しい民の暮らしに、税金の猶予を施し、数々の治水事業に尽し聖帝と称された。
仁徳天皇(にんとくてんのう)の御世(みよ)は『古事記』干支崩年から試算して西暦394年から427年となっており、皇位継承をめぐり父の言い残した三人の役割を兄御子(大山守)は謀反を企て、弟皇子に知らせ謀反を制圧した。
勝利した兄弟は、弟皇子と皇位を譲り合ったと美談があるが、『日本書紀』では自殺と記され、順調に皇位に就いたとは思えず、何かは波瀾があっての大雀命(仁徳天皇)擁立が有ったのだろう。
またある説に応神天皇と類似している点があって、同一人物かもしれないと、また存在そのものが疑われる説から、聖帝仁徳の裏面はいろいろと語られている。
説話によれば渡来した秦氏を使って、この時代河内平野に大坂湾岸部は洪水や耕作に適さない湿地地帯、そこで治水に着手したのが、池・河・道・堤などの治水事業に力を注いだと記され、港湾として墨江津を整備、茨田の堤と屯倉、丸迹池、依網池と堀江の海への水路などの社会事業を施したと記されている。
「日本書紀」には外交と内政では新羅が五十三年間朝貢は無かった。使者を遣わし朝貢のない事を問われた。戦いになり必死の抵抗についに新羅軍が潰れ五百人を殺し、四つの邑の民を捕えて帰った。
その後呉国・高麗国が朝貢をした。
蝦夷が叛いた。そこで田道を遣わして討たせた。蝦夷に破られ伊時の水門(石巻)で死んだ。田道の墓を掘った蝦夷は墓から出てきた大蛇に、蝦夷は沢山死んだ。
断片的に蝦夷と新羅国などが記されている。
仁徳天皇の存在について伝承上の人物とする反面『倭の五王』の中国の『宋書』の記述も見逃す事は出来ない。下記の◆「倭の五王」を参照。
それらの地名も現存し確かに関与し施策をした形跡は窺える。一方、仁徳天皇自身の人間像としては、女性関係が多くみられ、それによる皇后との嫉妬が多く語られ『古事記』では歌に詠まれて、皇后の出身有力豪族の葛城氏との関係も窺える。
女性にまつわる説話に「皇后の嫉妬と吉備の黒日売」では皇后石之日売命は、嫉妬されることが多く、天皇が召された妃を宮殿には入れられなかった。
天皇は吉備の海部直の娘の容姿が美しいので天皇が召されたが、黒日売は皇后の嫉妬深さに恐れて国元の吉備に逃げ帰ってしまった。
天皇は淡路に行った折に、黒日売に会いたさに島伝いに吉備に行かれ、暫しの間、黒日売と日々を過ごされたと言う。
その後皇后石之日売命が酒宴に奉じる御綱柏を採りに紀伊国に行かれた折、天皇は八田若郎女を召して大宮の中に入れられ、この際の皇后の嫉妬から不仲になられた皇后と天皇の不仲は以後皇后の郷、葛城(かつらぎ)に帰り二度と宮中には戻らず、筒城宮でなくなり、平城山に葬られ、三年後に八田日売は皇后になられた。「聖帝」と言われた仁徳帝も女性には積極的であったようだ。
★仁徳天皇*第十六代天皇、仁徳天皇はただ一人「聖帝」と評され、父は応神天皇、母は品陀眞若王の女仲姫命、第四子であり大雀命と言う。
大雀命は高津宮で天下を治めた。葛城の曾都毘古の女、石之日売命を皇后として、生まれた皇子は大江の伊邪本和気命、墨江の中津王、蝮の水歯別命、男浅津間若子宿祢の四人、髪長比売妃から生まれた御子は二人、八田若郎女妃からは御子が生まれず、宇遅能若郎女妃からも生まれなかった。
御子は合わせて六人である。
◆仁徳陵(百舌鳥古墳群)*大阪堺市の西部中央に位置する古墳中期に象徴される大型古墳群、墓域は河内・和泉に移った五世紀造営のピークを迎えた。その頃中国の『宋書』の記載される「和の五王」の時代と重なり、日本第一の大山古墳などが点在する。
◆倭の五(ご)王(おう)*『宋書』夷蛮(いばん)出(で)伝倭(でんわ)国(こく)条(じょう)に見える五人の倭国王、「讃さん」・「珍ちん」・「済せい」・「興こう」・「武ぶ」・の五人の王について、仁徳天皇もその一人に該当する考えである。
五王について『古事記』『日本書紀』で五王がどの天皇に該当するかについては、伝えられる天皇名や系譜関係から検討され試みられたが、讃については、それがホムタのホムと意訳からみて応神天皇、オホサザキの讃の音訳から仁徳天皇、珍は反正天皇の実名ミツハワケのミツの意訳、反正天皇とみなし、その兄とされる履中(りちゅう)天皇(てんのう)はあてる諸説がある。済は允(いん)恭(ぎょう)天皇(てんのう)に実名オアサツマワクゴノスクネのツ(津)の意訳。興は安康(あんこう)天皇(てんのう)の実名アナホの音訳とみる。
武についてはワカタケルのタケルの意訳とみて雄略天皇に否定するのが今日一般的見解である。
※応神天皇の神功皇后の九州で出産はとりもなおさず、九州に関係の深い氏族の大和朝廷の征服と穿った見方もできないわけでもない。
なれば仁徳天皇は難波・河内を拠点にした「河内王朝」の創始者と言ってもよいだろう。その理由に治水事業の所在地が未だ大阪近辺に地名として残されていて、その形跡もある。何より河内から泉にかけての古墳群と仁徳・応神の巨大古墳が何よりそれを物語る。
これほどの巨大古墳の造成は豊かな財力と支配地が広まっていて、支える豪族の背景が無ければ到底成しえないことである。












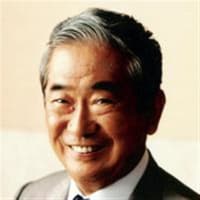






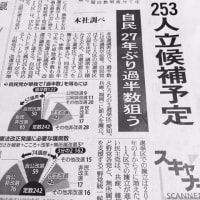
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます