三、“神(じん)功(ぐう)皇后(こうごう)の三韓(さんかん)征伐(せいばつ)と聖母像(せいぼぞう)
景(けい)行(こう)天皇(てんのう)の後、成(せい)務(む)天皇(てんのう)が即位するが、後継の皇子がなく、ヤマトタケル命の死後の第二子、足仲彦(たらしなかつひこ)(仲哀(ちゅうあい)天皇(てんのう))が即位した。ヤマトタケルの熊襲征伐後、再び朝廷に背いたので、天皇は九州に向かった。その時に下された神託に仲哀天皇は従わず、神の怒りに触れて急死する。
『古事記』では最初に帯中日子天皇は穴門の豊浦宮と香椎宮において天下統一された。
仲哀天皇は香椎宮で神の宣託(せんたく)(天照大神・住吉神)に従わず急死をした。
神功皇后は大神の指示通り新羅に遠征をした。
神功皇后は軍勢を整え、船を揃えて進軍すると大波が来て新羅の国の半ばまで達し、新羅の国王は降伏をした。
その時皇后は出産が差し迫り、帰国まで遅らせるために「石」を越しにつけ引き伸ばし、筑紫国に着き出産をした。
皇子が太子になって、筑紫から大和に帰られる時に、異母兄弟の香坂王と忍熊王の反逆に遭われ、太子軍は琵琶湖の湖上まで追跡し撃退をした。
そこから武内宿祢が供をして、近江・若狭の国々を廻られ、気比大神に参られた。
『日本書紀』は詳しく描かれている。神功元年から神功六九年まで政務と執り行った。神託に従って、神功皇后は、熊襲・土(つち)蜘蛛(ぐも)を征伐し従わせた。その後、住吉神の神託により新羅遠征に向かい、新羅は戦わずして降伏し。朝貢を約束した。
百済・高句麗も朝貢を約束させ服従させ、これを三韓征伐と言われている。帰還後には筑紫で誉田別皇子を出産した。
神功皇后が三韓征伐を終えて畿内に入ると、応神天皇の異母兄の籠坂(かごさか)王(おう)・忍(おし)熊(くま)王(おう)が反乱を起こし戦いとなった。武内宿祢(たけうちすくね)や武振熊命らの働きによって制圧をした。
勝利をした太子(応神天皇)をお連れし武内宿祢は穢(けが)れを祓(はら)う為に気比神社の参拝をしている。
『古事記』『日本書紀』も神功皇后は九州を中心に展開されており、九州に関連した王権と考えられる。
★神功皇后*『古事記』『日本書紀に』『風土記』などに見える伝承上の人物。仲哀天皇の皇后、父は開花(かいか)天皇(てんのう)の孫、名を気長足媛(きながあしひめ)尊(そん)と言う。父は開化天皇の孫、母は新羅国(くに)の王子天子天之(おうじあまこあまの)日(ひ)矛(ほこ)の五世(ごせい)の孫と伝える。
★仲哀天皇『古事記』『日本書紀』に見える伝承上の人物。父は日本武尊、母は垂仁天皇の両道入姫命。
皇后気(おきなが)長足(たらし)姫(ひめ)尊(みこと)(神功皇后)皇后と共に熊襲征伐に筑紫に香椎宮に至った時、新羅を討伐の神託を受けたがそれを信じなかったために急死をした。享年『記紀』とも五十二歳である。
★武内宿祢*孝元天皇の孫。伝承上の人物。建内宿祢とも書く。成務・仲哀・応神・仁徳・景行と神功皇后の各天皇に仕えた長寿大臣。蘇我氏を始め多くの氏族の祖。神功皇后の場合神の宣託を聞く役割を果たした。
弟の味師内宿祢の讒言(ざんげん)にたいし、盟(くが)神深(た)湯(ち)で潔白を証明するなどの性格を持つ。渡来人を指導して開発にあたらせる多くの伝承を持つ。天皇を補佐する理想に人物に描かれている。
そこで伝承は蘇我氏との関係を『記紀』に入ったとする説。
◆気比神社:敦賀市(つるがし)曙町(あけぼのちょう)にあって旧官幣(きゅうかんぺい)大社(たいしゃ)・祭神(さいじん)は伊奢(これしゃ)少別命(しょうべつみこと)・仲哀(ちゅうあい)天皇(てんのう)・神功皇后・日本武尊(にほんたける)・応(おう)神(じん)天皇(てんのう)・「気比宮社記(きひみやしゃき)」によれば神功皇后が三韓征伐の成功を祈願をし、穴門に向かう途中に千・満の珠を得たと記す。気比大神は海人族の信仰した神と思われる。
※神功皇后が実物に存在したかについては、その立証は難しいが、『新唐書』東夷倭日本「仲哀死以開曾孫女神爲王」と記されている。
『宋史』日本国神功天皇、開化天皇之曾孫女、又謂之息長姫天皇」天皇と有り、一時の本の歴史上神功皇后を天皇に加えていたが、大正時代に歴代天皇として外されている。
また神功皇后の卑弥呼説も今では時代的に符合しないので否定されている。国外でその名が見受けられる以上その存在をすべて架空とは言い難く、尚、神功皇后に代わる存在があるか検証の余地はあるのではないかと思われる。
神功皇后には神託と神の威光で、立ちはだかる神々を退け、謀反を制圧する神の加護が有った。男子にもなしえない熊襲(くまそ)の制圧と三韓(さんかん)征伐(せいばつ)と応神天皇の擁立には神託が必要だった。
神功皇后は仲哀亡き後の世継ぎの御子(応神天皇)を出産の三韓征伐の最中、出産を遅らせるための「月延石」や「鎮(ちん)懐石(かいせき)」などの説話は、天皇の世継ぎを生む覚悟の程を知らしめるものであった。
また『古事記』では神功皇后・応神天皇の編では「天之日矛」の新羅の国王の物語の説話が語られていて、応神・神功は渡来系に深い関係があるのではと推測がある。
また冒頭の帯中日子天皇は穴門の豊浦宮と香椎宮において天下統一された。
この記述で王権が九州の王権から取って代わったと言う説が生まれる。
卑弥呼と神功皇后の関連性は薄く、この伝説は朝廷に伝えられた朝鮮半島の南部平定伝承と、京都府綴喜郡に居住した「息長」一族の伝承や、母子信仰に基づくオホタラシヒメの伝承と習合して。7~8世紀の古代天皇制の思想の影響を受け、『記紀』に定着したものと思われている。
景(けい)行(こう)天皇(てんのう)の後、成(せい)務(む)天皇(てんのう)が即位するが、後継の皇子がなく、ヤマトタケル命の死後の第二子、足仲彦(たらしなかつひこ)(仲哀(ちゅうあい)天皇(てんのう))が即位した。ヤマトタケルの熊襲征伐後、再び朝廷に背いたので、天皇は九州に向かった。その時に下された神託に仲哀天皇は従わず、神の怒りに触れて急死する。
『古事記』では最初に帯中日子天皇は穴門の豊浦宮と香椎宮において天下統一された。
仲哀天皇は香椎宮で神の宣託(せんたく)(天照大神・住吉神)に従わず急死をした。
神功皇后は大神の指示通り新羅に遠征をした。
神功皇后は軍勢を整え、船を揃えて進軍すると大波が来て新羅の国の半ばまで達し、新羅の国王は降伏をした。
その時皇后は出産が差し迫り、帰国まで遅らせるために「石」を越しにつけ引き伸ばし、筑紫国に着き出産をした。
皇子が太子になって、筑紫から大和に帰られる時に、異母兄弟の香坂王と忍熊王の反逆に遭われ、太子軍は琵琶湖の湖上まで追跡し撃退をした。
そこから武内宿祢が供をして、近江・若狭の国々を廻られ、気比大神に参られた。
『日本書紀』は詳しく描かれている。神功元年から神功六九年まで政務と執り行った。神託に従って、神功皇后は、熊襲・土(つち)蜘蛛(ぐも)を征伐し従わせた。その後、住吉神の神託により新羅遠征に向かい、新羅は戦わずして降伏し。朝貢を約束した。
百済・高句麗も朝貢を約束させ服従させ、これを三韓征伐と言われている。帰還後には筑紫で誉田別皇子を出産した。
神功皇后が三韓征伐を終えて畿内に入ると、応神天皇の異母兄の籠坂(かごさか)王(おう)・忍(おし)熊(くま)王(おう)が反乱を起こし戦いとなった。武内宿祢(たけうちすくね)や武振熊命らの働きによって制圧をした。
勝利をした太子(応神天皇)をお連れし武内宿祢は穢(けが)れを祓(はら)う為に気比神社の参拝をしている。
『古事記』『日本書紀』も神功皇后は九州を中心に展開されており、九州に関連した王権と考えられる。
★神功皇后*『古事記』『日本書紀に』『風土記』などに見える伝承上の人物。仲哀天皇の皇后、父は開花(かいか)天皇(てんのう)の孫、名を気長足媛(きながあしひめ)尊(そん)と言う。父は開化天皇の孫、母は新羅国(くに)の王子天子天之(おうじあまこあまの)日(ひ)矛(ほこ)の五世(ごせい)の孫と伝える。
★仲哀天皇『古事記』『日本書紀』に見える伝承上の人物。父は日本武尊、母は垂仁天皇の両道入姫命。
皇后気(おきなが)長足(たらし)姫(ひめ)尊(みこと)(神功皇后)皇后と共に熊襲征伐に筑紫に香椎宮に至った時、新羅を討伐の神託を受けたがそれを信じなかったために急死をした。享年『記紀』とも五十二歳である。
★武内宿祢*孝元天皇の孫。伝承上の人物。建内宿祢とも書く。成務・仲哀・応神・仁徳・景行と神功皇后の各天皇に仕えた長寿大臣。蘇我氏を始め多くの氏族の祖。神功皇后の場合神の宣託を聞く役割を果たした。
弟の味師内宿祢の讒言(ざんげん)にたいし、盟(くが)神深(た)湯(ち)で潔白を証明するなどの性格を持つ。渡来人を指導して開発にあたらせる多くの伝承を持つ。天皇を補佐する理想に人物に描かれている。
そこで伝承は蘇我氏との関係を『記紀』に入ったとする説。
◆気比神社:敦賀市(つるがし)曙町(あけぼのちょう)にあって旧官幣(きゅうかんぺい)大社(たいしゃ)・祭神(さいじん)は伊奢(これしゃ)少別命(しょうべつみこと)・仲哀(ちゅうあい)天皇(てんのう)・神功皇后・日本武尊(にほんたける)・応(おう)神(じん)天皇(てんのう)・「気比宮社記(きひみやしゃき)」によれば神功皇后が三韓征伐の成功を祈願をし、穴門に向かう途中に千・満の珠を得たと記す。気比大神は海人族の信仰した神と思われる。
※神功皇后が実物に存在したかについては、その立証は難しいが、『新唐書』東夷倭日本「仲哀死以開曾孫女神爲王」と記されている。
『宋史』日本国神功天皇、開化天皇之曾孫女、又謂之息長姫天皇」天皇と有り、一時の本の歴史上神功皇后を天皇に加えていたが、大正時代に歴代天皇として外されている。
また神功皇后の卑弥呼説も今では時代的に符合しないので否定されている。国外でその名が見受けられる以上その存在をすべて架空とは言い難く、尚、神功皇后に代わる存在があるか検証の余地はあるのではないかと思われる。
神功皇后には神託と神の威光で、立ちはだかる神々を退け、謀反を制圧する神の加護が有った。男子にもなしえない熊襲(くまそ)の制圧と三韓(さんかん)征伐(せいばつ)と応神天皇の擁立には神託が必要だった。
神功皇后は仲哀亡き後の世継ぎの御子(応神天皇)を出産の三韓征伐の最中、出産を遅らせるための「月延石」や「鎮(ちん)懐石(かいせき)」などの説話は、天皇の世継ぎを生む覚悟の程を知らしめるものであった。
また『古事記』では神功皇后・応神天皇の編では「天之日矛」の新羅の国王の物語の説話が語られていて、応神・神功は渡来系に深い関係があるのではと推測がある。
また冒頭の帯中日子天皇は穴門の豊浦宮と香椎宮において天下統一された。
この記述で王権が九州の王権から取って代わったと言う説が生まれる。
卑弥呼と神功皇后の関連性は薄く、この伝説は朝廷に伝えられた朝鮮半島の南部平定伝承と、京都府綴喜郡に居住した「息長」一族の伝承や、母子信仰に基づくオホタラシヒメの伝承と習合して。7~8世紀の古代天皇制の思想の影響を受け、『記紀』に定着したものと思われている。












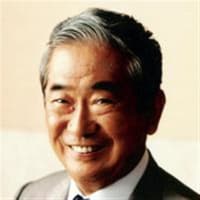






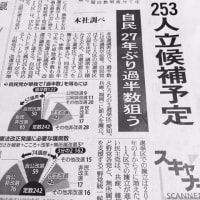
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます