
江戸時代は、五人組制度で町や村を統治していた。その掟帳から垣間見える農民の暮らしについての講義。五人組は豊臣時代からあり、掟の項目が増減・変遷しながら幕末まで厳しい支配体制が続いた。掟帳は庶民の暮らしを規制する法規集で、庄内でも地区ごとにかなりの数が古文書として残されている。中でも杉原先生が個人的に入手された櫛引地区の五人組帳は、宝暦九年と記され、江戸時代初期の貴重な史料。切支丹禁止や年貢完納等は無論、衣食住や休日についてもこと細かな記載がある。大組頭以外は木綿の合羽を着てはならない、寄合の賄は質素にして禁酒、賭け事・捨子捨馬の禁止、孝行者の届け出等、風紀・秩序を守ろうとするねらいがあった。しかし、農民達はお上の掟をただ黙々と守っていただけではない。三方国替えに反対する農民7万人が酒田の大浜に集結したという記録がある。藩主や幕府も農民の命懸けの直訴やいざという時の集団の力を怖れていたようだ。
杉原先生の講座では江戸時代の庶民の暮らしに焦点を当てて語っていただいた。自分の祖先の暮らしを想像しながら、興味深く拝聴した。
















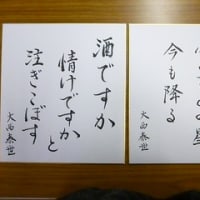



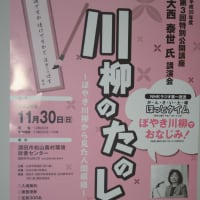
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます