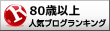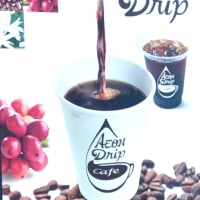東京や大阪で、銭湯の経営者の出身地を見ると、石川県、富山県出身者が多いのだそうである。
また、豆腐屋も石川、富山人が多いのだと。
明治のご一新以後、人々の出稼ぎや移動が自由になり、北陸の方が多く出稼ぎに江戸・京大阪に出るようになった。そしてハードな仕事に雇われて、営々と都会で開業できる地歩を固めたのだ。
そして銭湯・豆腐屋を自営できるようになった。
ことに、富山については、家庭薬の置き薬営業など、都会に訪問するかたちのものも見られる。
越中富山の反魂丹
銭湯って大変な仕事なのだ。
風呂場や脱衣場をきれいに掃除する。水を使う。湯舟に水を充たす。かまどを燃やす。客から湯銭を貰う。三助みたいなサービスもする。湯を落とす。またきれいに洗う。朝から晩まで体を動かし続けねばならない。盆も正月もなく水を使わねばならない。
それと燃料。木材の端切れなどを集めてこなければならない。都会といえど、燃料には機転も工夫もいる。雨の日だってあるから、余分の薪も工面する。そういうことを辛抱強く継続してやるには根気がいる。
北陸の人には、自分の目標を立てたらめげることなく持続して努力する意思の人が多いのだろう。
豆腐屋だって、朝から晩まで、夏でも冬でも水に手突っ込んで豆腐を作り、売るのだ。
富山を旅して、立山連峰から流れ下る大量の雪解け水がいくつもの急流を流れ下る地理を見た。
そういう自然環境を克服してきた富山人が、水を扱う仕事につき、努力を自己の心情体質に蓄えてきたに違いない。
そう思って、富山人に感銘を受けるのである。
宇奈月温泉の湯は、黒部峡谷を7キロも遡ったところからパイプで引いてくる。
黒部開発のためのトロッコのトンネルを掘る時、地熱が160度もの高温地帯を掘らなければならなかった。そんな話を聞くと、富山人は頑張る。偉い。と私は勝手に想像してみるのである。
コメント一覧

京都のユキ
最新の画像もっと見る
最近の「旅」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事