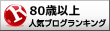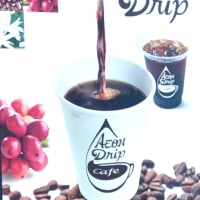足軽はこれより下、棟割長屋だった。




佐倉藩は、戦乱にも逢わず、震災や空襲にも遭わなかったので、江戸時代末期の城下町や武家屋敷が良い状態で残されていたらしい。
武家屋敷は、本丸跡に遠からぬ一角にあった。
へっつい、かまどなど、今のわれわれにも想定できるリアルなものだった。
関西でいう「おくどさん」スタイルである。
私は、甲冑の展示を見ていたが、住宅展示場のモデルルームを見慣れている家内は、
「押入れがない、納戸はある。納戸に夜具からなにから納めていたのか。」
とご意見。さすがに住まい勝手重視で見学してるなと、感心。
あとでパンフレットを見ると、押入れは3つの住宅とも皆無で、納戸はそこそこの広さを確保してある。
武士の格に応じて、門構え、玄関、客間のきまりが厳密のようだった。
武士の末裔とおぼしきボランティアのガイド氏が説明してくれた。
屋敷は、藩が造り、武士の地位に応じて貸し与えていた由で、昇進、あるいは扶持の増減のたびに割合頻繁に屋敷変えをされたらしい。
あるじの甲斐性により、暮らし方がころころ変わるというのは、落ち着かない生活だなと思った。
首になったら官舎を追い出される。これなら、従順たらざるを得ないのである。
藩によって住居が保証されていることは、反逆も、飛躍もできない閉塞感と感じるか、ぬるま湯人生と思えるか、見方は分かれるだろう。
また、戦乱もなく、武力が不要になっても、役目に応じた俸禄を代々にわたって支給し、無役でも最低のものは払わねばならない。首切りもしにくい。
藩士の生活を保障しなくてはならない殿様も大変だ。
百姓から年貢を取り立て、それを銭に替えて、よくもこのような非生産的な組織を維持しつづけたな。
徳川三百年、幕藩体制というのは、よく長持ちしたと感心するのであった。