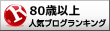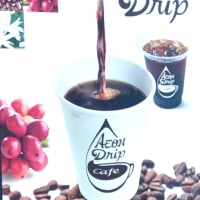外人向けの解説文をみると、渡しのことをフェリーと書いてある。櫓で漕ぐような小さな和船でも人や物を運ぶとフェリーでいいのかと、納得。
道路を挟んで直ぐ前に、浅草寺よりも古い待乳山聖天 がある。

ここの境内に長い築地塀があって、広重の錦絵に出てくると書いてあった。

私は、池波正太郎 の鬼平犯科帳や剣客商売など時代小説のファンである。
境内のはずれに彼の生誕記念碑があった。

彼の作品には、商家の番頭、手代や手職人、そして火盗改めの刑事に働く武士、岡っ引き、浪人やならずものが登場して、筋の中で個性を浮き立たせている。
池波は、父が日本橋の錦問屋の通いの番頭、母の実家が錺職人、自分は兜町の株屋や旋盤工、軍の電話交換局などさまざまな勤めをして、それらが登場人物のリアルな描写に役立っているようである。
また、地名も、剣客商売など、老剣客秋山小兵衛の隠宅と、その息子大治郎の剣道場が大川を挟んで設定されてあり、小梅村はいまの向島、橋場はこの少し上流にある地名である。押上も出てくる。実際にこのあたりを歩いてみると、作品の魅力がさらに飲み込めてくるのである。
これら、まだお読みでない方がいらしたら、是非ご一読されてはいかがですか。