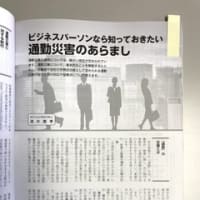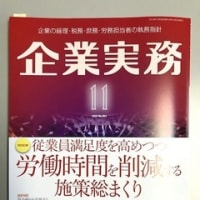社会保険労務士の酒井嘉孝です。
特定社会保険労務士という資格があります。
2007年の社会保険労務士法改正で加えられた制度で、社会保険労務士に裁判外紛争解決手続きの代理権が与えられたものです。
解雇、セクハラ、パワハラなどの労働問題が発生し、それを白黒つけて解決していこうとすると弁護士を立てて裁判をしていくわけですが、その場合解決まで年単位の期間を考えなければならず、費用も労力もかかります。
それを裁判外で迅速に(そして費用も安く)解決できるよう、労働局のあっせんや社会保険労務士会が運営する「社労士労働紛争解決センター」でのあっせんの場において労働問題を解決していく手段があります。そのあっせんの場で会社側または労働者側の代理人となれる社会保険労務士が「特定社会保険労務士」です。
「あっせん」は裁判官が白黒つけて賠償額を決めるというのとは少々趣が違い、お互いが歩み寄って解決していく(お金の場合解決金額を決める)というスタンスで進んでいきます。
また、テレビに出てくる裁判所のように裁判官を中心に会社側労働者側左右に分かれて相対峙するものではなく、別室で進めていくので顔を合わせることもないようです。
その特定社会保険労務士の試験を昨年11月に受験し、その合格発表が今日でした。
おかげさまで合格することができました。
この合格を受けて、特定社会保険労務士となるには全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿へ「付記」されてからなので少し先(最短で5月?)になります。
4月24日追記:付記となったのは4月1日付でした。
特定社会保険労務士という資格があります。
2007年の社会保険労務士法改正で加えられた制度で、社会保険労務士に裁判外紛争解決手続きの代理権が与えられたものです。
解雇、セクハラ、パワハラなどの労働問題が発生し、それを白黒つけて解決していこうとすると弁護士を立てて裁判をしていくわけですが、その場合解決まで年単位の期間を考えなければならず、費用も労力もかかります。
それを裁判外で迅速に(そして費用も安く)解決できるよう、労働局のあっせんや社会保険労務士会が運営する「社労士労働紛争解決センター」でのあっせんの場において労働問題を解決していく手段があります。そのあっせんの場で会社側または労働者側の代理人となれる社会保険労務士が「特定社会保険労務士」です。
「あっせん」は裁判官が白黒つけて賠償額を決めるというのとは少々趣が違い、お互いが歩み寄って解決していく(お金の場合解決金額を決める)というスタンスで進んでいきます。
また、テレビに出てくる裁判所のように裁判官を中心に会社側労働者側左右に分かれて相対峙するものではなく、別室で進めていくので顔を合わせることもないようです。
その特定社会保険労務士の試験を昨年11月に受験し、その合格発表が今日でした。
おかげさまで合格することができました。
この合格を受けて、特定社会保険労務士となるには全国社会保険労務士会連合会の社会保険労務士名簿へ「付記」されてからなので少し先(最短で5月?)になります。
4月24日追記:付記となったのは4月1日付でした。