[種別:普通 久留里線923D 木更津7:23→上総亀山8:30]
《木更津7:23発》
キハ38+キハ37+キハ30という、久留里線気動車の見本のような編成で、923Dは木更津駅を発車しました。

内房線としばらく並走した後、久留里線は右へと舵を切ります。車窓はいかにも田舎といった雰囲気です。陽が差せば線路わきのススキがいい味を出すのですが、鉛空の下ではあまり映えません。
3両の車内は満員。カメラ姿の人も少なくありません。首都圏から一時間というロケーションは、久留里線の絶対的なアドバンテージです。おまけに今日は三連休の中日。混むことは想定していましたが、こんな朝からここまで混んでいるとは。やはり、首都圏の鉄道ファンの密集度は群を抜いています。道理で「富士・はやぶさ」最終運転(2009年3月13日)の時の東京駅のようなことが起こるわけです。
《横田7:40着》

交換設備を持つ横田で924Dとすれ違います。久留里線で列車交換ができるのはここと久留里だけです。
923Dが到着すると、既に924Dが発車待ちをしていました。

駅舎側ホーム(木更津方面)から。横田駅には久留里側に構内踏切があり、駅舎も木造。古き良き日本の鉄道をそのままに残しています。これでタブレットがあれば(2012年3月で特殊自動閉塞に切り替え)……

向かいのホーム(久留里・上総亀山方面)から。去年までタブレット交換を行っていたせいか、左側通行の鉄則が守られています。

木更津側から。ホームも5両分なので、3両の923Dと4両の924Dが並ぶと壮観です。ただ、924Dがすぐ発車してしまったので、924Dの先頭は捉えることができず。無念。

1分ほどの邂逅を経て、924Dは木更津方面に去っていきました。

923Dも出発準備に取り掛かります。
《横田7:43発》
横田からはますます住宅の姿が消え、線路の両脇が畑になります。
それまで東を向いていた列車は、東横田を出てから方向転換、南を目指します。

7:51、馬来田(まくた)着。かつてはここにも交換設備があり、使われなくなったホームが残ります。
923Dはその後も、上総の平地を走り抜けます。このあたりは山が少ないため、遠くまで続く畑を見ることができます。
小櫃(おびつ)からは久留里の市街地に入り、再び住宅街の態をなしてきます。
《久留里8:08着》
久留里では926Dと交換。この時間帯は横田・久留里の交換設備をフルに活用して1時間ヘッドでの運転になっています。ローカル線としては多い方といえるでしょう。

駅舎向かいのホーム(木更津方面)から923Dを撮ります。まだ朝(しかも二番列車)ですが、私同様カメラを構える人が多数いました。駅中央に設けられた構内踏切を、カメラを持った人がせわしなく行きかいます。

久留里駅はタブレットの名残でホームが千鳥式(乗り場が平行にずれる)になっています。そのため、構内踏切からはこのように真下のアングルで列車を見ることができました。
《久留里8:11発》
久留里までは千葉県営鉄道として初めに建設された区間なのは前回にも書いた通りですが、ここからは国鉄久留里線となってからの延伸区間に入ります。

発車数分で景色は一転。平地をのんびりと走っていたのが、高低差が際立つ山あいを走る路線に変わります。

上り勾配とカーブが連続します。
駅間も長いので、ここら辺で車内探索に出かけることにしました。


最後尾のキハ30-98ですらこの混みっぷりです。

キハ30の運転台のうち、貫通路より右側の部分は折りたたむことができます。何も障害がないので、絶好の展望スペースに。


貫通扉の黄色は久留里線の証です。

中間のキハ37-2は運転室に誰も人が乗らないので運転台観察にはもってこい。

いかにも古そうなこの装置は車掌弁といって、今で言う非常停止ボタンの役割を果たしています。空気ブレーキ車両が減った現在、車掌弁が残るケースは稀です。

キハ30に比べて扉の間隔が長いので、すっきりとした印象の車内。

反対側から。3両のうちで唯一のトイレ付車両です。


先頭のキハ38-1002。キハ30の流れをくみつつもキハ37と似た車体構造を採用しているので、キハ30とキハ37を足して2で割ったような中身になっています。残念ながら先頭はカーテンを閉め切っていて、前面展望はできませんでした。

曇り空から小雨がパラパラと振り落ちます。こんな天気でも、田んぼから列車を狙うカメラマンの姿は絶えません。
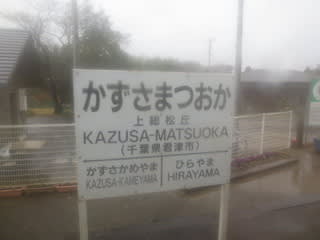
8:23、上総松丘着。小さなログハウスのような駅舎(?)が建ちます。
1時間が経過した923Dの旅も次がラストです。
《上総亀山8:30着》

鈍色の空の下、923Dは無事に上総亀山に到着しました。

ぞろぞろと乗客が上総亀山の駅舎を出ていきます。混んでいたのは鉄道ファンがいただけでなく、JR東日本の駅からハイキング(JR東海で言うところのさわやかウォーキング、JR北海道で言うところのヘルシーウォーキング)の日に当たっていたからでした。そういえば、『いかにも旅してます』感を醸し出す気合の入った服装をした年配の乗客が多いと思っていました。

上総亀山駅のホームは2両分しか対応してないため、一番後ろのキハ30はドア扱いをしません(貫通路でつながったキハ37から降りられます)。


キハ30の特徴的な吊り戸や、幕張車両センター所属を表す千マリのマークを観察します。

一旦扉を閉めた後、列車は再び前進。キハ38がホームからはみ出たところで停車します。かつては1面2線だった上総亀山駅ですが、駅舎側の線路はポイントが撤去され入れないようになっています。
キハ30が無事にホームに収まったところで、駅を出ることにします。
普段は無人ですが、この日は駅からハイキングにあわせて臨時改札が設けられていました。人でごった返す改札を、「ホリデーパス(2300円)」を見せてスルー。首都圏のJRの普通・快速列車が一日乗り放題となる切符で、久留里線は全線がフリー区間に入っています。既に千葉→上総亀山で1280円なので、半分近く元を取っています。

小雨で立ち止まる駅からハイキング参加者を尻目に駅舎を出ます。私も傘は持っていませんが、このぐらいの雨で立ち止まると思ったら大間違いだ!

駅に近い高台が一枚。駅として最低限の機能だけが揃っているのが分かります。あまりの薄暗さに、照明がついていました。

側線(機関車時代を考えると恐らくは機回し線)の向こうにも人影がちらほら。駅の周りには踏切はなく、駅の裏手に回るだけでも時間がかかります。というか、あそこは入って良いの?
この側線も駅舎側の線路同様ポイントが撤去され、現在使われていません。
折り返しの928Dの発車まで5分強となったところでホームに戻ります。が、ここにきて突然尿意が発生。駅すぐそばのトイレに駆け込みますが、ハイキング客と鉄道ファンで大混雑。どこか茂みに隠れてするか……とまで考えましたが、適当な茂みもありません。仕方なくトイレ行列に並びます。
トイレを絶った時点で残り約3分。急いで撮ります。

使われなくなった線路に哀愁を感じます。

キハ37の足回り。

JRカラーの駅名表と、国鉄色を残すキハ30の対比。



キハ30をいろいろな角度から。

先頭の出っ張りは踏切事故対策として後年つけられたものです。外吊りの扉に加えて、いかつさが増す結果となりました。
[種別:普通 久留里線928D 上総亀山8:46→木更津9:51]
《上総亀山8:46発》

15分ほどの滞在で上総亀山を後にします。

ネットで調べた運用を書き込んだ時刻表は、この旅のマストアイテム。
《久留里9:04着》

構内踏切からキハ30を捉えます。

反対には木更津からの925Dが到着。この列車は久留里止まりです。先程の923Dよりもテツ率が高い気がします。

ホームがいい具合にずれた久留里駅では、台車回りまでよく見渡せます。

キハ37の足回り。光線状態は悪いです。

1番線脇に眠る貨物ホーム。ここからの風景は、とても平成の鉄道のものとは思えません。

双方向の列車が向かい合う構内踏切付近は、もっとも人が溜まっていました。人数比からもわかる通り、国鉄色のキハ30に人気が集まっています。

編成写真を撮り終えた段階でタイムリミット。急いで構内踏切を駆け戻り、再び928Dに乗車します。
《久留里9:11発》

途中の横田で927Dと交換。写真では分かりませんが、キハ30の影に927Dが停まっています。
《木更津9:51着》

雨こそ止んだものの、結局終着木更津まで曇り模様のまま到着。
キハ38・キハ37・キハ30のゴールデントリオの朝の運用はここまで。キハ38・37の2両は941D(木更津16:46発)、キハ30に至っては日曜日の943D(木更津17:42発)までありません。土曜の夕方から日曜の朝にかけて、久留里線は全て2両になってしまうためです。







ゴールデントリオは一度祇園寄りの引き込み線に入った後、側線を通って車庫奥の電留線に引き上げていきました。
久留里線1往復目。これにて終了です。
(その3に続く)
《木更津7:23発》
キハ38+キハ37+キハ30という、久留里線気動車の見本のような編成で、923Dは木更津駅を発車しました。

内房線としばらく並走した後、久留里線は右へと舵を切ります。車窓はいかにも田舎といった雰囲気です。陽が差せば線路わきのススキがいい味を出すのですが、鉛空の下ではあまり映えません。
3両の車内は満員。カメラ姿の人も少なくありません。首都圏から一時間というロケーションは、久留里線の絶対的なアドバンテージです。おまけに今日は三連休の中日。混むことは想定していましたが、こんな朝からここまで混んでいるとは。やはり、首都圏の鉄道ファンの密集度は群を抜いています。道理で「富士・はやぶさ」最終運転(2009年3月13日)の時の東京駅のようなことが起こるわけです。
《横田7:40着》

交換設備を持つ横田で924Dとすれ違います。久留里線で列車交換ができるのはここと久留里だけです。
923Dが到着すると、既に924Dが発車待ちをしていました。

駅舎側ホーム(木更津方面)から。横田駅には久留里側に構内踏切があり、駅舎も木造。古き良き日本の鉄道をそのままに残しています。これでタブレットがあれば(2012年3月で特殊自動閉塞に切り替え)……

向かいのホーム(久留里・上総亀山方面)から。去年までタブレット交換を行っていたせいか、左側通行の鉄則が守られています。

木更津側から。ホームも5両分なので、3両の923Dと4両の924Dが並ぶと壮観です。ただ、924Dがすぐ発車してしまったので、924Dの先頭は捉えることができず。無念。

1分ほどの邂逅を経て、924Dは木更津方面に去っていきました。

923Dも出発準備に取り掛かります。
《横田7:43発》
横田からはますます住宅の姿が消え、線路の両脇が畑になります。
それまで東を向いていた列車は、東横田を出てから方向転換、南を目指します。

7:51、馬来田(まくた)着。かつてはここにも交換設備があり、使われなくなったホームが残ります。
923Dはその後も、上総の平地を走り抜けます。このあたりは山が少ないため、遠くまで続く畑を見ることができます。
小櫃(おびつ)からは久留里の市街地に入り、再び住宅街の態をなしてきます。
《久留里8:08着》
久留里では926Dと交換。この時間帯は横田・久留里の交換設備をフルに活用して1時間ヘッドでの運転になっています。ローカル線としては多い方といえるでしょう。

駅舎向かいのホーム(木更津方面)から923Dを撮ります。まだ朝(しかも二番列車)ですが、私同様カメラを構える人が多数いました。駅中央に設けられた構内踏切を、カメラを持った人がせわしなく行きかいます。

久留里駅はタブレットの名残でホームが千鳥式(乗り場が平行にずれる)になっています。そのため、構内踏切からはこのように真下のアングルで列車を見ることができました。
《久留里8:11発》
久留里までは千葉県営鉄道として初めに建設された区間なのは前回にも書いた通りですが、ここからは国鉄久留里線となってからの延伸区間に入ります。

発車数分で景色は一転。平地をのんびりと走っていたのが、高低差が際立つ山あいを走る路線に変わります。

上り勾配とカーブが連続します。
駅間も長いので、ここら辺で車内探索に出かけることにしました。


最後尾のキハ30-98ですらこの混みっぷりです。

キハ30の運転台のうち、貫通路より右側の部分は折りたたむことができます。何も障害がないので、絶好の展望スペースに。


貫通扉の黄色は久留里線の証です。

中間のキハ37-2は運転室に誰も人が乗らないので運転台観察にはもってこい。

いかにも古そうなこの装置は車掌弁といって、今で言う非常停止ボタンの役割を果たしています。空気ブレーキ車両が減った現在、車掌弁が残るケースは稀です。

キハ30に比べて扉の間隔が長いので、すっきりとした印象の車内。

反対側から。3両のうちで唯一のトイレ付車両です。


先頭のキハ38-1002。キハ30の流れをくみつつもキハ37と似た車体構造を採用しているので、キハ30とキハ37を足して2で割ったような中身になっています。残念ながら先頭はカーテンを閉め切っていて、前面展望はできませんでした。

曇り空から小雨がパラパラと振り落ちます。こんな天気でも、田んぼから列車を狙うカメラマンの姿は絶えません。
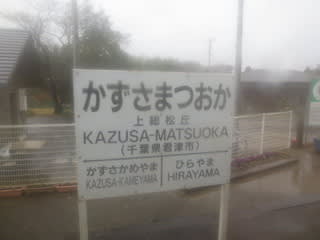
8:23、上総松丘着。小さなログハウスのような駅舎(?)が建ちます。
1時間が経過した923Dの旅も次がラストです。
《上総亀山8:30着》

鈍色の空の下、923Dは無事に上総亀山に到着しました。

ぞろぞろと乗客が上総亀山の駅舎を出ていきます。混んでいたのは鉄道ファンがいただけでなく、JR東日本の駅からハイキング(JR東海で言うところのさわやかウォーキング、JR北海道で言うところのヘルシーウォーキング)の日に当たっていたからでした。そういえば、『いかにも旅してます』感を醸し出す気合の入った服装をした年配の乗客が多いと思っていました。

上総亀山駅のホームは2両分しか対応してないため、一番後ろのキハ30はドア扱いをしません(貫通路でつながったキハ37から降りられます)。


キハ30の特徴的な吊り戸や、幕張車両センター所属を表す千マリのマークを観察します。

一旦扉を閉めた後、列車は再び前進。キハ38がホームからはみ出たところで停車します。かつては1面2線だった上総亀山駅ですが、駅舎側の線路はポイントが撤去され入れないようになっています。
キハ30が無事にホームに収まったところで、駅を出ることにします。
普段は無人ですが、この日は駅からハイキングにあわせて臨時改札が設けられていました。人でごった返す改札を、「ホリデーパス(2300円)」を見せてスルー。首都圏のJRの普通・快速列車が一日乗り放題となる切符で、久留里線は全線がフリー区間に入っています。既に千葉→上総亀山で1280円なので、半分近く元を取っています。

小雨で立ち止まる駅からハイキング参加者を尻目に駅舎を出ます。私も傘は持っていませんが、このぐらいの雨で立ち止まると思ったら大間違いだ!

駅に近い高台が一枚。駅として最低限の機能だけが揃っているのが分かります。あまりの薄暗さに、照明がついていました。

側線(機関車時代を考えると恐らくは機回し線)の向こうにも人影がちらほら。駅の周りには踏切はなく、駅の裏手に回るだけでも時間がかかります。というか、あそこは入って良いの?
この側線も駅舎側の線路同様ポイントが撤去され、現在使われていません。
折り返しの928Dの発車まで5分強となったところでホームに戻ります。が、ここにきて突然尿意が発生。駅すぐそばのトイレに駆け込みますが、ハイキング客と鉄道ファンで大混雑。どこか茂みに隠れてするか……とまで考えましたが、適当な茂みもありません。仕方なくトイレ行列に並びます。
トイレを絶った時点で残り約3分。急いで撮ります。

使われなくなった線路に哀愁を感じます。

キハ37の足回り。

JRカラーの駅名表と、国鉄色を残すキハ30の対比。



キハ30をいろいろな角度から。

先頭の出っ張りは踏切事故対策として後年つけられたものです。外吊りの扉に加えて、いかつさが増す結果となりました。
[種別:普通 久留里線928D 上総亀山8:46→木更津9:51]
《上総亀山8:46発》

15分ほどの滞在で上総亀山を後にします。

ネットで調べた運用を書き込んだ時刻表は、この旅のマストアイテム。
《久留里9:04着》

構内踏切からキハ30を捉えます。

反対には木更津からの925Dが到着。この列車は久留里止まりです。先程の923Dよりもテツ率が高い気がします。

ホームがいい具合にずれた久留里駅では、台車回りまでよく見渡せます。

キハ37の足回り。光線状態は悪いです。

1番線脇に眠る貨物ホーム。ここからの風景は、とても平成の鉄道のものとは思えません。

双方向の列車が向かい合う構内踏切付近は、もっとも人が溜まっていました。人数比からもわかる通り、国鉄色のキハ30に人気が集まっています。

編成写真を撮り終えた段階でタイムリミット。急いで構内踏切を駆け戻り、再び928Dに乗車します。
《久留里9:11発》

途中の横田で927Dと交換。写真では分かりませんが、キハ30の影に927Dが停まっています。
《木更津9:51着》

雨こそ止んだものの、結局終着木更津まで曇り模様のまま到着。
キハ38・キハ37・キハ30のゴールデントリオの朝の運用はここまで。キハ38・37の2両は941D(木更津16:46発)、キハ30に至っては日曜日の943D(木更津17:42発)までありません。土曜の夕方から日曜の朝にかけて、久留里線は全て2両になってしまうためです。







ゴールデントリオは一度祇園寄りの引き込み線に入った後、側線を通って車庫奥の電留線に引き上げていきました。
久留里線1往復目。これにて終了です。
(その3に続く)


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます