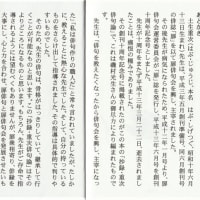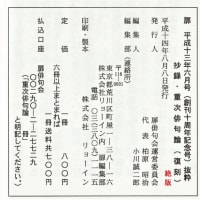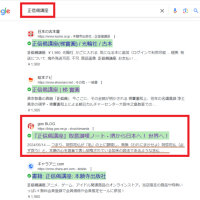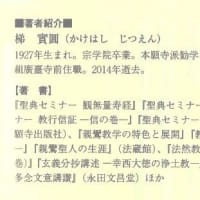前田秀一 プロフィール
私が、読書を意識したのは中学生の頃、当時としては珍しくなかった越境通学をしていた電車の中で、父から買ってもらった「偉人伝」を夢中になって読んでいた時のことでした。
今につながる『親鸞聖人』は格別として、何故か、『渡辺崋山』が未だに印象が強く残っております。世界史観を持った芸術的知識人に憧れたということでしょうか。
『親鸞聖人』は、その後、『出家とその弟子』(倉田百三著)に繫がり、『歎異抄』(唯円房著)、そして、1974年母の死を機縁として日常の聴聞に与っている恵日山 眞光寺若院・木村世雄博士(文学)からの『Ocean 真宗入門』(ケネス・タナカ著、島津恵正訳、2003年)ご紹介に繋がり信心を深めるに至っております。
中学、高校時代に親友の兄上の感化を受けて大阪市立大学に進学し、同級の友人から『ナイロンの発見』(井本稔著、創元社百花文庫・初版本)を紹介され、「応用化学」を専攻したことに我が意を得た思いに浸りました。
東洋文化の「華」ともいわれ、中世には世界的に商取引の貴重品であった「絹」糸を化学合成の力で創出するという壮大なテーマに挑戦して、「ナイロン」(ポリアミド繊維)を世に出したアメリカ・デュポンの若き化学者・カローザスの生き様が描かれていました。
その結末は、さらに高強度の繊維、後の「テトロン」(ポリエステル繊維)の開発を目指して挑戦している最中、悩み、苦しみの果てに自ら命を絶つという壮絶な人生を送った偉人の物語でした。
その著者・井本稔先生こそ、「高分子化学」専攻(井本研究室)⇒「大日本インキ化学工業株式会社」と私の人生の道の選択に大きく関わっていただくこととなった恩師でありました。
当時、自称日本の「MIT(マサチュセッツ工科大学)」といわれた大阪市立大学に在籍したお陰で、教養部時代には気鋭の先生方による講義受講の機会に恵まれ、その後の我が人生に大きく影響を受けることになりました。
梅棹忠夫(当時・理学部生物学科生物生態学専攻助教授 ⇒ 国立民族学博物館長)
『日本探検』(1960)、『文明の生態学史観』(1967)、『知的生産の技術』(1969)
川喜田二郎(当時・文学部地理学助教授 ⇒ KJ法本部・川喜田研究所理事長)
『日本文化探検』(1961)、『発想法』(1967)
2002年(平成14年)7月末、40年間在職したDIC株式会社を退職して娘の家族の招きに応じて「自分探し」の旅に出た時、北海道・旭川「三浦綾子文学記念館」で、『千利休とその妻たち』上・下巻に出迎えられ驚きました。
最果ての地と思っていた旭川で「堺」の文化を発見したという驚きは、カルチャー・ショックとも言え、日ごろ無頓着でいた我が終の棲家・「堺」の歴史と文化の重みに気付かされました。
その取り組みの方法を模索する中、立ち寄った旭屋書店の店頭に積み上げられた「NPO」のキーワードは、私に新しい人生観を与えてくれました。
『やさしいNPO法の解説』(橘幸信、正木寛也、1998年)
『NPO 起業・経営・ネットワーキング』(今田 忠、2000年)
想いを新たに、「堺」の再発見、再生、創造、魅力情報の発信をライフワークとして取組むことを心に決め、改めて視野を世界に向けた時、堺市と20年間に渡って友好提携関係にある中国・連雲港市との交流のあり方が見えてきました。
その想いの結果として、「徐福伝説」との出会いがあり、「徐福論」を学位論文テーマとして取組んでいる新進気鋭の学者・逵 志保博士(国際文化:愛知県立大学非常勤講師)との交流が始り、伝説のダイナミズムを学ばせていただきました。
『徐福伝説考』(1991年)、『徐福論-いまを生きる伝説』(2004年)
さらに、作家・池上正治先生との出会いに導かれ、ご薫陶をいただいて“徐福”の故郷・連雲港市「第5回カン楡県徐福祭」で我がまち「堺」の歴史と文化を紹介し、友好交流を市民のテーマと位置づける取り組みについてご紹介する光栄に恵まれました。
『徐福-日中韓をむすんだ「幻」のエリート集団』(2007年)
「徐福伝説」への取り組みの中で、堺市博物館長・角山 榮先生にご縁をいただき、初心に帰って「茶の湯」の文化を学ぶこととなり、その実践の方向づけとして、角山先生ご提唱の「CHAの心」に接し原点回帰いたしました。
『堺-海の都市文明』(2000年)、『茶の世界史』(1980年初版)
CHA:Communication、Hospitality、Associate
そして今、「CHAの心」の実践の中から新たな出会いに恵まれ、“すずめ踊り”を絆として杜の都・仙台と都市間交流を目指す堺の“まち”文化の創造に取組む機会を得ております。
『堺市史』第7巻別編(堺市、1930年)
『仙台市史』第15回配本 全30巻 通史編3 近世1
(仙台市史編さん委員会、2001年)
マハトマ・ガンジー「変化を見たいなら、あなたがその変化になればいい」。
“すずめ踊り”を通した仲間から、衝撃的な言葉を教えていただき、目からうろこがこぼれ落ちた思いになりました。
そうだ、心に積み残していた原点に取り組もうと多くの先達の研究成果(文献)に導かれて、「十六世紀 茶の湯におけるキリシタン受容の構図」に関する小論を発表しました。
論文 「十六世紀 茶の湯におけるキリシタン受容の構図」
註(引用文献)および参考文献 -私の後世に豊かな示唆を与えていただいた論文
この小論の成果は、私を、さらに『山上宗二記』へ導き、その中に臨済禅の公案でもあるかのように茶湯者の覚悟十體として記されている「濃茶呑ヤウ」という言葉に釘づけになりました。その公案の意図するところを追い求めて、この度、「茶湯者の覚悟“濃茶呑ヤウ」を発表しました。
論文 『山上宗二記』 「茶湯者の覚悟“濃茶呑ヤウ”」
SDGs魅力情報 堺から日本へ!世界へ! 詳しくはこちらから