サルベージしたOASYSのフロッピーディスクから小説が出てきたので試しにアップしてみます。方向性迷走ついでに、もはや何でもありという感じです。もうやけくそです。万が一反応がそれなりにあったら続きupします(笑)
いつの日かきっと海賊がきて
私のことをさらって行ってくれる。
私のことをさらって行ってくれる。
イネは口にこそ出しはしなかったが、ずっとそう思いながら暮らしてきた。
その事を兄の七平にさえも秘密にしてきたのは「願い事」というものはむやみに人に話すものではないと信じていたからでもなければ、その考えの馬鹿さ加減…とりわけこんな山奥に海賊たちがやって来るなどという荒唐無稽さ…に気がついていたからでもなかった。
自分をここから「救出」する企てを成功させるには、すべてが秘密のうちに行われなければならない─────そう信じていたからに他ならなかった。
その事を兄の七平にさえも秘密にしてきたのは「願い事」というものはむやみに人に話すものではないと信じていたからでもなければ、その考えの馬鹿さ加減…とりわけこんな山奥に海賊たちがやって来るなどという荒唐無稽さ…に気がついていたからでもなかった。
自分をここから「救出」する企てを成功させるには、すべてが秘密のうちに行われなければならない─────そう信じていたからに他ならなかった。
一週間降り続いた大雪は大晦日の朝になっても一向に止む気配はなかった。
小屋の前の雪をどけてなんとか出入り口だけはは確保しているものの、今日も猟には出られそうにない。
戸口に立ち七平は目を細めて大きく天を仰いだが、どんよりと鉛色にくすんでいるはずの雲さえもはげしい吹雪のせいで見る事はできなかった。
家の中に戻ると小屋の中央の囲炉裏の前にぼけっと座り込み、ただじっと火を見つめている妹の姿が視界に入ってくる。
忌々しいやつめ!もう一週間も俺様はこの光景を見せられ続けてきたのだ。
思えばこいつは生まれた時からこうだったような気がする。何もしない為に生まれてきた汚らしい肉塊、神々の排泄物───それがこのイネという女なのだ。
小屋の前の雪をどけてなんとか出入り口だけはは確保しているものの、今日も猟には出られそうにない。
戸口に立ち七平は目を細めて大きく天を仰いだが、どんよりと鉛色にくすんでいるはずの雲さえもはげしい吹雪のせいで見る事はできなかった。
家の中に戻ると小屋の中央の囲炉裏の前にぼけっと座り込み、ただじっと火を見つめている妹の姿が視界に入ってくる。
忌々しいやつめ!もう一週間も俺様はこの光景を見せられ続けてきたのだ。
思えばこいつは生まれた時からこうだったような気がする。何もしない為に生まれてきた汚らしい肉塊、神々の排泄物───それがこのイネという女なのだ。
この雪がやんだら山を降りよう───七平はそう心に決めていた。
町に何かあてがあるわけではなかった。が、このままここにいると自分はこの女のこともきっと殺してしまうだろうという懸念が頭の中にはあった。
実際彼は1年程前から寝たきりになっていた母にも毒キノコの汁を飲ませ続けて昨晩とうとう殺してしまったのだった。
生まれてこのかた数十年、人里はなれた山の中でろくに教育も受けずに育った七平でも実の母を我が手にかけて微塵の罪悪感も感じなような人間が尋常でないという事くらいはわかっていた。
が、寧ろ彼は自分をそんな状況に追い込んだこの環境に対して恨めしく思い、ここから抜け出す事こそが救われる為の唯一の方法であると信じて疑わなかった。
町に何かあてがあるわけではなかった。が、このままここにいると自分はこの女のこともきっと殺してしまうだろうという懸念が頭の中にはあった。
実際彼は1年程前から寝たきりになっていた母にも毒キノコの汁を飲ませ続けて昨晩とうとう殺してしまったのだった。
生まれてこのかた数十年、人里はなれた山の中でろくに教育も受けずに育った七平でも実の母を我が手にかけて微塵の罪悪感も感じなような人間が尋常でないという事くらいはわかっていた。
が、寧ろ彼は自分をそんな状況に追い込んだこの環境に対して恨めしく思い、ここから抜け出す事こそが救われる為の唯一の方法であると信じて疑わなかった。
囲炉裏をはさんだ妹の向かい側には数時間前に息絶えたばかりの母の亡骸が熊の毛皮を被ったまま横たわっていた。
そして排泄物のつーんと鼻をつくような匂いが小屋の中をただよっていた。
それらが死んでからの肉体の弛緩によるものか、それともその前のモノなのかといった考えても仕方のないどうしようもない事が何故かふと彼の頭をよぎった。
いずれにせよ、この悪臭から逃れるためには死体を外に出す必要があった。
そして排泄物のつーんと鼻をつくような匂いが小屋の中をただよっていた。
それらが死んでからの肉体の弛緩によるものか、それともその前のモノなのかといった考えても仕方のないどうしようもない事が何故かふと彼の頭をよぎった。
いずれにせよ、この悪臭から逃れるためには死体を外に出す必要があった。
「ひもじいよ」
この一週間ひとことも口を聞かなかったイネが始めて口を開いた。
「なんだとぉ!」七平の頭の中には反射的に怒りがこみあげた。
この穀潰しのメス豚め!いやブタだったならいっそ潰して食ってしまえたものを!
「ひもじ・・・」とイネが再び言ったがはやいか七平は妹のことを力一杯ケリあげた。哀れな妹はボロ雑巾のようにようにその場にうずくまり暫く動かなかったがまた九官鳥のように無表情に声を発した。
「あんちゃん・・・くいもん」
決して広くはない小屋の中に再び鈍く重い音が響く。
この一週間ひとことも口を聞かなかったイネが始めて口を開いた。
「なんだとぉ!」七平の頭の中には反射的に怒りがこみあげた。
この穀潰しのメス豚め!いやブタだったならいっそ潰して食ってしまえたものを!
「ひもじ・・・」とイネが再び言ったがはやいか七平は妹のことを力一杯ケリあげた。哀れな妹はボロ雑巾のようにようにその場にうずくまり暫く動かなかったがまた九官鳥のように無表情に声を発した。
「あんちゃん・・・くいもん」
決して広くはない小屋の中に再び鈍く重い音が響く。
兄は何回か本気で妹を蹴った後に今度は襟頸を引っ掴み狂ったように顔といわず頭といわず只々ひたすら殴打した。
気がつくと再びボロ雑巾の前でぼんやりと立ち尽くしている自分に気づく。
手がやけに痛い。
ゆっくりと手を顔の前までもっていき、恐る恐る手を裏返してみる。
血がべっとりとつき丁度薬指の甲のあたりに折れた黄色い歯がささっていた。
メスブタは死んでしまったのだろうか?結局俺はたった二人しかいなかった家族を皆殺しにしてしまったのだろうか?と考えてはみたものの、それは今となっては七平にとってどうでも良い事であった。
どっちにしても俺は雪が止んだら山を降りる。そしてその日はもうそこまでやって来ているのだ。
そう考えると七平の胸には今までは決して感じた事のなかった不思議な期待のようなものがこみ上げてくるのだった。
山を降りたらまず最初に何をしようか。七平はこのところその事ばかり考えていたが生まれてこのかた殆ど山を降りた事のない彼にとって、山は毎晩見ている星空よりも遠い得体の知れない存在だったので結局何も思いつきはしなかった。
どんなに大きな樹にのぼっても到底手でふれる事のできない夜空でさえ、その星の並びかたまで正確に言う事ができるというのに、その日のうちに降りることのできる山の下での生活はまるで想像できないのはどうしてなのだろう?
そういった不思議さについて考えるだけでも充分楽しかったし、完全に自分の価値観を越えたところにある世界の事も結局何も思いつかないのに、あえて考えようと足掻いてみる行為そのものが心地よかった。
思えば彼は生まれてこのかたこの山での生活の中で、こんな風に頭を使って想像をめぐらす事は一度だってなかった。だから今は思索にふけっているだけでも充分に興奮する事ができた。
明日には雪は止むだろうか?遅くとも三日以内には止むだろう。そう思うとまたもや山の下での生活の事を考えたくなった。が、やはり何も思いつかなかった。
手がやけに痛い。
ゆっくりと手を顔の前までもっていき、恐る恐る手を裏返してみる。
血がべっとりとつき丁度薬指の甲のあたりに折れた黄色い歯がささっていた。
メスブタは死んでしまったのだろうか?結局俺はたった二人しかいなかった家族を皆殺しにしてしまったのだろうか?と考えてはみたものの、それは今となっては七平にとってどうでも良い事であった。
どっちにしても俺は雪が止んだら山を降りる。そしてその日はもうそこまでやって来ているのだ。
そう考えると七平の胸には今までは決して感じた事のなかった不思議な期待のようなものがこみ上げてくるのだった。
山を降りたらまず最初に何をしようか。七平はこのところその事ばかり考えていたが生まれてこのかた殆ど山を降りた事のない彼にとって、山は毎晩見ている星空よりも遠い得体の知れない存在だったので結局何も思いつきはしなかった。
どんなに大きな樹にのぼっても到底手でふれる事のできない夜空でさえ、その星の並びかたまで正確に言う事ができるというのに、その日のうちに降りることのできる山の下での生活はまるで想像できないのはどうしてなのだろう?
そういった不思議さについて考えるだけでも充分楽しかったし、完全に自分の価値観を越えたところにある世界の事も結局何も思いつかないのに、あえて考えようと足掻いてみる行為そのものが心地よかった。
思えば彼は生まれてこのかたこの山での生活の中で、こんな風に頭を使って想像をめぐらす事は一度だってなかった。だから今は思索にふけっているだけでも充分に興奮する事ができた。
明日には雪は止むだろうか?遅くとも三日以内には止むだろう。そう思うとまたもや山の下での生活の事を考えたくなった。が、やはり何も思いつかなかった。
そのうち七平はいつしかその場でうとうととまどろんでいた。
それは丑の刻ぐらいだっただろうか?七平はドンドンという小屋の木の戸を激しく叩く音におこされた。
彼が意識がまだはっきりと覚醒しないうちにその音はバキバキと木を無理矢理突き破る音に変わっていた。
七平が慌てて上体を起こした時にはもう既に真夜中の客たちが壊れた戸口から吹き込む吹雪ととも中に行進を始めていた。
「ひい、ふう、みい・・・・・」
彼らの身長が子供のように小さかったからだろうか?それとも戸を壊した以外は別段、殺気のようなモノは感じさせず極めて穏やかに蟻のように規則正しく縦に並んで入ってきたせいだろうか?
七平の心はこの異常な事態の中でも不思議と穏やかなままで、なぜか正体不明の小鬼たちの数をゆっくりと数えていた。
珍客たちはみな同じ風貌でその身の丈は七平の腰のあたりに届くくらいしかなかった。全員が全員ボロボロの布をまとい前には赤いよだれかけのような物をかけ、顔はとすえば、そう、顔には三日月の形に覗窓をくりぬいた不気味に笑ったような表情の石の仮面をつけていた。
その小鬼たちは真っ直ぐ一列に行進し壁に張りつくように規則正しく並んで止まった。
七番目の小人だけは戸のところでくるりと振り向いて自分たちが入ってきた「穴」に向かって蚕の糸のようなものを吐き出した。
いったいそれが彼の何処から出されているのかは七兵のいる角度からは見ることができなかったが、その糸は間もなくその穴を完全に塞ぎ、もう吹雪がはいって来る事もなかった。
その作業が終わるとそいつも列の最後尾に同じように並んでそして七人の小鬼たちは置物のように動かなくなった。
彼が意識がまだはっきりと覚醒しないうちにその音はバキバキと木を無理矢理突き破る音に変わっていた。
七平が慌てて上体を起こした時にはもう既に真夜中の客たちが壊れた戸口から吹き込む吹雪ととも中に行進を始めていた。
「ひい、ふう、みい・・・・・」
彼らの身長が子供のように小さかったからだろうか?それとも戸を壊した以外は別段、殺気のようなモノは感じさせず極めて穏やかに蟻のように規則正しく縦に並んで入ってきたせいだろうか?
七平の心はこの異常な事態の中でも不思議と穏やかなままで、なぜか正体不明の小鬼たちの数をゆっくりと数えていた。
珍客たちはみな同じ風貌でその身の丈は七平の腰のあたりに届くくらいしかなかった。全員が全員ボロボロの布をまとい前には赤いよだれかけのような物をかけ、顔はとすえば、そう、顔には三日月の形に覗窓をくりぬいた不気味に笑ったような表情の石の仮面をつけていた。
その小鬼たちは真っ直ぐ一列に行進し壁に張りつくように規則正しく並んで止まった。
七番目の小人だけは戸のところでくるりと振り向いて自分たちが入ってきた「穴」に向かって蚕の糸のようなものを吐き出した。
いったいそれが彼の何処から出されているのかは七兵のいる角度からは見ることができなかったが、その糸は間もなくその穴を完全に塞ぎ、もう吹雪がはいって来る事もなかった。
その作業が終わるとそいつも列の最後尾に同じように並んでそして七人の小鬼たちは置物のように動かなくなった。
【自分で勝手に解説】
あの書き出しだとイネは主人公か、少なくとも主要人物のひとりみたいな雰囲気を醸し出していますが、いきなり殺されるとは自分で読んでてびっくりです(笑)。
小鬼のくだりはどこか「1Q84」を彷彿とさせますが、OASYSの取説の発行年を見ると1991年6月となっているので随分と昔に書いたはずです。
冒頭に記した「サルベージ」というのはソニーのVAIOノートを購入した時にリッチテキストコンバーターというソフトも併せて買ったのでオアシス故障後に眠っていたワープロフロッピーが晴れてPCで読み込めるようになったという寸法です。
ちなみにOASYSというのは富士通から発売されていたワープロ専用機です。ワープロのことをちゃんと説明しようとすると2投稿分くらい必要なのですが今回はやめておきます。
     |











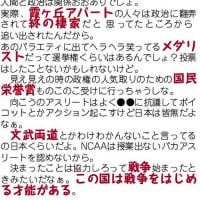
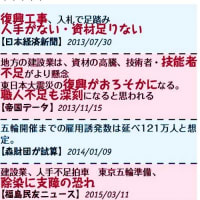












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます