昨日の「情報ライブ ミヤネ屋」高木美也子氏 、松尾貴史氏らコメンテーターが
「裁判員制度がはじまれば私たちが死刑の判断をしなければならない、いきなり重罪からではなく窃盗など市民生活に身近なものからにしてくれたらよかったに」
…というような趣旨のことを言った。
いつも強気のコメンター陣が困惑し、狼狽えているようにすら見えた。
ここに死刑存廃論議の本質があるのではないかと思った。
世論調査をすると80%が死刑存続派だというけど、賛成派の中身もいろいろあるんぢゃないだろうか?
たとえば「死」といものの意味を考え、内容を積極的に吟味してその上での賛成者、ってこととなるとなるとやっぱり廃止派と同じくらいしかいないんぢゃねーのか?…って思えてしまうのだ。
つまり…「死刑制度」という大きなオブジェが鎮座しているのが今の状況だとすれば、それを必死にどかそうとするのが廃止派で、賛成派の大半というのはその前にただ座っている人たちなんぢゃないか?いや、「あんな大きな物を移動させるヤツなんていないさ」とばかりに、その前にすらいないかもしれない。
これが逆の立場だったらどうだろう?
いや逆でなくってもいい、例えばそのオブジェが“法案”という仮置き場にあるとしよう。
その場所から賛成派は“施行エリア”をめざし、反対派で“廃案エリア”をめざして引っ張りあいましょう!といった場合に賛成軍団に参加する人が本当に80%もいるのだろうか?と思ってしまうのだ。
もっと乱暴な言い方をさせてもらえれば、この問題に限らず“現状維持派”というのは極端なハナシ、思考停止していても成り立つのではないか。
「本当にダメな制度ならとっくになくなっているはずだ」とい人もいるけれど、ダメなものなのになくならない政治や行政のゴミは世の中には掃いて捨てるほどある。
悪事を犯した手足を押さえつけ、暴れる心を諫めるのが「通常の刑罰」だとすると、息の根を止めてしまう「死刑」はあきらかに異質なものだ。
それがいいとか悪いとかいう評価は別として次元が違うものだということについては多くの理解が得られるんぢゃないだろうか。
だからその異質な「死」というものを徹底的に考察したうえで出た死刑存続論があればある意味それは廃止論よりもさらに高度な理屈になりえるかもしれない。
でも、いずれにしてもその理屈を理解、納得することなしに裁判員として「死」の決定に参加しなければならないという状況はコワイくて仕方がない。
今回のもし弁護側が「復活の儀式」とか突飛なことをいわずに、しおらしく反省を見せていれば死刑は回避できた可能性があったという専門家の意見があったけど、「生」と「「死」の「境界線」ってそんなもんなの?…って思ってしまう。
もしそうだとしたら、同じウソをつくにしても反省してるフリのほうがラクなのに…ひょっとしたら、突飛な発言はホント?とか深読みをしてしまう。
某新聞の社説に
「今回の判決はやむを得ないとしても、未成熟な少年が立ち直る機会を奪われてしまう恐れがないかどうかも、冷静に考えたい。」
「今回の判決はやむを得ないとしても」というところに読者からの批判をかわそうという意図がみえみえだ。
むしろ、専門家でも判断が難しいといわれている死刑判断の唯一の基準だった「永山基準」の突然の崩壊、規制緩和されたという、このターニグポイントを含めて論議してくれなきゃ…。
だって来年からおいらたちは死刑執行かかわらなきゃいけないんだ。
「裁判員制度がはじまれば私たちが死刑の判断をしなければならない、いきなり重罪からではなく窃盗など市民生活に身近なものからにしてくれたらよかったに」
…というような趣旨のことを言った。
いつも強気のコメンター陣が困惑し、狼狽えているようにすら見えた。
ここに死刑存廃論議の本質があるのではないかと思った。
世論調査をすると80%が死刑存続派だというけど、賛成派の中身もいろいろあるんぢゃないだろうか?
たとえば「死」といものの意味を考え、内容を積極的に吟味してその上での賛成者、ってこととなるとなるとやっぱり廃止派と同じくらいしかいないんぢゃねーのか?…って思えてしまうのだ。
つまり…「死刑制度」という大きなオブジェが鎮座しているのが今の状況だとすれば、それを必死にどかそうとするのが廃止派で、賛成派の大半というのはその前にただ座っている人たちなんぢゃないか?いや、「あんな大きな物を移動させるヤツなんていないさ」とばかりに、その前にすらいないかもしれない。
これが逆の立場だったらどうだろう?
いや逆でなくってもいい、例えばそのオブジェが“法案”という仮置き場にあるとしよう。
その場所から賛成派は“施行エリア”をめざし、反対派で“廃案エリア”をめざして引っ張りあいましょう!といった場合に賛成軍団に参加する人が本当に80%もいるのだろうか?と思ってしまうのだ。
もっと乱暴な言い方をさせてもらえれば、この問題に限らず“現状維持派”というのは極端なハナシ、思考停止していても成り立つのではないか。
「本当にダメな制度ならとっくになくなっているはずだ」とい人もいるけれど、ダメなものなのになくならない政治や行政のゴミは世の中には掃いて捨てるほどある。
悪事を犯した手足を押さえつけ、暴れる心を諫めるのが「通常の刑罰」だとすると、息の根を止めてしまう「死刑」はあきらかに異質なものだ。
それがいいとか悪いとかいう評価は別として次元が違うものだということについては多くの理解が得られるんぢゃないだろうか。
だからその異質な「死」というものを徹底的に考察したうえで出た死刑存続論があればある意味それは廃止論よりもさらに高度な理屈になりえるかもしれない。
でも、いずれにしてもその理屈を理解、納得することなしに裁判員として「死」の決定に参加しなければならないという状況はコワイくて仕方がない。
今回のもし弁護側が「復活の儀式」とか突飛なことをいわずに、しおらしく反省を見せていれば死刑は回避できた可能性があったという専門家の意見があったけど、「生」と「「死」の「境界線」ってそんなもんなの?…って思ってしまう。
もしそうだとしたら、同じウソをつくにしても反省してるフリのほうがラクなのに…ひょっとしたら、突飛な発言はホント?とか深読みをしてしまう。
某新聞の社説に
「今回の判決はやむを得ないとしても、未成熟な少年が立ち直る機会を奪われてしまう恐れがないかどうかも、冷静に考えたい。」
「今回の判決はやむを得ないとしても」というところに読者からの批判をかわそうという意図がみえみえだ。
むしろ、専門家でも判断が難しいといわれている死刑判断の唯一の基準だった「永山基準」の突然の崩壊、規制緩和されたという、このターニグポイントを含めて論議してくれなきゃ…。
だって来年からおいらたちは死刑執行かかわらなきゃいけないんだ。










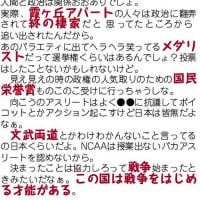
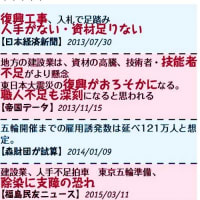







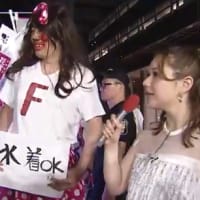





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます