 卒業式の練習に入る前に子どもに必ず確認することがあります。
卒業式の練習に入る前に子どもに必ず確認することがあります。まず、目をつむらせて
「君たちの前に2つの箱があるとします。一つは、大きな箱だけどあまり心がこもっていないものが入っています。もう一つは、箱は小さいけど、心がたっぷり入っています。どちらか一つを受け取るとしたら、君たちはどちらを選びますか?」
こういって、目をつむったまま挙手させます。
こういうと、ほとんどの子どもが、小さくても心が入っている方に手を挙げます。
そこで、
「私も、君たちと同じです。それだけ、心が入っていると言うことは大事なことなのですね。」
と語りかけます。
卒業式の練習では、歩き方、証書の受け取り方、着座の姿勢、礼の仕方など・・・、どうしても形式がの指導が必要なので、肝心の心が抜けてしまうこともあります。
「では、どんな心だと思いますか?」
と続けます。
心構えができている場合には、
「中学校へ行ってもがんばりますという決意の心。」
「在校生に、後の学校をよろしく頼むという心だと思います。」
「両親や先生方へ、これまで温かいご指導をありがとうございましたという感謝の心。」
とすばらしい意見が子どもたちから出てきます。
もし、言葉で出てこなくても、少し小出しにヒントをあげると、必ず、それに似た言葉が子どもから出てくるはずです。思いを引き出してあげるのです。
その上で、
「心というものには、形がありません。卒業式は、その心を形にして表す場です。」
と話します。
お辞儀、旅立ちの言葉、証書授与の動き方、歌・・・、すべてその心とつなげて表してみましょう。
ここまで、話すと子どもたちは、きっと、わかるはずです。在校生にも同じように指導します。全員がこのような気持ちで式に臨めば、きっと、心温まる式ができることでしょう。
あとは、練習で真剣に指導を重ねることです。そして、所々で評価を返し、進歩を認めてあげることだと思います。
PS:この時期、具合が悪くて無理をしている子どもが必ずいますので、体育館での練習では、全体を見ながらも、一人一人の子どもの顔色をじっと見てあげてください。以前、合奏をしているときにステージの端に立っていた子が、一瞬ふらっとして落下しかけたのを、全速力で走って駆け寄り、抱き抱えて事なきを得たことがあります。それ以来、この時期の健康観察は、入念に行うようにしています。













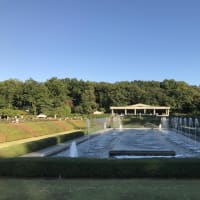




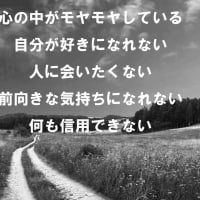



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます