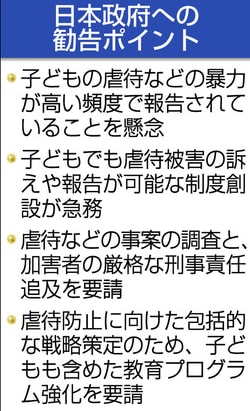丹野 清人 平成31年02月09日 11:15
単一国籍制度の国は、世界で少数派
2018年の夏、テニスの大坂なおみ選手の快挙が日本を沸かせた。全米オープンで初優勝を飾った彼女はハイチ系アメリカ人の父親と日本人の母親のもと、日米で育った経歴を持ち、「日本人初の四大大会制覇」と報じられたのは記憶に新しい。だが、2年後に迫る東京オリンピックに“日本人”として出場するかどうかは不明だ。
アメリカと日本の両国の国籍を持つ彼女は、いわゆる二重国籍者であり、日本国は基本的に二重国籍を認めていない。彼女は22歳の誕生日を迎える前に、どちらかの国籍を選択しなければならず、選択しない場合は、自動的に日本国籍を喪失する可能性もある。
どちらの国籍を選ぶのか、それは本人が決めることだ。だが、最終的に彼女は米国籍を選択するのではないだろうか。いかに日本愛に溢れていても、米国籍を取得してアメリカを拠点に活躍したほうが、選手としてはメリットが大きいからだ。
17年、カズオ・イシグロ氏がノーベル文学賞を受賞した際も、日本人の偉業を喜ぶ声が多かった。しかし彼はとうの昔に日本国籍を離脱し、イギリス国籍を選んでいる。いずれのケースも、日本が二重国籍を認めていれば、経験せずに済んだジレンマだ。実は先進諸国のなかで二重国籍を認めていない国は少数派で、日本は「時代遅れ」ともいえる制度を採用していることになる。
単一国籍制度のメリット・デメリットを整理していこう。ある人間がこの世に生を受けたとき、国籍はどのようにして決まるのか。大きく分けて「出生地主義」と「血統主義」がある。「出生地主義」を採用する国では、たとえ両親が別国籍であろうと、その国で生まれさえすれば国籍を与える仕組みとなっている。現在は米国やカナダ、ドイツ、フランスなどが採用している。
一方、日本、中国、韓国などが採用するのは「血統主義」だ。日本の場合、父親か母親のどちらかが日本人なら、自動的にその子には日本国籍が与えられる。親が日本人で日本国籍を取得しながらも、出生地が「出生地主義」の国だった場合、その子は出世後3カ月以内に国籍留保届をしたうえで、22歳までは二重国籍となる。
1人の人物が一国の国籍を持つ、いわゆる単一国籍主義は妥当かつシンプルに見えて、ときに厄介な事例も生み出す。典型的なのはかつて日本からブラジルに渡った移民のケースだ。移住先で彼らは農園を経営し、成功をおさめていった。しかしどの国でも外国人の土地取得には制限がかかるもので、農場を大規模化するには、現地の国籍を取得=日本国籍を捨てざるをえないことが起こる。「捨てたのは財産を守るためのやむなき選択であり、日本国籍も認めてほしい」と長年訴え続けている者もいる。
あるいはそこまで歴史を遡らずとも、最近は留学や就職などで海外に出ていく人も増えた。現地で恒久的な仕事に就き、配偶者を得ることや家族を持つことは珍しくない。そして徐々に昇進し、管理職や経営者などになると、立場上、その国の国籍を取得したほうが好ましい場合が多い。そんな必要に迫られて外国籍を取得していく彼らから、日本国籍を取り上げていくというのが現状の制度なのである。
もっとも、現実的には国に申告せず二重国籍生活を送っている人も少なからずいる。仮にある人物がアメリカに帰化申請をしたとしても、それを日本政府に申告する義務はないからだ。アメリカから日本に連絡も行かないし、ばれたところで罰則規定もない。
ただし、大坂選手のような著名人になってくると話は別だ。日本政府も調べるだろうし、そこで二重国籍がわかった場合は無視できなくなる。
ヒューマニズムから生じた日本の国籍法
歴史を紐解くと、日本の国籍法は世界最先端の国籍法として始まった。明治以来、多くのお雇い外国人が日本に来るなか、1899年につくられたのが、日本の最初の国籍法である。そこでは日本人男性の妻となる外国人女性は日本国籍を取得し、外国人男性の妻となる日本人女性は日本国籍を失った。
驚くのは、当時としては極めて先進的な国籍離脱をも認めていたことだ。19世紀末から20世紀初頭は、世界は戦争の時代だった。兵役義務を負う男性に国籍離脱を認めることは軍事機密が漏れる恐れや、兵役逃れが起こる危険性も伴う。そのため、多くの国が国籍離脱を許しておらず、許可を与えたのはおおむね戦後だった。
外国への帰化を認め、夫婦、さらに家族が同じ国籍になる。こうした考え方はナショナリズムではなく、ヒューマニズムから生まれたものだ。たとえば、ドイツ領とフランス領のはざまで常に揺れ動いていたアルザス・ロレーヌ地方などでは、生まれた年によって家族内でフランス国籍やドイツ国籍に分かれるため、戦場では親子兄弟同士で銃口を向けあうといった悲劇が頻発していた。そうした事態を避けるため、人道的配慮から法律が制定されたのだ。また明治政府が文明国として西欧の先進国に劣らないことを示そうと、進んだ法体系を採ったという背景もある。
一方で問題も生まれた。戦後も父系制血統主義(父の国籍を子の国籍とする考え方)を採っていたため、国際結婚した日本人男性の子は日本国籍を取得できるが、国際結婚した日本人女性の子は日本国籍を取得できなかった。これは女性差別だということで1984年に法改正が行われ、両親のどちらかが日本人であるならば子どもも日本国籍を取得できることになった。
つまり、日本人であるかどうかは、その時々のルール(国籍法)いかんによって変わる。そして出発点はヒューマニズムに基づいたルールでも、時代や状況が変われば現状にそぐわなくなることもあるのだ。
かつては日本のような単一国籍主義が世界でも主流だったが、現在は、OECD諸国の圧倒的多数が二重国籍を認めるようになっている。日本がモデルとしたドイツでも、「血統主義」から「出生地主義」に方針を切り替え、二重国籍を認めるようになった。
元自国民は「棄民」ではなく「資産」
なぜ、世界の潮流は変わったのか。転機となったのは80年代以降である。それ以前ならば、移民は移動先の地に骨を埋めるのが普通だった。一家で海外に渡ることのコストを考えれば、「合わなければ帰国」という選択肢は考えにくい。将来はその国の国民となるからこそ、自国籍を放棄して、かの国で新たな国籍を取得することが妥当だったともいえる。一国が責任を持ってその人の国籍を管理するという考えもあながち不当ともいえない。それが国をまたいでの移動コストが一気に安くなったことやEUの発足などで、世界中の人々の移動が加速していった。
さらに昨今は海外旅行が当たり前になり、異国人同士が第三国で結婚・出産し、別の国で生活を始めることも普通になった。国をまたいでのビジネスや、企業の経営者に外国人が就くケースも増えてきているし、あるいは労働力として外国人を大量に受け入れる可能性も高い。根本的な社会システムの整備も必要になるだろう。
実際問題として、二重国籍を認めることのデメリットはほとんどないはずだ。それどころか、海外に出ていった元自国民を「棄民」として扱うのではなく、国の「資産」としてつなぎ留めるメリットもある。これまで経済危機に陥った韓国やメキシコでは、海外で活躍する元自国民人からの投資や援助を期待して、帰国や再帰化を容易にする法律を制定したことがあった。そろそろ日本でも二重国籍を認める議論が、真剣になされるべきではないだろうか。

丹野清人(たんの・きよと)
首都大学東京人文社会学部教授
1966年生まれ。専門は外国人移民。一橋大学大学院社会学研究科社会問題社会政策専攻博士課程単位修得退学。2014年より現職。著書に『越境する雇用システムと外国人労働者』(東京大学出版会)、『国籍の境界を考える』『「外国人の人権」の社会学』(ともに吉田書店)など。(構成=三浦愛美 写真=AFP/時事)
2020年、東京オリンピックが開催される。近年増えた、肌や瞳の色が異なる日本人選手の活躍を日々目の当たりにして、改めて日本人の多様性に気づかされるはずだ。それが議論が深まる契機になることを期待したい。