イデオロギーの特徴は,証拠を無視して一つの立場にとらわれることであると指摘されている(Hilborn、1996).性差別主義,人種差別主義,そして人類平等主義は実証可能な裏付けなしにある信念体系にとらわれているという意味で,イデオロギーだ
ドリーン・キムラ『男の能力・女の能力』
マスコミが提示する構図や自分の思い込みから何となく想定していた「◎◎問題」は,調査するとすぐに崩れることが多い.先入観を壊し,実際の姿に迫ろうとすること,それがフィールドワーク
『自分で調べる技術』宮内泰介著より
フィールドワークは立体的.聞き取り調査が中心的で,そこに観察,資料収集などの他の要素が付随する.関心があることについて,図書館やネットで調べてうっすらといろんな問題が分かる中で「◎◎」という問題を深掘りしようとしたとき,次にするのが聞取り調査
『自分で調べる技術』宮内泰介著要約
聞き取り調査の場合は,誰がキーパーソンか探せ.誰に聞くのか,がすごく大切.なるべく多くの人に話を聞くことは,同時に「誰に話を聞くべきなのか」を探っていくプロセスでもある.なお,調べたいことによってキーパーソンは変わるので注意!
『自分で調べる技術』宮内泰介著要約
聞取りのテクニック:
①十分な準備と熱意をもつこと
→ある程度知った上で,熱意をもって聞く人に,人は話をしてしまう
②相手が話しやすいように,場を作る
→進んで話してくれる人なのか,話しにくそうにしているのか
なお,聞き取りに失敗はつきもの!
『自分で調べる技術』宮内泰介著要約
聞き取り調査の注意ポイント:
聞いた情報は正しいのか?「一次情報か二次情報か」という区別を.また語りは相互作用である.複雑な感情を持つ中で,今回はこのような論点で話した,というだけに過ぎないとの一歩引いた理解をすること!
『自分で調べる技術』宮内泰介著要約
聞く以外のフィールドワーク「参与観察」:
聞いた上で,併せて現場で一緒に体験しながら考えることも大切.ポイントは何となく分かった気になるのではなく,メモ取ったり写真とったりすること!そして.分からないことは聞く!理解が深まる
『自分で調べる技術』宮内泰介著筆者要約
アンケート調査の功罪.調査対象の選び方(調査対象がはっきりしていた方がいい),質問の作り方,この調査で何を知りたいのかの明確化が必要.結構大変なので,しっかりした調査データを二次利用することを考えた方がいい
『自分で調べる技術』宮内泰介著筆者要約
アンケートもどきのよいところ:
その過程で,面白い話が聞けたりして,結果論的にフィールドワークになっていることもある.ただし,アンケートもどきは結論を導く者では無く,あくまで調査プロセスの中の暫定的な”データ”にすぎないと理解すべし
『自分で調べる技術』宮内泰介著筆者要約
社会を知り,問題を発見し,解決するプロセス:
文献調査→フィールドワーク→まとめる→文献調査→フィールドワーク→・・・と円環状に進んでいく.もどかしい回り道のような作業でもある.
『自分で調べる技術』宮内泰介著筆者要約
※本にはないですが「仮説」をもたずに探っていくのがコツらしい
調査倫理:
民俗学者の宮本常一は『調査地被害』を書いた.「調査だから」「学問だから」等と特権がある訳では一切ない.詰問してはいけない.敬意を忘れてはいけない.借りた資料は丁寧に扱い,早めに返す.調査結果や報告書はお世話になった方へ送るべし.
『自分で調べる技術』宮内泰介著筆者要約
産業カウンセラーの倫理綱領読んでたら、第10条個別面接と組織への働きかけで、必要に応じ組織に働きかけ環境改善に取り組むため、社会規範、産業組織論、人間行動科学、労働科学等の学識をもち、他の専門家とネットワークをつくる、とある。確かにそれは価値あると思った。※上記筆者要約です。
くしゃみが止まらなかった日以来、腰が痛い。ちょっと気を抜くとギックリなりそう、、イタくてねこ背になる。電車降りたら微妙に雨だし傘ないし、困ったもんだ(ー ー;)










 どうなるかより、どうしたいか。 @eric_motto
どうなるかより、どうしたいか。 @eric_motto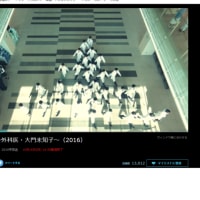


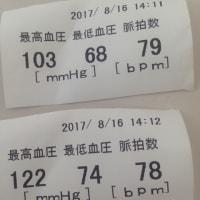


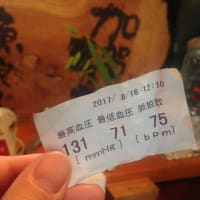



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます