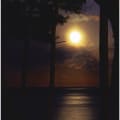『古事記』雄略天皇 1
大長谷若建命、坐長谷朝倉宮、治天下也。天皇、娶大日下王之妹・若日下部王。无子。又娶都夫良意富美之女・韓比賣、生御子、白髮命、次妹若帶比賣命。二柱。故爲白髮太子之御名代、定白髮部、又定長谷部舍人、又定河瀬舍人也。此時吳人參渡來、其吳人安置於吳原、故號其地謂吳原也。
初大后坐日下之時、自日下之直越道、幸行河內。爾登山上望國內者、有上堅魚作舍屋之家。天皇令問其家云「其上堅魚作舍者誰家。」答白「志幾之大縣主家。」爾天皇詔者「奴乎、己家似天皇之御舍而造。」卽遣人令燒其家之時、其大縣主懼畏、稽首白「奴有者、隨奴不覺而過作甚畏。故、獻能美之御幣物。能美二字以音。」布縶白犬、著鈴而、己族名謂腰佩人、令取犬繩以獻上。
故、令止其著火。卽幸行其若日下部王之許、賜入其犬、令詔「是物者、今日得道之奇物。故、都摩杼比此四字以音之物。」云而賜入也。於是、若日下部王、令奏天皇「背日幸行之事、甚恐。故、己直參上而仕奉。」是以、還上坐於宮之時、行立其山之坂上歌曰、
久佐加辨能 許知能夜麻登 多多美許母 幣具理能夜麻能 許知碁知能 夜麻能賀比爾 多知邪加由流 波毘呂久麻加斯 母登爾波 伊久美陀氣淤斐 須惠幣爾波 多斯美陀氣淤斐 伊久美陀氣 伊久美泥受 多斯美陀氣 多斯爾波韋泥受 能知母久美泥牟 曾能淤母比豆麻 阿波禮
卽令持此歌而返使也。
*最後にBingちゃんの回答解説があります
≪英訳≫
Oho-hatsuse-no-Wakatake-no-Mikoto(Emperor Yuryaku) came to the palace of Asakura in Hase, Yamato, and ruled the country. The Emperor married the sister of Prince Okusaka, and they had no children. He then married the daughter of Karami-no-Kimi, Tsuburahoomi’s daughter, and had two children, Shiraga-no-Mikoto and Wakatarashi-no-Mikoto. In commemoration of Shiraga-no-Mikoto’s name, he established the Shiragabe clan. He also established Toneri(officials) in the Hase and Kawase regions.
At this time, Wu(呉) people (Chinese) came across the sea and were settled in Kurehara(Wu-hara), hence the name.
When Empress came to Kusaka, Emperor visited Kawachi via Tadagoe (a direct road to Kusaka). When he climbed a mountain to view the land, he saw a house, the roof of which decorated tall trees. He inquired about the owner of the house and was told, ‘It belongs to the village head of Shiki.’ The Emperor said, ‘That person has built a house resembling my palace.’ He ordered it to be burned. The village head, filled with fear, bowed and said, ‘I acted without realizing my mistake. I am terrified.’ So, he presented valuable offerings: a white dog with a cloth and a bell, and made his relative, Koshihaki take the dog's rope and present it. Therefore, he halted the burning of the house.
He visited the residence of Prince Oku-kusaka and presented the dog, saying, ‘This is a rare item I obtained on my journey today. Please accept it.’ Prince Oku-kusaka responded, ‘To come here on this day with the sun at your back is a cause for great concern. Therefore, I shall personally serve you.’ Upon returning to the palace, Emperor stood on a hill and composed this song:
Amidst the mountains of Kusakabe,
And the distant mountains of Heguri,
Amongst the many mountains in between,
Flourish dense thickets of broad-leafed oak trees,
At the roots of those trees, bamboo thrives,
Towards the tips, sturdy bamboo shoots arise,
As lushly as the thriving bamboo,
As steadfastly as the sturdy bamboo,
A wife with the resolve to lie down together, oh.
He sent this song to the princess.
≪この英文の和訳≫
大雄津彦命(おほはつせのわかたけのみこと)(雄略天皇)は大和の長谷(はせ)にある朝倉宮(あさくらのみや)に住み、国を治められました。命(みこと)は大日下王(おほくさかのおおきみ)の妹である若日下部王わかくさかべのおおきみ)と結婚されましたが、御子はありませんでした。その後、命は都夫良意富美(つぶらおほみ)の娘である韓比賣(からひめ)と再婚し、二人の子供、白髪命(しらがのみこと)と若帯比賣命わかおびひめのみこと)をもうけました。白髪命の名前から白髪部(しらがべ)を定められました。また長谷部(はつせべ)の舎人(とねり・役人)や河瀬部(かわせべ)の舎人も定められました。
この時期、呉人(くれびと)が海を渡ってやってきて、彼らを吳原(くれはら)に住まわせました。これが呉原の名前の由来です。
初めて皇后が日下(くさか)においでになったとき、大夫(皇后の夫)は日下の直越(ただごえ)を通って河内(かわち)に向かいました。山に登り、国土を見渡すと、高い装飾された屋根と高い木がある家を見つけました。大雄津彦命はその家の所有者を尋ね、答えは「志幾(しき)の大縣主家(おおあがたぬしのいえ)」であるとのことでした。すると大雄津彦命は言いました、「あの家の主は、私の宮殿を模して家を建てているようです。」そしてその家を焼き払うように命じました。大縣主は恐れおののき、礼を述べて言いました、「私は誤って分をわきまえずに行動しました。恐れ多く存じます。」そして、彼は貴重な贈り物を差し出しました。白い犬に布をかけて鈴をつけて、一族のコシハキという人に犬の繩を取らせて献上しました。依つて火をつけることをおやめになりました。そこでそのワカクサカベの王のところににおいでになつて、その犬を贈って仰せられますには「これは今日道で得ためずらしい物です。贈物として差しあげましよう」と言つて、くださいました。この時にワカクサカベの王が申されますには「日を背中にしておいでになることは畏れ多いことでございます。依つてわたくしが參上してお仕え申しましよう」と申しました。かくして皇居にお還りになる時に、その山の坂の上にお立ちになつて、お歌いになりました御歌、
日下部((さかベ)の山と、
遠くの平群(へぐり)の山との
その間のさまざまな山の中で、
繁茂している広葉のカシの木、
その木の根元には竹が豊かに生え、
先の方にはしっかりとした竹が育ち、
繁茂する竹のように密生し、
しっかりとした竹のようにしっかりとしていて、
一緒に寝る決意を持った妻、ああ。
この歌をその姫の許に持たせてお遣りになりました。
令和5年9月12日(火) 2023
*Bingちゃんの回答解説
古事記で「シラガの太子の御名の記念として白髮部(しらがべ)をお定め」などと「部」(ベ)を定めてどうするのでしょうか?
「部」(ベ)とは、古代日本において、天皇や豪族が自分の子孫や臣下に与えた氏族名のことです。部は、その人の出自や職業、居住地などを示すもので、同じ部に属する者は一族として結束し、互いに支援したり、共同で祭祀を行ったりしました。部は、天皇や豪族の権力を示すものでもあり、部を多く持つ者は多くの人々を支配しているということになりました。古事記には、天武天皇が白髪部を定めたことや、応神天皇が大伴部や物部などの豪族を任命したことなどが記されています12。部は、日本古代社会の政治的・社会的な組織として重要な役割を果たしていたのです。
「部」(べ)一族という感じですか?
はい、そういう感じです。部は、一族の名前として使われることもありました。例えば、大伴部は大伴氏の一族を指し、物部は物部氏の一族を指します。部は、日本古代の歴史や文化に関する興味深い話題ですね。