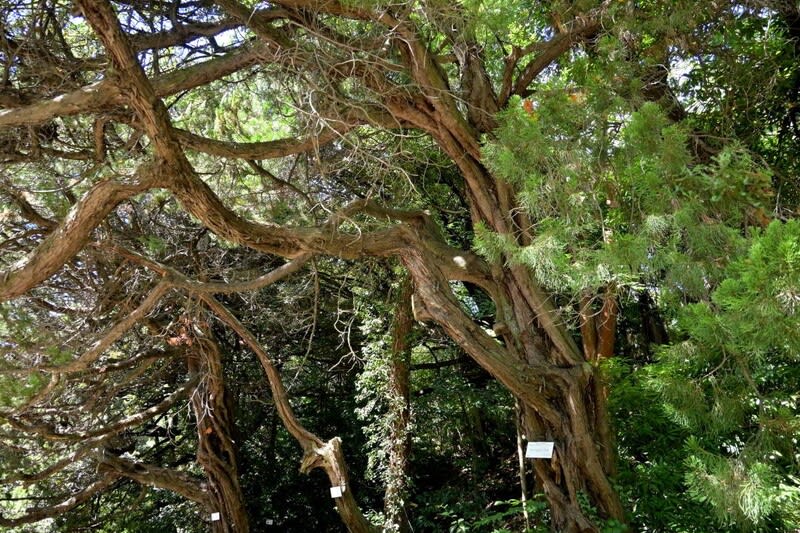世田谷ボロ市*歩きカメラ39
「毎年12月15・16日、1月15・16日の4日間開催される世田谷のボロ市。
430年以上にわたる歴史のある伝統の市です。東京都指定無形民俗文化財に指定されています。
骨董類、古着、植木から玩具、日用雑貨、食料品など、多種多様な商品が販売されます。
露店数750店舗、来場者数 数十万人という、活気のある“市”の雰囲気をぜひ味わってください。」
近くて面白そうで冷やかしもできるということで、今日の歩きカメラは9人でした。
9時に新宿に待ち合わせて、9時半ごろには東急世田谷線の上町駅に降り立った。世田谷線はスイカが使えますが、切符を買う方は臨時駅員さんが大挙して出勤。そりゃ混雑していました。世田谷線の電車は2両編成で頻繁にくるが乗り切れないくらいの大混雑。
スリにご注意!
Aさんの写真は

お昼の12時にボロ市会場の真ん中あたりでくす玉が破られました。
区長さんや消防署の所長さん、商店街の会長さんたちでした。
目の前が江戸時代に代官屋敷があったところで、大きな茅葺き屋根の家が保存されていた。

ボロ市なんでなんの役に立つのかわからないものばかり。

瓢箪の酒壺かと思ったらランプシェードのようだ。

柚子にしては凸凹柚子。
柚子は皮を使うので、、、けっこう凸凹なので使いがいがあるかも。

切り枝の蝋梅です。
もう咲いているんですねー。
Bさんの写真は

これは、まだまだ朝早いようで人混みも大したことがない。
ところが12時ごろになると、倍の人混みになって押し合いへし合いで前に進めなくなった。

そんな中で、ひとりの歩きカメラのメンバーが、白人さんに英語で話しかけて写真を撮らせてもらっていた。
60歳を過ぎてから英語の勉強を始めて、こりゃちょうど良いと話しかけたもの。
一石二鳥ですね。
勉強になって話を聞けて写真も撮って、一石三鳥だったか!

古いお雛様人形は誰が買うのか?
きっと、白人たちが日本の古物を買い漁っていると聞いたから、彼らが良いお客さんなのかもしれない。
世田谷ボロ市では白人は目立っていたが、いつもいっぱいいる中国人のうるさい中国語が聞こえなかった。
韓国人も少ない気がします。
本国に帰ればこんな市はどこにでもあるという事なのかもしれない。
アジアの街だったら、どこでもボロ市みたいだからだし〜〜〜。

くす玉行事が行われた反対側に代官屋敷が保存されていた。
刺股などは時代劇で見るけど実物をまじまじみるのは初めてだ。
棒の先に刃物がいっぱいついているから、これで押さえられたら痛くて動けないよ。

代官屋敷の茅葺き屋根ですね。
Cさんの写真は

東急世田谷線の電車はかっこいいでしょ!
専用軌道なので速度が速い。
道路と兼用の路面電車には制限速度があった。
それに線路の幅が広いのに気が付きます。
JRなどに比べると、幅が倍近く感じてしまいます。
最近、宇都宮でもトラムと呼ばれる市電が走り出したりして、この形の公共交通に注目が集まっています。

12月と1月に2日づつ開催されます。
430年の歴史があるから、江戸初期から始まったのでしょう。

何を売っているのか、、、わけわかめ。
もしかして香辛料か?

ただの食器しか思えないが、、、由緒でもあるのかな、嘘っぱちの口上で騙したり騙されたりがボロ市の醍醐味なのか。
それじゃ漫才じゃないか。

わりかしまともな実用品。
Dさんの写真は

おぉっと思いますが、きっと何か裏があるのだろう。
まともに信じちゃ、、、売り手の言葉に引っかかるだけ。
丁々発止を楽しんでください。
でも、、、こんなお面は白人観光客に人気だろうなーーー。
「ハイ、このお面は貴重なものでもうもうこの先では彫るひとがいませんから、手に入らなくなりますよーーー」
確か2万円と言っていたと聞いたが、、、。

これはボロ市にしては超まともな製品です。
12000円とか茶碗一つ2000円とか、、、なかなかキレイなシリーズですね。
私も2客ぐらいほしくなりましたから。

インディゴブルーシリーズです。
染め物で搾り染めにしてはリーズナブルかな。
これも真っ当な商品でしょう。

こっちは、、、イヤイヤ真っ当どころか、怪しいもののオンパレード。
どこから仕入れたんだい、ってものばかりを売っています。
これでも白人は買うんだろうな〜〜〜。
どんどん買ってくださいな。
というわけで、39回目の歩きカメラは、写真を撮るどころではなく、皆さん山ほど買い込んで帰路は大変だったんじゃないか。そういう「写真どころじゃない」歩きカメラも良いものです。
次回は亀戸の河津桜を見に行きます。
代々木健康友の会の「歩きカメラ部」*03−5411−9589