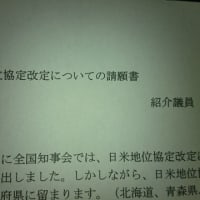自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か
Business Journal 2月8日(日)6時0分配信
最高裁判所の元裁判官で明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏が、1月16日に上梓した『ニッポンの裁判』(講談社現代新書)において、衝撃の告発をしている。1月29日付当サイト記事『与党・自公、最高裁へ圧力で言論弾圧 名誉毀損基準緩和と賠償高額化、原告を点数化も』でも報じたが、自民党と公明党による実質上の言論弾圧が行われているというものだ。
2001年、当時与党であった自民党は、森喜朗首相の多数の失言を受けて世論やマスコミから激しく批判され、連立与党の公明党も、最大支持母体の創価学会が週刊誌などから「創価学会批判キャンペーン」を展開されるなど、逆風にさらされていた。そのような状況下、自公は衆参法務委員会などで裁判所に圧力をかけ、裁判所がそれを受けて最高裁を中心に名誉棄損の主張を簡単に認めるように裁判の基準を変え、賠償額も高額化させ、謝罪広告などを積極的に認めるようになった。
両党が森内閣や創価学会への批判を封じるために最高裁に圧力をかけたという事実はもちろん、最高裁が権力者である自公与党の意向を受けて裁判における判断基準を変えていたことも、民主主義の大原則である言論の自由、また三権分立をも根底から脅かす、大きな問題である。
また、名誉棄損の基準が歪み、それを悪用した恫喝訴訟が民事でも刑事でも蔓延しており、大きな社会問題となって各方面に影響が広がっている。瀬木氏の告発を報道する国内メディアが相次ぎ、海外の報道機関も取材に訪れていることから、さらに騒動は拡大する見通しだ。時の政権が実質上の言論弾圧をしていた事実が明らかになったことで、政界にも動揺が走っている。
●政界に広がる反響
前回記事は瀬木教授の最高裁内部の実態の告発を中心としていたが、政界での事実経緯を振り返るため、今回は当時の議会での動きを振り返ってみたい(以下、肩書はいずれも当時のもの)。
森政権や創価学会が世論から批判を強く浴びていた01年3月、法務大臣の高村正彦氏(自民党)は参院法務委員会で、「マスコミの名誉毀損で泣き寝入りしている人たちがたくさんいる」と発言した。これを受けて故・沢たまき氏(公明党)は「名誉侵害の損害賠償額を引き上げるべきだと声を大にして申し上げたい」と、同月の参院予算委員会で損害賠償額の引き上げについて、まさに“声を大にして”要求。魚住裕一郎氏(同)も同年5月の参院法務委員会で「損害賠償額が低すぎる」「懲罰的な損害賠償も考えられていけばいい」と強く要求した。
そして同月の衆院法務委員会で、公明党幹事長の冬柴鐵三氏が大々的にこの問題を取り上げて「賠償額引き上げ」を裁判所に迫った。これを受けて最高裁民事局長は「名誉毀損の損害賠償額が低いという意見は承知しており、司法研修所で適切な算定も検討します」と回答した。
つまり、自民党と公明党の圧力によって最高裁が名誉棄損の基準を変えていたのだ。そして裁判所が安易に名誉毀損を認めるようになり、その結果、不祥事を起こし追及されている側がそれを隠ぺいするために、また性犯罪者が告訴を取り下げさせるために、告発者や被害者を名誉毀損だとして訴える“恫喝訴訟”が頻発するようになった。
このような経緯について、現役の国会議員からも与党に対して批判の声が上がっている。衆議院議員の落合貴之氏(維新の党)は、告発に驚きを隠さない。
「実質的な恫喝目的で名誉棄損を悪用するケースや、公益通報者を保護しないケースなど、多様な陳情が寄せられています。その原因が、与党の自民党の圧力にあったという告発に大変驚いています。恫喝訴訟の問題については、国民を適切に保護するために、また被害者の方々が保護されるように、議員としてしっかりと取り組んでいきたいと思います」
一方、都内の区議会などでも反響が上がっている。世田谷区議を務める田中優子氏(無所属)は、次のように語る。
「性犯罪者側が、被害者女性や支援者を訴えている恫喝訴訟問題などに強い憤りを感じていました。しかし、その元が与党による最高裁への圧力だと聞き、大変驚いています。司法がこんな状態では、いったい国民は何を信じればよいのでしょうか。このような問題は区議としても注視して、被害者が適切に保護されるように尽力していきます」
このように本問題については、政界でも国会から地方議会に至るまで、多くの議員から批判の声が上がっており、今後国会での質問主意書などで取り上げられる可能性も高い。
これは現在の安倍政権ではなく、過去の自民党・公明党の問題であるが、安倍政権が過去の与党の問題に対しても毅然とした対応をできるのか、今後の動きに注目が集まっている。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150208-00010001-bjournal-bus_all&p=2
裁判官の人間性で、判決はいかようにも変わる! 『ニッポンの裁判』『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏が暴く「判決決定のからくり」
現代ビジネス 2月4日(水)6時2分配信
2015年1月16日、講談社現代新書より、日本の裁判のリアルな実態を描いた『ニッポンの裁判』が刊行された。冤罪連発の刑事訴訟、人権無視の国策捜査、政治家や権力におもねる名誉毀損訴訟、すべては予定調和の原発訴訟、住民や国民の権利など一顧だにしない住民訴訟・・・・・・、裁判の「表裏」を知り抜いた元エリート裁判官の瀬木比呂志氏(明治大学法科大学院専任教授)をも驚愕させたトンデモ判決のオンパレードは、司法に淡い期待を抱く読者を打ちのめした。その衝撃的な内容はネットでも話題になり、発売直後に早々に重版が決定している。
本書は「元裁判官による裁判批判の書」であると同時に、裁判官の意思決定のメカニズムについても踏み込んだ解説をしている。一般には、裁判官は、提出された証拠の事実認定を行い、それを法律に当てはめることで、オートマチックに判決を下しているようなイメージが流布している。しかし、瀬木氏は「それは幻想に過ぎない」と断ずる。実際の司法判断はもっと生臭く、裁判官の人間性によって、判決の内容もいかようにも変わるというのだ。だとすると、著しく劣化した裁判官は、著しく劣化した判決を連発することになる・・・・・・。知られざる「判決決定のからくり」について瀬木氏に聞いた。
Q.『ニッポンの裁判』は、横断的な判例分析・解説・批判という性格をもっていますが、それに先立ち、第1・2章で、裁判官がいかに判決を下すのか、その判断構造の実際、判断決定の心理メカニズムを克明に描いている点がすばらしいと思いました。事実関係さえ同じであれば、どんな裁判官でもおおむね似たような判決が出るものと思っていましたが、判決というのは、実は、きわめて個性的、属人的なものだったんですね。
瀬木:裁判官の判断は、A 実際に判決に記されているように、個々の証拠を検討して、あるいはいくつかの証拠を総合評価して断片的な事実を固めた上で、それらの事実を総合し再構成して、事実認定を行い、それを法律に当てはめて結論を出しているのだろうか、それとも、B そのような積み上げ方式によってではなく、ある種の総合的直感に基づいて結論を出しているのだろうか。こういう問題ですね。
考え方は分かれますが、僕はBだと思います。裁判官、元裁判官にもこの考え方は多いですし、学者では、『日本人の法意識』(岩波新書)等で一般にも知られる川島武宜(たけよし)教授(東京大学)が、はっきりとこちらの考え方をとっています。
つまり、裁判官は、主張と証拠を総合して得た直感によって結論を決めているのであり、判決に表現されている前記のような思考経過は、後付けの検証、説明にすぎないということです。
もちろん、裁判官が審理のある段階で得た以上のような最初のまとまった心証については、裁判官は、その後の審理の中で、それが本当に正しいものであるか否かを注意深く検証し続けなければなりません。このことも当然です。最初の直感に自信をもちすぎることはきわめて危険であり、民事でも刑事でも、誤った裁判の原因になりやすいのです。
Q.裁判官は、緻密な事実認定と法解釈によって、論理的に判決を下すと思い込んでいたのですが、実際には、きわめて直感的に結論を下すのだという点、これはショッキングでした。誤解を恐れない言い方をすれば、理屈は後付けだったんですね。
瀬木:全くそのとおりであり、本書の第1章や『民事訴訟の本質と諸相』(日本評論社)で引用した近年の脳神経科学の成果も、これを裏付けています。人間の判断はまずは直観としてやってくるのであり、理屈は、その事後的な検証、また、後付けの説明として行われます。それは裁判でも同じことです。
だからこそ、裁判官の人間性やバックグラウンドが決定的に重要なのですよ。そういうものがすぐれている人間でなければ、いい裁判もできないし、指導的な判例も作れません。
つまり、裁判官の、一般的・法的能力、洞察力、識見とヴィジョン、謙虚さ、人権感覚、民主的感覚等の重要性ということです。
裁判官の判断が、裁判官のあらゆる能力、もちあわせている知識、経験、人間や社会に対するものの見方、人権感覚等の総合的な函数であるなら、知的能力だけは高くても冷たくエゴイスティックな裁判官が人々にやさしい判断を下すわけがないし、人はよくても能力や総合的なヴィジョンに欠ける裁判官が社会のあるべき方向を指し示す判決を下すことも難しいでしょう。実際、個々の判決を見てゆくと、そのとおりのものになっています。
ここに、キャリアシステムの一つの大きな問題点があります。キャリアシステムというのは、司法試験に合格した若者が司法修習を経てそのまま裁判官・検察官になる官僚裁判官・検察官システムをいいますが、日本のピラミッド型キャリアシステムの下では、当事者を訴訟記録の片隅に記されているただの記号としかみない、また、普通の人々の心の持ち方や動き方がさっぱりわからない裁判官が発生しがちであり、裁判官の能力やモラルが落ち込むと、その傾向が一気に加速されやすい。そういう裁判官に、いい裁判ができるわけがないのです。
Q.本書を読んで、初めて、リアリズム法学なるものを知りました。このインタビューを読んでいる読者にもわかりやすいように解説していただけますか。
瀬木:詳しくは第2章のとおりですが、簡単に説明しましょう。
リアリズム法学の代表格の学者、実務家は、ジェローム・フランク(1889~1957)です。
フランクは、「法」が固定した不変のものであってそこから演繹的に結論が導き出されるという考え方をドグマであるとしてしりぞけ、社会・人文科学一般の分析を援用しながら、実際には、裁判官こそが、法を欲し、法を創造し、また、変更しているのであり、書かれた「法」は、裁判官が判断を行うに当たっての「一つの素材」ないしは「判断を規整する一つの枠組み」でしかないとしました。
また、裁判において問題となる「事実」も、なまの出来事から抽象され法的な評価を加えられた事実であって、客観的存在としての「事実」とは異なるとしました。
そして、判決は、「法律」と「事実」によって決定されるというよりも、いずれかといえばむしろ、「刺激」と「人格」、つまり、「〔広義の裁判過程において裁判官に与えられる〕刺激」と「〔裁判官の〕人格」によって決定されると定式化したのです。ここで、「刺激」というのは、裁判官の外側から裁判官に働きかける諸要素であり、証拠、法律のほか、世論等の社会的な諸要因をも含むでしょう。「人格」というのは、裁判官個人に属する諸要素であり、性格、各種の偏見ないし嗜好、習慣ないし性癖等を含むでしょう。
要するに、フランクは、法的判断とは、法をその規整の枠組みとしながらも、本質的には、裁判官の個人的な価値選択であり、政策判断であり、その全人格の反映であると論じたのです。
このリアリズム法学は、アメリカにおける哲学流派、哲学的方法の代表的なものであるプラグマティズムの系譜を引いており、僕自身の思想もプラグマティズムから大きな影響を受けているので、僕には、うなずける部分がかなりあります。なお、先にふれた川島教授の学説も、リアリズム法学の影響を受けています。
Q.ある意味大変ラディカルな考え方ともいえますが、瀬木さんも、この考え方に賛同されるのでしょうか。
瀬木:賛同できる部分も大きいですね。
しかし、先のようなリアリズム法学の考え方については、それがかなりの程度に当てはまる領域と、そうではない領域があると思います。
一般的にいえば、その判断が広義の「価値」に関わり、社会や政治、行政のあり方に大きな影響を与える訴訟(このような訴訟を「価値関係訴訟」と呼びたいと思います。普通の刑事事案でも再審請求事件等はこれに該当します)、また、その中でもそのような傾向の大きい事案ほど、裁判官の価値観、人格、人間性によって結論が影響される度合いが大きいと思います。たとえば、憲法訴訟、行政訴訟、国家賠償請求訴訟、名誉毀損損害賠償請求訴訟、原発訴訟、刑事の大事件や再審請求事件等ですね。
『ニッポンの裁判』における僕の裁判分析については、確かに、僕なりの「プラグマティズム法学、リアリズム法学」の試みという側面があります。しかし、僕の分析は、対象となる裁判にひそむことのある虚偽意識的、イデオロギー的な欺瞞を指摘しつつも、論理一貫性や法律の趣旨をも重視しており、リアリズム法学ですべてが解けるといった単純な考え方によっているわけではありません。
Q.裁判官の人間性によって判断が左右されるとすると、近年叫ばれている「裁判官の劣化」は由々しき問題ですね。本書で紹介されているようなトンデモ判決も、裁判官の質の低下によってもたらされている可能性がありますね。
瀬木:そうですね。法的・知的能力一般の低下傾向、そして、リベラルアーツ的なバックグラウンドが薄くなってきていること、その双方が問題ですね。
近年、刑事のみならず民事においても、コモンセンス、良識を欠いた非常識な判決が増えています。たとえば、民事の象徴的なケースとして、第5章で取り上げた、認知症の老人が家族のわずかな隙をついて外に出、電車にはねられた事件で、JRの家族に対する損害賠償請求を認めた名古屋地裁(2013年8月9日、上田哲裁判長)、名古屋高裁(2014年4月24日、長門栄吉裁判長)の判決、ことに前者があります。
第一審判決は、妻のみならず別居の長男に対する請求まで認めているのですが、この裁判長が、悲しいことに、最高裁判所調査官経験者なのですね。この判決は、認知症患者の介護に当たっている家族や医療関係者を震撼させ、インターネットには、「それでは、『認知症の老人は座敷牢にでも閉じ込めておけ』とでもいうのか?」との批判の声まで出ました。刑事では、「明日はあなたも殺人犯」ですが、民事では、「明日はあなたも高額賠償義務者」なのです。
僕の感覚からしても、かつては、中間層の職人裁判官たちでも、このような判決は書かなかったと思うのです。無理のない範囲の低額和解を勧め、当事者らがのまなければ、注意義務違反を認めることは困難である、として棄却したでしょう。こうした事案では、鉄道会社も、債権が成立していると思われる外観がある以上株主からの追及がありうることなどを考えて訴訟は起こすが、勝敗にはこだわらない、というのが本音であると思われ、したがって、棄却の判断によって傷付く者は、実際にはいないからです。
だから、認容判決によって悪い先例を作るべきではありません。また、こうした判決によって、認知症をわずらう老人の面倒をみようという親族や施設が減少してしまうといった萎縮効果、波及効果のことも考えるべきです(なお、控訴審判決は、長男に対する請求は認めず、妻に対する認容額も半分にするなど一定の配慮を行っており、その意味では和解的な判決ともいえます)。
こうした事故は、結局のところ、社会に弱者保護のためのシステムが構築され、機能していないことから起こります。そして、かつての職人的裁判官たちであれば、「この鉄道会社の請求を認容するのはいくら何でもコモンセンスに反する」ということには、最低限気付いたと思いますね。その程度の良識、また、社会に関するヴィジョンは、多数派の裁判官たちももっていました。社会のひずみの全責任を裁判で弱者に押し付けるのは、明らかに、正義と公平の原理に反するからです。
また、これは、裁判官が当事者の視点に立って裁判を行えているか、という問題でもあります。最後は当事者の視点に立って判断するようにすれば、非常識判決は避けられるのです。本件の場合でいえば、認容判決については、被告は到底承服できないと考えるでしょうし、棄却判決については、原告も不満はあるもののそう判断されるのもやむをえないと受け止めるであろうことは、容易に想像がつくでしょう。
僕が、この本の次に、『リベラルアーツの学び方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、5月ころ刊)という本を出すことにしたのは、以上のことと関係があります。法律家を目指す若者に限らず、中堅以下の層におけるリベラルアーツ的な教養の劣化は、大変深刻な問題です。この本に挙げた例からもわかるとおり、すでに、現在40代以下の裁判官たちには、この傾向が強く出てきていますからね。
Q.『絶望の裁判所』では、竹崎前最高裁長官を頂点とする最高裁事務総局の裁判官支配、統制による弊害が指摘されていましたが、これも、裁判官の質の劣化に関係しているのでしょうか? 最高裁が腐っているから現場が疲弊するのか、そもそも低レベルの裁判官が増えているから、前近代的な司法統制がまかりとおるのか? 「鶏卵論争」のような質問で恐縮ですが。
瀬木:第7章で、制度的な側面について、裁判への影響という観点から『絶望の裁判所』を強力に補足したとおり、いずれも正しいといえますね。鶏卵というより、相乗作用でしょう。
昨日、今書いている原稿の関連で、コッポラの『地獄の黙示録』を見ていたのですが、あれはすごい映画ですね。何回見ても飽きないし、すべてのシーンがすばらしい。『市民ケーン』レヴェルの作品かもしれないとさえ思いました。もっとも、劇場公開版のほうが後の完全版よりいいというところは珍しい。完全版では、人物たちの性格があいまいになってしまっています。
その、『地獄の黙示録』の、川をさかのぼるにつれてどんどん状況が悪く、絶望的になってゆくという感じ、あれは、2000年前後以降の裁判所の雰囲気そのままです。
日本全体の状況がそのようになってゆかないことを強く祈りたいですね。そのことは、第8章の末尾で、2000年代における最高裁のかつてない腐敗に関連して、書いておきました。
Q.今言われた第7章「株式会社ジャスティスの悲惨な現状」、これも面白かったですね。裁判所を、顧客からの信頼を失ったブラック企業にたとえて揶揄した内容で、瀬木さん一流のブラックジョークが効いていて、クスクス笑いながら読みました。しかし、これから進路を決める司法修習生にとっては笑い事ではないですね。これを読んだら、まともな修習生は裁判官になろうとは思わないのではないでしょうか。
瀬木:いや、国民にとっても笑い事ではないのですよ。そういう裁判所の裁判官が裁判をするのですからね。
カスタマーアンケートの結果が満足度二割を割り、「カスタマーのための徹底的な構造改革」後も、結果はほとんど変わらない。
売上げは、構造改革や社外独立事業者のかつてない大幅増員、エリート社員の三割増員にもかかわらず全分野で激減。
エリート社員の不祥事も目立ち始め、2000年代以降は、8件もの性的な不祥事が連続して発生。
エリート職員はわずか2900人であるにもかかわらず、各社員が10年に1度人事部の「リストラ査定システム」をくぐらなければならず、近年は、これによって、毎年数人が首を切られ、少なくともそれと同程度ないしそれ以上の人間が肩叩きで退職。しかも、首を切られる社員や肩叩きにあう社員は必ずしも成績不良者とは限らない。
エリート社員たちの服務規律は、明治20年に作られたものであり、正式な休職の制度もなく、したがって、社員たちは、病気になった場合には、回復の見込みが早期に立たなければ退職するほかない。有給休暇についても正式な制度はなく、支社長たちの「取決め」によっている。
今日では多くの大学のほか大企業にも設けられているハラスメント防止のためのガイドラインも、相談窓口や審査機関もなく、セクシュアル、パワー、モラル等の各種のハラスメントが横行し、しかもハラスメントを行っている上司たちにはその意識すらない。
こういうことです。僕は、「企業ならすでにつぶれている」とだけ書きましたが、なるほど、いわれてみれば、これは一種のブラック企業ですね。
裁判官には優秀な人やすぐれた人もたとえば5パーセントから10パーセントとかそういった水準ではなお存在すると思いますが、全体がこうでは、つまり、構造的な問題が大きくては、改善は容易ではない。いい人やすぐれた人は上にはいけないのですからね。
僕は、学生たちには、裁判官になるなとは言っていませんが、僕の本も含め、さまざまな情報をよく検討して考えたほうがよいことは、間違いがないでしょうね。
Q.こうした絶望的な現状を伝えることは、むしろ、「絶望の裁判所」を「超・絶望の裁判所」にするだけだという意見もありうると思うのですが?
瀬木:確かに、『絶望の裁判所』に対する感想には、書物を評価するものの中にも、「司法の絶望的な状況を知らされても、その解決策は必ずしも早期に実現する可能性が高いとは思われないので、さらに絶望的にならざるをえない」というものも散見されましたね。
これについては、C・ダグラス・ラミス(アメリカ人政治学者、評論家。日本在住)の書物『影の学問、窓の学問』(加地永都子ほか訳、晶文社)の序文が、一つの答えを示しています。その序文で、著者は、読者に対して、こういう意味のことを問いかけます。
「あなたが住んでいる世界は、実は、リアルな世界、一つの惑星ではなく、広大な宇宙船の中に作られた仮想世界である。しかし、誰もそのことは知らない。さて、もしもそれが可能であるとしたら、あなたは、禁じられた領域である宇宙船の窓辺にあえて歩み寄り、広大無辺な虚空の広がりを見、自分がリアルな世界だと思ってきた場所が実は構築された仮想世界にすぎなかったことを知りたいか? それとも、そんなことは知らないまま安らかに一生を終えたいか?」
著者の答えは、「知りたい」であり、僕の答えも同じです。
でも、数人の賢い後輩たち(法律家とそれ以外の)にこの問いを投げかけてみたところ、純粋に「知りたい」という答えは一つもなく、うちの二人は、答えを保留し、一か月くらい後になってから、「やっぱり知らないまま死ぬほうがいいかもしれないと思います」と答えました。
賢明で考え深い後輩たちのこの迷いはとても興味深いですね。人間の多くは、「普通の意味でいえば知らないほうが幸せな事実」は知らないですませるほうがいいと思うものなのかもしれません。
しかし、前記の書物で、ラミスは以下のように述べます。
「学問する者は前方にそのどちらがあるかを知らずに、カーテンをあけ外を見ようとする。もしそこに虚無を見るならば、彼は引き返し、人びとに外を見なさい、この世界は虚空のただ中に漂う人工の宇宙船だと分かるでしょうと告げるのだ。そしてもし人びとが、何故このように悲惨な、怖るべき知らせをもたらすのかと問うたら、彼は何と答えるべきか。答えはいくらでもある。自己を認識することで人間は強くなるかもしれない。社会に新しい概念―つまり可能性と共同行動―をうみ出す力となるかもしれない。人びとが真の状況を理解すれば、苦境から抜け出す道も見出せるだろう、少なくとも希望のある方向へ一歩を踏み出せるだろう。このように彼は好きな答えをすればよい。その答えは、当たるかもしれないし、外れるかもしれない。しかしこれらは彼の第一の答えではない。学問をする者として彼はまずこう答えればよいのだ。『なぜなら事実その通りなのだから』と」
ラミスのいうとおり、学者の役割は、まず第一に、「人々に事実、真実を知らせる」ことでしょう。それを知らなければ、人々が連帯して適切な行動をとることも、そうすることによって状況を打開することもできないからです。「学問の自由」が憲法で保障されているのも、たとえば学者のこのような役割を踏まえてのことと考えます。ことに社会・人文科学系の学者については、そうした役割を果たすのでなければ、その存在に、一般の人々にとってどれほどの意味があるでしょうか?
Q.「絶望の裁判所」で今も働いている同僚に対して、何かメッセージはありますか。
瀬木:今年も、かなりの数の裁判官の後輩、また裁判官や元裁判官の先輩から年賀状をいただきました。
僕は外に出て批判する立場になりましたから、彼らに対してあまり大きなことはいえないと思っています。
だから、心ある裁判官たちには、僕の言葉ではなく、高名なインタヴュアーであるスタッズ・ターケルの書物から、三つの言葉を贈りたいと思います。
次のような言葉です。
「お上の言葉がいまほど尊大に国民に押しつけられている時代は、かつてない。お上がこれほど大胆に、恥ずかしげもなく権力を振りかざす時代にあって、無抵抗が時代の風潮になってしまったような感すらある。だが、その見方は必ずしも当たっていない」
「生来の希望的観測に従って行動することを私たちに躊躇させるものは恐怖心だ、と私は思っているんです。その中でもいちばん大きな恐怖は、排除される恐怖、追放される恐怖、群れを離れる恐怖だと思います。しかし、希望に基づいて行動するためには、自ら進んで追放される覚悟が必要なのです。希望に溢れた人間になるためには、その恐怖心を克服することが必要なのです。本物の共同体を作り出すためには、共同体を失う恐怖心を克服しなければならないのです」
「信念と希望のあいだには大いに関係があると私は思うんです。基本的に信念というのは、確信がもてなくても先へ進んで行動を起こすということだと思いますが、その原動力になっているのは希望なんです。希望があるから、人は行動を起こすんです。そして行動を起こすということじたいに大きな意味があるんです。うまくいってもいかなくても、私は諦めません。希望も死にはしません」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150204-00041921-gendaibiz-bus_all
深刻な裁判所の劣化 裁判官の猥褻&パワハラ行為、和解強要や被害者恫喝…広がる司法不信
Business Journal 1月15日(木)6時0分配信
昨年12月14日、衆議院議員総選挙の投票と同時に、国民が最高裁判所裁判官を審査する国民審査投票が行われた。この国民審査とは、権力を監視し法を司る最高裁の裁判官として適切な人物かどうかを国民が審査する制度で、審査対象の裁判官の氏名が記載された投票用紙に、罷免を望む人物がいれば×印を記入して投票する。有効投票のうち過半数が罷免を望まない限り罷免されず、一度審査を受けて罷免されなければ、その後10年は審査を受けることがない。
一般論として、衆院選の際は選挙にばかり報道も国民の関心も向かってしまう。その上、任命されてから最初の衆院選で国民審査を受けることから、最高裁裁判官としてのキャリアも短いため、判断材料も少なく、裁判官の実績や人物像が十分に把握されていない。このような状況で、国民の大多数が罷免を望むということは考えにくい。従って、この罷免率(罷免を可とする票の割合)は低いことが常であり、この制度は形骸化していると指摘されることが多くなっている。
●司法への不信が深刻化
最近の国民審査での罷免率は、2005年は平均7.8%(対象は6名)、09年は6.7%(対象は9名)だった。しかし12年には平均8.1%(対象は10名)にまで上昇していた。その罷免率が、先月の衆院選の際の国民審査では、平均9.2%(対象は5名)にまで高まっていることがわかった。ちなみに、各対象裁判官の罷免率の詳細は以下の通りである。
【14年12月 国民審査罷免率一覧 罷免率の高い順】
木内道祥(弁護士出身):罷免率 9.57%
池上政幸(検察官出身):罷免率 9.56%
山崎敏充(裁判官出身):罷免率 9.42%
鬼丸かおる(弁護士出身):罷免率 9.21%
山本庸幸(行政官出身):罷免率 8.42%
※罷免率は、有効投票数約4600万票の中で×を投じた票の割合を元に計算
今回罷免率が全体的に高まったのは、投票率が低く、投票したのは問題意識の高い層が多かったためという要因も考えられ、加えて最高裁を中心に裁判所全体の問題ある実態が明らかとなり、司法への不信が日本中に広まっていることも挙げられるだろう。
昨今、民事では裁判官が裁判を早く終わらせるために和解を強要する事件や、裁判官が原告や被告の一方の主張のみを判決文に写し書き、裁判を終わらせる事件が多発している。また刑事では、検察や警察の主張を無理やりに追認するような内容の判決が多発し、冤罪の疑いの強い事件が多く指摘されている。
また昨年には、最高裁で長く勤務し、その内部を知り尽くす元裁判官の瀬木比呂志明治大学法科大学院専任教授が、最高裁の実態を克明に描いた書籍『絶望の裁判所』(講談社新書)を出版した。同書では、裁判官の倫理観が欠如している実態や、裁判官の能力が低下している実態が克明に描かれている。裁判所内部では、最高裁を中心に、裁判官は多くの裁判を処理することが求められており、その作業に専念するのに伴って、良心や良識が失われていき、和解を強要したり恫喝してでも、裁判を多く処理する裁判官が出世する実態になっているという。さらに同書では、裁判官によるパワハラや猥褻行為が内部では多発している様子が告発され、長くベストセラーとなり大きな反響を呼んでいる。
(参考:14年6月2日付当サイト記事『裁判官による性犯罪、なぜ多発?被害者を恫喝、和解を強要…絶望の裁判所の実態』、6月4日付『冤罪を免れるのは困難、中身を見ず和解を強要…裁判所の病理を元裁判官が告発』)
このように、裁判所の問題が多く指摘されたことで、司法への不信が高まっているという事情があるのではないだろうか。
●山本氏の罷免率が低い理由
最高裁は現在、選挙における一票の格差の問題について、「違法状態にあるが選挙は有効」とする判断を続けている。このように選挙を無効とはしないために、今回の衆院選でも比例代表の得票率は、自民党が33.1%、公明が13.8%しかないにもかかわらず、議席数では両党を合わせて3分の2を超える大多数となっている。
先月の総選挙の際、12月13日付当サイト記事『自民党、得票率わずか35%でも大多数 ゆがんだ政治を許す裁判所、その改革方法とは?』でも、いびつな選挙を許している裁判所に関する瀬木氏の指摘を紹介した。
今回の国民審査の結果を受けて、瀬木氏は次のように語る。
「罷免率が平均で9%以上というのは、非常に高い割合になってきていると思います。09年、12年と比べ、増加が顕著です。およそ国民の10人に1人が最高裁裁判官の罷免を積極的に求めている状況であり、司法への信頼が大きく失われてきているのではないでしょうか」
今回、行政官出身の山本氏の罷免率が低く、一方で木内氏、池上氏、山崎氏の罷免率が高い結果となったことについて、こう見解を述べた。
「罷免率が低い山本氏は内閣法制局出身で、13年7月の参議院選挙の無効が争われた裁判において『無効とされた選挙において一票の価値(<各選挙区の有権者数÷各選挙区の定数>を<各選挙区の議員一人当たりの有権者数÷全国平均の有権者数>と比較した割合)が0.8を下回る選挙区から選出された議員は、すべてその身分を失うものと解すべき』と、明確に一票の格差の違法を判断しています。その上で、『選挙制度の憲法への適合性を守るべき立場にある裁判所としては、違憲であることを明確に判断した以上はこれを無効とすべきであり、そうした場合に生じ得る問題については、経過的にいかに取り扱うかを同時に決定する権限を有するものと考える』と判断しています。この点が、最高裁の中でも権力の監視機能をきちんと果たしている裁判官として評価されたのではないでしょうか」
つまり、国民は一票の格差の是正を求めており、さらに突き詰めれば、最高裁が権力に迎合するのではなく、独立し、毅然として権力のチェック機能を果たすことを求めているといえるのではないだろうか。
一人一票の原則を尊重し、参院選の無効を認定したことで山本氏が評価されたのだとすれば、この国民審査の結果は国民の重要な声を反映している。
仮に政権が暴走したとしても、司法はその行為を独立した立場から監視して判断し是正できる、非常に重要な存在である。この国民審査の結果が司法改革に反映されることを期待したい。
実際のところ、国民審査について多くの報道では「全員が信任された」ことしか報じていないが、報道機関は罷免率が平均9%以上と非常に高い状態に達している事実と併せて、その詳細な内容を伝えるべきである。そして私たち国民は国民審査において適切に票を投じ、明確に意見を出せるようにすることが大切だ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150115-00010003-bjournal-bus_all&p=3
Unknown (風来坊)2015-02-11 17:19:46参院選の不正選挙裁判に引き続き、今回の衆院選不正選挙裁判でも最高裁と言う場所が多分に絡んできますので、改めて周知と言う事で。
最高裁が自民公明の圧力に屈したと言うよりも、始めから時の政権与党と最高裁は癒着していたのでしょうね。
参院選の不正選挙裁判の時も立法府から同様の癒着が有っても何ら可笑しくない。
法の番人が自ら法の支配を否定したのでは政治および法律と言うシステムが機能不全に陥り、それは暴力の支配の肯定に繋がりかねない。
自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150208-00010001-bjournal-bus_all
裁判官の人間性で、判決はいかようにも変わる! 『ニッポンの裁判』『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏が暴く「判決決定のからくり」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150204-00041921-gendaibiz-bus_all
深刻な裁判所の劣化 裁判官の猥褻&パワハラ行為、和解強要や被害者恫喝…広がる司法不信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150115-00010003-bjournal-bus_all
情報有難う御座いますm(__)m
Business Journal 2月8日(日)6時0分配信
最高裁判所の元裁判官で明治大学法科大学院教授の瀬木比呂志氏が、1月16日に上梓した『ニッポンの裁判』(講談社現代新書)において、衝撃の告発をしている。1月29日付当サイト記事『与党・自公、最高裁へ圧力で言論弾圧 名誉毀損基準緩和と賠償高額化、原告を点数化も』でも報じたが、自民党と公明党による実質上の言論弾圧が行われているというものだ。
2001年、当時与党であった自民党は、森喜朗首相の多数の失言を受けて世論やマスコミから激しく批判され、連立与党の公明党も、最大支持母体の創価学会が週刊誌などから「創価学会批判キャンペーン」を展開されるなど、逆風にさらされていた。そのような状況下、自公は衆参法務委員会などで裁判所に圧力をかけ、裁判所がそれを受けて最高裁を中心に名誉棄損の主張を簡単に認めるように裁判の基準を変え、賠償額も高額化させ、謝罪広告などを積極的に認めるようになった。
両党が森内閣や創価学会への批判を封じるために最高裁に圧力をかけたという事実はもちろん、最高裁が権力者である自公与党の意向を受けて裁判における判断基準を変えていたことも、民主主義の大原則である言論の自由、また三権分立をも根底から脅かす、大きな問題である。
また、名誉棄損の基準が歪み、それを悪用した恫喝訴訟が民事でも刑事でも蔓延しており、大きな社会問題となって各方面に影響が広がっている。瀬木氏の告発を報道する国内メディアが相次ぎ、海外の報道機関も取材に訪れていることから、さらに騒動は拡大する見通しだ。時の政権が実質上の言論弾圧をしていた事実が明らかになったことで、政界にも動揺が走っている。
●政界に広がる反響
前回記事は瀬木教授の最高裁内部の実態の告発を中心としていたが、政界での事実経緯を振り返るため、今回は当時の議会での動きを振り返ってみたい(以下、肩書はいずれも当時のもの)。
森政権や創価学会が世論から批判を強く浴びていた01年3月、法務大臣の高村正彦氏(自民党)は参院法務委員会で、「マスコミの名誉毀損で泣き寝入りしている人たちがたくさんいる」と発言した。これを受けて故・沢たまき氏(公明党)は「名誉侵害の損害賠償額を引き上げるべきだと声を大にして申し上げたい」と、同月の参院予算委員会で損害賠償額の引き上げについて、まさに“声を大にして”要求。魚住裕一郎氏(同)も同年5月の参院法務委員会で「損害賠償額が低すぎる」「懲罰的な損害賠償も考えられていけばいい」と強く要求した。
そして同月の衆院法務委員会で、公明党幹事長の冬柴鐵三氏が大々的にこの問題を取り上げて「賠償額引き上げ」を裁判所に迫った。これを受けて最高裁民事局長は「名誉毀損の損害賠償額が低いという意見は承知しており、司法研修所で適切な算定も検討します」と回答した。
つまり、自民党と公明党の圧力によって最高裁が名誉棄損の基準を変えていたのだ。そして裁判所が安易に名誉毀損を認めるようになり、その結果、不祥事を起こし追及されている側がそれを隠ぺいするために、また性犯罪者が告訴を取り下げさせるために、告発者や被害者を名誉毀損だとして訴える“恫喝訴訟”が頻発するようになった。
このような経緯について、現役の国会議員からも与党に対して批判の声が上がっている。衆議院議員の落合貴之氏(維新の党)は、告発に驚きを隠さない。
「実質的な恫喝目的で名誉棄損を悪用するケースや、公益通報者を保護しないケースなど、多様な陳情が寄せられています。その原因が、与党の自民党の圧力にあったという告発に大変驚いています。恫喝訴訟の問題については、国民を適切に保護するために、また被害者の方々が保護されるように、議員としてしっかりと取り組んでいきたいと思います」
一方、都内の区議会などでも反響が上がっている。世田谷区議を務める田中優子氏(無所属)は、次のように語る。
「性犯罪者側が、被害者女性や支援者を訴えている恫喝訴訟問題などに強い憤りを感じていました。しかし、その元が与党による最高裁への圧力だと聞き、大変驚いています。司法がこんな状態では、いったい国民は何を信じればよいのでしょうか。このような問題は区議としても注視して、被害者が適切に保護されるように尽力していきます」
このように本問題については、政界でも国会から地方議会に至るまで、多くの議員から批判の声が上がっており、今後国会での質問主意書などで取り上げられる可能性も高い。
これは現在の安倍政権ではなく、過去の自民党・公明党の問題であるが、安倍政権が過去の与党の問題に対しても毅然とした対応をできるのか、今後の動きに注目が集まっている。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150208-00010001-bjournal-bus_all&p=2
裁判官の人間性で、判決はいかようにも変わる! 『ニッポンの裁判』『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏が暴く「判決決定のからくり」
現代ビジネス 2月4日(水)6時2分配信
2015年1月16日、講談社現代新書より、日本の裁判のリアルな実態を描いた『ニッポンの裁判』が刊行された。冤罪連発の刑事訴訟、人権無視の国策捜査、政治家や権力におもねる名誉毀損訴訟、すべては予定調和の原発訴訟、住民や国民の権利など一顧だにしない住民訴訟・・・・・・、裁判の「表裏」を知り抜いた元エリート裁判官の瀬木比呂志氏(明治大学法科大学院専任教授)をも驚愕させたトンデモ判決のオンパレードは、司法に淡い期待を抱く読者を打ちのめした。その衝撃的な内容はネットでも話題になり、発売直後に早々に重版が決定している。
本書は「元裁判官による裁判批判の書」であると同時に、裁判官の意思決定のメカニズムについても踏み込んだ解説をしている。一般には、裁判官は、提出された証拠の事実認定を行い、それを法律に当てはめることで、オートマチックに判決を下しているようなイメージが流布している。しかし、瀬木氏は「それは幻想に過ぎない」と断ずる。実際の司法判断はもっと生臭く、裁判官の人間性によって、判決の内容もいかようにも変わるというのだ。だとすると、著しく劣化した裁判官は、著しく劣化した判決を連発することになる・・・・・・。知られざる「判決決定のからくり」について瀬木氏に聞いた。
Q.『ニッポンの裁判』は、横断的な判例分析・解説・批判という性格をもっていますが、それに先立ち、第1・2章で、裁判官がいかに判決を下すのか、その判断構造の実際、判断決定の心理メカニズムを克明に描いている点がすばらしいと思いました。事実関係さえ同じであれば、どんな裁判官でもおおむね似たような判決が出るものと思っていましたが、判決というのは、実は、きわめて個性的、属人的なものだったんですね。
瀬木:裁判官の判断は、A 実際に判決に記されているように、個々の証拠を検討して、あるいはいくつかの証拠を総合評価して断片的な事実を固めた上で、それらの事実を総合し再構成して、事実認定を行い、それを法律に当てはめて結論を出しているのだろうか、それとも、B そのような積み上げ方式によってではなく、ある種の総合的直感に基づいて結論を出しているのだろうか。こういう問題ですね。
考え方は分かれますが、僕はBだと思います。裁判官、元裁判官にもこの考え方は多いですし、学者では、『日本人の法意識』(岩波新書)等で一般にも知られる川島武宜(たけよし)教授(東京大学)が、はっきりとこちらの考え方をとっています。
つまり、裁判官は、主張と証拠を総合して得た直感によって結論を決めているのであり、判決に表現されている前記のような思考経過は、後付けの検証、説明にすぎないということです。
もちろん、裁判官が審理のある段階で得た以上のような最初のまとまった心証については、裁判官は、その後の審理の中で、それが本当に正しいものであるか否かを注意深く検証し続けなければなりません。このことも当然です。最初の直感に自信をもちすぎることはきわめて危険であり、民事でも刑事でも、誤った裁判の原因になりやすいのです。
Q.裁判官は、緻密な事実認定と法解釈によって、論理的に判決を下すと思い込んでいたのですが、実際には、きわめて直感的に結論を下すのだという点、これはショッキングでした。誤解を恐れない言い方をすれば、理屈は後付けだったんですね。
瀬木:全くそのとおりであり、本書の第1章や『民事訴訟の本質と諸相』(日本評論社)で引用した近年の脳神経科学の成果も、これを裏付けています。人間の判断はまずは直観としてやってくるのであり、理屈は、その事後的な検証、また、後付けの説明として行われます。それは裁判でも同じことです。
だからこそ、裁判官の人間性やバックグラウンドが決定的に重要なのですよ。そういうものがすぐれている人間でなければ、いい裁判もできないし、指導的な判例も作れません。
つまり、裁判官の、一般的・法的能力、洞察力、識見とヴィジョン、謙虚さ、人権感覚、民主的感覚等の重要性ということです。
裁判官の判断が、裁判官のあらゆる能力、もちあわせている知識、経験、人間や社会に対するものの見方、人権感覚等の総合的な函数であるなら、知的能力だけは高くても冷たくエゴイスティックな裁判官が人々にやさしい判断を下すわけがないし、人はよくても能力や総合的なヴィジョンに欠ける裁判官が社会のあるべき方向を指し示す判決を下すことも難しいでしょう。実際、個々の判決を見てゆくと、そのとおりのものになっています。
ここに、キャリアシステムの一つの大きな問題点があります。キャリアシステムというのは、司法試験に合格した若者が司法修習を経てそのまま裁判官・検察官になる官僚裁判官・検察官システムをいいますが、日本のピラミッド型キャリアシステムの下では、当事者を訴訟記録の片隅に記されているただの記号としかみない、また、普通の人々の心の持ち方や動き方がさっぱりわからない裁判官が発生しがちであり、裁判官の能力やモラルが落ち込むと、その傾向が一気に加速されやすい。そういう裁判官に、いい裁判ができるわけがないのです。
Q.本書を読んで、初めて、リアリズム法学なるものを知りました。このインタビューを読んでいる読者にもわかりやすいように解説していただけますか。
瀬木:詳しくは第2章のとおりですが、簡単に説明しましょう。
リアリズム法学の代表格の学者、実務家は、ジェローム・フランク(1889~1957)です。
フランクは、「法」が固定した不変のものであってそこから演繹的に結論が導き出されるという考え方をドグマであるとしてしりぞけ、社会・人文科学一般の分析を援用しながら、実際には、裁判官こそが、法を欲し、法を創造し、また、変更しているのであり、書かれた「法」は、裁判官が判断を行うに当たっての「一つの素材」ないしは「判断を規整する一つの枠組み」でしかないとしました。
また、裁判において問題となる「事実」も、なまの出来事から抽象され法的な評価を加えられた事実であって、客観的存在としての「事実」とは異なるとしました。
そして、判決は、「法律」と「事実」によって決定されるというよりも、いずれかといえばむしろ、「刺激」と「人格」、つまり、「〔広義の裁判過程において裁判官に与えられる〕刺激」と「〔裁判官の〕人格」によって決定されると定式化したのです。ここで、「刺激」というのは、裁判官の外側から裁判官に働きかける諸要素であり、証拠、法律のほか、世論等の社会的な諸要因をも含むでしょう。「人格」というのは、裁判官個人に属する諸要素であり、性格、各種の偏見ないし嗜好、習慣ないし性癖等を含むでしょう。
要するに、フランクは、法的判断とは、法をその規整の枠組みとしながらも、本質的には、裁判官の個人的な価値選択であり、政策判断であり、その全人格の反映であると論じたのです。
このリアリズム法学は、アメリカにおける哲学流派、哲学的方法の代表的なものであるプラグマティズムの系譜を引いており、僕自身の思想もプラグマティズムから大きな影響を受けているので、僕には、うなずける部分がかなりあります。なお、先にふれた川島教授の学説も、リアリズム法学の影響を受けています。
Q.ある意味大変ラディカルな考え方ともいえますが、瀬木さんも、この考え方に賛同されるのでしょうか。
瀬木:賛同できる部分も大きいですね。
しかし、先のようなリアリズム法学の考え方については、それがかなりの程度に当てはまる領域と、そうではない領域があると思います。
一般的にいえば、その判断が広義の「価値」に関わり、社会や政治、行政のあり方に大きな影響を与える訴訟(このような訴訟を「価値関係訴訟」と呼びたいと思います。普通の刑事事案でも再審請求事件等はこれに該当します)、また、その中でもそのような傾向の大きい事案ほど、裁判官の価値観、人格、人間性によって結論が影響される度合いが大きいと思います。たとえば、憲法訴訟、行政訴訟、国家賠償請求訴訟、名誉毀損損害賠償請求訴訟、原発訴訟、刑事の大事件や再審請求事件等ですね。
『ニッポンの裁判』における僕の裁判分析については、確かに、僕なりの「プラグマティズム法学、リアリズム法学」の試みという側面があります。しかし、僕の分析は、対象となる裁判にひそむことのある虚偽意識的、イデオロギー的な欺瞞を指摘しつつも、論理一貫性や法律の趣旨をも重視しており、リアリズム法学ですべてが解けるといった単純な考え方によっているわけではありません。
Q.裁判官の人間性によって判断が左右されるとすると、近年叫ばれている「裁判官の劣化」は由々しき問題ですね。本書で紹介されているようなトンデモ判決も、裁判官の質の低下によってもたらされている可能性がありますね。
瀬木:そうですね。法的・知的能力一般の低下傾向、そして、リベラルアーツ的なバックグラウンドが薄くなってきていること、その双方が問題ですね。
近年、刑事のみならず民事においても、コモンセンス、良識を欠いた非常識な判決が増えています。たとえば、民事の象徴的なケースとして、第5章で取り上げた、認知症の老人が家族のわずかな隙をついて外に出、電車にはねられた事件で、JRの家族に対する損害賠償請求を認めた名古屋地裁(2013年8月9日、上田哲裁判長)、名古屋高裁(2014年4月24日、長門栄吉裁判長)の判決、ことに前者があります。
第一審判決は、妻のみならず別居の長男に対する請求まで認めているのですが、この裁判長が、悲しいことに、最高裁判所調査官経験者なのですね。この判決は、認知症患者の介護に当たっている家族や医療関係者を震撼させ、インターネットには、「それでは、『認知症の老人は座敷牢にでも閉じ込めておけ』とでもいうのか?」との批判の声まで出ました。刑事では、「明日はあなたも殺人犯」ですが、民事では、「明日はあなたも高額賠償義務者」なのです。
僕の感覚からしても、かつては、中間層の職人裁判官たちでも、このような判決は書かなかったと思うのです。無理のない範囲の低額和解を勧め、当事者らがのまなければ、注意義務違反を認めることは困難である、として棄却したでしょう。こうした事案では、鉄道会社も、債権が成立していると思われる外観がある以上株主からの追及がありうることなどを考えて訴訟は起こすが、勝敗にはこだわらない、というのが本音であると思われ、したがって、棄却の判断によって傷付く者は、実際にはいないからです。
だから、認容判決によって悪い先例を作るべきではありません。また、こうした判決によって、認知症をわずらう老人の面倒をみようという親族や施設が減少してしまうといった萎縮効果、波及効果のことも考えるべきです(なお、控訴審判決は、長男に対する請求は認めず、妻に対する認容額も半分にするなど一定の配慮を行っており、その意味では和解的な判決ともいえます)。
こうした事故は、結局のところ、社会に弱者保護のためのシステムが構築され、機能していないことから起こります。そして、かつての職人的裁判官たちであれば、「この鉄道会社の請求を認容するのはいくら何でもコモンセンスに反する」ということには、最低限気付いたと思いますね。その程度の良識、また、社会に関するヴィジョンは、多数派の裁判官たちももっていました。社会のひずみの全責任を裁判で弱者に押し付けるのは、明らかに、正義と公平の原理に反するからです。
また、これは、裁判官が当事者の視点に立って裁判を行えているか、という問題でもあります。最後は当事者の視点に立って判断するようにすれば、非常識判決は避けられるのです。本件の場合でいえば、認容判決については、被告は到底承服できないと考えるでしょうし、棄却判決については、原告も不満はあるもののそう判断されるのもやむをえないと受け止めるであろうことは、容易に想像がつくでしょう。
僕が、この本の次に、『リベラルアーツの学び方』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、5月ころ刊)という本を出すことにしたのは、以上のことと関係があります。法律家を目指す若者に限らず、中堅以下の層におけるリベラルアーツ的な教養の劣化は、大変深刻な問題です。この本に挙げた例からもわかるとおり、すでに、現在40代以下の裁判官たちには、この傾向が強く出てきていますからね。
Q.『絶望の裁判所』では、竹崎前最高裁長官を頂点とする最高裁事務総局の裁判官支配、統制による弊害が指摘されていましたが、これも、裁判官の質の劣化に関係しているのでしょうか? 最高裁が腐っているから現場が疲弊するのか、そもそも低レベルの裁判官が増えているから、前近代的な司法統制がまかりとおるのか? 「鶏卵論争」のような質問で恐縮ですが。
瀬木:第7章で、制度的な側面について、裁判への影響という観点から『絶望の裁判所』を強力に補足したとおり、いずれも正しいといえますね。鶏卵というより、相乗作用でしょう。
昨日、今書いている原稿の関連で、コッポラの『地獄の黙示録』を見ていたのですが、あれはすごい映画ですね。何回見ても飽きないし、すべてのシーンがすばらしい。『市民ケーン』レヴェルの作品かもしれないとさえ思いました。もっとも、劇場公開版のほうが後の完全版よりいいというところは珍しい。完全版では、人物たちの性格があいまいになってしまっています。
その、『地獄の黙示録』の、川をさかのぼるにつれてどんどん状況が悪く、絶望的になってゆくという感じ、あれは、2000年前後以降の裁判所の雰囲気そのままです。
日本全体の状況がそのようになってゆかないことを強く祈りたいですね。そのことは、第8章の末尾で、2000年代における最高裁のかつてない腐敗に関連して、書いておきました。
Q.今言われた第7章「株式会社ジャスティスの悲惨な現状」、これも面白かったですね。裁判所を、顧客からの信頼を失ったブラック企業にたとえて揶揄した内容で、瀬木さん一流のブラックジョークが効いていて、クスクス笑いながら読みました。しかし、これから進路を決める司法修習生にとっては笑い事ではないですね。これを読んだら、まともな修習生は裁判官になろうとは思わないのではないでしょうか。
瀬木:いや、国民にとっても笑い事ではないのですよ。そういう裁判所の裁判官が裁判をするのですからね。
カスタマーアンケートの結果が満足度二割を割り、「カスタマーのための徹底的な構造改革」後も、結果はほとんど変わらない。
売上げは、構造改革や社外独立事業者のかつてない大幅増員、エリート社員の三割増員にもかかわらず全分野で激減。
エリート社員の不祥事も目立ち始め、2000年代以降は、8件もの性的な不祥事が連続して発生。
エリート職員はわずか2900人であるにもかかわらず、各社員が10年に1度人事部の「リストラ査定システム」をくぐらなければならず、近年は、これによって、毎年数人が首を切られ、少なくともそれと同程度ないしそれ以上の人間が肩叩きで退職。しかも、首を切られる社員や肩叩きにあう社員は必ずしも成績不良者とは限らない。
エリート社員たちの服務規律は、明治20年に作られたものであり、正式な休職の制度もなく、したがって、社員たちは、病気になった場合には、回復の見込みが早期に立たなければ退職するほかない。有給休暇についても正式な制度はなく、支社長たちの「取決め」によっている。
今日では多くの大学のほか大企業にも設けられているハラスメント防止のためのガイドラインも、相談窓口や審査機関もなく、セクシュアル、パワー、モラル等の各種のハラスメントが横行し、しかもハラスメントを行っている上司たちにはその意識すらない。
こういうことです。僕は、「企業ならすでにつぶれている」とだけ書きましたが、なるほど、いわれてみれば、これは一種のブラック企業ですね。
裁判官には優秀な人やすぐれた人もたとえば5パーセントから10パーセントとかそういった水準ではなお存在すると思いますが、全体がこうでは、つまり、構造的な問題が大きくては、改善は容易ではない。いい人やすぐれた人は上にはいけないのですからね。
僕は、学生たちには、裁判官になるなとは言っていませんが、僕の本も含め、さまざまな情報をよく検討して考えたほうがよいことは、間違いがないでしょうね。
Q.こうした絶望的な現状を伝えることは、むしろ、「絶望の裁判所」を「超・絶望の裁判所」にするだけだという意見もありうると思うのですが?
瀬木:確かに、『絶望の裁判所』に対する感想には、書物を評価するものの中にも、「司法の絶望的な状況を知らされても、その解決策は必ずしも早期に実現する可能性が高いとは思われないので、さらに絶望的にならざるをえない」というものも散見されましたね。
これについては、C・ダグラス・ラミス(アメリカ人政治学者、評論家。日本在住)の書物『影の学問、窓の学問』(加地永都子ほか訳、晶文社)の序文が、一つの答えを示しています。その序文で、著者は、読者に対して、こういう意味のことを問いかけます。
「あなたが住んでいる世界は、実は、リアルな世界、一つの惑星ではなく、広大な宇宙船の中に作られた仮想世界である。しかし、誰もそのことは知らない。さて、もしもそれが可能であるとしたら、あなたは、禁じられた領域である宇宙船の窓辺にあえて歩み寄り、広大無辺な虚空の広がりを見、自分がリアルな世界だと思ってきた場所が実は構築された仮想世界にすぎなかったことを知りたいか? それとも、そんなことは知らないまま安らかに一生を終えたいか?」
著者の答えは、「知りたい」であり、僕の答えも同じです。
でも、数人の賢い後輩たち(法律家とそれ以外の)にこの問いを投げかけてみたところ、純粋に「知りたい」という答えは一つもなく、うちの二人は、答えを保留し、一か月くらい後になってから、「やっぱり知らないまま死ぬほうがいいかもしれないと思います」と答えました。
賢明で考え深い後輩たちのこの迷いはとても興味深いですね。人間の多くは、「普通の意味でいえば知らないほうが幸せな事実」は知らないですませるほうがいいと思うものなのかもしれません。
しかし、前記の書物で、ラミスは以下のように述べます。
「学問する者は前方にそのどちらがあるかを知らずに、カーテンをあけ外を見ようとする。もしそこに虚無を見るならば、彼は引き返し、人びとに外を見なさい、この世界は虚空のただ中に漂う人工の宇宙船だと分かるでしょうと告げるのだ。そしてもし人びとが、何故このように悲惨な、怖るべき知らせをもたらすのかと問うたら、彼は何と答えるべきか。答えはいくらでもある。自己を認識することで人間は強くなるかもしれない。社会に新しい概念―つまり可能性と共同行動―をうみ出す力となるかもしれない。人びとが真の状況を理解すれば、苦境から抜け出す道も見出せるだろう、少なくとも希望のある方向へ一歩を踏み出せるだろう。このように彼は好きな答えをすればよい。その答えは、当たるかもしれないし、外れるかもしれない。しかしこれらは彼の第一の答えではない。学問をする者として彼はまずこう答えればよいのだ。『なぜなら事実その通りなのだから』と」
ラミスのいうとおり、学者の役割は、まず第一に、「人々に事実、真実を知らせる」ことでしょう。それを知らなければ、人々が連帯して適切な行動をとることも、そうすることによって状況を打開することもできないからです。「学問の自由」が憲法で保障されているのも、たとえば学者のこのような役割を踏まえてのことと考えます。ことに社会・人文科学系の学者については、そうした役割を果たすのでなければ、その存在に、一般の人々にとってどれほどの意味があるでしょうか?
Q.「絶望の裁判所」で今も働いている同僚に対して、何かメッセージはありますか。
瀬木:今年も、かなりの数の裁判官の後輩、また裁判官や元裁判官の先輩から年賀状をいただきました。
僕は外に出て批判する立場になりましたから、彼らに対してあまり大きなことはいえないと思っています。
だから、心ある裁判官たちには、僕の言葉ではなく、高名なインタヴュアーであるスタッズ・ターケルの書物から、三つの言葉を贈りたいと思います。
次のような言葉です。
「お上の言葉がいまほど尊大に国民に押しつけられている時代は、かつてない。お上がこれほど大胆に、恥ずかしげもなく権力を振りかざす時代にあって、無抵抗が時代の風潮になってしまったような感すらある。だが、その見方は必ずしも当たっていない」
「生来の希望的観測に従って行動することを私たちに躊躇させるものは恐怖心だ、と私は思っているんです。その中でもいちばん大きな恐怖は、排除される恐怖、追放される恐怖、群れを離れる恐怖だと思います。しかし、希望に基づいて行動するためには、自ら進んで追放される覚悟が必要なのです。希望に溢れた人間になるためには、その恐怖心を克服することが必要なのです。本物の共同体を作り出すためには、共同体を失う恐怖心を克服しなければならないのです」
「信念と希望のあいだには大いに関係があると私は思うんです。基本的に信念というのは、確信がもてなくても先へ進んで行動を起こすということだと思いますが、その原動力になっているのは希望なんです。希望があるから、人は行動を起こすんです。そして行動を起こすということじたいに大きな意味があるんです。うまくいってもいかなくても、私は諦めません。希望も死にはしません」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150204-00041921-gendaibiz-bus_all
深刻な裁判所の劣化 裁判官の猥褻&パワハラ行為、和解強要や被害者恫喝…広がる司法不信
Business Journal 1月15日(木)6時0分配信
昨年12月14日、衆議院議員総選挙の投票と同時に、国民が最高裁判所裁判官を審査する国民審査投票が行われた。この国民審査とは、権力を監視し法を司る最高裁の裁判官として適切な人物かどうかを国民が審査する制度で、審査対象の裁判官の氏名が記載された投票用紙に、罷免を望む人物がいれば×印を記入して投票する。有効投票のうち過半数が罷免を望まない限り罷免されず、一度審査を受けて罷免されなければ、その後10年は審査を受けることがない。
一般論として、衆院選の際は選挙にばかり報道も国民の関心も向かってしまう。その上、任命されてから最初の衆院選で国民審査を受けることから、最高裁裁判官としてのキャリアも短いため、判断材料も少なく、裁判官の実績や人物像が十分に把握されていない。このような状況で、国民の大多数が罷免を望むということは考えにくい。従って、この罷免率(罷免を可とする票の割合)は低いことが常であり、この制度は形骸化していると指摘されることが多くなっている。
●司法への不信が深刻化
最近の国民審査での罷免率は、2005年は平均7.8%(対象は6名)、09年は6.7%(対象は9名)だった。しかし12年には平均8.1%(対象は10名)にまで上昇していた。その罷免率が、先月の衆院選の際の国民審査では、平均9.2%(対象は5名)にまで高まっていることがわかった。ちなみに、各対象裁判官の罷免率の詳細は以下の通りである。
【14年12月 国民審査罷免率一覧 罷免率の高い順】
木内道祥(弁護士出身):罷免率 9.57%
池上政幸(検察官出身):罷免率 9.56%
山崎敏充(裁判官出身):罷免率 9.42%
鬼丸かおる(弁護士出身):罷免率 9.21%
山本庸幸(行政官出身):罷免率 8.42%
※罷免率は、有効投票数約4600万票の中で×を投じた票の割合を元に計算
今回罷免率が全体的に高まったのは、投票率が低く、投票したのは問題意識の高い層が多かったためという要因も考えられ、加えて最高裁を中心に裁判所全体の問題ある実態が明らかとなり、司法への不信が日本中に広まっていることも挙げられるだろう。
昨今、民事では裁判官が裁判を早く終わらせるために和解を強要する事件や、裁判官が原告や被告の一方の主張のみを判決文に写し書き、裁判を終わらせる事件が多発している。また刑事では、検察や警察の主張を無理やりに追認するような内容の判決が多発し、冤罪の疑いの強い事件が多く指摘されている。
また昨年には、最高裁で長く勤務し、その内部を知り尽くす元裁判官の瀬木比呂志明治大学法科大学院専任教授が、最高裁の実態を克明に描いた書籍『絶望の裁判所』(講談社新書)を出版した。同書では、裁判官の倫理観が欠如している実態や、裁判官の能力が低下している実態が克明に描かれている。裁判所内部では、最高裁を中心に、裁判官は多くの裁判を処理することが求められており、その作業に専念するのに伴って、良心や良識が失われていき、和解を強要したり恫喝してでも、裁判を多く処理する裁判官が出世する実態になっているという。さらに同書では、裁判官によるパワハラや猥褻行為が内部では多発している様子が告発され、長くベストセラーとなり大きな反響を呼んでいる。
(参考:14年6月2日付当サイト記事『裁判官による性犯罪、なぜ多発?被害者を恫喝、和解を強要…絶望の裁判所の実態』、6月4日付『冤罪を免れるのは困難、中身を見ず和解を強要…裁判所の病理を元裁判官が告発』)
このように、裁判所の問題が多く指摘されたことで、司法への不信が高まっているという事情があるのではないだろうか。
●山本氏の罷免率が低い理由
最高裁は現在、選挙における一票の格差の問題について、「違法状態にあるが選挙は有効」とする判断を続けている。このように選挙を無効とはしないために、今回の衆院選でも比例代表の得票率は、自民党が33.1%、公明が13.8%しかないにもかかわらず、議席数では両党を合わせて3分の2を超える大多数となっている。
先月の総選挙の際、12月13日付当サイト記事『自民党、得票率わずか35%でも大多数 ゆがんだ政治を許す裁判所、その改革方法とは?』でも、いびつな選挙を許している裁判所に関する瀬木氏の指摘を紹介した。
今回の国民審査の結果を受けて、瀬木氏は次のように語る。
「罷免率が平均で9%以上というのは、非常に高い割合になってきていると思います。09年、12年と比べ、増加が顕著です。およそ国民の10人に1人が最高裁裁判官の罷免を積極的に求めている状況であり、司法への信頼が大きく失われてきているのではないでしょうか」
今回、行政官出身の山本氏の罷免率が低く、一方で木内氏、池上氏、山崎氏の罷免率が高い結果となったことについて、こう見解を述べた。
「罷免率が低い山本氏は内閣法制局出身で、13年7月の参議院選挙の無効が争われた裁判において『無効とされた選挙において一票の価値(<各選挙区の有権者数÷各選挙区の定数>を<各選挙区の議員一人当たりの有権者数÷全国平均の有権者数>と比較した割合)が0.8を下回る選挙区から選出された議員は、すべてその身分を失うものと解すべき』と、明確に一票の格差の違法を判断しています。その上で、『選挙制度の憲法への適合性を守るべき立場にある裁判所としては、違憲であることを明確に判断した以上はこれを無効とすべきであり、そうした場合に生じ得る問題については、経過的にいかに取り扱うかを同時に決定する権限を有するものと考える』と判断しています。この点が、最高裁の中でも権力の監視機能をきちんと果たしている裁判官として評価されたのではないでしょうか」
つまり、国民は一票の格差の是正を求めており、さらに突き詰めれば、最高裁が権力に迎合するのではなく、独立し、毅然として権力のチェック機能を果たすことを求めているといえるのではないだろうか。
一人一票の原則を尊重し、参院選の無効を認定したことで山本氏が評価されたのだとすれば、この国民審査の結果は国民の重要な声を反映している。
仮に政権が暴走したとしても、司法はその行為を独立した立場から監視して判断し是正できる、非常に重要な存在である。この国民審査の結果が司法改革に反映されることを期待したい。
実際のところ、国民審査について多くの報道では「全員が信任された」ことしか報じていないが、報道機関は罷免率が平均9%以上と非常に高い状態に達している事実と併せて、その詳細な内容を伝えるべきである。そして私たち国民は国民審査において適切に票を投じ、明確に意見を出せるようにすることが大切だ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150115-00010003-bjournal-bus_all&p=3
Unknown (風来坊)2015-02-11 17:19:46参院選の不正選挙裁判に引き続き、今回の衆院選不正選挙裁判でも最高裁と言う場所が多分に絡んできますので、改めて周知と言う事で。
最高裁が自民公明の圧力に屈したと言うよりも、始めから時の政権与党と最高裁は癒着していたのでしょうね。
参院選の不正選挙裁判の時も立法府から同様の癒着が有っても何ら可笑しくない。
法の番人が自ら法の支配を否定したのでは政治および法律と言うシステムが機能不全に陥り、それは暴力の支配の肯定に繋がりかねない。
自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150208-00010001-bjournal-bus_all
裁判官の人間性で、判決はいかようにも変わる! 『ニッポンの裁判』『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏が暴く「判決決定のからくり」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150204-00041921-gendaibiz-bus_all
深刻な裁判所の劣化 裁判官の猥褻&パワハラ行為、和解強要や被害者恫喝…広がる司法不信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150115-00010003-bjournal-bus_all
情報有難う御座いますm(__)m