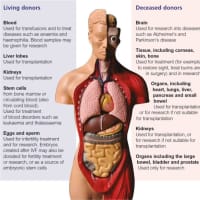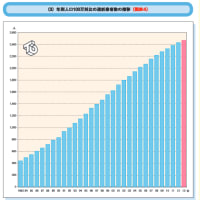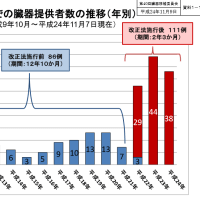【あの世への旅立ち】
●先祖の霊を供養するには
先祖供養には、なかなか厳しい面があります。
先祖の霊が地獄でもがき苦しんでいる時に、地上の子孫が仏壇などの前で一生懸命に先祖供養をすると、
先祖は自分を助けるための白い縄が上からするすると下りてきたように感じます。
それをつかんで手繰ると、上がることができ、子孫の所に出てきます。
その際、子孫の側に、先祖を供養して成仏させる力があれば、先祖は救われますが、
その力がないと、子孫が逆に引っ張り込まれることも多々あります。
そのため、先祖供養はしっかりと真理を勉強した上で行っていただきたいのです。
死んだ人が霊界についての知識を持っていないと、説法を聴いても法話の内容をすんなりとは理解できません。
したがって、先祖供養の際には、子孫が、亡くなった人のレベルに合わせて、
私の説いている教えの一部を噛み砕き、その人に分かるようなかたちで伝えてあげることが大事です。
先祖供養をしている内に、自分の方が体が重くなったり調子が悪くなるようなら、力不足なのです。
その場合には幸福の科学の精舎や支部で供養をした方がよいでしょう。
個人では、そう簡単には地獄霊に勝てません。
死は、人間にとって、一大事です。
真理を知らない人にとって、死んだ時には本当にびっくり仰天し、突如、落下して大慌てしている状態になります。
そういう人を供養するには少し時間がかかり、そう簡単にはいきません。
まず、生きている人の方ができるだけ悟りの力を強くしていくことが大切です。

http://raisekofuku-plan.jp/tabidachi.html

 |
(1)心肺(しんぱい)停止(医学的死)
心臓が止まり、肉体が死ぬと、魂は肉体を抜け出し、多くの場合、天井のあたりから自分の肉体を見下ろします。この段階では、魂と肉体をつなぐ「霊子線(れいしせん)」がつながっており、魂は肉体の痛みなどを、まだ感じています。
|
 |
(2)通夜(つや)
通夜式が、通常、死後一日置いて行われるのは、魂と肉体をつなぐ「霊子線」が切れるのを待つためです。死んですぐ荼毘に付すと、魂と肉体がまだつながっているため、魂は苦しみ、安らかにあの世に旅立てません。
|
 |
(3)葬儀
葬儀は単なる儀式ではなく、亡くなった方の魂が自分の死を悟り、この世や家族への執着を断って、あの世への旅立ちの必要性に気づく機会です。僧侶の読経は、本来、亡くなった方にそのことを悟らしめるために行われるべきものです。
|
 |
(4)初七日~四十九日
魂は、死後、七日間くらいは自宅周辺にとどまっていますが、死後、四十九日ほどたつと、「導きの霊」などに、あの世へ旅立つことを本格的に促されます。魂が安らかにあの世へ旅立てるように、「初七日」や「四十九日」などの節目で法要を行うのです。
|
 |
(5)埋葬
昨今、「散骨」や「樹木葬」などが流行っていますが、お墓は、死後、自分が死んだと分からずに迷っている魂に、死を悟らしめる縁(よすが)となります。また、遺された人々が、故人に供養の心を手向けるときの、「アンテナ」のような役割もあります。お墓をつくり埋葬することは、大切なことなのです。
|
 |
(6)お盆、その他の供養
お盆になると、先祖供養が盛んに行われます。お盆の時期には、霊界と地上との交流が盛んになり、「地獄の門が開く」とも言われています。また、新盆(にいぼん。死後、初めてのお盆)を過ぎても、ときどき、先祖を供養することで、天国に還った霊人はもちろん、地獄に墜ちた方にも、光を手向けることができます。(※ただし、供養する側の悟りが低いと、死後、迷っている霊の悪しき影響を受けることもあります。まず供養する側が、あの世の知識を学び、心の修行を重ねていることが大切です。)
|