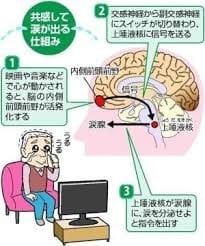誰しも4人の祖父母がいる。
孫にとり4人すべてに可愛がってもらえれば、
これほど嬉しいことはない。
でも、おじいちゃん、おばあちゃんが早くに亡くなるなど、
いろんな理由でまったく知らない子もいるだろう。
とても寂しいことである。
僕もそれに近い。
父方の祖父母はまったく知らない。一度でも会ったことがあったろうか。
その記憶さえない。
わずかに母方の祖母だけが、
幼い日一緒に住んでいたという記憶があるだけだ。
とは言っても、祖母としてのはっきりとした記憶を持っているわけではない。
半ば強引に手繰り寄せようとしても、
確かな思い出はなかなか浮かんでこない。
祖母が孫を猫かわいがりするような、
逆に孫が「おばあちゃん、おばあちゃん」と慣れ親しむ、
そんな普通にあるはずの祖母と孫との
睦まじい光景さえも浮かんで来はしないのである。
正直なところ、祖母というより
「どこかのお婆ちゃん」との思いの方が強かった。
そんな寂しい思いさえさせる存在だった。

この「原田のばあちゃん」について、
ただ一つ、よく覚えていることがある。墓掃除だ。
祖母にとっては自分の連れ合いだった人、
つまり僕にはまったく記憶のない祖父となる人が眠る
原田家代々の墓へ小学生になるかならないかの僕を連れて行き、
掃除の手伝いをさせたのである。
西洋映画にでも出てきそうな鉄柵をぐるり巡らせた
広くて立派な墓だったようだが、原爆爆心地に近かったため、
その熱光線を浴びた鉄棒はぐにゃりと曲がり、
石壁に垂れ下がるようにして残されていた。
そんな有様をばあちゃんは、ため息交じりにじっと眺めていた。
原田家は代々のキリスト教である。
キリスト教では、当時はまだ土葬と決められていたから、
地面は今みたいにコンクリートではなく土だった。
そうとあって、ちょっと油断すると雑草に覆われてしまう。
ばあちゃんが繁く通ったのは、そんな理由もあった。
僕はもっぱら雑草を取り除くのを手伝う役なのだが、
手伝いになったかどうか。
そして、そんなことをしながらどんな話をしていたのだろうか、
まったく思い出せない。
そもそも、ちゃんと話なんかしたことがあったのか。
今は火葬が許され、立派にコンクリート面となった、
その墓に原田のばあちゃんも祖父と一緒に眠っている。
そして墓は僕の父、と言うより母に引き継がれて
今は当家の墓所となっている。
本来なら、僕が守り継がなければならないのだが、
今は長崎に在住している3人の姪たちがその役を担ってくれている。
原田のばあちゃんも守られているはずだ。
ただ、姪には見も知らぬ人である。
原田のばあちゃんは、どこか寂しく、悲しい。