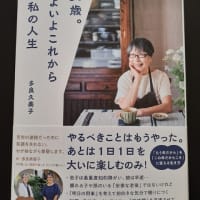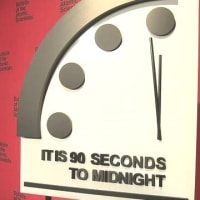腰は右にくの字に折れ、脚はOの字。時に歩きにくく、汚れた道を、身を打ちつけながら凌いできた81年という時。懐かしい。無垢な幼い日々。
一 福島のおねえちゃん
小学1、2年生の時の担任だった福島先生は、学校でも僕を「たー坊」と呼んだ。僕も「福島のおねえちゃん」と言った。何せ50㍍と離れていないご近所さん同士。年の差を考えれば一緒に遊ぶなんてことはあるはずもないが、小さい頃から出会うたびに「たー坊」「おねえちゃん」と親しんでいたから、そう呼び合うのはごく自然なことだった。母にすれば、そうであっても先生を「おねえちゃん」なんて呼ぶのは申し訳ないことだと思ったのだろう、「学校では先生と呼ばんといかんよ」と言った。「うん、分かった」頷いてはみたものの、やっぱり、ひょいと「おねえちゃん」と出てしまうのだった。
「たー坊行くよ。用意出来てるね」おねえちゃんは毎朝決まって、そう声をかけてくれた。学校へ一緒に行くのだ。母は笑顔ながらに「先生が迎えに来てくれるよ。ほれ早く」真新しい布製のランドセルを背に急かせた。玄関の戸を少し開け、そこからおねえちゃんが来るのを待ちわびたように覗き見る。ほどよく日に焼けた顔、すらりと引き締まった体、まるでスポーツ選手のようだ。「たー坊」と呼ぶのと同時に戸を開け、「おねえちゃん、おはよう」と言った。「あっ」あわてて母を振り返り、ちょんと頭を下げた。
学校の途中には長い石段があった。「さあ頑張って」おねえちゃんが手を引いてくれる。それがまたうれしくて、少しくらいの風邪なんかでは決して休まなかった。
そんなおねえちゃんが、突然いなくなってしまった。二年生の二学期頃だったと思う。おねえちゃんの名が「鈴木」に変わった。「結婚されたのよ」母がそう教えてくれた。結婚がどんなものかも分からず、まして結婚すると姓が変わるのだということなど理解できようもない年頃。
「結婚されたので学校を辞められ、引っ越されたの」おねえちゃんは学校からも、ご近所からもいなくなった。どこか遠くへ行ってしまった。もう「たー坊行くよ」と声をかけてくれることも、手を引いてもくれないのだね。「なぜ、なぜ」と責め、わあわあと泣き出した僕を母は困惑顔で抱き締めたのだった。小さな小さな、初恋とも言えぬ物語。恋しいなあ、おねえちゃん。
二 出口先生 痛かった
出口先生のビンタは痛かった。教室の後ろにクラスメート3人と一緒に立たされ、いきなりパン、パン、パン、パンとやられたのである。さらに屋上へ連れていかれ、コンクリートに直接正座させられた。授業一時限の間だったから40分ほどだったと思う。置き去りにされた4人はポロポロ涙を流した。小学6年生になったばかりの頃だった。
なぜなのか。思い当たることはあった。仲良くしていたクラスメートが転校することになった。それで僕ら4人は何かプレゼントすることを思いつき、それぞれ小遣いから50円を出し合って学校帰りに繁華街のデパートへ揃って買いに行ったのである。手ごろなボールペンを買い、「明日渡そうね」と話しながらデパートを出たところに、帰宅中の出口先生とばったり。「お前たち、何しているんだ」「実は、○○君にプレゼントを買いに来たんです」先生に隠すことでもないので正直に話すと、「そうか、早く家に帰れ」僕らは先生に分かってもらえたのだと思っていた。

ところが翌朝、「昨日の4人後ろに立て」と言われたのだ。おずおずと整列すると、何も言わず、いきなりビンタが飛んできた。茫然とし、「なぜなのか」と心で問うた。「転校していく友だちにプレゼントするのは悪いことなのか」「そのため、50円出し合ったのがいけないのか」、それとも「学校帰りに繁華街へ買いに行ったのがいけないのか」。だが、どんなに考えても「悪いことをした」とは思えなかった。学生時代、柔道の選手だった体つきの先生を見ると、「なぜなんですか」と聞く勇気も出てこない。結局、悔しさをかみ殺し、声を出さず涙を流すだけだった。
子供心に抱いた「なぜ」は解けないまま過ぎ、50年ほど後に一晩泊まりの同窓会で出口先生と顔を合わせたことがあった。だが、互いにどこか気まずい風で、言葉を交わすことはなかった。やがて先生は亡くなられてしまった。この年齢となり、先生に恨みなんてあろうはずもない。ただ「なぜ」の答えがほしかった。頬をさするとビンタの痛さが蘇る。
三 ごめんなさい 山下先生
あだ名は『エス』。僕が名付けた。中学3年生の英語の授業。黒板の前には山下先生が立っていた。教師になってまだ2、3年ほどの若い女先生だった。『S』と書けば、なぜ、こんなあだ名にしたかおおよそ想像がつくはずだ。はち切れんばかりの若い女性の姿、形を見れば、ごく自然にこんなあだ名になる。中学3年生、いかにも思春期の男の子が考えそうなことだ。また、この年頃の男の子というのは女性の気をひきたくて、奇抜な行動をしたり、いたずらを仕掛けるものである。
ある日のこと。山下先生の授業が始まる前、学級委員長だった僕はクラスの皆に「今度の山下先生の授業では、何を聞かれても一切返事をしないことにしようよ。皆、どう?」そう提案すると、皆が「面白そうだ」と手を挙げてくれのだ。女子までも「いいわね」と同調したのは、なぜか分からない。ともかく満場一致のいたずら作戦となった。

授業が始まった。先生が「ここはこうで、こういう意味です。●●君分かりますか」と尋ねる。だが●●君、一言も返事をしない。「分かりますか」再度聞かれても同じだ。仕方なく別の生徒に尋ねてみたが、これまた返事なし。さすがに不審に思った山下先生。「皆、どうしたんですか」教室には先生の声が響くばかりだった。ベテランの先生だったら、そんな生徒の悪だくみなど簡単に見破り、その張本人を前に引っ張り出すことなぞ造作もなかっただろう。だが、何せ山下先生は純粋無垢な新米教師だ。生徒の悪だくみにまんまと引っかかってしまったのである。しまいにはどうしてよいのか分からず、しくしく泣き出してしまった。
若き女先生の涙、こうなるとは思いもしなかった。この悪だくみの張本人だった僕はすぐさま白旗を挙げた。立ち上がり、先生に向かって「Sorry ごめんなさい」頭を下げた。生徒が初めて口を開いた瞬間だった。
四 「アラン君」はやめて
『ゴリカッパ』何ともひどいあだ名を、それも女性に対してつけたものだ。高校の時の音楽教師・荒木先生には申し訳ないやら、お気の毒やら。強く弁明しておくが、決して僕が名付けたものではない。いつの頃からかは知らないが、先輩たちからずっと受け継がれてきたらしい。そんなあだ名をつけられるほどの、何と言うか〝お顔立ち〟ではないと思えるのにである。
ある日の授業で、どういうことだったのか覚えてもいないが、荒木先生は全員合唱する形でフランス国歌『ラ・マルセイエーズ』を教え、歌わせた。そして、だいたい歌えるようになったのを見計らい、何を思われたのか知らないが「はい●●君、一人で歌ってみて」と僕を名指ししたのである。もちろんどぎまぎするばかり。そんな僕にはお構いなしに、『ゴリ……』、いや荒木先生はピアノを弾き始めた。「ええい、もう」まさに意を決して歌い始めた。
「アロン ザンファン ドゥ ラ パトリーエ」たどたどしいフランス語で、どうにか一番を歌い終えた。親友が「ヨッ」と声をかけ、拍手してくれ、それにつられるようにパラパラと続いた。以来、僕は荒木先生のお気に入りの生徒の一人になった。廊下ですれ違うと、「おはよう、アロン君」と言うものだから、近くを歩いていた女生徒2人が、「えっ」「何っ」顔を見合わせ、すかさず「ぷっ」と吹き出した。
しばらくすると、僕は生徒の間で「アラン」と言われるようになった。荒木先生が「アロン君」と言ったのを、例の女生徒が「アラン君」と聞き違え、「そう言えば●●君、アラン・ドロンにちょっぴり似てるわね」なんてことで、校内に「アラン」と広めたらしい。あの二枚目スターに! 1人にんまりするより、恥ずかしさに身がすくむ思いだった。それもこれも元はと言えば荒木先生のせい。俯き加減に廊下を歩いていると、その先生が向こうからやってきた。そして「おはよう、アラン君」と声をかけてきたのだった。