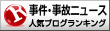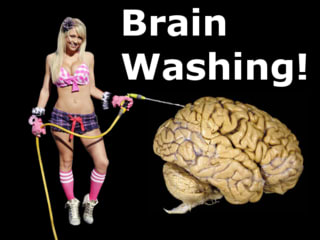
“洗脳” という言葉ほどトリッキーな言葉はめずらしい。洗脳というものについて多少でも自分の頭で考えたことのある人は、必ずその字面に異和感を覚えるはずである。
洗脳 = 脳を洗う
洗う というのは汚れなどの好ましくないものをきれいな媒体を利用して抜き去り、汚れていない望ましい状態にすることを意味するのではないか。つまり、プラスイメージがある。
“洗脳”の語源
この言葉の日本語への導入は1950年代で、英語の brainwashing の直訳である。この語は朝鮮戦争を背景に出てきた用語である。朝鮮戦争当時、共産軍の捕虜になったアメリカ軍兵士に対して強制的な共産主義教育が施された。資本主義の誤り、白人至上主義の誤り、帝国主義の誤り等々、誤った歴史観と世界観を共産軍の毛沢東主義とマルクス・レーニン主義によって正す目的で、英語を話す中国軍の将校たちが捕虜収容所の年若いアメリカの兵士たちに対して信念と使命感から再教育をしたのである。言うなれば、強制的な“改宗”である。中国軍側は間違った思想に気づかせて目覚めさせなくてはいけないという使命感でヤンキーの兵士たちを教育したのである。再教育とはいえ、受け容れるまで眠らせない、食事を与えない等々、ほとんど拷問に近いかたちであった。
思想改造された米軍捕虜たちが本国アメリカに帰還してその“非人道的な拷問”の実態が明らかになり、 brainwashing と呼ばれ、問題になった。実際、帰還兵の中にはすっかり思想改造され て、アメリカ批判、帝国主義批判、共産主義賛美をし始める者も出てきた。Brainwashing は瞬く間に当時の流行語になり、映画や小説にもなった。
て、アメリカ批判、帝国主義批判、共産主義賛美をし始める者も出てきた。Brainwashing は瞬く間に当時の流行語になり、映画や小説にもなった。
実は、英語のこの brainwashing は中共軍が使っていた中国語の “洗脳” の英語への直訳だったのである。 英語の brainwashing の初出は1950年10月7日で、マイアミニュース紙上に初めてこの語が活字となってメディアに現れた。つまり、日本語の“洗脳”は中国語の“洗脳”の直接の移入ではなく、英語の brainwashing を経由して、間接的に入って来たものである。つまり、“洗脳”は英語圏に入ってからすぐに再び日本語の漢字の海に飛び込んで、元の漢字の“洗脳”として日本語世界に泳ぎだしたのである。
朝鮮戦争以前
話がややこしくて恐縮だが、朝鮮戦争の中共軍が米軍捕虜の思想改造を実施する以前に中国共産党は一部の“反動的”な自国民に対して同様の思想改造をしていて、それをすでに“洗脳”と呼んでいた。この“洗脳”という言葉は、毛沢東の共産主義思想の足りない“国民の敵”に対する強制的な再教育の意味で使ったのが最初だったのである。アメリカのGIに対して行う前に、中国の地主階級や知識階級といった“反動分子”に対してさんざん使ってきた再教育システムとその名称だったのである。その“再教育システム”が朝鮮戦争で米軍捕虜に対してなされたときにも同様にそれを中国語の“洗脳”という言葉で呼んでいて、米軍捕虜がその言葉を本国に持ち帰ったという次第である。
易経の“洗心”
“洗脳” という言葉は中国語起源であるが、実は同じ中国語には歴史的な類例がある。それは“洗心”である。これは“無心”“無私”に通じる中国思想の概念で、出典は「易経」(BC2500 - AD1722)である。のちに道教、仏教、特に禅宗にも流れ込んだ歴史ある概念である。「きれいな心」「澄んだ心」「汚れのない心」「けがれない心」「曇りない心」にすること、という風に理解していいかもしれない。日本人にも非常に理解しやすい概念ではなかろうか。洗心学園という学校法人も全国にいくつか実在する(ちなみに“洗脳学園”は実在しない)。この“洗心”が中国語の大海にすでに溶け込んでいたために、1940年代の中国共産党の党員の頭に“洗脳”という言葉がひょいと浮かび上がってきたものと推察される。ここで重要な点は、狂信的な毛沢東主義者の頭から出てきたにせよ、悪い意味はまったくなく、“洗心”の現代版、文字通りの良い意味、中国思想に根差したストイックな意味で使われ始めたという点である。
“洗脳”の論理的な意味
さて、今日使われる “洗脳” という言葉には、「間違った考え方を植えつけられる」という被害的な意味、マイナスイメージがある。これは日本語だけでなく、英語の brainwashing でも同じである。最初にも言及したが、 washing は文字通り 洗う ということで、本来むしろプラスのイメージがある。汚れを流し去るということはどんな文化圏でもプラスイメージを持っている。逆に、汚す、シミをつける、というのはマイナスイメージを持つ言葉である。
つまり、“洗” 脳 という言葉には常にプラスイメージがつきまとうことにな る。毛沢東主義、マルクス・レーニン主義を“歴史的真理”として標榜していた1940-50年代の中国共産党の党員たちにとっては、他の主義、思想はすべてウソ、誤り、クソに他ならなかった。そういったものを洗い流せばいやでも、“真理”が見えるという論理であった。“洗脳”という思想改造は汚れた服を洗濯してあげるのと同じで、善意の行為だったのである。したがって、彼ら毛沢東主義者の用語をそのまま受け容れて使っていくこと自体に、“脳の洗濯”は良いことだという暗黙の認識も引き継がれているのである。「きれいにしてあげてるんだよ」ということである。洗脳の“洗”には洗脳者の側の善意、真理、正義の意味が含まれているのである。Brainwashing を画像検索するといろいろ出てくるが、“洗脳”を文字通りに絵にしたものは、どうしても“洗ってきれいにしている図”になってしまうことがわかる。
る。毛沢東主義、マルクス・レーニン主義を“歴史的真理”として標榜していた1940-50年代の中国共産党の党員たちにとっては、他の主義、思想はすべてウソ、誤り、クソに他ならなかった。そういったものを洗い流せばいやでも、“真理”が見えるという論理であった。“洗脳”という思想改造は汚れた服を洗濯してあげるのと同じで、善意の行為だったのである。したがって、彼ら毛沢東主義者の用語をそのまま受け容れて使っていくこと自体に、“脳の洗濯”は良いことだという暗黙の認識も引き継がれているのである。「きれいにしてあげてるんだよ」ということである。洗脳の“洗”には洗脳者の側の善意、真理、正義の意味が含まれているのである。Brainwashing を画像検索するといろいろ出てくるが、“洗脳”を文字通りに絵にしたものは、どうしても“洗ってきれいにしている図”になってしまうことがわかる。
思想改造や再教育を受けた“被害者側”がその相手側の善意を含んだ用語を使うことは、洗脳者を免罪することになってしまう。加害者であるはずの洗脳者の“善意”を認めることになってしまう。
“洗脳”という言葉の自己“洗浄”力
別の例を挙げよう。Aが引いている荷車を、Bが後ろから押すとする。Bは善意で押して、“協力した”と主張する。“協力”とは相手の利益になる行為である。しかし、Aは、Bに余計なことをされて迷惑だと思ったとしよう。ここでBの行為を指す言葉が“協力”しかなかったとしよう。そうすると、Bの行為は“協力”と呼ばれ続け、迷惑に思ったA自身も他の言葉が見つからず“Bはわたしを協力した”と言っていれば、Bはいつまで経っても、免責されたままになる。“協力”という言葉を使っているかぎりは、AはBを非難することができない。Bを非難、批判するためには、Aは“協力された”ではなく、“妨害された”と言わなければならないのである。
この例を使って、“洗脳”を見直すと、Bによって洗脳されたと感じている側がいつまでもその事実を、Bが“協力した” と呼んでいるようなものである。AはBによる行為を非難したいと思っていても、その行為を語るときに“妨害した”と言わずに、Bはわたしに“協力”した、と言い続けているようなものなのである。Bの側はAにして良いことをしたと常に言われていることになる。
つまり、“洗脳”という言葉自体が洗脳者を自動的に免罪してしまうのである。被害者側自身がその“洗脳”という言葉を使うたびに、洗脳者を免責するという皮肉な結果になってしまうのである。“洗脳”という言葉にはこうした自動的自己免責機能が備わっている。テフロンのフライパンのようにどんな批判も焦げ付かずに跳ね返してしまう自己“洗浄”作用がある。そればかりではない。その語を不用意に使う者がいつまでたっても“洗脳”の円環から抜け出せない“使用者再洗脳作用”も備えていると言ってもいいだろう。この“洗脳”の呪縛は、“洗脳”という言葉を使い続けるかぎり、いつまで経っても解けることはない。
トロイの木馬
一般的に言って、利害対立関係にある相手集団の言葉を自分たちの言語世界に導入すると、“トロイの木馬”となる危険がある。長い間それはコンピューターウィルスのように気づかれることがない。
たとえば、“アメリカインディアン”という言葉は15世紀のコロンブスという白人の地理学的誤解を引きずった言葉であって、それは当事者のインディアンたちにとっては本来侮辱的である。自分たちがその言葉を使うことは自分たちに関する相手の誤解を受け容れることになるのであるから、当然屈辱的になるはずである。しかし、長い間このトロイの木馬は気づかれることはなかった。最近になって、この言葉の“洗脳的危険性”が認識されて、“アメリカ先住民 native Americans”という言葉に差し替えられ始めたのである。“たかが言葉” ではないことがわかってきたのである。
中国の共産主義者が使った“洗脳”という言葉を、相手の資本主義国のアメリカ人は“見事な木馬”とし て讃嘆して、自分たちの言語世界に引き入れてしまった。この言葉が英語に直訳されて brainwashing として1950年にアメリカのメディアに現れると、その具体的かつ斬新なイメージが一般大衆に強いインパクトを与えた。そして、アメリカの大衆もメディアもこの brainwashing という新しい言葉に見事に“洗脳” されてしまったのである。これはまさにリチャード・ドーキンズが言うところの ミーム meme の絶大な威力である。簡潔にしてビビッドなこの言葉に対して、「brain washing か、うまいことを言うなあ、一本取られたわい」と思ったのである。言い方を変えれば、アメリカ人は中国人のこの造語の素晴らしさに脱帽し、屈服したのである。”washing” の持つ“洗心”以来のストイックな善意の意味を、ジョーク好きなアメリカ人はシニカルな逆説表現として実に面白いと思ったのである。そして、その受け売りのまま、その語のもつ潜在的な“洗脳力”に気づかないまま、 brainwashing を使い始めてしまったのである。このトロイの木馬の不死身のウィルスはずっと生き続ける。 “洗脳” という語の文字面(もじづら)の、ぞわぞわとした異和感はそこにある。この言葉がトリッキーであるというのはこの意味である。
て讃嘆して、自分たちの言語世界に引き入れてしまった。この言葉が英語に直訳されて brainwashing として1950年にアメリカのメディアに現れると、その具体的かつ斬新なイメージが一般大衆に強いインパクトを与えた。そして、アメリカの大衆もメディアもこの brainwashing という新しい言葉に見事に“洗脳” されてしまったのである。これはまさにリチャード・ドーキンズが言うところの ミーム meme の絶大な威力である。簡潔にしてビビッドなこの言葉に対して、「brain washing か、うまいことを言うなあ、一本取られたわい」と思ったのである。言い方を変えれば、アメリカ人は中国人のこの造語の素晴らしさに脱帽し、屈服したのである。”washing” の持つ“洗心”以来のストイックな善意の意味を、ジョーク好きなアメリカ人はシニカルな逆説表現として実に面白いと思ったのである。そして、その受け売りのまま、その語のもつ潜在的な“洗脳力”に気づかないまま、 brainwashing を使い始めてしまったのである。このトロイの木馬の不死身のウィルスはずっと生き続ける。 “洗脳” という語の文字面(もじづら)の、ぞわぞわとした異和感はそこにある。この言葉がトリッキーであるというのはこの意味である。

ちなみに この brainwashing は英語になった中国語の単語ベスト10(使用頻度)のうち、第3位である。第1位は ketchup茄汁(18世紀)、第2位は tea茶(17世紀) である。“洗脳”という穏やかならぬ言葉が、日常的な食品とならぶほどに深く根付いて使用されていることがわかる。