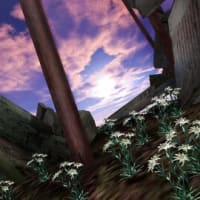なかにし礼さんの歌で最も親しみやすいのは、
何と言ってもこれでしょう。
この歌の大ヒットのきっかけは、かつて人気バラエティー番組だった
「欽ちゃんのどこまでやるの!」(テレビ朝日系、略して欽どこ)。
細川がレギュラー入りした背景には、
その以前に彼が『8時だョ!全員集合』の本番中にアキレス腱断裂を負ってしまい
数ヶ月にわたる休養を余儀なくされたことがある。
復帰後初の仕事が『欽どこ』へのゲスト出演だったのだが、
その際に細川が自分の出番が終わってもなかなか帰ろうとせず
「テレビに出られるって、いいなあ」と感慨深げに話していた姿に
萩本が「よかったら、来週も来ない?」と声を掛けた経緯が、萩本の著書でたびたび語られる。
(一部ウィキペディア解説より)
1982年1月16日に細川がレコーディングしたが、この時点ではレコード化の予定はなく、
デモテープの段階であった。
その後、細川がレギュラー出演していたテレビ朝日系列バラエティ『欽ちゃんのどこまでやるの!』の
メインパーソナリティである萩本欽一が番組内で何か一曲歌うことを提案し、
デモテープの中からこの曲が採用された。
『欽ちゃんのどこまでやるの!』の番組内では、1月27日の放送で初披露して以来、
9月15日まで毎週歌われ、また「途中で楽曲を止められる」という萩本欽一の番組演出などで一躍有名となり、
覚えやすいメロディも手伝い幅広い年齢層に浸透した。
そう言えば本人出演のカラオケ映像もありましたね。
(残念ながら削除されてしまいましたが)
良い役してましたねー、美人を連れてオープンカーに乗ったりして。
ちなみに舞台は北国とはまったく関係ない(笑)。
北酒場 1982 - 細川たかし | Kita Sakaba - Hosokawa Takashi (Lyrics + Romaji)
1982年、第24回日本レコード大賞
作詞:なかにし礼
作曲:中村泰士(なかむらたいじ)


-------------------------------------------------------------------------------------------------
このまま中村泰士さんも紹介します。
まず、自分にとって忘れられないテレビ出演は、「笑っていいとも」のなかにあった
「私のメロディ」の審査員出演でした。
私のメロディ 1983 ラッツ&スターまね
ちなみに、ピアノ演奏は当時フュージョングループ「ザ・スクエア(のちのT-SQUARE)」に所属していた
和泉宏隆氏 でした。
面白かったなあ。(笑)
そして、忘れていけないのは、ちあきなおみの不滅の名曲「喝采」でした。
(1972・第14回日本レコード大賞)
「喝采」ちあきなおみ/1972(昭和47)年
作詞:吉田 旺
作曲:中村泰士
編曲:高田 弘
歌詞:Uta-Net
https://www.uta-net.com/song/1310/
「背景のオーケストラもすごい。
特にバイオリンが美しくてゾクゾクする。
歌謡曲というジャンルはあまり聞かないのだけれど、
思い出してみたら昭和の時代はこういう綺麗な音がたくさんありましたね。
イントロから終わりまで完璧な芸術作品です。」
kirara Arc さんのコメント。
「3分の歌の中に3年間のドラマが描かれていますね。
その3年間の映像が見えてくるのがすごい。」
eiji kamo さんのコメント。
「この年のレコード大賞(今と重みが月とスッポンぐらい違う)は、
この曲と小柳ルミ子の『瀬戸の花嫁』の一騎打ちと言われていたけど、
世の中的には小柳ルミ子を応援する声が圧倒的で、
特に子供はみんな小柳ルミ子が大好きだった。
そのころ、小学中学年の私もご多分に漏れず。
大賞がこちらになって、文字通り泣きじゃくってしまったが、
30代、40代、...と歳を重ねるにつれ、
この曲、ちあきなおみの凄さにただただ敬服、
素晴らしいとしかいいようがない。」
多摩川ゴロー さんのコメント。
中村さんは、生前最後に「ヤフージャパン・ニュース」でインタビューに応えていました。
「中村泰士さん、最後のインタビューで語っていた“僕の仕事の完成形”」
https://news.yahoo.co.jp/byline/nakanishimasao/20201225-00214416/
『正直、病気のことを聞いた時はショックでした。
なぜかというと、これこそが「僕の仕事の完成形だ」と言えることに、
まさに取り掛かったところだったんで。
というのはね、僕が新しい音楽の在りようとして考えた
“G POP(ジーポップ)”というものを打ち出していこう。
そう思って動き出したところだったんです。
音楽的にGENTLEで、GREATで、心の中のGOLDと言えるもの。
そういう曲を“G POP”と名付けて、一つのジャンルとして確立しようと。
演歌歌手の方でも、ポップス歌手の方でも、
自分のオリジナル曲が絶えた時というのはどれだけしんどいか。
そして、アイドルの人たちも、アイドル活動を終えたら、その後の道というのが難しくなる。
それを僕は見てきたので、そういった人たちも“G POP”というジャンルが確立されれば、
長く歌うものを手にすることができるんじゃないか。
今は歌手が若くなった分、歌手生命がどんどん短くなっている。
昔は歌手生命が長かった。
一曲をずっと歌っていた。
歴史にのっとった楽曲で、優れた楽曲。
それこそが日本のクラシックになると思うし、そこを目指せればと思ったんです。
これをやるのは、いろいろな蓄積がある人間がやった方がいいだろうし、
その“旗振り”をするには、今きちんと自分が走ってないといけない。
昔の名前で出ている古い作家であってはいけない。
そう思って、ギターをもう一回きちんと勉強して、
11月のレコーディングで11曲の新曲をYouTubeにアップしました。』
長文なので一部しか紹介できませんが、
中村先生は病気(ガン)の進行に意気消沈しそうになりながらも、
「仕事の完成形」への夢をも語っていました。
志半ばだっただけに、残念でなりません。
“今は歌手が若くなった分、歌手生命がどんどん短くなっている。”
アニメも歌番組も若い、というよりも「幼い」アイドルがもてはやされる今の状況では
一生歌える歌手なんかいらない、と言わんばかりの音楽シーンに危機感を覚えます。
“何もわからない子供なら元気でもてはやされるし、
学生時代のうちに歌で人気者になって、卒業後は社会人で人生やり直せる。”
大人やメディアがそうさせる風潮は、「エンタテインメントのインスタント化」みたいで
日本の音楽文化の低レベル化にも繋がっていると感じずにはいられません。
では最後に、中村泰士さんの「G POP チャンネル」から、
10月11日収録された「大阪ヒューマンランド~やんか!」をご紹介して終わりたいと思います。
これはNHK大阪「わが心の大阪メロディー」のエンディング用に書き下ろされ、
2001~2005年に自ら指揮した歌でした。
個人的には、上沼恵美子氏の出演や構成がマンネリ化してきて、
そろそろ「関西全体」とか「西日本」定義などの再構築が必要になっていると思います。
「大阪」だけだったら "どぎつい" イメージが先行してしまうので・・・
(否定できないでしょ?)
なかにし礼さん、中村泰士さんの
ご冥福をお祈り申し上げます。
2020年10月11日 三重 クラギ文化ホール 「大阪ヒューマンランド〜やんか!」
作詞・作曲:中村泰士
歌詞:JOYSOUND
https://www.joysound.com/web/search/song/187340


2023年10月25日付訪問者数:182名様
お付き合いいただき、ありがとうございました。
何と言ってもこれでしょう。
この歌の大ヒットのきっかけは、かつて人気バラエティー番組だった
「欽ちゃんのどこまでやるの!」(テレビ朝日系、略して欽どこ)。
細川がレギュラー入りした背景には、
その以前に彼が『8時だョ!全員集合』の本番中にアキレス腱断裂を負ってしまい
数ヶ月にわたる休養を余儀なくされたことがある。
復帰後初の仕事が『欽どこ』へのゲスト出演だったのだが、
その際に細川が自分の出番が終わってもなかなか帰ろうとせず
「テレビに出られるって、いいなあ」と感慨深げに話していた姿に
萩本が「よかったら、来週も来ない?」と声を掛けた経緯が、萩本の著書でたびたび語られる。
(一部ウィキペディア解説より)
1982年1月16日に細川がレコーディングしたが、この時点ではレコード化の予定はなく、
デモテープの段階であった。
その後、細川がレギュラー出演していたテレビ朝日系列バラエティ『欽ちゃんのどこまでやるの!』の
メインパーソナリティである萩本欽一が番組内で何か一曲歌うことを提案し、
デモテープの中からこの曲が採用された。
『欽ちゃんのどこまでやるの!』の番組内では、1月27日の放送で初披露して以来、
9月15日まで毎週歌われ、また「途中で楽曲を止められる」という萩本欽一の番組演出などで一躍有名となり、
覚えやすいメロディも手伝い幅広い年齢層に浸透した。
そう言えば本人出演のカラオケ映像もありましたね。
(残念ながら削除されてしまいましたが)
良い役してましたねー、美人を連れてオープンカーに乗ったりして。
ちなみに舞台は北国とはまったく関係ない(笑)。
北酒場 1982 - 細川たかし | Kita Sakaba - Hosokawa Takashi (Lyrics + Romaji)
1982年、第24回日本レコード大賞
作詞:なかにし礼
作曲:中村泰士(なかむらたいじ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
このまま中村泰士さんも紹介します。
まず、自分にとって忘れられないテレビ出演は、「笑っていいとも」のなかにあった
「私のメロディ」の審査員出演でした。
私のメロディ 1983 ラッツ&スターまね
ちなみに、ピアノ演奏は当時フュージョングループ「ザ・スクエア(のちのT-SQUARE)」に所属していた
和泉宏隆氏 でした。
面白かったなあ。(笑)
そして、忘れていけないのは、ちあきなおみの不滅の名曲「喝采」でした。
(1972・第14回日本レコード大賞)
「喝采」ちあきなおみ/1972(昭和47)年
作詞:吉田 旺
作曲:中村泰士
編曲:高田 弘
歌詞:Uta-Net
https://www.uta-net.com/song/1310/
「背景のオーケストラもすごい。
特にバイオリンが美しくてゾクゾクする。
歌謡曲というジャンルはあまり聞かないのだけれど、
思い出してみたら昭和の時代はこういう綺麗な音がたくさんありましたね。
イントロから終わりまで完璧な芸術作品です。」
kirara Arc さんのコメント。
「3分の歌の中に3年間のドラマが描かれていますね。
その3年間の映像が見えてくるのがすごい。」
eiji kamo さんのコメント。
「この年のレコード大賞(今と重みが月とスッポンぐらい違う)は、
この曲と小柳ルミ子の『瀬戸の花嫁』の一騎打ちと言われていたけど、
世の中的には小柳ルミ子を応援する声が圧倒的で、
特に子供はみんな小柳ルミ子が大好きだった。
そのころ、小学中学年の私もご多分に漏れず。
大賞がこちらになって、文字通り泣きじゃくってしまったが、
30代、40代、...と歳を重ねるにつれ、
この曲、ちあきなおみの凄さにただただ敬服、
素晴らしいとしかいいようがない。」
多摩川ゴロー さんのコメント。
中村さんは、生前最後に「ヤフージャパン・ニュース」でインタビューに応えていました。
「中村泰士さん、最後のインタビューで語っていた“僕の仕事の完成形”」
https://news.yahoo.co.jp/byline/nakanishimasao/20201225-00214416/
『正直、病気のことを聞いた時はショックでした。
なぜかというと、これこそが「僕の仕事の完成形だ」と言えることに、
まさに取り掛かったところだったんで。
というのはね、僕が新しい音楽の在りようとして考えた
“G POP(ジーポップ)”というものを打ち出していこう。
そう思って動き出したところだったんです。
音楽的にGENTLEで、GREATで、心の中のGOLDと言えるもの。
そういう曲を“G POP”と名付けて、一つのジャンルとして確立しようと。
演歌歌手の方でも、ポップス歌手の方でも、
自分のオリジナル曲が絶えた時というのはどれだけしんどいか。
そして、アイドルの人たちも、アイドル活動を終えたら、その後の道というのが難しくなる。
それを僕は見てきたので、そういった人たちも“G POP”というジャンルが確立されれば、
長く歌うものを手にすることができるんじゃないか。
今は歌手が若くなった分、歌手生命がどんどん短くなっている。
昔は歌手生命が長かった。
一曲をずっと歌っていた。
歴史にのっとった楽曲で、優れた楽曲。
それこそが日本のクラシックになると思うし、そこを目指せればと思ったんです。
これをやるのは、いろいろな蓄積がある人間がやった方がいいだろうし、
その“旗振り”をするには、今きちんと自分が走ってないといけない。
昔の名前で出ている古い作家であってはいけない。
そう思って、ギターをもう一回きちんと勉強して、
11月のレコーディングで11曲の新曲をYouTubeにアップしました。』
長文なので一部しか紹介できませんが、
中村先生は病気(ガン)の進行に意気消沈しそうになりながらも、
「仕事の完成形」への夢をも語っていました。
志半ばだっただけに、残念でなりません。
“今は歌手が若くなった分、歌手生命がどんどん短くなっている。”
アニメも歌番組も若い、というよりも「幼い」アイドルがもてはやされる今の状況では
一生歌える歌手なんかいらない、と言わんばかりの音楽シーンに危機感を覚えます。
“何もわからない子供なら元気でもてはやされるし、
学生時代のうちに歌で人気者になって、卒業後は社会人で人生やり直せる。”
大人やメディアがそうさせる風潮は、「エンタテインメントのインスタント化」みたいで
日本の音楽文化の低レベル化にも繋がっていると感じずにはいられません。
では最後に、中村泰士さんの「G POP チャンネル」から、
10月11日収録された「大阪ヒューマンランド~やんか!」をご紹介して終わりたいと思います。
これはNHK大阪「わが心の大阪メロディー」のエンディング用に書き下ろされ、
2001~2005年に自ら指揮した歌でした。
個人的には、上沼恵美子氏の出演や構成がマンネリ化してきて、
そろそろ「関西全体」とか「西日本」定義などの再構築が必要になっていると思います。
「大阪」だけだったら "どぎつい" イメージが先行してしまうので・・・
(否定できないでしょ?)
なかにし礼さん、中村泰士さんの
ご冥福をお祈り申し上げます。
2020年10月11日 三重 クラギ文化ホール 「大阪ヒューマンランド〜やんか!」
作詞・作曲:中村泰士
歌詞:JOYSOUND
https://www.joysound.com/web/search/song/187340

2023年10月25日付訪問者数:182名様
お付き合いいただき、ありがとうございました。