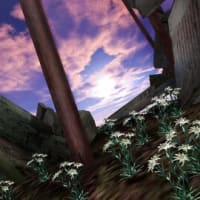2019年4月29日追記:
ホームタウンの札幌と函館で桜が満開になりましたので、テンプレートを「桜モード」にいたしました。
------------------------------------------------------------------------------------------
やはり、何度でも言っておきたい事がある。
北海道新聞 2019年4月23日記事
「<JR「自立」への道筋 中長期計画を読む>1 新幹線 31年度500億円に」
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/299001?rct=n_jrhokkaido
JR北海道が9日に発表した中期経営計画と長期経営ビジョンには、12年後、
北海道新幹線の札幌延伸実質初年度となる2031年度に、連結純損益を黒字化して「自立経営」する姿が描かれた。
どのような手段で再生の道を歩もうとしているのか。
計画の詳しい内容を検証し、実現可能性を探る。
計画などによれば、2031年度の鉄道運輸収入は1160億円で、2018年度の6割増。
増収の大半を北海道新幹線が占める。
島田修社長は新計画発表時、新幹線の収入について
「(現在の年80億円弱から)500億円規模に増える見込み。2031年にどんと上がる」と力を込めた。
2016年3月に開業した北海道新幹線(新青森~新函館北斗)は、利用低迷で「年100億円規模の赤字」を生み続けている。
利用増に向け、今年3月のダイヤ改正で東京~新函館北斗間の所要時間を最大4分短縮し、
3往復で「4時間切り」を実現。
2020年度までにその本数を増やすほか、外国人観光客や修学旅行利用への営業強化も図る。
それでも今後は修繕費がかさみ、赤字幅はピークで年150億円に膨らむ見通し。
これを、札幌延伸時に一気に収支均衡まで改善させるという。
カギを握るのが新幹線の高速化。
現在の最高時速260キロを320キロに上げ、東京~札幌間を4時間半で結ぶことが前提とする。
最大の課題は、貨物列車との共用走行問題。
新幹線は青函トンネルなど82キロの区間で、貨物列車とのすれ違いを考慮し速度を140~160キロに制限されている。
解決策としては、貨物列車の減便や海上輸送への転換が浮上している。
ただ、これらの案は道内物流網全体への影響が大きく、協議は難航必至だ。
計画発表当日、JR貨物は
「当社の経営の根幹にも関わる。新幹線札幌延伸後も鉄道事業者として北海道経済を支える」
とのコメントを出して、けん制の構え。
関係者は「計画は、高速化しか立て直し策がないようで、視野が狭い感じ」と冷ややかだ。
JR北海道は国の仲介を期待するが、4月12日の衆院国土交通委員会では、
石井啓一国交相が「JR北海道が関係者との調整を精力的に行う必要がある」と答弁。
先行きは見通せない。
■維持困難路線 決着見えず
新幹線が2012年後の「増収の柱」なのに対し、
5年以内の決着を目指すのが「単独では維持困難」な10路線13区間の見直しだ。
廃線方針の日高線(鵡川~様似)など5区間はバス転換して、年20億円の赤字を解消。
鉄路維持方針の宗谷線(名寄~稚内)など8区間は、
年120億円の赤字のJR負担額を3分の1程度に抑える枠組み作りを目指す。
バス転換方針5区間のうち、地元合意ができていないのは日高線(鵡川~様似)、留萌線(深川~留萌全線)、
根室線(富良野~新得)の3区間。
長期経営ビジョンでは学校や病院の近くにバス停を設けたり、バス増便したりすることで
「鉄道よりも便利で効率的な交通体系」を実現するとした。
計画発表会見で「存続はあり得ないのか」と問われた小山俊幸副社長は協議の期限は設けないとしつつ、
「利用が極めて少ない線区。理解いただけるよう最大限努力したい」と述べ、
存続の考えはないことを改めて強調した。
日高線では沿線7町長が昨年(2018)11月、日高門別~様似間の廃線でいったん合意したものの、
その後に浦河町長が全線復旧を主張。
留萌線と根室線は、実質的な協議にも入れていない。
8区間については、JRは両計画とは別にJR独自の想定として、2021年度以降、国や道、沿線自治体から
年80億円の財政支援を求めることをにじませる内容の収支見通しを出した。
国は8区間の支援額について「地元自治体と同水準」としており、
単純計算では道と沿線自治体で年40億円の負担が必要になる。
JR北海道は2019、2020年度を「第1期」、2021~2023年度を「第2期」の集中改革期間と設定。
第1期には、沿線自治体とまとめた利用促進策「アクションプラン」を実施し、
各線区の営業赤字を2017年度と同水準に保つとともに、支援の枠組み作りを進めたい考え。
だが、財政難の道や自治体には、そのままの負担は難しい額で、議論の行方次第で存廃論が浮上する可能性もある。
存続に向けた方策を協議するため、道は4月19日、沿線自治体や識者を集めた検討会の初会合を開催。
赤字の圧縮や国の負担割合引き上げなどについて、年内に結論を出す方針。
4月23日には、鈴木直道氏が道知事に就任する。
夕張市長として石勝線夕張支線の廃線をJRに提案し、代替交通への支援を得た「攻めの廃線」を実現。
鈴木氏は、知事選後のインタビューで「必要な鉄路は残す。そのために必要な財源も国にしっかり求める」と答えた。
「必要な鉄路」とは果たしてどこを指すのか。新知事の考え次第でJR再生の行方は大きく動きそうだ。
<ことば>中期経営計画と長期経営ビジョン
国土交通省が昨年7月、2019、2020年度に計400億円台の財政支援実施を決めた際、
JR会社法に基づく監督命令で策定を求めていた。
中期経営計画は2019~2023年度、長期経営ビジョンは2019~2031年度が対象。
経費削減と増収に向けさまざまな策を講じ、
北海道新幹線札幌延伸の実質初年度である2031年度に、連結純損益を黒字化して国の支援に頼らない「自立経営」を達成するとした。
財政支援額は計画には盛り込まれていないが、JRは独自に公表した収支計画に基づき
2030年度まで年280億円の公的支援が必要と主張。
うち、存続を目指す単独維持困難路線8区間分は年80億円と推計される。
8区間への支援は、「自立経営」後も必要としている。
------------------------------------------------------------------------------
では、ここでまた持論を。
笑ってしまうほど「甘い!」
あまりにも整備新幹線に頼り切った「机上の空論」。
東京から離れるほど乗客は減る一方だったではないか。
札幌に4時間半で到達したらば、すべて赤字がチャラにできる、と思ってる。
「甘い!」
車内販売も「ビュッフェ」もない新幹線なんて、なんて無味乾燥な空間なのか。
車内販売のない新幹線だったら、サービスエリアで休憩を入れる高速バスのほうがよっぽど快適だ。
札幌から函館の観光も、「在来線乗り換え」という手間が発生するのは
旅慣れた若者やビジネスマンならともかく、ご年配・ましてや団体客には「苦労」となる。
それなら4時間かかっても、在来線特急「スーパー北斗」のほうが良い、という客が多いはずだ。
そして、「東京~札幌間」観光&ビジネス客を飛行機客から奪えるか否かは
旅行代理店&旅行サイトで「旅行/出張(新幹線&ホテル・旅館)パック」の商品で
いかにバラエティーを出せるか、にもかかっている。
今「新幹線&ホテル・パック」は東海道&山陽新幹線で「広島」までなら比較的豊かだが、
「九州方面」の新幹線パックはほとんどなく、「東北方面」「新潟・北陸方面」は2名以上でないとないに等しい。
だから、「東京~札幌間、新幹線&ホテルパック」(1名から)の商品を揃えられるか?
そこにかかっているだろう。
あとは、以前「北海道新聞社説」で鈴木知事登場の際に書いたブログを再度ご覧ください。
ホームタウンの札幌と函館で桜が満開になりましたので、テンプレートを「桜モード」にいたしました。
------------------------------------------------------------------------------------------
やはり、何度でも言っておきたい事がある。
北海道新聞 2019年4月23日記事
「<JR「自立」への道筋 中長期計画を読む>1 新幹線 31年度500億円に」
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/299001?rct=n_jrhokkaido
JR北海道が9日に発表した中期経営計画と長期経営ビジョンには、12年後、
北海道新幹線の札幌延伸実質初年度となる2031年度に、連結純損益を黒字化して「自立経営」する姿が描かれた。
どのような手段で再生の道を歩もうとしているのか。
計画の詳しい内容を検証し、実現可能性を探る。
計画などによれば、2031年度の鉄道運輸収入は1160億円で、2018年度の6割増。
増収の大半を北海道新幹線が占める。
島田修社長は新計画発表時、新幹線の収入について
「(現在の年80億円弱から)500億円規模に増える見込み。2031年にどんと上がる」と力を込めた。
2016年3月に開業した北海道新幹線(新青森~新函館北斗)は、利用低迷で「年100億円規模の赤字」を生み続けている。
利用増に向け、今年3月のダイヤ改正で東京~新函館北斗間の所要時間を最大4分短縮し、
3往復で「4時間切り」を実現。
2020年度までにその本数を増やすほか、外国人観光客や修学旅行利用への営業強化も図る。
それでも今後は修繕費がかさみ、赤字幅はピークで年150億円に膨らむ見通し。
これを、札幌延伸時に一気に収支均衡まで改善させるという。
カギを握るのが新幹線の高速化。
現在の最高時速260キロを320キロに上げ、東京~札幌間を4時間半で結ぶことが前提とする。
最大の課題は、貨物列車との共用走行問題。
新幹線は青函トンネルなど82キロの区間で、貨物列車とのすれ違いを考慮し速度を140~160キロに制限されている。
解決策としては、貨物列車の減便や海上輸送への転換が浮上している。
ただ、これらの案は道内物流網全体への影響が大きく、協議は難航必至だ。
計画発表当日、JR貨物は
「当社の経営の根幹にも関わる。新幹線札幌延伸後も鉄道事業者として北海道経済を支える」
とのコメントを出して、けん制の構え。
関係者は「計画は、高速化しか立て直し策がないようで、視野が狭い感じ」と冷ややかだ。
JR北海道は国の仲介を期待するが、4月12日の衆院国土交通委員会では、
石井啓一国交相が「JR北海道が関係者との調整を精力的に行う必要がある」と答弁。
先行きは見通せない。
■維持困難路線 決着見えず
新幹線が2012年後の「増収の柱」なのに対し、
5年以内の決着を目指すのが「単独では維持困難」な10路線13区間の見直しだ。
廃線方針の日高線(鵡川~様似)など5区間はバス転換して、年20億円の赤字を解消。
鉄路維持方針の宗谷線(名寄~稚内)など8区間は、
年120億円の赤字のJR負担額を3分の1程度に抑える枠組み作りを目指す。
バス転換方針5区間のうち、地元合意ができていないのは日高線(鵡川~様似)、留萌線(深川~留萌全線)、
根室線(富良野~新得)の3区間。
長期経営ビジョンでは学校や病院の近くにバス停を設けたり、バス増便したりすることで
「鉄道よりも便利で効率的な交通体系」を実現するとした。
計画発表会見で「存続はあり得ないのか」と問われた小山俊幸副社長は協議の期限は設けないとしつつ、
「利用が極めて少ない線区。理解いただけるよう最大限努力したい」と述べ、
存続の考えはないことを改めて強調した。
日高線では沿線7町長が昨年(2018)11月、日高門別~様似間の廃線でいったん合意したものの、
その後に浦河町長が全線復旧を主張。
留萌線と根室線は、実質的な協議にも入れていない。
8区間については、JRは両計画とは別にJR独自の想定として、2021年度以降、国や道、沿線自治体から
年80億円の財政支援を求めることをにじませる内容の収支見通しを出した。
国は8区間の支援額について「地元自治体と同水準」としており、
単純計算では道と沿線自治体で年40億円の負担が必要になる。
JR北海道は2019、2020年度を「第1期」、2021~2023年度を「第2期」の集中改革期間と設定。
第1期には、沿線自治体とまとめた利用促進策「アクションプラン」を実施し、
各線区の営業赤字を2017年度と同水準に保つとともに、支援の枠組み作りを進めたい考え。
だが、財政難の道や自治体には、そのままの負担は難しい額で、議論の行方次第で存廃論が浮上する可能性もある。
存続に向けた方策を協議するため、道は4月19日、沿線自治体や識者を集めた検討会の初会合を開催。
赤字の圧縮や国の負担割合引き上げなどについて、年内に結論を出す方針。
4月23日には、鈴木直道氏が道知事に就任する。
夕張市長として石勝線夕張支線の廃線をJRに提案し、代替交通への支援を得た「攻めの廃線」を実現。
鈴木氏は、知事選後のインタビューで「必要な鉄路は残す。そのために必要な財源も国にしっかり求める」と答えた。
「必要な鉄路」とは果たしてどこを指すのか。新知事の考え次第でJR再生の行方は大きく動きそうだ。
<ことば>中期経営計画と長期経営ビジョン
国土交通省が昨年7月、2019、2020年度に計400億円台の財政支援実施を決めた際、
JR会社法に基づく監督命令で策定を求めていた。
中期経営計画は2019~2023年度、長期経営ビジョンは2019~2031年度が対象。
経費削減と増収に向けさまざまな策を講じ、
北海道新幹線札幌延伸の実質初年度である2031年度に、連結純損益を黒字化して国の支援に頼らない「自立経営」を達成するとした。
財政支援額は計画には盛り込まれていないが、JRは独自に公表した収支計画に基づき
2030年度まで年280億円の公的支援が必要と主張。
うち、存続を目指す単独維持困難路線8区間分は年80億円と推計される。
8区間への支援は、「自立経営」後も必要としている。
------------------------------------------------------------------------------
では、ここでまた持論を。
笑ってしまうほど「甘い!」
あまりにも整備新幹線に頼り切った「机上の空論」。
東京から離れるほど乗客は減る一方だったではないか。
札幌に4時間半で到達したらば、すべて赤字がチャラにできる、と思ってる。
「甘い!」
車内販売も「ビュッフェ」もない新幹線なんて、なんて無味乾燥な空間なのか。
車内販売のない新幹線だったら、サービスエリアで休憩を入れる高速バスのほうがよっぽど快適だ。
札幌から函館の観光も、「在来線乗り換え」という手間が発生するのは
旅慣れた若者やビジネスマンならともかく、ご年配・ましてや団体客には「苦労」となる。
それなら4時間かかっても、在来線特急「スーパー北斗」のほうが良い、という客が多いはずだ。
そして、「東京~札幌間」観光&ビジネス客を飛行機客から奪えるか否かは
旅行代理店&旅行サイトで「旅行/出張(新幹線&ホテル・旅館)パック」の商品で
いかにバラエティーを出せるか、にもかかっている。
今「新幹線&ホテル・パック」は東海道&山陽新幹線で「広島」までなら比較的豊かだが、
「九州方面」の新幹線パックはほとんどなく、「東北方面」「新潟・北陸方面」は2名以上でないとないに等しい。
だから、「東京~札幌間、新幹線&ホテルパック」(1名から)の商品を揃えられるか?
そこにかかっているだろう。
あとは、以前「北海道新聞社説」で鈴木知事登場の際に書いたブログを再度ご覧ください。