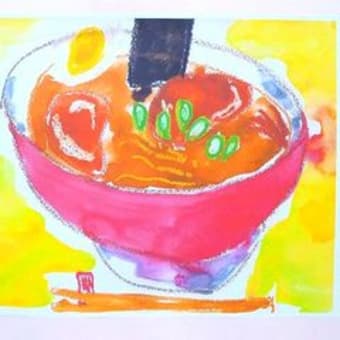「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
昨日のケース会議でのことです。ある一人の生徒さんについて、「ブロックを把握する割合が増えた」という報告がありました。
小さなブロックを掴むことなんて「誰でも出来ること」、と思われるかもしれません。しかし、ハンディをもつ生徒さんにとって、それは何年か越しでの成果なのです。提示された課題に注目し、何をすれば良いのか感じ取り、理解し、気持ちを動かし、それに従って手を動かし、指を動かし、そして掴む。神経が指先にまで及んではじめて可能となる行為です。体を支えながらの、全身集中の行為です。
ですから、いつも出来るとは限りません。まだ、出来る「割合が増えた」という段階なのです。何回か前までは、「偶然かな?」と思われるくらいの確実性のない行為だったそうです。でも今では、「意図して掴んでいる!」と確信できます、とのことでした。
「出来る」「出来ない」のイチゼロの尺度では、計ることの出来ないものがあります。特殊教育では、ゼロからイチの間の成果を見ていきます。それが、成果の「割合」です。とても小さな変化なのですが、とても大きな成果なのです。先の例でも、「指先にまで神経が及んだ!」ということは画期的なことです。そこからいろいろな可能性が広がってきますし、他の把握行動にはどんなものがあるかと、日常生活を見直す必要も出てきます。課題がどんどん出てきて、気持ちが高まります。
小さな変化を見つけられる目、というものに私達は誇りを持ちます。その目があってはじめて、講師は生徒さんを心からほめながら、また自らも手応えを感じながら、喜びをもって指導に当たれます。
イチゼロの尺度では、「今日も出来ませんでした」、「まだダメです」、となって、喜びも希望もなくなってしまいます。「数の理解、まだ不完全です」、「ひらがなの読み、完璧ではありません」ではなく、どこまで出来ているのか、ということの正確な把握が学習を次に進める力となります。
行きつ戻りつしながらも、小さな変化に大きな成果を認め、親御さんとも共に喜びながらの日々です。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp