 「伊能忠敬の足跡」アマゾン電子書籍紹介。角川・BOOK★WALKER
「伊能忠敬の足跡」アマゾン電子書籍紹介。角川・BOOK★WALKER
伊能忠敬(1745年~1818年)江戸後期の測量家。洋学の科学的な理論に基ずき沿岸の実地測量から精密な日本地図「大日本沿岸輿地全図」伊能図、を作成した。上総国山辺郡小関家に出生。幼名を三治郎と称した。母の亡き後、婿養子の父の実家であった武佐郡小堤村の神保家に移り、その後1762年(法暦12)18才の時、下総国佐原村の豪家であった伊能三郎衛門家に入り婿し忠敬と名乗る。そこでは酒造や地主経営のほか、米穀・薪の取引、店貸、金融、運送業などの諸営業を展開して家産を拡大した。また村役人として天明の飢饉状況の中で、貧民の救済活動を行ったり、利根川の洪水対策に尽力を尽くした。その功績をたたえられ領主旗本から名字帯刀を許され、三人扶持を給せられて士分格となった。1794年(寛政6)家督を譲り、通称を勘解由と改めた。翌年江戸深川黒江町に居を移し、幕府天文方の高橋至時に師事し、自宅に施設を整えて天体観測を継続した。そして1800年幕府の命を受けて蝦夷地の測量に入り、以後17年間10次にわたり日本国中の沿岸を実施測量をした。その測量の距離は4万キロ以上に及び、3種の方位盤によって約6万回の方位が行われた。「伊能図」の精密さは、庶地点で天体観測による緯度測定のほかに、精巧な器具を作成し、在来の測地技術をもって驚異的な頻度で実測したことによってもたらされた。この測量の様子は伊能図とともに幕府に献上された。
最新の画像[もっと見る]
-
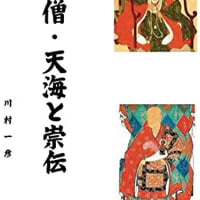 「政僧・天海と崇伝」オンデマンド・アマゾン。@880円
3年前
「政僧・天海と崇伝」オンデマンド・アマゾン。@880円
3年前
-
 歴史の回想「古事記が紡ぐ一ノ宮の神々」オンデマンド・アマゾン。@1320円203ページ
3年前
歴史の回想「古事記が紡ぐ一ノ宮の神々」オンデマンド・アマゾン。@1320円203ページ
3年前
-
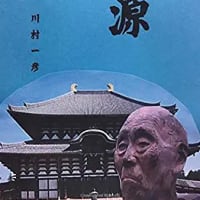 歴史の回想・「重源」オンデマンド・アマゾン。@1100円124ページ
3年前
歴史の回想・「重源」オンデマンド・アマゾン。@1100円124ページ
3年前
-
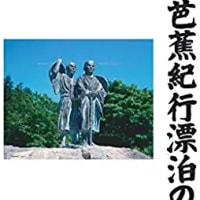 「芭蕉紀行漂泊の憧憬」オンデマンド・アマゾン。@1540円
3年前
「芭蕉紀行漂泊の憧憬」オンデマンド・アマゾン。@1540円
3年前
-
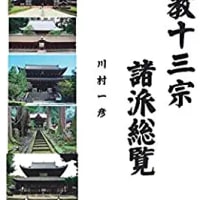 「日本仏教十三宗・諸派総覧」オンデマンド・アマゾン。@1540円
3年前
「日本仏教十三宗・諸派総覧」オンデマンド・アマゾン。@1540円
3年前
-
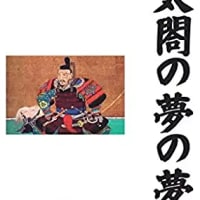 「太閤の夢の夢」オンデマンド・アマゾン。@1760円302ページ
3年前
「太閤の夢の夢」オンデマンド・アマゾン。@1760円302ページ
3年前
-
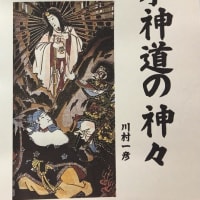 歴史の回想「日本神道の神々」アマゾン・オンデマンド@1210円
3年前
歴史の回想「日本神道の神々」アマゾン・オンデマンド@1210円
3年前
-
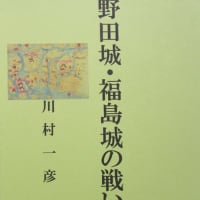 歴史の回想「野田城・福島城の戦い」アマゾン電子書籍紹介・角川・グーグル・楽天ブックス。
4年前
歴史の回想「野田城・福島城の戦い」アマゾン電子書籍紹介・角川・グーグル・楽天ブックス。
4年前
-
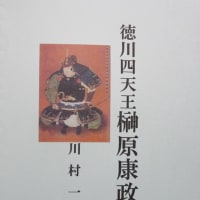 歴史の回想「徳川四天王・榊原康政」電子書籍紹介・アマゾン・グーグル・角川・楽天ブックス。
4年前
歴史の回想「徳川四天王・榊原康政」電子書籍紹介・アマゾン・グーグル・角川・楽天ブックス。
4年前
-
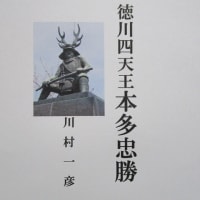 歴史の回想「徳川四天王・本多忠勝」電子書籍紹介」・アマゾン・グーグル・楽天ブックス。
4年前
歴史の回想「徳川四天王・本多忠勝」電子書籍紹介」・アマゾン・グーグル・楽天ブックス。
4年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます