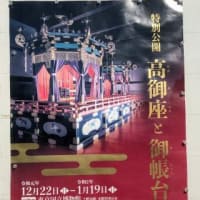大人の社会科見学第一弾の勝鬨橋橋脚内見学ツアー。
ようやくまとまったので、POSTします。
都営大江戸線勝どき駅から徒歩で向かうと、
普段見ているアングルとは、反対のアングルで見えてきます。

そしてこちらは、その場所からの勝鬨橋。

勝鬨橋を渡って行くと、途中、使われていない信号機が。

橋の上下をしていた頃の歩行者用信号機の様です。
橋を渡りきってた橋の袂にあるちらは、
今回のツアーのベースとなるかちどき 橋の資料館です。

この資料館は、勝鬨橋を稼働するために使用していた
変電所だそうです。
受付を済ませて橋の資料館に入ります。
こちらは、資料館1Fにある直流発電機。二基ありました。

後で聞いたんですが、交流で受電した後、
この直流発電機で直流にすると言う変電をして、
直流電力で橋のモーターを動かしていたそうです。
資料館2Fにあるのは、配電盤がありました。
こちらは高圧配電盤。

そしてこちらが、低圧配電盤です。

ちなみに、高圧配電盤の裏側は、こうなっています。

垂直に見える銅色のものは、電線(と言うのか)です。
剥き出しなので、稼働したら結構危険ですね。
今は、物置として使われていました。
ツアーは、まず運転室を見ることから始まります。

写真は運転盤で、様々な計器とボタン類が沢山ありました。
写真左上に写っているのは、説明してくれる係りの人。
ツアーは、1回5名程度で行われるんですが、
私が参加した回の参加者は、私を含めて3人。
対して、係りの人は4人居たので、贅沢なツアーになりました。
いよいよ、橋脚内へ。
係りの人を見ると青色の安全帯をしているのが判るでしょうか?
これと同じものをツアー参加者も付けて、
ほぼ垂直のラッタルを伝って降りていきます。
降りた橋脚の底には、こんなに広い空間が。
橋は、この写真のような感じで跳ね上がるわけですが、

容易に桁を跳ね上げるために、桁の端についている錘が付いています。
これは、その桁の橋に付いている錘のための空間です。

で、その桁(約950t)と錘(約1050t)をさせているのが、
トラニオン軸と言う、この軸。

今なら、ベアリングなどを使ってスムーズに動く様に
するんでしょうが、この軸にはベアリングは使われておらず、
グリースで摩擦を減らしていたそうです。
そしてこれが、橋桁を動かす機器類。

多分、モーターです。
125馬力のモーターが、左右に一つずつありました。
これは、一番手前が開度検出器、
真ん中のホイール状の物が多分ブレーキ、
一番奥にモーターらしき物が見えます。

これで、あとは上に戻って、小一時間の橋脚内見学ツアーは終了。
普段見れないところが見れたので、非常に面白かったです。
オマケ。
橋の資料館にある、勝鬨橋のジオラマです。
かちどき 橋の資料館 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kachidoki/