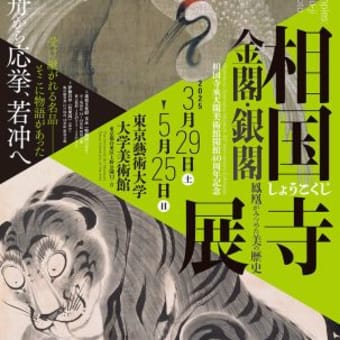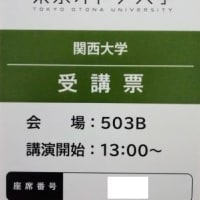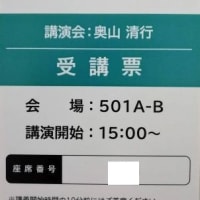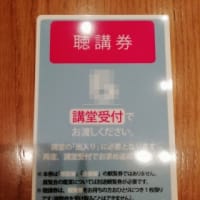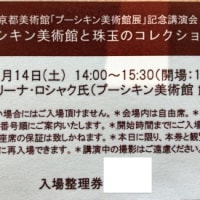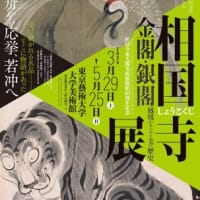上野の東京都美術館で行われる
ブリューゲル展講演会に行って来ました。
今日の講演テーマは
「ブリューゲル一族と16、17世紀フランドルの絵画制作」
と言う事で、
講師は東京都美術館学芸員の髙城靖之さん。
東京都美術館の特別展の場合、記念講演会は、
3~4回くらいある様な気がしますが、
このブリューゲル展の場合は、今回が2回目で、
且つ、最終回。
ブリューゲルの研究者って、少ないんですかね?
ブリューゲル自体は、一族で150年ほどの長きにわたって
絵画を描き続け、フランドルの絵画界に影響を与え続けた
一族なんですけどね:-p
今回の講演の要旨は以下の感じです。
- ピーテル・ブリューゲル一世。《バベルの塔》や《農民の婚宴》などが有名。
- ピーテル一世の子供、孫、ひ孫の世代まで画家として活躍している
- ブリューゲル一族は15人から20人くらい画家を輩出している
- 今回の展覧会は、殆どが個人蔵なので、「また見てみたい」と思っても、次の機会はなかなか無いかも
- ピーテル一世。
- ブリューゲル一族は主にネーデルラントで活躍した。
- フランドルと言う言い方をすることもある。フランドルは、ネーデルラントの経済の中心地であったので、ネーデルラントを指してフランドルと言うこともある。また、南ネーデルラントをフランドルと言う事もある。
- ピーテル一世の活躍した16世紀は、宗教画が中心の時代で、イタリアで絵画を学んだ時代
- 《サクランボの生母》。失われたレオナルドの作品であるが、多くの画家が“コピー”しているので、後の世代に知られている。
- この時代のネーデルラントの有力な画家に、ピーテル・クック・ファン・アールストが居る。彼は、ピーテル一世の前の有力なネーデルラントの画家であり、《三連祭壇画》で著名。ピーテル一世は、彼に弟子入りした。
- ピーテル一世は、ピーテル・クック・ファン・アールストに弟子入りしたが、師匠の影響を殆ど受けていらず、むしろヒエロニムス・ボスの影響を受けている。
- (ボスは、まか不思議な怪物のいる地獄を描いているが)地獄を描くのは、ボスが始めたわけではなく、この時代のネーデルラントに根付いていたものだった
- ネーデルラントの人々が絵画を学んだイタリアでは悪魔は人の姿で描かれるが、ネーデルラントの方では、悪魔はバケモノの姿で描かれている。
- ピーテル一世もその伝統を受け継いで(地獄絵を描いて)いる
- ピーテル一世は(この時代のスタンダードだった)宗教画だけに興味を持ったわけではなく、自然にも関心を持ち風景画も描いた
- ピーテル一世の長男ピーテル二世が父の農民の世界への興味を受け継いだ。次男のヤンは父ピーテル一世の自然への興味を受け継いだ
- ピーテル二世の《鳥罠》の主題は、ピーテル二世が初めて描いたわけでは無い。これは、ピーテル一世の《鳥罠のある冬風景》のコピー作品である。当時は、コピー画を描くのはネガティブな時代ではなかった。いろんな画家が描いていた
- ピーテル二世はピーテル一世のコピー画をたくさん描いている。
- ピーテル二世の《七つの慈悲の行い》もピーテル一世の版画《慈悲》の翻案。
- ピーテル二世の《野外での婚礼の踊り》もピーテル一世の版画を下にしている(左右反転)と見られている。
- ピーテル二世はピーテル一世の下絵を下にコピー画を描いている
- 16世紀後半から17世紀にかけては、非常に市民層が裕福になっていて、絵画の購買層として台頭したので、コピー画の市場があったと見られている。当時のネーデルラントで持ち家を持っていた市民は平均して25枚くらい絵画を持っていたとみられている。貴族層が持っていた絵画の人気があり、そのコピー画は(当然)人気があった。ピーテル一世の絵画はハプスブルク家が多数所有していたので、そのコピーは市民層に人気があった
- ピーテル一世の次男ヤン一世は、父の自然への興味を受け継いだ。
- 《田舎道をいく馬車と旅人》は、ハガキ2枚程度の大きさ(小ささ)の中に雄大な風景を描いているのが注目ポイント。普通、この様な作品を描く場合には、もっと大きくなるが、ヤン一世は、この小さい絵画の中にも細かい部分をキチンと書き込んでいて、拡大してもちゃんと見ることが出来る。これは、ヤン一世の技術が優れた事も示している。
- 《水浴をする人たちがいる川の風景》は、ピーテル二世の《鳥罠》と構図が一致していて、《鳥罠》の違う季節を描いていると考えることができる。
- また、《スケートをする人がいる冬の川の風景》と言う素描は、《鳥罠》と一緒である。
- 《机上の花瓶に入ったチューリップと薔薇》。ピーテル一世は花は描かなかったので、これは、ヤン一世が切り開いた分野。当時チューリップはネーデルラントに入ってきたばかりで、非常に貴重なものだった。絵の中に描かれている筋が入ったチューリップは育成が難しく中々無くて高価だった。筋が入ったものは、実はウイルス性の病気であり、(当然に)育成が難しかった。
- 花の絵は貴族や聖職者に喜ばれる。兄のピーテル二世は一般市民相手で貧乏だったが、ヤン一世は貴族や聖職者をパトロンに持つことが出来て裕福だった
- ヤン一世の子供がヤン二世。
- 《嗅覚の寓意》《聴覚の寓意》と言う二つの絵画
- 《嗅覚の寓意》の方は、女性が嗅覚を擬人化している他、鼻のいい犬、麝香猫、香水が描かれている。
- 《聴覚の寓意》でも、やはり女性が聴覚を擬人化して表し、耳が良い鹿、鳥や楽器が描かれている
- 実はこれらの寓意画は、父ヤン一世がルーベンスと描いた作品の翻案
- ヤン二世の《聖ウベルトゥスの幻視》も同様に、ヤン一世とルーベンスが描いた作品の翻案である
- ヤン一世の《市場から帰路につく農民たち》を、ブリューゲル一族では無いヨセフ・ファン・ブレダールが《市場に赴く農民のいる風景》として翻案したように、“ブリューゲル風の作品”は非常に人気があった
- 複数の画家が分担して作品を仕上げるのが共作であるが、17世紀のフランドルでは一般的に行われていた。主役となる人物を描く画家と、その周囲を描く画家がいるのが一般的手法
- ブリューゲル一族のヤン・ファン・ケッセル1世の《花輪の枠》なども、同様の手法で描かれている
- 当時、ネーデルラントでは絵画の需要が無尽蔵にあった。故に、共作と言う事が行われたが、これは、それぞれの得意分野を活かして効率的な絵画制作を追求した(合理的な)考え方
- ヤン二世も父ヤン一世と同様に花の絵を描いた。
- 彼は、父から絵を学び、年の離れた弟たちに絵を教えており、旧世代と新世代をつないでいる
- ヤン二世の長男は、ヤン・ピーテル・ブリューゲルであるが、ここで、“ヤン”と“ピーテル”が一緒に出てきてしまった(笑)
- ヤン二世の次男が、アブラハム
- アブラハムは、他のブリューゲル一族の画家とはちょっと違うところがある。(他のブリューゲル一族はイタリアに勉強に行っても戻ってきたが)アブラハムは、イタリアに行って、そのまま戻ってこなかった
- 《果物と東洋風の鳥》と言うアブラハムの作品。果物をそのまま下に置いたりしているが、これは当時のイタリアの静物画のスタイルだった。
- アブラハムは当時のイタリアのスタイルを取り入れながら、ブリューゲル一族のスタイルも融合させた作品を描いていた
- アブラハムは、ブリューゲル一族の最後の大物。以降の子孫は画家になったと言う記録はあるが、作品は残っていない
- ヤン・ファン・ケッセル一世も、“ブリューゲル”と言う文字は入っていないが、実はブリューゲル一族。
- ヤン・ファン・ケッセル一世は、《蝶、カブトムシ、コウモリの習作》を大理石に描いている
- 絵画が描かれたものは、カンヴァスがいまは良く知られているが、他にも多数ある。
- カンヴァスの前は木の板に描くのが一般的。
- ネーデルラントはオークが多い。オークは生育はポプラよりも遅いが、固く、虫にも食われにくく、湾曲しにくい。
- カンヴァス。イタリアでは15世紀後半から使用。軽く持ち運びに便利で安価。湿度変化によって麻布が伸縮。キチンと処理をしないと、絵の具の剥落、麻布の劣化を招く
- 銅板に描かれた絵画もある。16世紀末から17世紀にフランドルで普及。
- 背景としては、銅の圧延技術の向上がある。また、銅版画が普及してフランドルでは銅に馴染みがあった。銅は薄く携帯しやすく耐久性も高い。また、環境変化の影響も受けない。油絵を描く前に、カンヴァスに下塗りを施すが、下塗りと銅の色が同じだったので下地処理の簡略化が可能だと言うメリットもあった。フランドルでは画商が数多くおり、ヨーロッパ内の他、新大陸のアメリカにも絵画が販売されていたが、軽さ、薄さ、耐久性から輸送や輸出に適していた。
- 石。イタリアのセバスティアーノ・デル・ビオンボがスレート板に描いたものが知られている
- イタリアでは、戦乱などで絵画作品が失われることが多かったが、石の堅牢さと不変性は、火や虫食いで作品が失われることを防いだ。
- ヤン・ファン・ケッセル一世はなぜ大理石に絵を描いたのかは良く分からないが、大理石のマーブル模様を意識的に利用して虫の羽根の透明性を上手く描けるだろうと考えていたと考えることができる。
すべてをメモる事は出来ませんでしたが、まぁ、こんな感じ?
講演のストーリーも理解しやすく、非常に勉強になりました。