原発なくそうの思いで集まっている茨木市民有志グループです。
ニュース、お知らせ、お願い、短いコメントは
ブログ「なくそう原発茨木」をご覧ください。


阿武山原子炉設置反対茨木市民運動 原子炉と住民の意思と科学者
神山治夫2011・12・28
① 福島原発事故を受けて、各地原発の定期点検後の再稼働が地元住民、自治体の合意が得られず、出来ない状況が起こっている。 2011年12月26日現在で稼働中の原発は全国54基中、関西電力高浜原発3号機など6基のみとなった(毎日新聞12月26日付)。 高浜3号機も2月には定期点検入りとなり、九州電力に続いて関西電力も全て停止することとなる。
② 住民合意がなければ、原発の設置はおろか、再稼働も不可能である。 原子炉の設置、運転と住民合意との関係で最初の本格的な矛盾、対立となったのが1957年8月に起こった阿武山関西研究用原子炉の設置に反対する茨木市市民運動であった。
③ 当時の状況を概括すると、1953年12月8日、国連総会においてアイゼンハワー米大統領が「原子力平和利用Atoms for Peace」の演説を行った。 1955年11月1日、東京で始まった「原子力平和利用博覧会」はその後広島を含む7都市で行われた。 「最初に放射能雨の洗礼を浴びせ、次は原子力平和利用を装った外国の営利主義からの抜け目のない攻勢である」(毎日新聞)との一部の警告もあったが、広島での博覧会においてみられたように、原爆は絶対悪だが、平和利用は絶対善、人類のホープ、明るい未来を約束するものというキャンペーンが一世を風靡する状態となった。 「輝かしい原子力時代を迎えることは明らか」と述べた渡辺広島市長や長田新氏、一時的には森滝市郎氏などの反核運動家、あるいは平和主義者であり民主的学者と目された末川博立命館大学総長なども相次いで原子力平和利用を称賛した。 原子力平和利用の在り方に批判的とされた専門学者もその例外ではなかった。(「原発とヒロシマ」田中利幸2011年岩波)
茨木市民運動の勝利に大きく貢献した原子物理学者立教大学教授武谷三男氏すら当運動に招かれて吹田市で開催された市民公聴会の発言冒頭で「原子力というのは人類の将来のホープであるということは、これは明らかなことであります。」と述べている。(「原子炉安全神話」を拒否した茨木市民・科学者のたたかいの記録・1957年発行冊子の復刻版p16)
④ 1954年3月の国会で突然2億3500万円の原子力開発予算が修正提案で提案され採択された。 この予算をめぐって財界、一部大学の工学部などが積極的にのりだした。 一気に日本への原子炉導入に向けての取り組みが各界あげて一斉に加速された。 その先端となったのが関西への研究用原子炉の設置であった。
⑤ しかし、その各界あげての原子力平和利用推進の大きな流れの前に大きく立ちはだかったのが、茨木市民による原子炉設置反対住民運動であった。 茨木市民の反対はきわめてprimitiveな「水道源をおびやかし、生活と故郷をおびやかす原子炉を身近に置くことは許さない」というものであった。 この運動は、要求はきわめてprimitiveな原初的なものであったが、戦後民主主義の一つの大きな到達点であった地方自治のありようをフルに生かした運動が展開された。 組織された「茨木市阿武山原子炉設置反対期成同盟」の委員長には田村英茨木市市長が就任し、茨木市議会対策会議が委員を出し、その下に各町内会、その他商工団体、農協、婦人団体、青年団体、医師会、歯科医師会、文化団体などを網羅した運動となった。 市民の生命と暮らしを守るという戦後民主主義の下で課せられた地方自治体の責務、役割、可能性を見事に発揮したとも云える。
最初に立ちあがった茨木市旧安威村の住民決起大会で、旧村長抱義一氏は「設置するならどこか遠い所へ持っていってもらいたい」と述べ、高島好隆市議は「本当の安全度は疑問である。自分たちの生まれ育った土地を護るためあくまで反対する」と述べている。(「京阪新聞」昭和32年8月25日付)
田村英茨木市長は声明のなかで反対理由についての第一に「茨木市住民の大部分は安威川の水により生活している」ことを指摘し、「安威川は茨木市の生活資源であると言っても過言でない。阿武山の水は大部分安威川に流れ込んでいる。阿武山の水のいかんはただちに安威川の水質に重大な影響を及ぼすのである。」ことを述べて反対理由にあげている。(「阿武山原子炉設置反対理由」田村英)
⑥ 原子炉設置を推進しょうとする側の関係学者もこの住民のprimitiveな不安・要求を無視して進むことはできなかった。 そこで住民説得のために持ちだされた論理が「原爆と違って平和利用の原子炉は絶対安全なものである」というものであった(1957年8月27日高槻市主催原子炉問題聴聞会)。 それは、今、痛切に反省されなければならない現在に続く「安全神話」の始まりであった。
⑦ 「茨木市民は原爆と原子炉の違いもわからない無知から反対している」とのキャンペーンに抗して、茨木市民は市議会代表、婦人団体代表を派遣し、自ら専門科学者に接触し、坂田昌一氏、武谷三男氏など当時の原子物理学の重鎮たちに訴えて、科学者たちの関心を引き起こした。 専門科学者は「原子炉は絶対安全なもの」という誤った論理をさすがに看過することはできなかった。 学者社会の中のいろいろな立場上の困難さをのりこえて、武谷三男氏、服部学氏は、直接現場に入り、住民の中に入って自らの見解を述べ、「原子炉は本質的に危険なものである」と明言した(1957年9月10日茨木市反対期成同盟主催聴聞会)。 茨木市民の危惧、要求が理にかなったものであると支持した。 また、全国25大学の140名に及ぶ専門学者が連名で阿武山原子炉設置計画の白紙撤回を求める要望書を組織し提出した(1957年10月付関西研究用原子炉設置準備委員会委員各位宛「関西原子炉設置に関する要望書」)。
武谷三男氏は後日著書の中で「あれがまだできてない公害反対運動のトップなんだ。茨木の関西原子炉反対運動ね。あれが最初でしょうね。日本の。あのとき、でも茨木の人たちはよく勉強していましたよ。非常によく勉強していましたね」(武谷三男『現代技術の構造』技術と人間、1981・p273)、「ほんとに市をあげての反対運動をやった。この経験が、今日ほとんど忘れられているように思うんですね。その設置に反対して、かなり熱心で、しかもりっぱな闘争をやって、それは成功したんですね」(同前・p157)と述べている。(引用・「初期原子力政策と戦後の地方自治-相克の発生 : 関西研究用原子炉交野案設置反対運動を事例に」樫本喜一・人間社会学研究集録. 2006, 2, p.81-110)
1957年12月20日、京都大学自治会代表者会議は声明を発表し、その中で「地元民の反対運動が研究者に大きな影響を与え、良心的な研究者の反省を呼びおこし、それが組織に迄高められたことは高く評価すべきことであり、・・・」と総括している。(「声明―関西研究用原子炉に対する我々の態度―」京都大学自治会代表者会議・1957年12月20日)
⑧ 茨木市民は科学者の支持・協力を得て行く中でその原初的な主張を通しながら、基本的な主張を明確にして行った。 その第一は「原子炉は本質的に危険なものである」という主張であった。 この主張に確信を与えたのは、推進側学者と武谷三男氏との間でかわされた吹田市での公開討論であった。 推進側学者の論点はことごとく武谷三男氏によって論破された(1957年9月11日吹田市並びに吹田市議会主催「関西研究用原子炉設置についての公聴会議事録」・日本共産党茨木市委員会発行冊子「阿武山原子炉設置反対運動の勝利のために」所載速記録)。 茨木市阿武山原子炉設置反対期成同盟は「原子炉は本質的に危険なものである」という大見出しを掲げた「情報2号」を全市民に配布し(1957年12月5日付)、公開討論の速記録(抄)を伝えた。 武谷三男氏は公開討論の中で次のように述べている。 「今後もし動力炉が入って来て、そうしてこれが日本の重要なエネルギー源になるほど大きくなって来たならば、それがもし乱暴に扱われたときの被害、安全々々と言いながら乱暴に扱われたときの被害は恐るべきものに達するだろうと私は今から心配しております。」(前掲速記録1957年発行冊子の復刻版「原子炉安全神話を拒否した茨木市民・科学者のたたかいの記録」p26) これが茨木市民と良心的科学者とが共有した心配であった。 残念ながら福島でその心配は現実のものとなった。
⑨ また、茨木市民の主張のもう一つの大きな特徴となったのが「宇治川・大阪なら危険だが、安威川・茨木ならまあいいか」という論理は絶対受け入れられないという事であった。 原子炉設置計画は当初、京都府宇治市に置かれる計画であった。 しかし、大阪府知事、大阪市長、大阪財界、大阪大学などが大阪市民の水源地がおびやかされるとして同案に反対し阿武山案となったいきさつがあった。 阿武山案になった途端に大阪府知事、大阪市長、大阪財界、大阪大学が積極的誘致を表明するようになった。 大都市を守るため、大都市の発展のためには小都市、あるいは過疎地は犠牲にしてもよいという考え方がまかり通っていた。 そういう論理が茨木市民の怒りに火をつけた。 しかし、その論理は結局、その後も原発設置にはつきまとい、東京・首都圏なら危険だが福島ならまあいいかの論理となり、大阪・京阪神なら危険だが福井若狭ならまあいいかとなってまかり通っている。 その論理は政府の「原子炉立地審査指針」という准法制化にさえされている。 福島の事故によって、その論理の非人間性が明らかとなり怒りとなっている。
高槻・茨木・吹田など旧三島郡の住民は大阪市を守るために淀川右岸の護岸は左岸よりも弱くされているとの噂は子供のころからよく聞かされていた。
⑩ 茨木市民の運動は、その端緒となったprimitiveな原初的な、かつ人間の基本権にかかわる主張の故に、政治家も学者も無視し得ないものであり、それが科学者の学問的良心をよびさまさせる方向で展開され、かつ、戦後民主主義の到達点の一つであった地方自治の原則を生かした運動形態を取ったが故に、計画撤回をかちとる成果となった。 これはその後も今も重要な課題となっている地元住民の納得と合意抜きには原発の建設は認められないという原則の初例となった。
1958年5月14・15日開催された日本学術会議原子力問題委員会において茨木市議会を代表して陳述した高島好隆議員は、「私どもは ・・・ 日本ビール(後のサッポロビール)の工場誘致に成功し、愛知トマトの工場を始め名古屋製糖の協同乳業、日世コーンのアイスクリーム工場 ・・・ などの食品工場が既に操業している現状であります」と述べ、地域の産業発展計画に対する悪影響を指摘して反対理由にあげている。(「高島代表の陳述内容」1958年5月 日・報告ビラ) これはその後原発が建設された過疎地域自治体が地域経済が破壊され、原発マネーに頼らざるを得ない状況が作り出される中で地域住民の不安や反対をおしのけて建設を容認していったこととあわせて重い検討課題となって来ている。 茨城県東海村村長村上達也氏は「原発に依存して地域社会を作るのは限界で、そこから脱したまちづくりを考えるべきではないか。」と述べている。(毎日新聞2011年10月8日付)
この市民運動はわずか一年半ほどの運動であったが、その間に原子力平和利用に関する様々な問題点が提起された。 しかし、推進する側には教訓としてなんら汲み取られる事なく、安全神話はますます拡大され、住民の理解と納得を得る努力が金銭による懐柔に流され、大都市の発展のために犠牲を地方にかぶせる手法がまかり通って来た。 その行き着く先が福島の重大事故であった。 この危険性は今も続いている。
⑪ 茨木市民が切り開いた住民の合意なしに原子炉は設置させないという先例は、その後全国17カ所にわたって原発が設置されるという事で崩されて行った。 「この経験が、今日ほとんど忘れられているように思うんですね。」という前掲武谷三男氏の発言(1981年)、嘆きとなっているが、同時に25カ所にわたって住民の反対運動によって原発の建設が白紙撤回され、あるいは実施させていないことにも注目しなければならない。 そしてそれが今福島の事故を受けて関係自治体を中心とした再稼働を許さない大きなたたかいとなっている。
原発建設を食い止めている地区。 新潟県巻町・石川県珠洲市・福井県小浜市・福井県川西町三里浜・京都府久美浜町・京都府舞鶴市・京都府宮津市・兵庫県御津町・兵庫県香住町・三重県紀勢町南島町芦浜・三重県紀伊長島町城の浜・三重県海山町大白浜・三重県熊野市井内浦・和歌山県日置川町・和歌山県日高町・和歌山県古座町・岡山県日生町鹿久居町・山口県豊北町・山口県萩市・徳島県海南町・徳島県阿南市・愛媛県津島町・高知県窪川町・高知県佐賀町・宮崎県串間市(しんぶん赤旗2011年8月3日付「志位和夫講演」より)。
今、福島の大きな過酷な経験を得て、原発が果たして人間にとってのホープであるのか、地球環境をも破壊しつくす悪魔の凶器であるのか問いなおされている。 しかし、原発を推進して来た関係財界、政治家、学者たちは相変わらずなお、その経験を率直に学ぼうとせず、福島事故の原因もあきらかになっていないまま、原発再稼働を進め、事もあろうに国外への輸出すら推進して憚らない。 こういう状況の中で、あらためて阿武山原子炉設置反対茨木市民運動の記録を再発掘し、茨木市民はもとよりひろく日本の原発に関心をもつ住民に知らせて行き、運動の経験を思い起こし、現在に生かすことは、今日的な意義があるだろう。










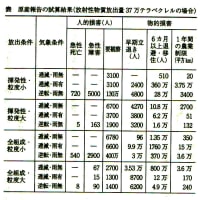

実に重大なことダ!
おとなにとっては頭をかかえるほど難しいテーマでも、小学生の子供に聞けば実に簡単に正解が出ることって、結構たくさんあるんですよ。
「原発はいいものか、悪いものか?」って、子供に聞けば、一発で答えが返ってくるでしょう。「悪い」と。「いやだ」と。
子供に正解を教わったほうがいい、筆頭クラスの問題かもしれませんね、「原発」ってのは。
アメリカインデアンの言葉にこういうのがあるそうです。「この土地は未来の子供たちから借りたものだ。だから、そのまま未来の子供たちに返さなければならない」と。
※「インデアン」の呼称について異議のある方はその旨お申し出ください。最近では「アメリカ先住民」などの呼称がつかわれることことが多いです。なぜこの呼称をあえて使うのか、その理由をお答えします。