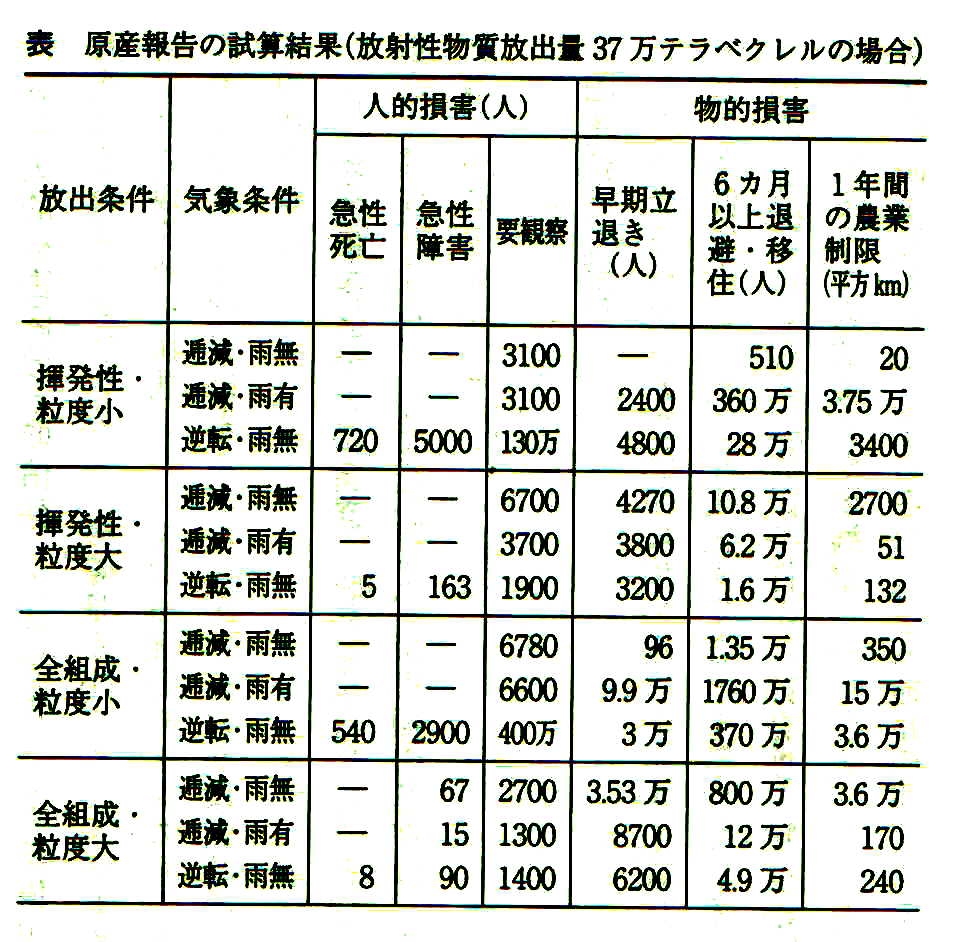原発なくそうの思いで集まっている茨木市民有志グループです。
ニュース、報告、呼びかけ、お願い、短いコメントなどは
ブログ「なくそう原発茨木」blog.goo.ne.jp/c262uouiをご覧ください。
今。「関西広域連合の声明に抗議する。」、「原発と憲法」についてと「原発なぜアカン展」、
「阿武山原子炉反対茨木市民運動展」のパネル展の案内を載せています。 あちらも御覧あれ!
おおい町戸別訪問体験記
ニュース、報告、呼びかけ、お願い、短いコメントなどは
ブログ「なくそう原発茨木」blog.goo.ne.jp/c262uouiをご覧ください。
今。「関西広域連合の声明に抗議する。」、「原発と憲法」についてと「原発なぜアカン展」、
「阿武山原子炉反対茨木市民運動展」のパネル展の案内を載せています。 あちらも御覧あれ!
おおい町戸別訪問体験記
★おおい町へ! ・・・・
政府・関電から若狭大飯原発の再稼動を迫られているおおい町で、稼働を許さないとたたかっている方たちが4月27日から5月1日の間に、おおい町3000戸の全所帯に「大飯原発再稼働反対」の署名を持って訪問する活動をするという報道を聞き、4月29日、支援に行ってきました。
行く前には、次のようなことを予想していました。
★おおい町へむかって車を走らせながら ・・・・
話に応じてくれるのは、よくて4軒に1軒だろう
「どっから来たんや?」と聞かれて「大阪から来た」などというと、「何も分っとらんよそ者がごちゃごちゃ言うな。おまえら電気使うてるだけのくせに。地元のこと分かって来とんのか!」というふうに反発されるのではないか。
賛成・反対、マスコミでは「地元では半々」と報じられているが、新聞社やテレビ局からの電話アンケーなら「秘密保持性」については「安心感」があるのである程度正直に答えても、訪ねてきた「原発反対派」の我々には、次の家で何を言われるか分からないので、直接面と向かうと黙り込んでしまうか、話はしてくれても、はっきりと「反対」というような立場からの意見はほとんど言ってくれないのではないか。いや、その前にやっぱり話そのものをしてくれないのでは? などなどなど。
★さあ、おおい町の村へ入って、話してみると ・・・・
ところが実際の結果は「へえーっ?」と驚くものでした。
訪問したのは名田庄という、山の中と言ってもいいくらいの、戸数57軒の集落でした。 27軒と話して、拒否されたのはたった2件。 そのうちの一人は相当高齢のおばあちゃんで、我々を何かのセールスと最期まで勘違いしていて、トンチンカンな話のまま「終わり」。 もう一人は30代の女性で、「うちに来られても困ります」と、戸を閉められてしまいました。 でも、こんな応対はこの二人だけ。 あとはみんな、ほんとによく話してくれ、なんとかきっかけを見つけてこっちの方から話を切り上げないと話が終わらないという状態でした。
★「町の説明会あんなん茶番や!」本音を聞かしてくれる町民 ・・・・
「外人部隊」であることの「ひけめ意識」についても全く逆でした。 始めは私たちに対し慎重な感じだった人も、「大阪から来ました」というと、「じゃあ安心」という感じで、途端に顔から緊張感が消えて、近所に対しては時々警戒するような目配りと気配を見せても、私たちには「よそ者」という安心感があるようで、賛成、反対別にして「それはそれはご苦労様ですねぇ」とみんな言ってくれ、眉を開いて話をしてくれます。
「26日の、町の説明会、知っとるでしょう。 私も行ってきた。 あんなん茶番や。 『町民とは話し合いをしました』ゆうためだけのもんですわ。 はじめからそうなんですわ。 なんせ10人ほどの人が発言してね、そのうち8人くらいの人が反対なんですわ。 賛成意見の人なんか2人しかおらんのですから。 お坊さんと民宿の経営者の人がな、ほんまにようがんばらはってなあ。 『産業の振興と安全性とは別問題や!』言わはってな。 あの民宿の人、もう原発の客、絶対にこんようにされますで。 間違いなしに。 あの人これからどうすんのかなあ。 ほんまに頭下がりますわ」
庭先で洗車をしていた30歳くらいの男性は、「私のおやじは『高浜』で働いてるんです。 それでも、『ゲンパツ』に対してはみんな何も言えへんけど、みんな一緒の気持ちですよ。 ええと思てるもんなんかおらへん。 ただ、政府がこんなふうな、原発がらみの仕事しかないような町にしてきたんですから、政府が責任もって仕事と雇用をちゃんとしてくれんと、『反対』だけゆうてても、どうしようもないと思うんですわ」などと、地元の人にだとこんなふうには本音は語ってないんじゃないかと思えるような話をしてくれるんです。 「外人部隊」であることが返って「威力」を発揮した、という感じでした。 この人このあと、「あの川の向こうにもちょっとだけやけど、まだ家あるよ」と指さして親切に教えてくれたんです。 私たちがいわゆる「反対派」であることは勿論百も承知でです。
★「原発ないほうがいい」派が7割 ・・・・
計数的にご報告しますと、「賛成」者、数%。 「分からない。答えない」 3割弱。 残りの約7割の人は「恐いです。ないほうがいい」でした。 びっくりするでしょう?しかも、「分からない。 答えない」の人も、内心は「いやだ!」と言いたいが言えない。 もしくは「恐い」と思いながらも、原発産業に関わっているごく身近な人から「それでも電気はいるんやし」と言われ、或いは自分にそう言い聞かせ、それ以上はつらいから、自分の頭の中から追い払って考えないようにしている、というのがホンネだとはっきり、ほんとにはっきり、その気持ちが伝わってくるんです。 そしてそんな立場の人たちもみんな、私たちが訪問したこと、私たちが話すことについては、ほんとに「誠実」に受け答えをしてくれるんです。 ずっと都会に住んできた人間としては、戸惑いを覚えてしまうほど、みんな、こちらが誠実に話しかければ、立場、考えが違っても、ほんとに誠実に応対してくれるんです。 都会では初めて訪ねてきたような者が政治的立場の違う者だった場合は、実につっけんどんな対応をされることなど珍しくないのに、めんくらってしまうほど、相手に対して誠実なんですね。
地元住民のこういう気持ちに直接接することが出来たので、「行ってよかった」と、ほんとに思ってます。 おっかなびっくり回り始めて、すぐ楽になり、最後には意気揚々と引き上げました。 この日、大飯町の山手では、八重桜がまさに“満開”でした。 (茨木市松ケ本町・Y生)
政府・関電から若狭大飯原発の再稼動を迫られているおおい町で、稼働を許さないとたたかっている方たちが4月27日から5月1日の間に、おおい町3000戸の全所帯に「大飯原発再稼働反対」の署名を持って訪問する活動をするという報道を聞き、4月29日、支援に行ってきました。
行く前には、次のようなことを予想していました。
★おおい町へむかって車を走らせながら ・・・・
話に応じてくれるのは、よくて4軒に1軒だろう
「どっから来たんや?」と聞かれて「大阪から来た」などというと、「何も分っとらんよそ者がごちゃごちゃ言うな。おまえら電気使うてるだけのくせに。地元のこと分かって来とんのか!」というふうに反発されるのではないか。
賛成・反対、マスコミでは「地元では半々」と報じられているが、新聞社やテレビ局からの電話アンケーなら「秘密保持性」については「安心感」があるのである程度正直に答えても、訪ねてきた「原発反対派」の我々には、次の家で何を言われるか分からないので、直接面と向かうと黙り込んでしまうか、話はしてくれても、はっきりと「反対」というような立場からの意見はほとんど言ってくれないのではないか。いや、その前にやっぱり話そのものをしてくれないのでは? などなどなど。
★さあ、おおい町の村へ入って、話してみると ・・・・
ところが実際の結果は「へえーっ?」と驚くものでした。
訪問したのは名田庄という、山の中と言ってもいいくらいの、戸数57軒の集落でした。 27軒と話して、拒否されたのはたった2件。 そのうちの一人は相当高齢のおばあちゃんで、我々を何かのセールスと最期まで勘違いしていて、トンチンカンな話のまま「終わり」。 もう一人は30代の女性で、「うちに来られても困ります」と、戸を閉められてしまいました。 でも、こんな応対はこの二人だけ。 あとはみんな、ほんとによく話してくれ、なんとかきっかけを見つけてこっちの方から話を切り上げないと話が終わらないという状態でした。
★「町の説明会あんなん茶番や!」本音を聞かしてくれる町民 ・・・・
「外人部隊」であることの「ひけめ意識」についても全く逆でした。 始めは私たちに対し慎重な感じだった人も、「大阪から来ました」というと、「じゃあ安心」という感じで、途端に顔から緊張感が消えて、近所に対しては時々警戒するような目配りと気配を見せても、私たちには「よそ者」という安心感があるようで、賛成、反対別にして「それはそれはご苦労様ですねぇ」とみんな言ってくれ、眉を開いて話をしてくれます。
「26日の、町の説明会、知っとるでしょう。 私も行ってきた。 あんなん茶番や。 『町民とは話し合いをしました』ゆうためだけのもんですわ。 はじめからそうなんですわ。 なんせ10人ほどの人が発言してね、そのうち8人くらいの人が反対なんですわ。 賛成意見の人なんか2人しかおらんのですから。 お坊さんと民宿の経営者の人がな、ほんまにようがんばらはってなあ。 『産業の振興と安全性とは別問題や!』言わはってな。 あの民宿の人、もう原発の客、絶対にこんようにされますで。 間違いなしに。 あの人これからどうすんのかなあ。 ほんまに頭下がりますわ」
庭先で洗車をしていた30歳くらいの男性は、「私のおやじは『高浜』で働いてるんです。 それでも、『ゲンパツ』に対してはみんな何も言えへんけど、みんな一緒の気持ちですよ。 ええと思てるもんなんかおらへん。 ただ、政府がこんなふうな、原発がらみの仕事しかないような町にしてきたんですから、政府が責任もって仕事と雇用をちゃんとしてくれんと、『反対』だけゆうてても、どうしようもないと思うんですわ」などと、地元の人にだとこんなふうには本音は語ってないんじゃないかと思えるような話をしてくれるんです。 「外人部隊」であることが返って「威力」を発揮した、という感じでした。 この人このあと、「あの川の向こうにもちょっとだけやけど、まだ家あるよ」と指さして親切に教えてくれたんです。 私たちがいわゆる「反対派」であることは勿論百も承知でです。
★「原発ないほうがいい」派が7割 ・・・・
計数的にご報告しますと、「賛成」者、数%。 「分からない。答えない」 3割弱。 残りの約7割の人は「恐いです。ないほうがいい」でした。 びっくりするでしょう?しかも、「分からない。 答えない」の人も、内心は「いやだ!」と言いたいが言えない。 もしくは「恐い」と思いながらも、原発産業に関わっているごく身近な人から「それでも電気はいるんやし」と言われ、或いは自分にそう言い聞かせ、それ以上はつらいから、自分の頭の中から追い払って考えないようにしている、というのがホンネだとはっきり、ほんとにはっきり、その気持ちが伝わってくるんです。 そしてそんな立場の人たちもみんな、私たちが訪問したこと、私たちが話すことについては、ほんとに「誠実」に受け答えをしてくれるんです。 ずっと都会に住んできた人間としては、戸惑いを覚えてしまうほど、みんな、こちらが誠実に話しかければ、立場、考えが違っても、ほんとに誠実に応対してくれるんです。 都会では初めて訪ねてきたような者が政治的立場の違う者だった場合は、実につっけんどんな対応をされることなど珍しくないのに、めんくらってしまうほど、相手に対して誠実なんですね。
地元住民のこういう気持ちに直接接することが出来たので、「行ってよかった」と、ほんとに思ってます。 おっかなびっくり回り始めて、すぐ楽になり、最後には意気揚々と引き上げました。 この日、大飯町の山手では、八重桜がまさに“満開”でした。 (茨木市松ケ本町・Y生)