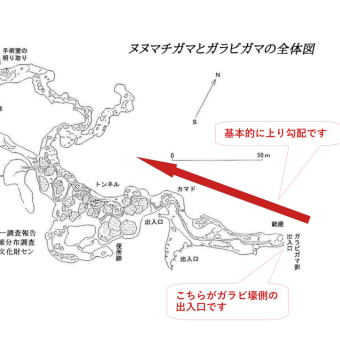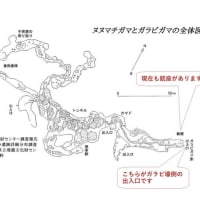個人的に気になる点その2 「合囲地境」説について
今回も兵事主任の証言について、個人的に気になるもう一つの点を説明したいと思います。
まずは再度の引用から。
「「島がやられる二、三日前だったから、恐らく三月二十日ごろだったか。青年たちをすぐ集めろ、と、近くの国民学校にいた軍から命令が来た」。自転車も通れない山道を四㌔の阿波連(あはれん)には伝えようがない。役場の手回しサイレンで渡嘉敷だけに呼集をかけた。青年、とはいっても十七歳以上は根こそぎ防衛隊へ取られて、残っているのは十五歳から十七歳未満までの少年だけ。数人の役場職員も加えて二十余人が、定め通り役場門前に集まる。午前十時ごろだっただろうか、と富山さんは回想する。「中隊にいる、俗に兵器軍曹と呼ばれる下士官。その人が兵隊二人に手榴(しゅりゅう)弾の木箱を一つずつ担がせて役場へ来たさ」
すでにない旧役場の見取り図を描きながら、富山さんは話す。確か雨は降っていなかった。門前の幅二㍍ほどの道へ並んだ少年たちへ、一人一個ずつ手榴弾を配ってから兵器軍曹は命令した。「いいか、敵に遭遇したら、一個で攻撃せよ。捕虜となる恐れがあるときは、残る一個で自決せよ」。一兵たりとも捕虜になってはならない、と軍曹はいった。少年たちは民間の非戦闘員だったのに…。富山さんは証言をそうしめくくった」1988年6月16日付『朝日新聞』(夕刊)
渡嘉敷島の集団自決において軍の命令や強制があったという立場の考察では、この証言が決定的な証拠として取り上げられています。少なくとも兵器軍曹が「自決せよ」と言っており、集団自決の手段として手榴弾が使用されたことからも、その入手経路を解明する一つの証拠ともなり得るものです。
しかし、この兵器軍曹の発した言葉は「命令」と断言できるのでしょうか。「指示」「訓示」という可能性はないのでしょうか。
兵器軍曹が「命令」したとされる上記の証言では、命令される側は15~16歳程度の少年たちです。いわゆる一般市民でもありますから、軍の命令系統に入っていたことにもなりますが、そもそも軍と住民の関係はどのようなものだったのでしょう。
それを考察する前に、例え話をしたいと思います。
Aさんは十数人規模の会社に転職しました。仕事自体は特に問題ないのですが、この会社の社長はゴルフが大好きで、月に一度ほどのゴルフ大会を会社の休業日に開催します。
さて、Aさんはこのゴルフ大会に出るのでしょうか、出ないのでしょうか。
これは休日を利用したゴルフ大会なので、当然ながら会社の業務とは全く関係がありません。従って業務命令ではありませんので、大会出場を拒否しても何の問題もありません。
しかしAさんは拒否できるのでしょうか。「業務とは関係ないから出ませんよ」とハッキリ言えることができるのでしょうか。
みなさんもゴルフ大会ではないにしろ、業務命令とは言えないようなことなのに、従わなければいけないような経験をお持ちだと思われます。中小企業の方はもちろんのこと、数百人や数千人規模の会社に勤めておられる方ならば社長ではなく上司で、会社全体ではなく部課の組織内で同じような経験があると思われます。
本来なら拒むことができるのに、Aさんはほぼ間違いなくゴルフ大会に出ることでしょう。
社長とAさんは雇用関係でありますが、同時に主従関係でもあります。日本人の思考、あるいは行動原理からすれば雇用関係というよりも主従関係のほうが前面に出てくるのではないでしょうか。そしてもう一つ、Aさんが出るか出ないかを決めるものに「場の空気」や「その場の雰囲気」といったものが、少なからず左右してくるのではないでしょうか。
だから拒否はできないのです。この点については、特にこういった経験がある方には説明するまでもありませんが、明確な規定がないにもかかわらず、それぞれの主従関係や雰囲気といったような「見えない拘束力・束縛力」によって、Aさんは拒否できないということになります。
軍と住民の関係も上記の例え話と同じような状況にあったのではないでしょうか。いやむしろ戦争という非常事態であったならば、戦争行為、あるいは戦闘行為がメインであるならば、軍と住民の主従関係といったものは、より強い拘束力や束縛力があったのではないかと思われます。
ただし、実際のところ軍と住民の関係、この場合は海上挺身第三戦隊と渡嘉敷村には明確な規定がありませんでした。別の言い方をすれば、渡嘉敷村は戦闘序列の枠外にあったということでもあります。もっと具体的なことをいえば、あくまで理論上ではありますが、戒厳令が布告されない限り、渡嘉敷村は自治体として海上挺身第三戦隊の「命令」を拒否することが可能だったのです。当時の渡嘉敷村村長からも「軍から直接命令されることはなかった」という証言があります。ちなみにその当時沖縄県全体でも戒厳令は布告されていません。
個人的にはこの明確な規定がなかったということが、集団自決の実像解明を困難にしている遠因だと考えていますが、ここではこれ以上追究しません。
そうとはいえ、軍と住民の関係というのは集団自決の実像解明において、非常に重要な要素が含まれていることは確実であり、現に様々な視点から考察されているものでもあります。
特に集団自決が軍の「命令」や「強制」によって行われたという主張の文献では、その関係が隷属的なもの、支配的なものという観点で考察されております。つまり、たとえ軍からの指示や要請であったとしても、住民側にとっては逆らうことができない絶対的な命令であり、その命令によって集団自決が強制されたということになります。
また、もう一つの特徴として渡嘉敷村民をスパイとして処刑した事件も取り上げられており、集団自決とスパイ処刑事件がワンセットのようなかたちで考察されているのがほとんどです。ここでは集団自決の一点にのみに絞っておりますので、スパイ処刑事件について知りたい方はご自分でお調べになってください。
そういったなかでも典型的なのが「合囲地境」説です。ご存知の方もあるかと思われますが、ご存じない方のために、安仁屋政昭氏の論文「沖縄戦の集団自決(強制集団死)」を以下に引用いたします。少し長いとは思いますが、非常にわかりやすい文章です。
「合囲地境(ごういちきょう)における集団死
沖縄戦のとき、南西諸島全域は、空も海も米軍によって制圧され、九州や台湾との往来は遮断され、包囲されていました。
沖縄守備軍は、県や市町村の所管事項に対しても、指示・命令を出し「軍官民共生共死の一体化」を強制しました。県民の行動は、すべて駐屯部隊の指揮官によって規制され、ここには民政がなかったのです。このような戦場を軍事用語では合囲地境と言いました。合囲地境は敵の合囲(包囲)または攻撃があったとき、警戒すべき区域として「戒厳令」によって区画したところです。
合囲地境においては駐屯部隊の上級者が全権を握って憲法を停止し、立法・行政・司法の全部または一部を軍の統制下に置くことになっていました。沖縄戦の時、戒厳令は宣告されなかったものの、南西諸島全域は事実上の合囲地境でした。県知事や市町村長の行政権限が無視され、現地部隊の意のままに処理されたのは、このような事情によるものでした。地域住民の指示・命令は、たとえ市町村役場の職員や地域の指導者たちが伝えたとしても、すべて「軍命」と受け取られました。
慶良間諸島の渡嘉敷島では赤松嘉次大尉が全権限を握り、座間味島では梅沢裕少佐が全権限を握っており、村行政は軍の統制下に置かれて、民政はなかったのです。このような軍政下で、軍命を伝える重要な役目を果たしたのが村役場の兵事主任(兵事係)でした。
兵事主任は、兵籍簿の調整・兵役年齢者の所在確認・←徴兵猶予願い等の処理・召集令状の伝達・戦没軍人遺家族や傷病軍人の援護など、軍事に関する地域の指導者でした。沖縄戦のときの兵事主任の主な任務は、現地部隊の要求する兵員を徴集して駐屯部隊に引き継ぐこと、軍命(労働力供出・避難・集結・退去等)を住民に伝えることでした。渡嘉敷村の兵事主任であった富山真順氏は、次のように証言しています。
①一九四五年三月二十日、赤松隊から伝令が来て兵事主任の富山真順に対し、渡嘉敷の住民を役場に集めるように命令した。軍の指示に従って「十七歳未満の少年と役場職員」を役場の前庭に集めた。
②その時、兵器軍曹と坪ばれていた下士官が部下に手榴弾を二箱持ってこさせた。兵器軍曹は集まった二十数名の者に手榴弾を二個ずつ配り、「米軍の上陸と渡嘉敷島の玉砕は必至である。敵に遭遇したら一発は敵に投げ、捕虜となる恐れのあるときには、残りの一発で自決せよ」と訓示した。
③米軍が渡嘉敷島に上陸した三月二十七日、兵事主任の富山氏に軍の命令が伝えられた。その内容は「住民を軍の西山陣地近くに集結させよ」というものであった。駐在の安里喜順巡査も集結命令を住民に伝えてまわった。
④三月二十八日、恩納河原の上流フィジガーで住民の「集団死」事件が起きた。このとき防衛隊員が手榴弾を持ち込み、住民の「自殺」を促した。
兵事主任の証言は、住民の「集団死」の実態を如実に伝えています。合囲地境における軍命を伝える兵事主任は重大な責務をになっていたことがわかります。日本国民は、軍の命令は「天皇の命令」と教えられてきました。捕虜になるよりも、「死を選ぶこと」が、「臣民の道」と信じていた一面もあります。天皇の軍隊と地域の指導者たちの教導に従って「生キテ虜囚ノ辱メヲ受ケズ」という「戦陣訓」を実践させられたのです。」
特に解説しなければならないほど難しい文章ではありませんし、軍と住民の関係がどういうもであったかの説明が、いわば凝縮されている形になっていることが窺われます。ちなみに朝日新聞から引用した兵事主任と安仁屋氏の引用文に出てくる兵事主任は同一人物であり、同じ証言であることがわかります。
そしてこの「合囲地境」説が「命令」や「強制」されたという主張の場において支持され、あるいはこの説をもとにしたさらなる主張が展開されているというのが現状で見受けられます。
「合囲地境」説を支持するかどうか、という問いに答えなければならないとすれば、基本的には支持します。前述しましたがこの当時は紛れもない戦争状態でしたし、戦争あるいは戦闘行為が継続中であるならば、当然軍が主導権を握らなければ支障が出てしまうことは、戦争を体験したことのない人でも十分に理解できることでしょう。事実上の合囲地境状態であったことは、必ずしも間違いではないと思います。
しかし、この「合囲地境」説を支持する、あるいは正しいと判断したという前提に立てば、二つの引用文に出てくる兵事主任の証言に、ある一つの疑問が生じてしまいます。
「命令」「強制」という観点からすれば兵事主任の証言の後半部分、具体的には「いいか、敵に遭遇したら、一個で攻撃せよ。捕虜となる恐れがあるときは、残る一個で自決せよ」の部分に焦点が集中しているかと思われます。
ここではその部分ではなく、「合囲地境」説に焦点を集中させてみると今度は前半部分、具体的には「「青年たちをすぐ集めろ、と、近くの国民学校にいた軍から命令が来た」。自転車も通れない山道を四㌔の阿波連(あはれん)には伝えようがない。役場の手回しサイレンで渡嘉敷だけに呼集をかけた。」という部分に矛盾が生じてしまうからです。
「青年たちをすぐ集めろ」という「命令」を兵事主任が受け、渡嘉敷地区には呼集をかけました。ただし、阿波連地区には上記の理由によって呼集をかけていません。つまり渡嘉敷地区だけの青年が集められたということです。
少なくとも該当証言の文脈を常識的に考えれば、そういった結果になると思います。
通信手段がなかったとはいえ、なぜ阿波連地区には呼集しなかったのかという疑問もあります。
ただ疑問点はそこではありません。「自転車も通れない山道を四㌔の阿波連(あはれん)には伝えようがない」という文脈を常識的に考えれば、本来なら阿波連にも連絡しなければならない、いや、軍からの「命令」なのでありますからそれを必ず実行しなければならないはずです。それをしなかった兵事主任の行動そのものが腑に落ちないのです。
「合囲地境」説を支持する、あるいは正しいと判断するという前提で考えた場合、端的にいえば兵事主任は軍の「命令」を無視したことになりませんか。別の言い方をすれば軍の「命令」に逆らった行動をしている、と言えるのではないでしょうか。軍の絶対的な支配下の状況において、兵事主任の行動は命令の不履行になり反逆ともとれる行動なのですが、軍はそれを許したのでしょうか。
再三指摘している通り、この証言には相互参照や相互補完が可能な資料が存在しません。従って兵事主任と兵器軍曹の具体的な、あるいは詳細なやり取りを検証することができませんので、なぜ阿波連地区を無視したのか、その後はどうなったのかは一切不明です。しかしながら、上記の証言が事実だという前提であれば、阿波連地区に呼集をかけなかったのは、兵事主任の独自判断であり、すなわち軍の「命令」を無視していることになります。「合囲地境における軍命を伝える兵事主任は重大な責務をになっていた」のであるならば、阿波連地区を呼集しなかったのは軍の命令を無視するどころか、重大な責務自体を放棄するようなものです。
もちろん、「自転車も通れない山道を四㌔の阿波連(あはれん)には伝えようがない」という、実行不可能というか、不可抗力的なものがあります。しかしながら、「すぐ集めろ」というのが軍の「命令」であり、「阿波連には伝えようがない」という証言がある以上、兵器軍曹の「命令」は渡嘉敷地区と阿波連地区の両方でなければならず、他の手段を用いて「命令」を遂行しなければなりません。それにもかかわらず、兵事主任は渡嘉敷地区のみの呼集にとどめました。その結果渡嘉敷地区だけの少年たちの前で手榴弾が配布され、兵器軍曹の「自決せよ」との「命令」が発せられるのです。
くどいようですが、兵事主任は両方に呼集をかけなければその「命令」を無視、あるいは独自の判断をしたことになるのです。住民は是が非でも服従しなければならない命令のはずなのに、無視あるいは独自の判断ができるということは、それだけ許容範囲があるということにもなり、従来は主従関係だった軍と住民という状況にも微妙な変化が現れるのではないでしょうか。
つまり「命令」だったのが「指示」や「訓示」だった可能性も否定できないのです。現在風にいえば「死ぬ気で頑張れ」という励ましの声が、本当に死ぬことは望んでいないということと同じように、必ずしも「死ね」とは命令していないのではないか、ということも推測できるのです。
これを常識的に解釈すれば「事実上の合囲地境」状態だった渡嘉敷村、いや沖縄県全体からすれば、絶対にあってはならない行為があった事実もあるわけですから、これは「合囲地境」説に矛盾することになるのではないでしょうか。
ただしこの証言一つだけで「事実上の合囲地境」を全て否定することはしませんし、そもそもこの資料だけではあまりにも情報が少なすぎて、これ以上の考察は不可能だと思います。
つまりは、それと同時に「事実上の合囲地境」ではなかったのではないかという仮説も、一方で成立することが可能になる状況でもあるわけです。
しかも「合囲地境」説を主張する根拠の一つとして採用された兵事主任の証言が、その「合囲地境」説を否定できるような事実をも掲示しているといった、ちょっとややこしい状況も生まれているということにもなります。
また、資料の恣意的な取捨選択こそが弊害だということを指摘いたしましたが、今回も証言の後半部は選択され、前半部が無視・排除されてしまっているということにもなっています。
再びAさんの例え話に戻ります。
Aさんはゴルフ大会に出ると決めたとき、積極的に出ようと思ったのでしょうか、それとも消極的なものだったのでしょうか。具体的には「社長のため、会社のために頑張るぞ」というようなものか、それとも「行きたくないけど社長の命令みたいなもんだからな…」というものなのかです。
積極的ならともかく、消極的だった場合は会社内の「見えない拘束力・束縛力」によって、その消極性の度合いが変化すると思います。やりたくもないのにやらされるのありますから、「社長」や「会社」に強制させられたと思うかもしれません。
皆さんはどちらの経験が多いでしょうか。
しかし会社の全従業員という観点からすれば、業務命令ではない休日のゴルフ大会の参加は、画一的に強制させられたとなるのでしょうか。社長や会社のためにと思って積極的に参加した人にまで、社長や上司あるいは会社によって強制させられたとなるのでしょうか。
もっとわかりやすい例を挙げるなら、過去何回となく行われてきて、今後も起こりうる可能性がある沖縄の「県民大会」の参加者は、積極的な参加なのでしょうか、それとも参加を「強制」されたのでしょうか。実際に参加した方はどう思われているのでしょうか。
「事実上の合囲地境」状態であるから、画一的にすべてを強制されたというのには疑問が残ります。現に絶対的なものであるはずの軍命令を、当時の兵事主任は無視した行動をとっているのです。そういった点を恣意的に排除してしまうと、集団自決の実像を解明することが困難になっていくのではないかと危惧します。
そして、あくまでも兵事主任の証言が事実であるならば、という前提条件があることも付言します。
以上の状況を踏まえて「合囲地境」説を考察するならば決して間違いではないが、かといって断定するには非常に早計であるというのが個人的な見解です。
というわけで、二つ目の気になる点を説明してみました。皆さんはどう思われるでしょうか。
次回以降に続きます。
追記
「細かいことはどうでもいいんだ!」「揚げ足をとるな!」と思った方もいるかもしれません。しかし歴史学のような学術研究というのは「重箱の隅をつつく」行為の繰り返しだと思っていますし、それは歴史学にとどまらず全ての学問に当てはまると確信しておりますので、「細かいこと」にこだわり、反論といった「揚げ足をとる」行為をこれからも平然と繰り返すつもりです。
そういったわけなので悪しからず…
参考文献
安仁屋政昭編『裁かれた沖縄戦』(晩聲社 1989年)
The Asia-Pacific journal:Japan Focus