ゲーデル命題に限らず自己言及を含んだ命題の否定形というのは不完全否定しかできていない物ですw)
たとえば原子命題として有名な「太郎は犬を飼っている」を述語命題として否定形を造ってみれば「太郎は犬を飼っていない」ですが、それに(太郎)という主語の名前を付けて 太郎「太郎は犬を飼っている」 と部分的に自己言及を含んだ形にすれば、その否定形は 太郎じゃない「太郎は犬を飼っていない」 となって、
(太郎)∧(太郎じゃない)「犬を飼っているのが太郎で犬を飼っていないのは太郎じゃない」
という クォーク命題 と 反クォーク命題 とからなる 中間子文 を構成可能です。
読んでいて頭がくらくらしてこない人はどうかしてますが、その原因こそは「肯定と否定とを併せ持つにもかかわらず肯定が強調されているばかりだ」という対称性の破れにこそあることがわかりますよね。このことは宇宙森羅万象におけるクォーク実在についても同様に成立しているのだと聞いたら驚かれますか?
クォーク「クォークは存在しない」 反クォーク「クォークは存在する」
これが宇宙におけるクォーク実在に関するクォーク命題なんです・・。
中間子文は クォーク反クォーク「クォークは存在しないのがクォークでありクォークが存在するのは反クォーク」 というモノになります。
強い相互作用の場では静電場とは違って、あるいは正反対で、中心電荷に同符号の強電荷を向けるようなくり込み状況といいますか、ま、いわゆるスクリーニングですよね、そのような場になっておりまして、その究極において中心電荷が消える、中心電荷が消えてもクォーク数1の量子数を持っている、すなわちクォーク反クォーク対からなる中間子だけで中心のクォーク一個を表現することが可能であるわけですw)
クォークと反クォークとが同数である集合においてクォーク一個を存在させることができます。
中心として原点Oを選ぶとします、そこにはクォークはございませんが、中心にクォークを向けてクォーク反クォーク対が凝縮しているとします、クォークと反クォークの数は同数です、ところが中心にとってクォークはより近くに存在しており反クォークはより遠くに存在しております、そして中心対称の構造になっております、それが幾層にも重なって無数のクォーク凝縮が生じておるわけなのですけれど、それで場としては原点Oにクォーク一個が存在すると等価であるということが(現象として)起こるのですw)
これが静電場ですと「中心電荷として幾何構造としては点で近似される電子を選ぶとしたら陽電子を中心電荷に向けた電子陽電子対からなる電子凝縮が中心電荷と共に広がっている」のですが、強い相互作用ではくり込みの向きが正反対なのですよ・・。
両者を比べますと、クォーク理論の方がすでに進んでおり、静電場の方は古色蒼然たる朝永理論のまま、ひょっとして日本だけかな、海外の実情を詳しく知りませんが、とにかくそういうことになりますよ?
ひょっとしたら「レプトンにも強い相互作用が働いていて同じだとかリサ女史が言ってる」とか?
(狭い島国に住んでおりますと何かと苦労が絶えません)
たとえば原子命題として有名な「太郎は犬を飼っている」を述語命題として否定形を造ってみれば「太郎は犬を飼っていない」ですが、それに(太郎)という主語の名前を付けて 太郎「太郎は犬を飼っている」 と部分的に自己言及を含んだ形にすれば、その否定形は 太郎じゃない「太郎は犬を飼っていない」 となって、
(太郎)∧(太郎じゃない)「犬を飼っているのが太郎で犬を飼っていないのは太郎じゃない」
という クォーク命題 と 反クォーク命題 とからなる 中間子文 を構成可能です。
読んでいて頭がくらくらしてこない人はどうかしてますが、その原因こそは「肯定と否定とを併せ持つにもかかわらず肯定が強調されているばかりだ」という対称性の破れにこそあることがわかりますよね。このことは宇宙森羅万象におけるクォーク実在についても同様に成立しているのだと聞いたら驚かれますか?
クォーク「クォークは存在しない」 反クォーク「クォークは存在する」
これが宇宙におけるクォーク実在に関するクォーク命題なんです・・。
中間子文は クォーク反クォーク「クォークは存在しないのがクォークでありクォークが存在するのは反クォーク」 というモノになります。
強い相互作用の場では静電場とは違って、あるいは正反対で、中心電荷に同符号の強電荷を向けるようなくり込み状況といいますか、ま、いわゆるスクリーニングですよね、そのような場になっておりまして、その究極において中心電荷が消える、中心電荷が消えてもクォーク数1の量子数を持っている、すなわちクォーク反クォーク対からなる中間子だけで中心のクォーク一個を表現することが可能であるわけですw)
クォークと反クォークとが同数である集合においてクォーク一個を存在させることができます。
中心として原点Oを選ぶとします、そこにはクォークはございませんが、中心にクォークを向けてクォーク反クォーク対が凝縮しているとします、クォークと反クォークの数は同数です、ところが中心にとってクォークはより近くに存在しており反クォークはより遠くに存在しております、そして中心対称の構造になっております、それが幾層にも重なって無数のクォーク凝縮が生じておるわけなのですけれど、それで場としては原点Oにクォーク一個が存在すると等価であるということが(現象として)起こるのですw)
これが静電場ですと「中心電荷として幾何構造としては点で近似される電子を選ぶとしたら陽電子を中心電荷に向けた電子陽電子対からなる電子凝縮が中心電荷と共に広がっている」のですが、強い相互作用ではくり込みの向きが正反対なのですよ・・。
両者を比べますと、クォーク理論の方がすでに進んでおり、静電場の方は古色蒼然たる朝永理論のまま、ひょっとして日本だけかな、海外の実情を詳しく知りませんが、とにかくそういうことになりますよ?
ひょっとしたら「レプトンにも強い相互作用が働いていて同じだとかリサ女史が言ってる」とか?
(狭い島国に住んでおりますと何かと苦労が絶えません)










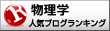








基本的には「L軌道にあるのはクォーク凝縮でH軌道に励起したのが中間子」なのだよ?