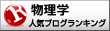かつて南部陽一郎としてもそう思っていた、その証拠は講談社ブルーバックスの文中にあり、そこでは「π中間子は南部=ゴールドストンボソン的な粒子なのではないか?」という疑問文で表明されていますw)
もちろん意味合いは違っただろうとは思うのです、もし同じ発想だったならばワインバーグ=サラム理論を内包してクォークの起源粒子たるMユニバース粒子を発案する方向でしょうから、もしそうだったとしたら南部がユニバーサルフロンティア理論を開拓していたはずです。惜しむらくはグラショウと同じ意味で言っていた、グラショウといえば戦略的な意味でワインバーグに対抗するために発想を対立させていた、すなわち「ワインバーグ=サラム理論の初期のストーリーは電弱統一とは無関係だし、かつ成立しない」と主張していたのでしょう。
その際に全員にとって欠けていた発想が私の【相互作用による対称性の破れ】だったように信じております!
アイソ対称性が自発的に破れたことによって出現するのはT・Nの二種から始まったT・N+反N・反Tの三重項だけではなくって、複合状態のT反N・N反N・T反T・N反Tの四種をも含むということ、さらに韓=南部模型における色変化の禁則からT反Tは強い相互作用に含まれないこと、などを雄弁に論じることができるのは《ユニバーサルフロンティア理論》だけなのです。南部の「南部=ゴールドストンボソン的な粒子」という言葉には日本的で曖昧模糊とした感情が含まれていたでしょう、なぜならワインバーグも擬ゴールドストンボソンとかを発案してグラショウの舌鋒などをかわしておったところですから。
そこがユニバーサルフロンティア理論だと明瞭でクッキリと表現できておりますよ・・。
当初は私としてもT反N・N反N・N反Tの三種については「荷電グルーオンの元か、あるいはπ中間子三重項の別表現ではなかったか?」という風に漠然としておりましたところ、一九六一年の南部理論に関しての検討が進んで「南部の質量付与機構に使われるのはπ中間子そのものではなくてクォーク凝縮だ」ということになっていきましたもので、私としてもT反N・N反N・N反Tにつきましても「クォーク凝縮に憑りついてπ中間子を構成する要素」であるように思想が変化していきました。するとπ中間子の定式を独自に弄らなければなりませんので、そこはやはり若干の勇気が必要だったものです。
π⁻を(d反u)ではなくて(dT反d反N+uT反u反N)などに変更しなければならないのですから大変です!
私が最初にT反Nをπ中間子と同一視して考えたのには分けがございまして、Tから始まったことになるW⁻の崩壊先が電子と反電子ニュートリノであるわけですよ、そこに持ってきてπ⁻が崩壊すればミューオンと反ミューニュートリノになるじゃないですか、その質量に関わらずに明らかにπ中間子の方が一回り大きな組み合わせに行きつく、ここは何とか説明しなくてはならないように思いましたね。
Tに対してT反Nだったら一回り大きな崩壊をすることが鋭く深く即座に納得できたじゃありませんか?
一時期はスーパーウィークといっていたT反Nはこうしてこじんまりとπ中間子の定式に収まりましたが、話はこれだけでは終わりません!
K中間子やB中間子がCP破れの崩壊をすると、そこには必ずT反NだかN反Tだかを起源とする「W粒子とZ粒子とがスピン0だか2だかで弱く結びついた系」が出現して、まさにそれこそが『超弱相互作用』だったのではないか・・。
と、いうことですw)(今日はたくさん表明できて楽しかったです、では・・)
もちろん意味合いは違っただろうとは思うのです、もし同じ発想だったならばワインバーグ=サラム理論を内包してクォークの起源粒子たるMユニバース粒子を発案する方向でしょうから、もしそうだったとしたら南部がユニバーサルフロンティア理論を開拓していたはずです。惜しむらくはグラショウと同じ意味で言っていた、グラショウといえば戦略的な意味でワインバーグに対抗するために発想を対立させていた、すなわち「ワインバーグ=サラム理論の初期のストーリーは電弱統一とは無関係だし、かつ成立しない」と主張していたのでしょう。
その際に全員にとって欠けていた発想が私の【相互作用による対称性の破れ】だったように信じております!
アイソ対称性が自発的に破れたことによって出現するのはT・Nの二種から始まったT・N+反N・反Tの三重項だけではなくって、複合状態のT反N・N反N・T反T・N反Tの四種をも含むということ、さらに韓=南部模型における色変化の禁則からT反Tは強い相互作用に含まれないこと、などを雄弁に論じることができるのは《ユニバーサルフロンティア理論》だけなのです。南部の「南部=ゴールドストンボソン的な粒子」という言葉には日本的で曖昧模糊とした感情が含まれていたでしょう、なぜならワインバーグも擬ゴールドストンボソンとかを発案してグラショウの舌鋒などをかわしておったところですから。
そこがユニバーサルフロンティア理論だと明瞭でクッキリと表現できておりますよ・・。
当初は私としてもT反N・N反N・N反Tの三種については「荷電グルーオンの元か、あるいはπ中間子三重項の別表現ではなかったか?」という風に漠然としておりましたところ、一九六一年の南部理論に関しての検討が進んで「南部の質量付与機構に使われるのはπ中間子そのものではなくてクォーク凝縮だ」ということになっていきましたもので、私としてもT反N・N反N・N反Tにつきましても「クォーク凝縮に憑りついてπ中間子を構成する要素」であるように思想が変化していきました。するとπ中間子の定式を独自に弄らなければなりませんので、そこはやはり若干の勇気が必要だったものです。
π⁻を(d反u)ではなくて(dT反d反N+uT反u反N)などに変更しなければならないのですから大変です!
私が最初にT反Nをπ中間子と同一視して考えたのには分けがございまして、Tから始まったことになるW⁻の崩壊先が電子と反電子ニュートリノであるわけですよ、そこに持ってきてπ⁻が崩壊すればミューオンと反ミューニュートリノになるじゃないですか、その質量に関わらずに明らかにπ中間子の方が一回り大きな組み合わせに行きつく、ここは何とか説明しなくてはならないように思いましたね。
Tに対してT反Nだったら一回り大きな崩壊をすることが鋭く深く即座に納得できたじゃありませんか?
一時期はスーパーウィークといっていたT反Nはこうしてこじんまりとπ中間子の定式に収まりましたが、話はこれだけでは終わりません!
K中間子やB中間子がCP破れの崩壊をすると、そこには必ずT反NだかN反Tだかを起源とする「W粒子とZ粒子とがスピン0だか2だかで弱く結びついた系」が出現して、まさにそれこそが『超弱相互作用』だったのではないか・・。
と、いうことですw)(今日はたくさん表明できて楽しかったです、では・・)