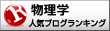南部理論を素直に信じたら「二つの自由電子が超伝導の際にはクーパー対になっていなくてはナラナイ」じゃないですか?
この場合におけるクーパー対とは、オービタルに入った二つの電子のようにスピン0で電荷-2というわけにはいかなくて、ま、言うならば【ネーターの定理】に背いた形で「電荷保存が破れる」モノを言う。まー、こーゆー摩訶不思議な解説を読んでいたら「本当かいな?」という妙な気分になるモノだが、UFTでは電荷保存は法則として成立させたいです・・。
2フェルミオン → クーパー対 (南部過程)
これが容易に起こり得ないというのは、その軽い電子においても「質量のこれだけの欠損が生じたら原子爆弾より大きくて水素爆弾未満のエネルギー放出があるはずだ」とだけ言えば十分でしょう?
南部過程が起こってしまったら「有った質量が無に帰する」からです・・。
UFTの結論では「ゆえに南部過程は電子の話ではあり得ない」「クォークのくり込みは電磁場とは逆向きになっている」「強い相互作用の場ではスクリーニングによって中心電荷が消失する」「ゆえに真のグローバルスタンダードは強い相互作用の理論に帰着される」この順序で従来のストーリーとは異なった世界観を支持いたします。
クォーク → 無数のクォーク凝縮 (南部理論による?)
ここにアインシュタイン流の“騙し絵的な自然観”が生きてきて「画像を見ていたら祝杯を入れる盃にみえるが、背景をじっと見ていたら二人の美女の横顔にみえる」という世界観ですが、この事がどういうことを意味するのかと言ったら「祝杯を挙げる盃と二人の美女とは等価である」つまりアインシュタインとしたら等価原理のことを言っていたのだと思うのですが、ここでは「一つのクォークと無数のクォーク凝縮とは等価である」ということになりますかね?
そもそも【真の南部理論】(ノーベル賞受賞論文)は「π中間子を質量0の南部=ゴールドストンボソンと近似的にみなして陽子の質量を計算する」という内容だったですけど、ま、そりゃーという形で“オマケ受賞”だったことは否めない、π中間子ではなくクォーク凝縮であったということになりますか・・、本日はここまで、では!
この場合におけるクーパー対とは、オービタルに入った二つの電子のようにスピン0で電荷-2というわけにはいかなくて、ま、言うならば【ネーターの定理】に背いた形で「電荷保存が破れる」モノを言う。まー、こーゆー摩訶不思議な解説を読んでいたら「本当かいな?」という妙な気分になるモノだが、UFTでは電荷保存は法則として成立させたいです・・。
2フェルミオン → クーパー対 (南部過程)
これが容易に起こり得ないというのは、その軽い電子においても「質量のこれだけの欠損が生じたら原子爆弾より大きくて水素爆弾未満のエネルギー放出があるはずだ」とだけ言えば十分でしょう?
南部過程が起こってしまったら「有った質量が無に帰する」からです・・。
UFTの結論では「ゆえに南部過程は電子の話ではあり得ない」「クォークのくり込みは電磁場とは逆向きになっている」「強い相互作用の場ではスクリーニングによって中心電荷が消失する」「ゆえに真のグローバルスタンダードは強い相互作用の理論に帰着される」この順序で従来のストーリーとは異なった世界観を支持いたします。
クォーク → 無数のクォーク凝縮 (南部理論による?)
ここにアインシュタイン流の“騙し絵的な自然観”が生きてきて「画像を見ていたら祝杯を入れる盃にみえるが、背景をじっと見ていたら二人の美女の横顔にみえる」という世界観ですが、この事がどういうことを意味するのかと言ったら「祝杯を挙げる盃と二人の美女とは等価である」つまりアインシュタインとしたら等価原理のことを言っていたのだと思うのですが、ここでは「一つのクォークと無数のクォーク凝縮とは等価である」ということになりますかね?
そもそも【真の南部理論】(ノーベル賞受賞論文)は「π中間子を質量0の南部=ゴールドストンボソンと近似的にみなして陽子の質量を計算する」という内容だったですけど、ま、そりゃーという形で“オマケ受賞”だったことは否めない、π中間子ではなくクォーク凝縮であったということになりますか・・、本日はここまで、では!