「逆さに立てた鉛筆は自発的に任意の方向に倒れる」というのが自発的破れの代表的な例だと聞きますけど、
その例示そのものが運動量保存則の破れを意味しておらないでしょうか?
それでいてW粒子やZ粒子がどうして運動量保存する崩壊を示すかと言いますと、そこはそれ元が質量を持たない南部=ゴールドストンボソンでありますから、偏ったままのその位置において運動量対称な崩壊をするのでしょうw)
それに対して、エンプティー粒子は巨大な質量をすでに有しているZ粒子そのものとかtあるいは反tクォークとかを封じ込めて成立してますので、擬ヒッグス機構としてテンガロンハットの円周方向が南部=ゴールドストンモードではなくなるのですよ!
Z粒子は電弱統一理論によるヒッグス場による質量であり、tあるいは反tクォーク周辺はクォーク凝縮による南部機構の質量です・・。
それらが偏って封じ込められていて瞬時に崩壊する、しかもtクォークと反tクォークの分の質量というかエネルギーはZ粒子に託されてしまって、全体として高エネルギーZ粒子の崩壊をする、となれば「運動量は前後において非保存になるのではないか?」というのが私の意見なのです。
このことはJ/Ψ中間子の崩壊現象が強相互作用崩壊であるにもかかわらずcフレーバーが消失してしまう、その理由を「c反c対は擬ヒッグス粒子の一つである」ことに求めてしまえば同時に解決します。
その件に関してはΥ(1s)中間子にとっても同じことです、c反c・b反b・t反tというのは、すべて擬ヒッグス粒子なのだ?
(仕事が増えてきました・・)
その例示そのものが運動量保存則の破れを意味しておらないでしょうか?
それでいてW粒子やZ粒子がどうして運動量保存する崩壊を示すかと言いますと、そこはそれ元が質量を持たない南部=ゴールドストンボソンでありますから、偏ったままのその位置において運動量対称な崩壊をするのでしょうw)
それに対して、エンプティー粒子は巨大な質量をすでに有しているZ粒子そのものとかtあるいは反tクォークとかを封じ込めて成立してますので、擬ヒッグス機構としてテンガロンハットの円周方向が南部=ゴールドストンモードではなくなるのですよ!
Z粒子は電弱統一理論によるヒッグス場による質量であり、tあるいは反tクォーク周辺はクォーク凝縮による南部機構の質量です・・。
それらが偏って封じ込められていて瞬時に崩壊する、しかもtクォークと反tクォークの分の質量というかエネルギーはZ粒子に託されてしまって、全体として高エネルギーZ粒子の崩壊をする、となれば「運動量は前後において非保存になるのではないか?」というのが私の意見なのです。
このことはJ/Ψ中間子の崩壊現象が強相互作用崩壊であるにもかかわらずcフレーバーが消失してしまう、その理由を「c反c対は擬ヒッグス粒子の一つである」ことに求めてしまえば同時に解決します。
その件に関してはΥ(1s)中間子にとっても同じことです、c反c・b反b・t反tというのは、すべて擬ヒッグス粒子なのだ?
(仕事が増えてきました・・)










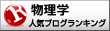








よし、暗中模索だが頑張るぞ・・・。