 | エンデの遺言―「根源からお金を問うこと」日本放送出版協会このアイテムの詳細を見る |
1972年といえば、沖縄が日本に返還(統合?)され、世界遺産条約が締結、『かけがいのない地球』をテーマとした国連人間環境会議が開催された記念すべき年。そんな年に私は生まれた。
たばこの箱に「健康のため吸いすぎに注意しましょう」の表示を大蔵省が決定し、バイシクルとエコロジーを掛けた”バイコロジー”という言葉が流行(!?)したのも、どうやらこの年らしい。
工学部で理系的思考力を学んだ後、化粧品会社の営業→旅行会社営業→(財)自治体国際化協会(CLAIR)勤務などを経て、まちづくりがやりたくて退職し、ニートの道を自ら選択。次なるステップを目指して自己鍛錬すべく、レーナ・リンダルさんの北欧視察に参加、環境やまちづくりのNPO、社会起業家などと関わりながら、10ヶ月ほど過ごす。
現在は(財)日本総合研究所にてNPO支援や国土計画のお手伝いをしている。
CLAIR在籍時に9.11を迎え、出張中に訪問した世界貿易センタービルは、テレビの中で呆気なく崩壊していった。そして米国追従の日本政府の対応には、アナーキーだったこの私にもテロと同じくらい衝撃が大きかった。世界の歯車が完全に狂っていると強く感じることになった。
たまたま日本に生まれ、日本に育ったけれど、戦争で唯一被爆した日本は、果たして自慢のできる国になることはできたろうか?
収入面では社会人だった自分も、本当の意味での社会人(a member of society)と呼べるだろうか?
気が付けば、私の周囲には「社会的な問題をビジネスとして取り組む何ともカッコイイ人々(社会起業家)」が増殖し、新しい日本社会を創ろうとしていた。しかも私より年下の人達が、汗と涙にマミれながら、もがいているではないか。
『モモ』を書いたミヒャエル・エンデは、「根源からお金を問い直そう」と語り、『星の王子さま』は、”肝心なことは眼に見えない”と言う。
本屋には、競争に勝って生き残る本や会社をよくする本は山ほどあるのに、社会をよくする本は殆んどない。本当のこのままでいいのだろうか?
様々な人やモノに刺激を受けながら、世界をよくするために私が選んだ手段は、地域コミュニティの再生をめざす『まちづくり』だった。
大きな都市を変えるのは途方もないけど、小さな街の変革は可能性が高い。今の日本を元気にするのは地方しかない。地方が変われば日本が変わり、日本が変われば世界はきっと変えられる!
…と、随分と大仰なことを書いてしまったけれど、堅いことは抜きにして『まちづくり』って、むちゃくちゃ楽しい~♪。
単独では成し遂げられないことも、人をつなぎ、人につながれ、手をつなぐことで大っきなモノが動かすことができる。
こんなに遣り甲斐があって面白いことは他にはない!?会社の中でチマチマした評価に一喜一憂してないで、どうせならみんなの笑顔を増やす仕事に従事したい。それこそ、自分が生きた唯一の証になるように思う。
私がめざす「まちづくり」は、松下幸之助さんの↓この言葉に凝縮されている。
著書「道をひらく」より。
「それは夢にすぎないだろうか
ただ おたがい おなじ国に生きる人間として
素直に心と心を寄せあい 手と手を握りあって
この国日本の 繁栄と平和と幸福とを
ひとすじに探し求めることができないだろうか
真剣になれば 意見の対立もおきるに違いない
だが 私たち日本人としての願いが一つなら
かならず そこに高い調和と力が生まれよう
それは 決して夢ではないはずだ」
こんな社会の力になりたい。
【興味・関心】
まちづくり、地域経営、コミュニティ・ビジネス、エコ村、農山漁村、ランドスケープデザイン、都市、建築、安藤忠雄、環境、持続可能社会、スローフード、社会起業家、社会的企業、教育、社会学、心理学、アート、仏教、GNH、プロジェクト・マネジメント、ソーシャル・キャピタル、結回る、NPO、ピーター・F・ドラッカー、ブータン、スリランカ、北欧、ポルトガル、イタリア、トルコ、沖縄、瀬戸内、豊島・直島、ジャズ、ボサノバ、楽器、国際交流、etc.














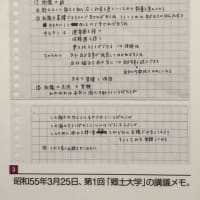

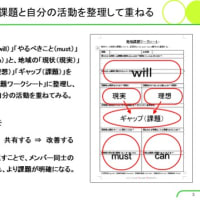
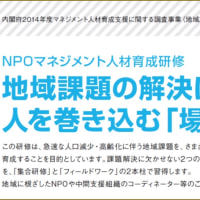
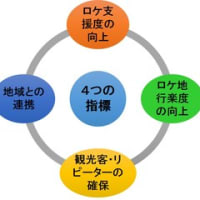








回答者の多くは中高年者です。高年者は本来、文化や伝統を継承し、まちの誇りを伝える役割を持っていたものです。せめて自分たちの逝った後のこと、この国の行方にも思いをはせてほしいなぁ~。